【介護職向け】実務経験証明書とは?取得方法や発行してもらう際の注意点を解説
文/倉元せんり(社会福祉士)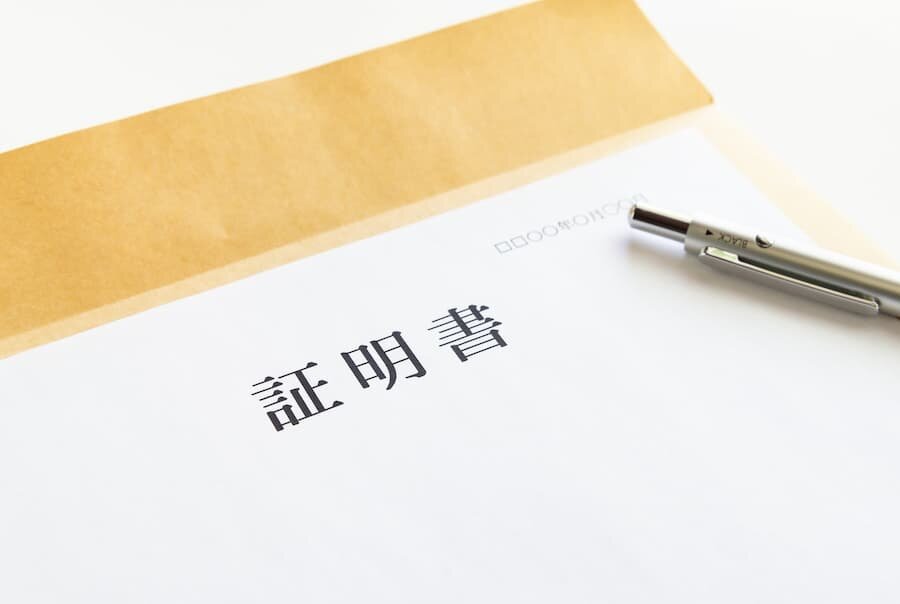
初めて介護福祉士国家試験を受験する方のなかには、「実務経験証明書とはなんだろう」「実務経験証明書の取得方法について知りたい」などの疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
実務経験証明書とは、介護福祉士国家試験を受験する際に、実務経験要件を満たしていることを証明する重要な書類です。「実務経験ルート」で試験に臨まれる方は必ず提出しなければならない書類ですが、実務経験証明書の発行方法や記載内容について不安を感じている方は少なくありません。
そこで本記事では、実務経験証明書の概要や取得方法、記載内容を詳しく解説します。実務経験証明書を取得する際の注意点も解説しますので、実務経験証明書を取得予定の方はぜひ参考にしてください。
1.実務経験証明書とは?
実務経験証明書とは、勤務期間や働いている(働いていた)事業所名など、実務経験に関する必要事項を証明する書類のことです。介護福祉士国家試験を受験する際は、受験資格として必要な3年以上の実務経験を証明するために使用します。
なお、実務経験として認められるのは「介護等の業務に従事したと認められる職種」での勤務期間に限られます。たとえ福祉関連の仕事であっても、この基準に該当しない職種での勤務期間は、実務経験として認められないので注意しましょう。
2.実務経験証明書が必要な場面
実務経験証明書は、介護福祉士国家試験を実務経験ルートで受験する方に必要となる書類です。
実務経験ルートでの受験資格には、以下の2つの要件があります。
- 実務経験3年以上+実務者研修
- 実務経験3年以上+介護職員基礎研修+喀痰吸引等研修
ここでいう実務経験3年以上とは「従事期間3年(1,095日)以上かつ従事日数540日以上」のことです。
3.実務経験証明書の取得方法
介護福祉士国家試験の受験の際に、実務経験証明書を取得する方法は、以下の3つのパターンとなります。
- 現在勤めている事業所で発行してもらう
- 退社した事業所で発行してもらう
- 自分で作成する
1つずつ見ていきましょう。
現在勤めている事業所で発行してもらう
現在勤務している事業所で実務経験証明書を取得する際は、事業所の事務担当者に作成を依頼します。証明書の発行までに1週間程度かかる場合があるので、余裕をも持って依頼するようにしましょう。
なお、実務経験見込みで国家試験を受験する方は、「実務経験見込証明書」の作成を依頼する必要があります。例えば、令和7年の介護福祉士国家試験を受験する方で、申し込み時点では実務経験が3年未満である場合を考えてみましょう。
このケースでは、3月31日までに「従事期間3年(1,095日)以上かつ従事日数540日以上」を満たす見込みであることを、職場に証明してもらわなければなりません。
手順としては、①国家試験申し込み時に、「実務経験見込証明書」の発行を職場に依頼。②国家試験に合格したら、見込み期間を満たしたことを証明するため、あらためて実務経験証明書の発行を依頼するという流れです。
このように、実務経験見込みの方は、同じ事業所から2回にわたって証明書を発行してもらう必要があることを覚えておいてください。
退社した事業所で発行してもらう
退社した事業所が複数ある場合は、それぞれの勤務先に連絡し、証明書発行を依頼してから証明書のフォーマットを郵送します。
事業所側の負担を軽減するためにも、フォーマットを郵送する際は、以下の対応を行うとよいでしょう。
- 記入例を同封する
- 勤務期間や勤務日数を事前に伝えておく
- 返送してもらう場合は、切手を貼った返信用封筒を同封する
退社した事業所の場合、証明書作成に時間がかかる可能性があるので、1か月ほどの余裕を持って依頼したり、返送希望日を伝えたりするようにしましょう。
自分で用意する
退社した事業所が倒産・廃業していた場合は、実務経験を証明できる書類を自分で用意しなければいけません。
その場合は、以下の書類を準備する必要があります。
| 提出目的 | 必要書類 |
|---|---|
| 施設・事業種類の確認 |
以下のいずれか1点(原本) ・閉鎖事項全部証明書もしくは履歴事項全部証明書 ・法人事業所のパンフレットやホームページ ・その他、施設や事業について確認できる書類 |
| 職種の確認 |
以下のいずれか1点(コピー可) ・雇用契約書、雇用通知書 ・労働契約書、労働条件書 ・辞令 ・給与明細、勤務表 ・その他、職種について確認できる書類 |
| 従業期間(雇用期間・在籍期間・登録期間)の確認 |
以下のいずれか1点(コピー可) ・勤務表、出勤表 ・給与明細、源泉徴収明細 ・雇用保険や年金記録に関する書類 ・その他、従業期間について確認できる書類 |
| 業務従事日数(出勤日数・労働日数)の確認 |
以下のいずれか1点(コピー可) ・勤務表、出勤表 ・給与明細 ・その他、業務従事期間について確認できる書類 |
これらすべての項目の書類と、自分で作成した「廃業した施設・事業所等の実務経験について(自己申告)」を受験申し込み時に提出します。
「廃業した施設・事業所等の実務経験について(自己申告)」の書式は国家試験の申し込み書類に同封されているので、注意書きを確認しながら作成しましょう。
4.実務経験証明書の記載内容
実務経験証明書には、氏名などの基本情報以外に、以下の項目の記載が必要となります。
- 就業期間及び介護等の実務に従事した(する)日数
- 施設(事業)種類
- 職種(職名)
それぞれの項目について解説します。
就業期間及び介護等の実務に従事した(する)日数
先述した通り、介護福祉国家試験を受験する際は、「従事期間3年(1,095日)以上かつ従事日数540日以上」の基準を満たしていなければなりません。1日の勤務時間に関する条件は設けられていないので、たとえ1時間のみの勤務でも1日の実務経験としてカウントされます。
ただし、従事期間と従事日数ではカウントの仕方が異なります。従事期間3年(1,095日)以上のなかには在職期間全体が含まれますが、従事日数540日以上のほうは、実際に業務に従事した日のみがカウントされます。休日や欠勤日、産前・産後休暇期間、育児休業期間などは従事日数に含まれないので注意が必要です。
施設(事業)種類
職種(職名)には、受験経験を満たす施設・事業名の記載が求められます。例えば、以下のような施設・事業が対象です。
- 特別養護老人ホーム
- ケアハウス
- 有料老人ホーム
- 老人デイサービスセンター
- 障害者支援施設 など
ほかにも、対象となる施設や事業は多いので、自分が対象になるかどうか、事前に公益財団法人社会福祉振興・試験センターのサイトで確認しておきましょう。
職種(職名)
職種(職名)には、受験経験を満たす職種を記載する必要があります。例えば、以下のような職種が対象です。
- 介護職員
- 介助員
- 看護補助者
- 看護助手
- 訪問介護員 など
介護業務を行ったと認められない場合は、受験資格を得られない可能性があるので、こちらも公益財団法人社会福祉振興・試験センターのサイトで確認しておきましょう。
5.実務経験証明書を取得する際の注意点
実務経験証明書を取得する際は、以下の3点に注意が必要です。
- 発行までに時間がかかる場合がある
- 有効期限がある
- 証明書代がかかる可能性がある
1つずつ見ていきましょう。
発行までに時間がかかる場合がある
実務経験証明書を事業所に依頼しても、対応が後回しになってしまう場合があり、なかには依頼から証明書発行までに1か月以上かかるケースも見られます。
「発行が遅れて受験申し込みに間に合わない」といった事態をさけるため、作成を依頼する際は返送希望日を伝えておくようにしましょう。
複数の事業所で勤務していた場合は従事日数内訳証明書も必要
従事日数内訳証明書とは、同じ期間に複数の事業所で働いていた場合に提出が求められる書類です。ダブルワークで事業所をかけ持ちしている方は、実務経験証明書と合わせて提出が必要となります。
従事している事業所すべてに記載してもらう必要があるので、実務経験証明書と一緒に作成を依頼しましょう。
証明書発行に費用がかかる可能性がある
事業所によっては、実務経験証明書の発行に手数料が発生する場合があります。発行後のトラブルを避けるためにも、証明書発行の依頼をする際に、あらかじめ手数料の有無を確認しておくと安心です。
まとめ
実務経験証明書は、実務経験ルートで介護福祉士国家試験を受験する方に必要な書類です。自作はできないので、現在勤めている事業所や退社した事業所に依頼して、作成してもらうようにしましょう。
ただし、事業所の状況によっては、証明書発行までに時間がかかる場合もあります。書類作成が間に合わないと国家試験の申し込みができなくなってしまうので、余裕を持って発行依頼をすることが大事です。
スピード転職も情報収集だけでもOK
マイナビ介護職は、あなたの転職をしっかりサポート!介護職専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを行います。
はじめての転職で何から進めるべきかわからない、求人だけ見てみたい、そもそも転職活動をするか迷っている場合でも、キャリアアドバイザーがアドバイスいたします。

SNSシェア















