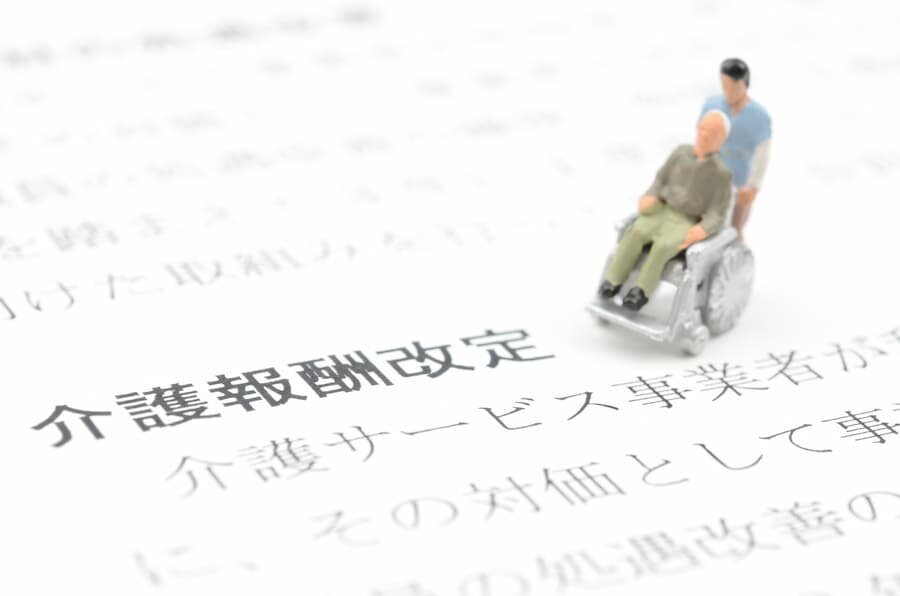特養とは?特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)での介護職員の仕事内容とやりがいについて
吉田 匡和 (よしだ まさかず) 社会福祉士・介護支援専門員(ケアマネジャー)・ 社会福祉主事
特別養護老人ホームは、自治体・社会福祉法人が運営する公的な施設です。ご利用者となるのは、介護が必要となり在宅での生活が困難になった高齢者で、民間運営の有料老人ホームなどに比べて低料金であることから需要が高まっています。
今回は、特別養護老人ホームでの働き方について、介護職員の業務内容や、求められる資質などをお伝えします。
また、その特徴や老人保健施設との違い、入所条件、費用などに加え、どのような職種が働いているのかについても紹介します。
特養とは
特別養護老人ホーム(以下:特養)は、社会福祉法と介護保険法により運営される高齢者施設です。
2000年の介護保険制度施行から「介護保険施設」となり、利用は措置制度(福祉サービスを受ける要件を満たしているか行政が判断し、行政権限としての措置により提供する制度)から直接契約に変更されました。
これにより、ご利用者の負担も応能負担から応益負担に改められ、介護制度施行から原則としてサービスの1割をご利用者が支払うシステム(2018年8月から現役並みに収入がある場合は最大3割)に変更されています。
特養に勤務する介護職員は一日3~4パターンの交代勤務制が一般的で、夜勤手当のほか事業所によっては早朝手当などが支給される場合もあります。
特養の特徴
特養は長期利用が可能な施設であり、民間が運営する有料老人ホームよりも費用の負担が抑えられています。
また、各市町村に設置されているので、都市部以外の人も利用しやすいことも特徴的です。
しかし、過去には介護保険制度によって申し込みが簡略化されたことで、特養入所を待つ「待機者」の増加が社会問題となっていました。
これを受けて厚生労働省は2015年4月の介護保険法改正で、入所要件を「要介護1以上」から「要介護3以上」に厳格化。2014年時点で、全国に52万人以上いた待機者が2017年には約30万人に減少するなど、一定の効果が図られました。
しかし軽度介護者が施設難民として在宅生活を余儀なくされるなど、新たな問題も発生しています。
特養の居室のタイプによって異なる業務内容
特養は居室の構成により「従来型」と「ユニット型」に分かれており、それぞれ職員の配置や業務の進め方が異なります。まずは、それぞれの違いを確認しましょう。
従来型特別養護老人ホーム
多床室(4人部屋など)中心の介護施設。多くのご利用者をチームでケアすることが基本であり、排せつ介助、食事介助、入浴介助やレクリエーションなどは、一日のタイムスケジュール(日課)に合わせて進行します。
<従来型のメリット>
- 集団ケアにより効率的なサービス提供ができる
- 同じフロアにたくさんの介護職員が配置されるので、職員間で業務をフォローしやすい
- 業務がマニュアル化されているので、新人でも仕事が覚えやすく教わりやすい
<従来型のデメリット>
- ご利用者の個別性を重視したサービスが提供しにくい
ユニット型従来型特別養護老人ホーム
約10人を一つの単位とした「ユニット」で個別ケアを行います。ユニット内はすべて個室で職員も固定されるため、ご利用者には常に同じ職員がケアをする安心感を与えられると考えられています。
また食事や入浴などもユニット内でコンパクトに行われます。
<ユニット型のメリット>
- 職員が固定されることでご利用者の状況を把握しやすい
- ユニット内での介護が中心のため動線が短い
- ご利用者の個別性を重視したサービスが提供しやすい
<ユニット型のデメリット>
- ユニットごとに職員配置が必要なため人材確保が難しい
- 担当ユニット以外のご利用者の状況が把握しにくい
- 業務のマニュアル化が難しいため、業務内容を覚えるのに時間がかかる
特養の入居にかかる料金
特養に入居した際にかかる月額費用の目安は8~16万円程です。料金構成は次の通りです。
- 介護保険サービス費(施設介護サービスの基本費用+サービス加算)
- 居住費
- 管理費
- 食費
- その他費用(日常生活費、理容費、娯楽費、医療費など)
これらの費用は、介護保険の適用によって介護報酬の1割~3割の自己負担額の支払いのみのサービスと、全額自己負担が必要なサービスに分かれています。
そのほか要介護度や多床室・ユニット型など居室のタイプによって料金が変わります。提供するサービスに応じて「サービス加算」が加算されます。

特養と老健の違い
特養と介護老人保健施設(以下:老健)は同じ介護保険施設ですが、その性質は次のように大きく異なります。
| 目的 | 利用期間 | 入所要件 | |
|---|---|---|---|
| 特養 | 生活介護(終身施設) | 原則終身利用可 | 要介護3以上 |
| 老健 | リハビリテーション(中間施設) | おおむね3~6か月 | 要介護1以上 |
何らかの理由により障害を負った方が一定期間リハビリテーションを行い、在宅復帰を目指すのが「老健」、在宅での介護が困難な方が、家庭になり代わって静養するのが「特養」といえるでしょう。
しかし近年では自立支援や地域包括ケアの観点から、リハビリを重視する特養が増えている一方で、家族介護が困難などの理由により、老健の退所が見込めず長期化するケースも発生しています。
特養の専門職と介護職員の配置基準
特養の職員の配置職種や人員体制は、介護保険法により基準が定められています。
施設長・介護職員・看護師・機能訓練指導員・栄養士・調理員・生活相談員・介護支援専門員など、さまざまな専門職が連携することにより、ご利用者のケアの向上を図っています。
介護職員・看護職員の配置基準
- 総数:常勤換算方法で入所者3人に対し1人以上
- 昼間はユニットごとに1人以上
- 夜間および深夜は 2ユニットごとに1人以上
- ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置
介護職員:1人以上は常勤(地域密着型特別養護老人ホームのみ)
特別養護老人ホームは常勤換算で3人以上
看護職員:地域密着型特別養護老人ホームは1人以上
1人以上は常勤(サテライト型は常勤換算で1人以上)
特養における介護職員の業務
介護職員の勤務は一日3~4パターンの交代制が一般的です。早番の翌日は遅番ないし夜勤、夜勤が明けた翌日は休みなど、負担の少ないようシフトが考慮されています。
| 勤務時間 | 業務内容 | |
|---|---|---|
| 早番 | 7:00~16:00 | 朝昼食介助・日中業務・就寝準備 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 朝食片付け・日中業務・昼夕食介助 |
| 遅番 | 11:00~19:00 | 昼夕食介助・日中業務・就寝準備 |
| 夜勤 | 17:00~翌9:00 | 夕朝食介助・就寝準備 |
※上記は一例です。シフトは事業所によって異なります
介護職員の待遇
公益財団法人介護労働安定センターが行った平成30年度「介護労働実態調査」から、介護職員の待遇についてみてみましょう。
調査において、以下は介護職員全体の通常月の税込み月収をたずねていますが、こちらはボーナスを抜いた金額になるため、実際の年収を12ヶ月で割った場合の月収より低く見えます。
全体では「20万円以上 25万円未満」が 24.3%で最も高く、次いで「15万円以上20万円未満」が 23.8%。平均月収は 約19万2,600円でした。
賞与については、全体では「制度として賞与の仕組みがある」が 60.4%、「経営状況によって支払われることもある」が 14.4%、「賞与はない」が 19.4%となっています。
特養で勤務する際の注意点
給与・キャリアパスといった介護職員の待遇は、社会福祉法人という経営母体は同じでも事業所によって異なります。
そのため、いくつかの募集要項を見比べたうえで待遇や評判などを考慮のうえ、応募した方がよいでしょう。
一例として、同じ県内で特養を運営している3つの社会福祉法人の募集要項を比較してみました。
| 特養A | 特養B | 特養C | |
|---|---|---|---|
| 基本給 | 203,000円~ 203,000円 | 175,570円~ 352,700円 | 186,800円~ 225,990円 |
| 資格手当 | 20,000円 | 4,000円 | 10,000円 |
| 夜勤手当 | 8,000円~ 11,000円/1回 | 5,000円~ 6,000円/1回 | 186,800円~ 225,990円 |
| 賞与 | 成果配分賞与 | 年2回 | 年3回 |
※基本給は経験などにより変動します
介護職員の離職理由
ひと頃よりも介護業界での離職率は減少したものの、産業全体よりも離職率はまだ高い傾向が見られます。
公益財団法人介護労働安定センターの平成30年度「介護労働実態調査」によると、仕事の満足度は「満足」と「やや満足」と答えた回答を合わせた『満足』は26.1%、「不満足」と「やや不満足」を合わせた『不満足』は16.6%、「仕事の内容・やりがい」は「満足」が 16.7%、「やや満足」が36.1%で合計値は52.8%と最も高かったと報告されています。
前年度となる平成29年度には介護関係の仕事を辞めた理由が調査されており、「職場の人間関係に問題があったため(20.0%)」、「法人や施設・事業所の理念や運営のあり方に不満があったため(17.8%)」が続くなど「仕事の満足度は高く、やりがいは感じているものの、職場環境や事業所の方針が自己に適していない」という悩みを抱えていることが浮き彫りになりました。
介護職員の仕事のやりがい
全国労働組合総連合が2014年に発刊した「介護施設で働く労働者のアンケート」と 「ヘルパーアンケート」報告集に「介護の仕事をやっていてよかったと思うこと」がつづられています。
- ご利用者や家族に笑顔が出てきて、ありがとうと感謝されるとき。
- 元気のなかったご利用者がサービス利用でどんどん元気になったとき。
- ターミナルケアの方が思い通りの終末期を自宅で迎えられたとき。
- ありがとう、助かるよと言っていただくと社会の役に立っていると実感する。
- ご利用者の家族から「いつも見てもらってありがとうございます」と言われると自分の仕事がむくわれた気がします。
- ご利用者から「ありがとう、いつも悪いね」と言われるととても嬉しいです。自分は人の役に立っているんだなと実感できる仕事だと思います。
- ご利用者や家族が笑顔で「ここを利用してよかった」と言ってくださるとき。
- 看取りのとき、ここ(施設)で本当に良くしてもらったと言ってくださるときに嬉しく思う。
- 認知症のご利用者からのやさしい言葉がけや、落ち着いて生活している姿を見ること、リハビリで出来ることが増えたとき。
出典:2014年度「介護施設で働く 労働者のアンケート」と「ヘルパーアンケート」報告集|全国労働組合総連合
ご利用者の尊厳を大切にし、サービス提供の向上を求める介護職員の言葉に優しさとプロとしての誇りを感じます。
介護には「お互いさま」という気持ちが大切
昨今の特養ではさまざまな事件やトラブルが発生し、社会的な話題にもなっています。しかし、本来特養は介護の必要がある高齢者が穏やかに生活するための施設です。
もし理想と乖離する職場に勤めてしまった場合は、同僚とともに具体的改善提案を出し、それでもダメな場合は転職を検討するのもよいかもしれません。
ご利用者は介護を受けることで生活できる、介護職員は介護を仕事にすることで生活できる。介護の仕事の根底にある「お互いさま」という気持ちを忘れずに、介護のプロとして取り組んでいきましょう。
- 参考URL
- 特養の設置目的(老人福祉法 第21条の5|厚生労働省
- 特別養護老人ホームの入所申込者の状況|厚生労働省
- 介護老人保健施設の在宅復帰支援に関する調査研究事業|厚生労働省
- 特別養護老人ホーム配置基準|函館市
- 平成30年度「介護労働実態調査」|公益財団法人介護労働安定センター
- 平成29年度「介護労働実態調査」|公益財団法人介護労働安定センター
- 2014年度「介護施設で働く 労働者のアンケート」と「ヘルパーアンケート」報告集|全国労働組合総連合
【日本全国電話・メール・WEB相談OK】介護職の無料転職サポートに申し込む
SNSシェア