介護動画『認知症ケアにはこの視点で関わる』注文をまちがえる料理店 和田行男さん×町永俊雄さん対談 配信!
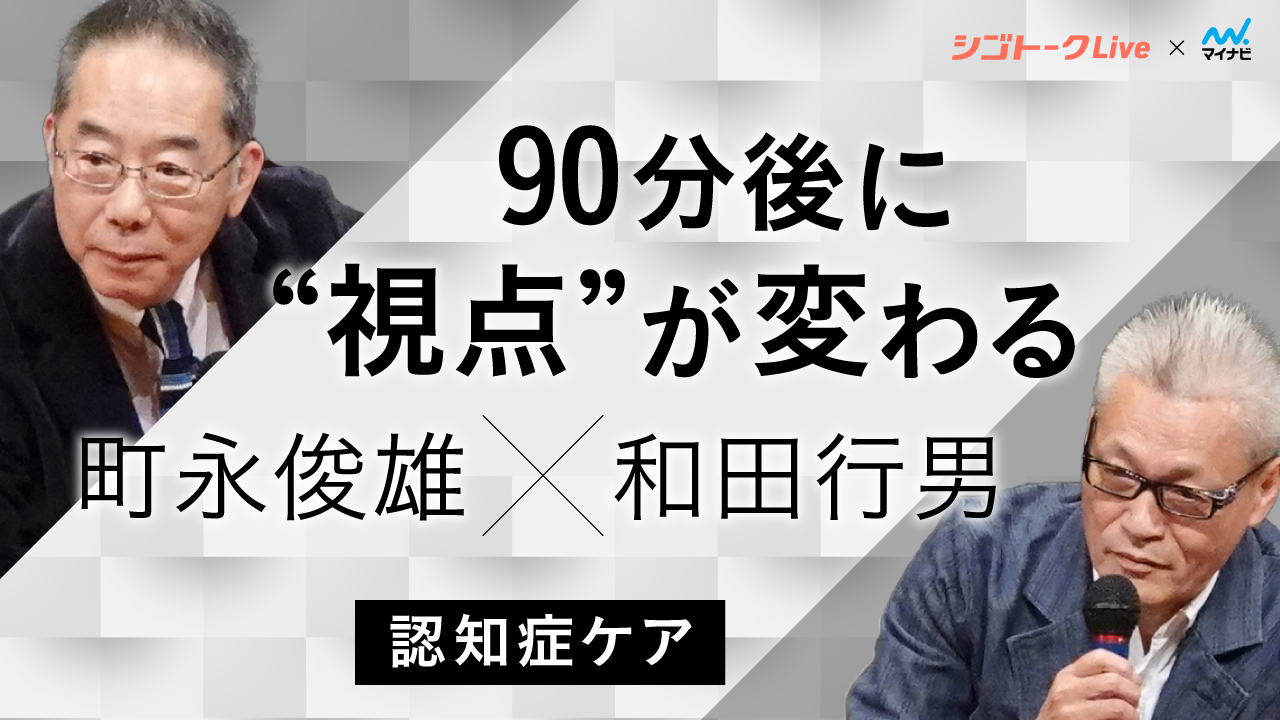
文:安藤梢
医療介護保育業界で働くみなさんへ、仕事に役立つ情報をお届けする動画コンテンツ「シゴトークLive」では、各業界の専門家によるお役立ち情報を配信しています。
今回は、介護業界で著名な和田さんが、ご自身が介護にかかわるうえで大切にしてきた事と、介護という仕事について語る動画をご紹介。
認知症介護の現場を知る介護福祉士の和田行男さんと、福祉ジャーナリストの町永俊雄さんの対談です。
和田行男さんは総合介護サービスを提供する「株式会社 大起エンゼルヘルプ」のディレクターであり、「注文をまちがえる料理店」の仕掛け人としても知られています。町永俊雄さんは福祉・介護の分野から、そんな和田さんの活動を長年にわたって見続け、交流を深めてきた経緯があります。
前半の動画では、和田さんのこれまでの経歴を振り返りながら、さまざまな介護経験を通して見えてくる「介護職にとって大切な視点」を町永さんが聞き出し、後半の動画では「介護の仕事について」をテーマに、お二人それぞれの視点からお話をされています。
「できない」とされていることを「できる」ようにする介護
もともと国鉄(現在のJR)に勤務していた和田さんが、介護の世界に飛び込んだのは今から34年前。国鉄時代に障害者の旅のサポートをした経験から、「どんな人でも社会の中で変わらぬ暮らし方をするにはどうすればよいか」を考え始めたのがきっかけだったそうです。
「和田さんの介護の起点となったものは?」という町永さんの問いかけに、和田さんは特別養護老人ホームで出会ったある女性とのエピソードを語ります。身体的にはまったく問題がなかったにもかかわらず寝たきりだったその女性を、食事のときだけでも起きて食べられるようにと、和田さんは試行錯誤をしていました。
「ところがある日、その方が興味を持ちそうな雑誌を車いすのテーブルに置いたら、両目をぱっちり開けてじーっと見ながら、雑誌を手にして読みだしたんです。そのときに、寝たきりという見たままの姿に騙されたらアカンと思いましたね。その方が主体的な行動をとれるようにすることが、僕らの支援として大切なのだと学びました」(和田さん)
和田さんが関わったわずか2カ月の間に、その女性は起き上がれるようになったといいます。町永さんはそうした介護の姿勢について、「この人は認知症の人、寝たきりの人、と決めつけてしまうのではなく、できることがあるんだという視点で接することが、和田さんの介護の基本になっている」と分析します。
さらに動画では、認知症の利用者を介護するうえで大切な「人への好奇心を持つこと」や「認知症に対する世間のイメージの変化」、「介護の専門職に必要な視点」などについて、詳しくお話をされています。
「お世話する」のではなく「最後まで生きる」を支える介護
動画後編では、認知症の利用者が社会と関わる必要性とそのリスクについてのお話から始まります。
「社会とのつながりをなくしたら、最後まで人として生きるとは言えない」という和田さん。その考えに賛同する町永さんは「認知症や高齢者をリスクと捉えてしまうことは社会の問題」だとし、社会全体でリスクを分かち合うことが必要だと話します。
和田さんがディレクターを務める介護施設で、認知症のショートステイご利用者が施設利用中に出ていってしまったケースを事例として挙げて、ご家族や社会に対してどのようにリスクを説明し、向き合っていけばよいのかも説明しています。
さらに介護の仕事について、最近では「代わりにやってあげる」ことを介護だと捉えられてしまっていることに、和田さんは警鐘を鳴らします。
「自分が働くことが仕事ではなく、利用者ができるようにすることが介護職の仕事。お世話するのではなく、人として最後まで生きることを手伝うことに、専門職としての役割がある」と言います。
動画後編ではさらに、町永さんと和田さんが2008年に医療職、介護職、ジャーナリストなどのメンバーとともに立ち上げた「お福の会」の活動について、会の宣言を引用して説明されているほか、「利用者の人権や尊厳を守る介護とは」、「若い世代の介護職へのアドバイス」など、介護職に携わる人たちへの実践的なメッセージが満載です。
SNSシェア












介護のみらいラボ編集部コメント
シゴトークLiveでは、認知症介護の現場を知る介護福祉士の和田行男さんと、福祉ジャーナリストの町永俊雄さんの対談を動画で配信!和田行男さんは総合介護サービスを提供する「株式会社 大起エンゼルヘルプ」のディレクターで、「注文をまちがえる料理店」の仕掛け人。町永俊雄さんは福祉・介護の分野から、そんな和田さんの活動を長年にわたって応援しています。