日本介護福祉士会会長 及川ゆりこさんに聞く(3)「人員配置、外国人介護職、介護福祉士会の目標」
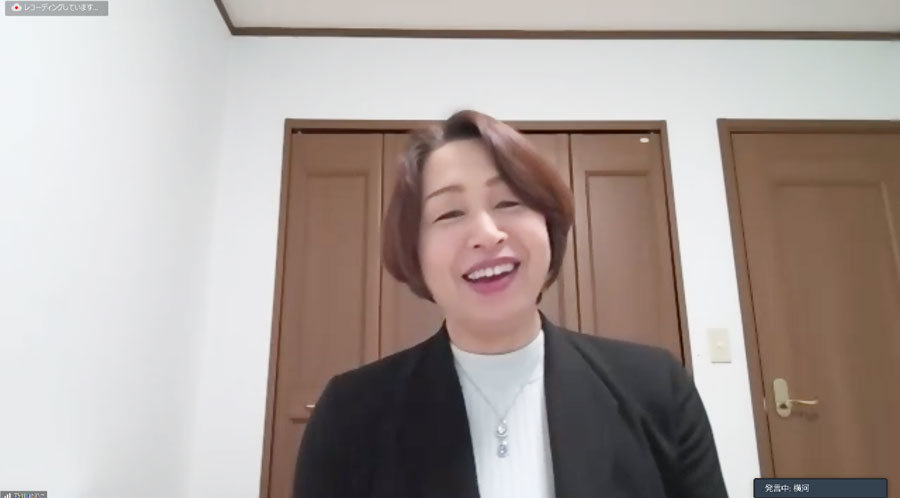
笑顔の及川会長
日本介護福祉士会・及川ゆりこ会長へのインタビュー最終回は、会長としての今後の活動や目標についてお話しいただきました。21年介護報酬改定で導入される夜勤帯の職員数の緩和や、外国人ケアワーカーの就労など、最近の介護業界をとりまく気になる話題についてもうかがいました。
(2021年4月現在)
介護福祉士が社会を支えてこそ、「介護離職ゼロ」が実現する
及川会長は2020年7月に就任した際、ホームページに「会長の挨拶」として、抱負を発表しました。それを見るとまず目に飛び込んでくるのが"介護離職ゼロ"の文字です。
「介護福祉士に求められる役割は、国民の社会生活をより良いものにすることです。その一つが、老いていく親の生活を安心して任せられる『介護離職ゼロ』の社会にすること(webサイトより)」―――この言葉には、会長自身の経験に裏打ちされた強い思いがありました。
「私自身がいま、要介護3の母を介護しています。母は認知症がひどく昼夜が逆転しており目が離せません。私自身、一時は「これではもう外で仕事はできないな」と思いました。でも、ケアマネジャーさんの勧めでショートステイを利用するようになったおかげで、こうして今も仕事を続けられています。
ケアマネジャーさんのひと言とショートステイやデイサービスの存在が、私にとってとても強い力になったのです。ご利用者のご家族が介護の制度や社会資源の使い方を知り、十分に使っていただければ、介護による離職はもっと減らせるのではないかと思います。
介護職員は、私の母のように昼夜逆転しているご利用者が夜中に起き出して階段を降りようとするとき、ご利用者の思いを受容して、専門的な、適切な対応をする必要があります。同じことをくり返すご利用者に対して、ついイラついている介護職員の姿を知れば、ご家族は大切な家族であるご利用者を預けようと思わなくなるでしょう。
「ここなら安心して預けられる」というご家族からの信頼を勝ち取った上で、ADLの改善につながる取り組みを実践していくことが、介護離職ゼロの社会につながるのだと考えています。そのために、現場で介護職員をしっかり束ねつつ、ご利用者にどんな対応が必要なのか、きちんとアセスメントもできる能力を備えたリーダーとしての介護福祉士の役割が重要です。"介護離職ゼロ"を全面に出したいと思ったのは、私たち介護福祉士は、社会的に福祉を支えるために存在しているのだという思いからです」
ADL結果を高め 介護のリスクを回避できるのは、人間の力
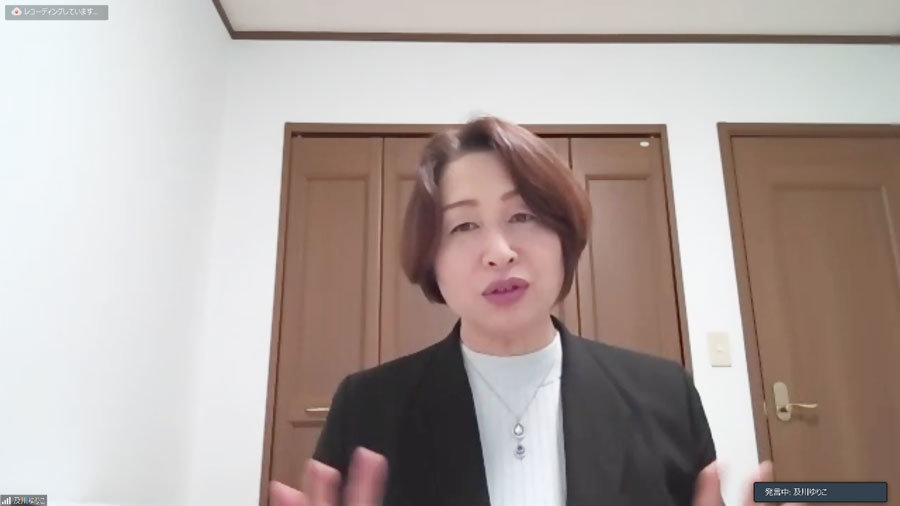
危険回避は、最終的に人間が判断して対応すると説明する及川会長
ところで今年は3年に1度の介護報酬改定の年。今回は「介護の効率化」を目指してICTを活用することが検討されました。具体的には、夜勤帯に見守りセンサーの活用や夜勤職員全員がインカムをもつことなどを要件に、夜勤職員配置の人数を緩和する方向性が打ち出されています。
――夜間職員配置の緩和策については、どのようなご意見をお持ちですか?
「人材不足の状況下では、必要な措置ではあると思います。しかし、私たちは効率的でありながら、効果的で最善の介護を提供しなければなりません。介護報酬改定の検討を行う『社会保障審議会介護給付費分科会』で、『考えられるリスクを極力減らすことを前提にしてほしい』と申し上げたところです。
介護ロボットはリスクを"感知"することはできるかもしれません。しかし、リスク回避を担保できるのは人間だけですので、極端な人員削減は良くないと思います。
夜勤帯には介護ロボットに見守りを任せ、職員はなるべく仮眠をとるということは、介護の質から見ると逆効果になることが証明されています。
特に私は、認知症の母がいるからこそ思うのですが、介護職員にとって日中、夜間の区別がつかないご利用者のケアは本当に大変なのです。夜間は睡眠薬をのんでいただいても、薬が切れたときに目覚めれば歩行にふらつきが出て転倒しやすく、却って介護の負担が重くなることになります。
転倒、骨折によって車いす生活になったご利用者は、歩行能力が低下してしまいます。これまでも、介護福祉士はADLの低下を避けようと一生懸命取り組んできました。ですから、ここで介護の質を下げたくないのです。介護報酬改定でADL(日常生活動作)が改善されるとより評価されるようになったことも事業所は考えて、実際に人数緩和が始まっても、効果、介護の質の両面から検証することが必要だと思います」
日本で働く外国人ケアワーカーをフォローしたい
2025年になると、人口ボリュームの大きい「団塊の世代」が75歳になり、後期高齢者の人口が大きく増えて介護ニーズが急増。厚生労働省は介護職員が全国で約38万人不足すると推計しています。「ICTによる効率化」という発想も介護力を補うという狙いあってのことです。
――介護人材不足の問題についてはどのように考えていますか?
「現在もすでに、人材が集まらないために介護の提供が継続できず、閉鎖される事業所が増えています。高齢社会で介護ニーズは高まっているのに、これでいいのだろうかという歯がゆい思いでいます。もちろん、人材確保のためには介護の仕事が魅力的な仕事であることだけでなく、給与面などの待遇改善が欠かせません。給与アップの前提となるのは介護基本報酬の上昇であり、当会も含め、介護関連の各団体が国に対して求めているところです。次の23年介護報酬改正に向けて、この1~2年はいろいろな観点からの検証が必要だと考えています」
―― 一方、外国人ケアワーカーが現場の新たな介護力として期待されています。
「新型コロナ禍の影響もありましたが、各事業者団体が人材招聘に向けて積極的に動いていることもあり、今後、海外からの人材が入ってくると期待しています。迎える側の私たちとしても、外国人ケアワーカーにとって勉強の場にもなり、日本でよい生活ができるようフォローしてさしあげたいと思います。もちろん、介護の質が低下しては困りますので、日本の生活にまだなじんでいない外国人ケアワーカーを精神的に支えたり、生まれ育った文化が違うことによる意思疎通のすき間を埋めたりすることが大切だと思います」
介護福祉士にもワークライフバランスの実現を

介護福祉士にもワークライフバランスが必要
一方、人材確保のためには、報酬だけでなく"働き方"も問われる時代になりました。2018年に成立した「働き方改革関連法」が順次施行され、企業には次々と"ワークライフバランス"の理念が浸透しつつあります。
「介護福祉士のワークライフバランスも今後、取り上げていきたいテーマです。具体的には当会内に、働き方を考える委員会を立ち上げたいと考えています。社会には働き方改革が浸透してきていますが、介護施設はそもそも24時間365日稼働しているので夜勤があり、残業も多い職場です。
毎年、インフルエンザの流行期には病欠で職員が減ってしまう分をカバーする職員の労働時間が長くなり、本来の休みを削ることも...。特に夜勤は生活のバランスが崩れてしまうんですね。私にも経験があるのですが、睡眠リズムや体調のバランスの乱れ、家族との接点が減ってしまうことによる孤立感。実際に、現場の介護福祉士が月に何回程度の夜勤を担っているか、きちんと調べて検討しなければと思っています。
こうした労働時間の問題に加え、特に管理職は精神的な負担も少なくありません。介護職員は人材が不足している上に、経歴も国籍も多様化しています。なかなか仕事になじめない方もいると思いますし、外国人ケアワーカーの場合はコミュニケーションや相互理解の問題があるでしょう。人材が多様化すればするほど、介護福祉士など経験の豊富なベテランに負担がかかるのではないかと思うのです」
"介護一辺倒"にはならず、自分自身も大切に
2025年になると、人口ボリュームの大きい「団塊の世代」が75歳になり、後期高齢者の人口が大きく増えて介護ニーズが急増。厚生労働省は介護職員が全国で約38万人不足すると推計しています。「ICTによる効率化」という発想も介護力を補うという狙いあってのことです。
――最後に、読者へのメッセージをお願いします。
「コロナの感染拡大で長期間にわたって制限のある生活が続いています。ご自身の家族に対する心配も少なくないなか、介護を自分の仕事として責任感をもって続けている皆さまに敬意を表します。
感染予防のためにとられている制限や対策に何かとがまんをなさっているご利用者に対して、それぞれの施設内でお声がけの方法など、さまざまな工夫をこらしておられることと思います。
皆さんが一生懸命、ご利用者のために働いていることはとてもありがたいことです。ただ、社会にとっても本当に大切な介護職員の方々だけに、どうか自分のお体も大事にしていただきたいと思います。
『片手は介護に、でももう一方の片手は自分のために』。だいぶ昔に聞いたこの言葉が今もずっと印象に残っています。皆さんには介護一辺倒の生活ではなく、気持ちのリフレッシュを意識して心がけてほしいですね。今はまだコロナ禍にあって外出できないのでなかなか難しいかもしれませんが、自分自身を大切にしてください。それが、ひいてはご利用者の生活の質の向上につながります。
また、業務のさまざまな場面で疑問に感じることや小さな不満も、どうかそれを声に出していただきたいと思います。何か問題があれば小さいことから解決していかなければいけません。問題をだまって見過ごさず、声に出し、ぜひ介護福祉士会に連絡してください。それもご自身の身を守ることになります。
最後に、知識と経験をもつ介護福祉士は重要な社会的資源です。どうかこれからも頑張ってください」
取材/中保裕子(医療ライター)
SNSシェア












介護のみらいラボ編集部コメント
感染者ゼロにはならないまま、長期化する "withコロナ"の時代。
「施設内に1~2人くらいは感染する方が出ても仕方ないという心構えでのぞんでほしい」 ―――大曲貴夫先生から第1回目にいただいたアドバイスです。どんなに感染対策にしっかり取り組んでいても、感染のリスクはゼロにはなりません。インタビュー最終回は「もしかしたらあのご利用者(職員)は新型コロナかも?」、そのとき介護職はどう対応すればよいのか、アドバイスをいただきました。