#10円玉#2B弾#50円玉#今日は何の日?#大やけど#摩擦#文房具店#昭和40年(1965年)の出来事#東京都#爆竹#癇癪玉#発火#綾瀬#花火#製造中止#足立区#駄菓子屋
【今日は何の日?】5月22日=足立区の小学6年生が2B弾で大やけど(1965年)/ 雑学ネタ帳
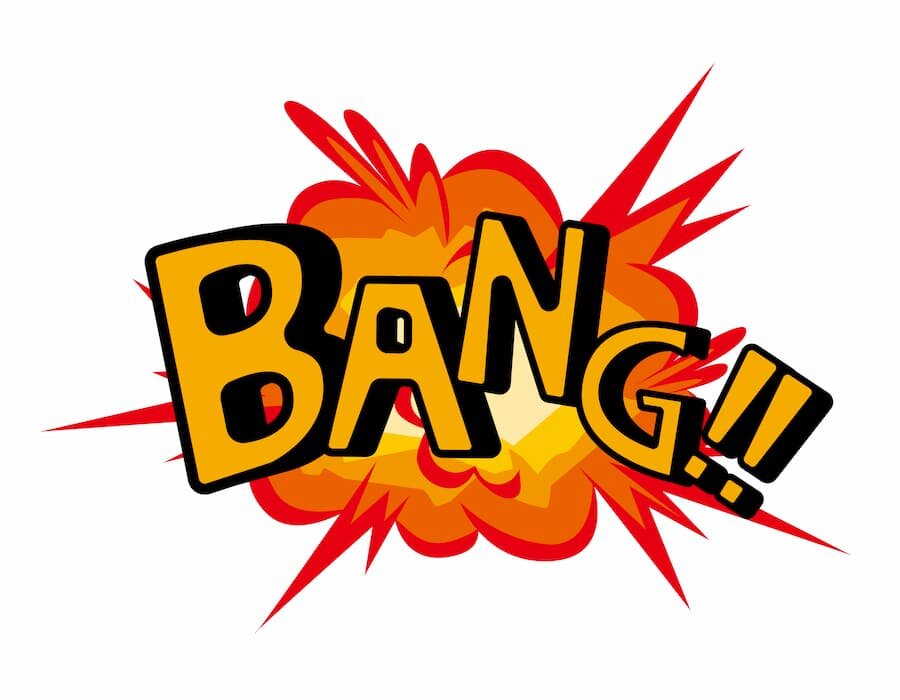
《画像はイメージです》
59年前の1965(昭和40)年。午後3時30分ごろ、東京・足立区綾瀬6丁目に住む小学6年生の少年(当時12歳)が、2B弾(にーびーだん or つーびーだん)花火20本をポケットに入れたまま自宅前で遊んでいたところ、突然爆発。左大腿部と左手に3週間の大やけどを負いました。
2B弾とは長さ6cm、直径5mm程度の棒状の花火の一種。マッチの擦り板やザラザラした壁や床でこすると火がつき、しばらく白煙を出した後に爆発するといった玩具でした。62(昭和37)年ごろから売られ始め、当時は駄菓子屋さんや文房具店で普通に売られており(20本で10円程度)、とくに戦争ごっこなどに使用する男子児童に人気のアイテムでした。
警視庁綾瀬署の調べによりますと、少年はズボンのポケットな50円玉1枚、10円玉1枚とともに20本もの2B弾を入れたまま遊んでおり、硬貨と2B弾が摩擦して発火したものと見ています。
こうした事故は全国各地で相次いでおり、各自治体などから製造中止を訴える要望が続出しており翌66(昭和41)年には製造中止。それでも子どもたちが遊びの中で火や爆発といった危険物を好む傾向は変わらず、短い導火線に火をつけることで爆発する爆竹(ばくちく)や、壁や地面に叩きつけることで爆発する癇癪玉(かんしゃくだま)などに、危険アイテムの役割は受け継がれました。
時代がさらに進んだ令和の現在、学校や公園、道路や広場などでこれらを使用して遊んでいたら、とても叱られることでしょう。
参照 : 昭和40年5月23日付の読売新聞朝刊
文 / 高木圭介
SNSシェア













介護のみらいラボ編集部コメント
高齢者や同僚との話題が浮かばないときにすぐ使える、ウケる、会話が自然と広がる、雑学ネタや豆知識が盛りだくさん!コミュニケーションの活性化にお役立てください。