就労支援A型とは?職員の仕事や必要な資格をわかりやすく解説
文/中村 楓(介護支援専門員・介護福祉士・介護コラムニスト)
障がい福祉サービスの1つである就労継続支援A型は、障がいのある方が働きながら社会参加や自立に向けたスキルを身につけられる福祉サービスです。しかし、就労継続支援A型という言葉を聞いたことがある人でも、詳しい仕事内容までは知らない人もいるかもしれません。そこで、就労継続支援A型で働く人の仕事内容と、その利用者さんを支える職員の業務内容ややりがいについて解説します。
- 目次
- 1.就労継続支援A型とは
- 就労継続支援B型との違い
- 就労移行支援との違い
- 2.就労継続支援A型の利用対象者と仕事内容
- 利用対象者
- 給料
- 仕事内容
- 3.就労継続支援A型を利用するまでの流れ
- 4.就労継続支援A型の職員の仕事内容
- 利用者さんの作業指導や支援
- 生活支援
- 個別支援計画の作成
- 関係機関との連携
- 求職活動や実習の支援
- 利用者さんの送迎
- 5.就労継続支援A型の人員配置と働ける職種
- 人員配置基準
- 働いている人の職種と要件
- 6.就労継続支援A型で働く人の給料
- 7.就労継続支援A型で働くために役立つ資格
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 介護福祉士
- 介護職員初任者研修
- サービス管理責任者
- 8.就労継続支援A型の職員になるには?
- 仕事選びのポイント
- 就労継続支援A型のやりがいとは
- まとめ
1.就労継続支援A型とは

就労継続支援A型とは、障がいや病気などで、一般企業で働くことが難しい方に対して、働く場を提供する福祉サービスです。就労継続支援A型では、事業所と正式に雇用契約を結び、最低賃金以上の給与を受け取りながら、就労に必要なスキルを習得できます。一般就労と異なり、利用者さんの障がいの程度や心身の状態を考慮した働き方ができる点が特徴です。利用者さんは、障がいに理解があるスタッフに支援してもらえるため、安心して働けるでしょう。
就労継続支援B型との違い
就労に関する福祉サービスには「就労継続支援B型」もあります。就労継続支援B型も一般企業で働くことが難しい方に対して、就労の場として提供される点では就労継続支援A型と同じです。就労継続支援A型との大きな違いは、雇用契約の有無です。就労継続支援A型は事業所と雇用契約を結ぶのに対して、就労継続支援B型は雇用契約がなく、工賃(成果に応じた報酬)が支払われます。
また、就労継続支援B型の目的は、障がいや病気の程度が重度な方を対象としており、就労のための訓練や支援を受けることです。そのため、利用者さんの年齢や障がいの重さによって、作業のペースや内容を柔軟に調整し、利用者さんの負担が少なく働ける環境を提供しています。
就労移行支援との違い
就労移行支援は、一般企業へ就職を目指す障がい者に対して、最長2年間の職業訓練や就職活動支援をするサービスです。就労移行支援は、利用者さんが一般就労できるようにスキルアップすることや就労準備を進めることが目的です。ただし、就労移行支援の利用中は事業所からの給与や工賃はありません。それは利用者さんが訓練や支援を受けることが目的であって、収入を得るためではないからです。また、所得に応じて利用料の自己負担が発生する可能性もあるため、心配な方は市区町村の窓口で相談するとよいでしょう。
2.就労継続支援A型の利用対象者と仕事内容

就労継続支援A型で働くためには、対象者の条件や給与・具体的な仕事内容を理解しておくことが大切です。ここから、詳しく解説します。
利用対象者
就労継続支援A型の利用者さんは、一般企業での就労が難しいものの働く意欲があり、事業所の支援のもとで雇用契約を結んで働ける方が対象です。原則65歳未満の方で、具体的には、次のような方が対象です。
1. 就労移行支援を利用したが、企業での雇用に結びつかなかった人
2. 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業で雇用に結びつかなかった人
3. 一般企業等での就労経験があるが、現在は離職をし、雇用関係がない人
就労継続支援A型には、福祉サービスという一面があります。うつ病・高次脳機能障害、パニック障害などの精神障害のほか、ADHDや自閉症スペクトラムなどの発達障害、知的障害、身体障害、難病など、心身になんらかの障がいがある人が対象です。障害者手帳の取得は必須ではなく、自治体の判断によって利用できる場合もあります。
給料
就労継続支援A型では、事業所と雇用契約を結ぶため、地域の最低賃金以上の給与が支払われます。1週間に20時間働くこともありますが、就労時間が1日4時間〜6時間の事業所が多い傾向です。厚生労働省が発表している「障害者の就労支援対策の状況」によると、就労継続支援A型の令和4年度の平均月額工賃(賃金)は、83,551円でした。しかし、障がいや病気の状態に合わせて就労時間が決められるため、平均金額よりも少なくなることも考えられます。
ただし、就労継続支援A型で働いた場合、利用料が発生する可能性もあります。多くの方は利用料の負担はありませんが、世帯の収入状況によっては自己負担が生じます。具体的な負担額は、居住地の自治体や事業所に確認しましょう。
仕事内容
就労継続支援A型事業所での仕事内容は、事業所の業種や規模によって異なります。次に紹介する仕事は、一例です。
| 軽作業 |
・商品の仕分けや梱包 ・ラベル貼り ・クリーニング作業 など |
| 製造業務 |
・簡単な部品の組立や加工 ・製品の検品 など |
| 農業や園芸作業 |
・野菜の栽培や収穫 ・花の手入れ ・屋外での作業 など |
| 清掃業務 |
・施設内外の清掃 ・オフィスビルなどの清掃作業 など |
これらの作業は、利用者さんの体力やスキルに応じて調整され、無理のない範囲で行われます。事業所の職員が利用者さんの特性を考慮しながら丁寧に指導するため、安心して作業に取り組めるでしょう。
3.就労継続支援A型を利用するまでの流れ
就労継続支援A型を利用するためには、自治体の窓口で「障害支援区分認定調査」の申請をする必要があります。通常この調査は、就労継続支援A型を提供する事業所と契約を結んだあとに行われます。すでに障害支援区分認定を済ませている方は、スムーズに進められるでしょう。次から、利用開始までの一般的な流れを解説します。
1. 自治体の窓口に申請
2. 障害支援区分認定調査
3. 障害支援区分の認定
4. サービス等利用計画案を提出
5. 支給の有無の決定
6. サービス利用開始
1.自治体の窓口に申請
居住地の自治体の窓口で申請します。申請書や本人確認書類など必要な書類は、自治体によって異なるため、確認しておきましょう。
2.障害支援区分認定調査
利用者さんの心身の状況や生活状態の聞き取りをします。必要であれば、主治医の意見書も準備しておきましょう。
3.障害支援区分の認定
障害支援区分は、調査結果を基に、各市区町村に設置されている審査会によって認定されます。障害支援区分は1〜6段階に分かれており、障がいの重さによって必要なサービス内容が決められる仕組みです。障害支援区分には有効期間がありますが、期間は申請者の障がいの状況によって異なります(3カ月〜36カ月の間)。
4.サービス利用計画案を提出
申請者は「指定特定相談支援事業者」でサービス等利用計画案を作成し、市区町村に提出します。
5.支給の有無の決定
サービス等利用計画案を踏まえ、支給決定がされます。「障害者福祉サービス受給者証」は、障害支援区分のほか、支給されるサービス内容や支給量・有効期間を記載したものです。「障害者福祉サービス受給者証」は、申請から約30日後に自宅へ郵送されます。
支給決定後、指定特定相談事業者は、利用者さんの意思や選択を尊重し、適切な支援内容を検討するための、サービス担当者会議を実施します。その際、家族の希望や利用者さんの課題も把握することも必要です。サービス担当者会議には、相談支援専門員や利用者本人(可能な範囲で)と家族・就労支援先の事業所が参加し「サービス等利用計画書」を作成します。
6.サービス利用開始
計画書に基づき、サービスの利用が開始されます。新規で支給された場合、3カ月間は1カ月ごとにモニタリングが行われ、サービス内容や利用状況が利用者さんに合っているか見直しされる仕組みです。3カ月経過後は、市区町村が定める期間ごと (少なくとも6カ月に1回)にモニタリングが実施されます。
4.就労継続支援A型の職員の仕事内容

就労継続支援A型の事業所で働く職員は、以下のような業務をしています。
- 利用者さんの作業指導や支援
- 生活支援
- 個別支援計画の作成
- 関係機関との連携
- 求職活動や実習の支援
- 利用者さんの送迎
次から、詳しく解説します。
利用者さんの作業指導や支援
職員は利用者さんが行う作業を指導し、スムーズに仕事が進められるようサポートします。作業内容は、製造業務や軽作業、農作業などさまざまです。就労継続支援A型では、利用者さんの特性に合わせて、無理なく取り組める内容や量で作業を進められます。作業手順をわかりやすく説明し、作業に慣れてきた段階で困ったことが起きていないか見守り、必要な支援を提供します。また、一般企業への就職や社会生活を身につけることも目的の一つです。
生活支援
職員は、利用者さんの体調管理や日常生活のサポートも担当します。たとえば、健康状態に配慮しながら働けるよう、適切な休憩を促したり体調の変化に対応したりすることも大切です。また、相談を通して利用者さんが将来、社会活動を営めるように支援します。
個別支援計画の作成
就労継続支援A型を利用するために、目標や希望を本人や家族から聞き取り「個別支援計画」を作成します。個別支援計画は定期的に計画を見直し、利用者さんの成長や変化に応じて内容を調整可能です。個別支援計画書には、就労に向けた具体的な支援内容や3カ月程度で達成できる短期目標・1年間かけて達成する長期目標が含まれています。
関係機関との連携
利用者さんの支援には、医療機関や福祉機関・家族との連携が欠かせません。職員は、情報共有や調整を行い、利用者さんにとって最善の支援が提供できるように連携を図ります。利用者さんだけでなく、家族の相談することやアドバイスをする場合もあります。また、一般企業への就職や実習支援のため、公共職業安定所(ハローワーク)や障害者就業・特別支援学校などとも関わります。
求職活動や実習の支援
利用者さんが将来的に一般就労を目指す場合、求職活動の支援や実習の調整も職員の仕事の一つです。公共職業安定所(ハローワーク)の使い方の説明や履歴書の書き方、面接の練習など、一般企業とのやりとりや実習先との調整をします。また、職員が利用者さんと企業の間に入り、障がい雇用について理解を深めてもらう役割もしています。
利用者さんの送迎
就労継続支援A型は、一般的に1人で通勤できる方が利用されています。しかし、なんらかの理由で自分で通所することが難しい場合、利用者さんの送迎をしている事業所もあります。
5.就労継続支援A型の人員配置と働ける職種

就労継続支援A型の事業所では、利用者さんのサポートをするための職員が配置されています。ここでは、就労継続支援A型の事業所の人員配置基準や働いている職種を解説します。
人員配置基準
就労継続支援A型事業所には、利用者さんに適切な支援をするために人員配置基準が定められています。
| 職種 | 配置要件 |
|---|---|
| 管理者 |
1人 ※同敷地内の他事業所の管理者・他職種との兼務も可能 |
| サービス管理責任者 |
・利用人数60人まで:1人 ・利用人数61人以上の場合は、40人ごとに1人を追加配置。ただし、端数が出た場合は1人加える ※1人は専任かつ常勤 ※管理者との兼務可能 |
| 職業指導員/生活指導員 |
常勤換算法で、利用者数を10で除した人数以上 ・職業指導員:1人以上 ・生活指導員:1人以上 ※職業指導員と生活指導員のうち、1名以上は常勤 ※常勤換算法とは事業所の勤務の延べ時間数と常勤職員の勤務時間で除することで、事業所の必要職員数を換算する方式 |
就労継続支援A型の事業所では、常勤の管理者が1名以上と、利用者数に応じてサービス管理責任者を配置することが義務づけられています。職業指導員や生活支援員も同様に、利用者さんの人数に対して、必要な人数を配置することが求められます。
働いている人の職種と要件
就労継続支援A型事業所では、さまざまな職員が利用者さんを支援しています。それぞれの業務内容は次の通りです。
| 職種 | 業務内容 |
|---|---|
| 管理者 |
・事業所全体の運営/管理 ・職員の指導 ・業務調整 |
| サービス管理責任者 |
・利用者さんの支援計画の作成 ・サービスの質を管理 |
| 職業指導員 |
・利用者さんの作業の指導 ・職業スキルの向上をサポート ・利用者さんの特性に合わせた指導が求められる |
| 生活支援員 |
・利用者さんの生活面の支援 ・働く環境の整備 ・利用者さんの体調管理 ・利用者さんの相談対応 |
管理者は、事業所の運営や管理、関係機関との連携がおもな業務内容です。管理者は、次のような条件を満たしている必要があります。
- 社会福祉主事資格要件(社会福祉士・精神保険福祉士)に該当
- 社会福祉事業に2年以上従事
- 社会福祉施設長認定講習会を終了
- 企業の経営を1年以上経験
サービス管理責任者は、一定の実務経験を満たしたうえで、相談支援従事者初任者研修とサービス管理者責任者等基礎講習を受講し、サービス管理者等実践研修(令和3年度から実施)を修了している方が対象です。
職業指導員と生活支援員は、どちらも働くために必要な資格はありません。それぞれ役割は異なりますが、利用者さんと関わる機会が多い職種です。初めて福祉に関わる方でも仕事がしやすく、働きながらスキルアップも目指せます。
6.就労継続支援A型で働く人の給料
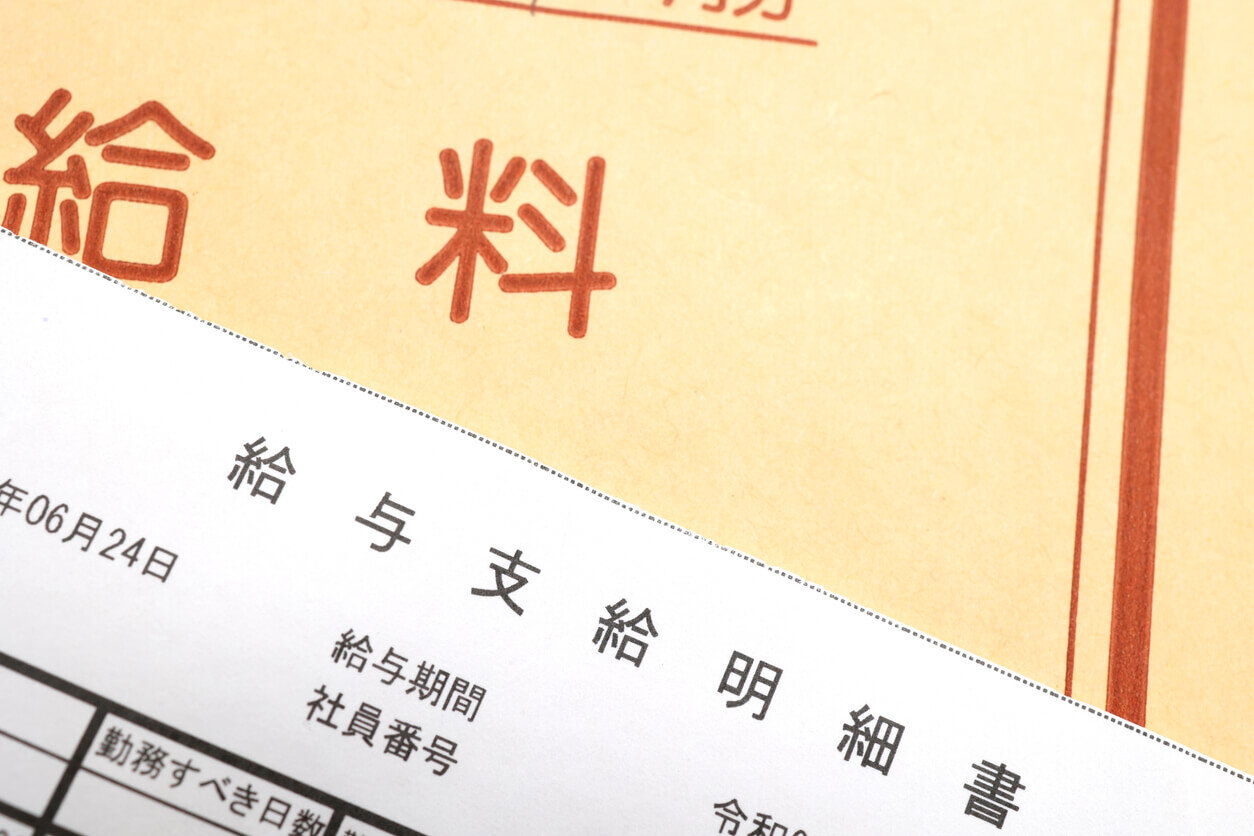
就労継続支援A型で職員として働く人の平均給料は、約25万8千円です。障害福祉サービス全体の平均給与額である312,310円と比較すると、あまり高い水準とはいえません。しかし、就労継続支援A型では夜勤や残業はほとんどないメリットがあります。就労継続支援A型は通所施設で、利用者さんの生活リズムに合わせた勤務体制が組まれるからです。
また次の表のように、福祉関連の資格の取得やサービス管理責任者につくことで、キャリアアップや給与アップが望めます。
| 資格 | 平均給与額 |
|---|---|
| 全般(資格なし) | 295,280円 |
| サービス管理責任者等 | 387,970円 |
| 社会福祉士 | 355,240円 |
| 精神保健福祉士 | 339,180円 |
| 介護福祉士 | 341,070円 |
(参考:令和4年処遇調査|厚生労働省)
就労継続支援A型で働く場合、プライベートやスキルアップに時間が取りやすく、ライフワークバランスも充実するでしょう。また、自分自身のキャリアの成長によって収入を増やせる点は、大きな魅力です。
7.就労継続支援A型で働くために役立つ資格

就労継続支援A型で働く際に資格があると、より専門的な支援が行えます。
- 社会福祉士
- 介護福祉士
- 介護職員初任者研修
- サービス管理責任者
次から解説します。
社会福祉士
社会福祉士は、福祉全般に関する知識をもち、利用者さんの相談支援や福祉サービスの調整ができる国家資格です。生活上に困難を抱えた方の支援や介助ができるため、病院や保健所・児童相談所・介護施設など、さまざまな場所で活躍できます。高齢化社会が進んでおり、今後も社会福祉の需要が高まると予測できるでしょう。受験するためには、実務経験や養成施設等を卒業する必要があります。
精神保健福祉士
精神保健福祉士は国家資格であり、精神的な障がいがある方や家族に対して、生活支援や社会復帰のサポートができる専門職です。社会福祉士や介護福祉士と比べて、より心の健康に特化した資格です。精神保健福祉士の資格を所持していることで、就労継続A型施設で働く精神的な不調や障がいを抱える方の就労や生活に関する相談や助言、必要な訓練などが行えます。精神保健福祉士になるには相談実務業務を経験し、養成施設等で1年以上学ぶ必要があるなど、さまざまなルートがあるため、受験要項を理解しておきましょう。
介護福祉士
介護福祉士は、利用者さんの介助や日常生活の支援ができる、介護職の国家資格です。就労継続支援A型では、働く身体介助が必要な利用者さんに対して支援できるスキルが身につくでしょう。介護福祉士の資格を取得するためには、3年以上実務経験と介護福祉士実務者研修を終了している必要があります。介護福祉士も利用者さんの心身の状態に合わせた接し方を学べるため、就労継続支援A型でも役立つ資格です。
介護職員初任者研修
介護職員初任者研修では、介護の基本的な知識や技術を学び、高齢者や障がい者の生活を支援するために必要なスキルを習得できます。そのため、福祉の仕事に興味がある人や初めて福祉業界で働く方にとって最適な研修です。研修で学習した身体介助や生活援助を通して、利用者さんの状況や障がいを深く理解し、より質の高い支援ができるでしょう。介護職員初任者研修は、自治体や民間のスクールで受講できます。ただし、受講場所によって、費用や進めるペースが異なるため、受講前に確認することが大切です。受講後もキャリアアップを目指しやすい研修なため、計画的に上位資格の取得を目指しましょう。
サービス管理責任者
サービス管理責任者は、利用者さんの個別支援計画の作成やサービスの質を管理します。福祉職員として経験を積んだあと、キャリアアップとしても役立つ資格です。サービス管理責任者になるためには、障がい者の保険・医療・福祉・就労・教育分野における直接支援・相談業務を3年〜10年経験し、加えて初年度に「相談支援従事者初任者研修」を31.5時間、5年ごとの「相談支援従事者現任研修」を18時間、それぞれ修了する必要があります。
8.就労継続支援A型の職員になるには?

就労継続支援A型の職員として働く場合、サービス管理責任者のような資格や福祉に関する実務経験があると有利です。必須条件ではないため、未経験者でも積極的に採用している事業所もあります。また、資格取得を目指す場合、実務経験が必要な場合があります。なかには、就労継続支援A型の事業所で働きながら研修を受けられるところもあるため、就労支援に必要な知識や技術を身につけながら、研修で学びを深められます。
就労継続支援A型の求人情報は、インターネットの就職・転職サイトや公共職業安定所(ハローワーク)で探すことが可能です。福祉分野への就職支援を行っている、各都道府県にある福祉人材センターに相談してみてもよいでしょう。
仕事選びのポイント
就労継続支援A型を提供している事業所は、社会福祉法人やNPO法人・営利法人などがあります。事業所の経営主体や規模・市区町村によって給与も異なるため、 事業所の事業規模や業務内容をみて、自分の得意や資格を生かせる事業所を選びましょう。
また、就労継続支援A型で働く利用者さんのなかには、障がいによってコミュニケーションがうまく取れず、トラブルに発展することも少なくありません。そのため、見学や面接時に、職員と利用者さんとの雰囲気が良いか見ておくことも大切です。困ったときに相談できるサポート体制が整っているか、面接時に確認しておくと安心です。
就労継続支援A型のやりがいとは
就労継続支援A型で働く利用者さんは、一般企業で働くことが難しい方です。そのため、サポートを受けながら少しずつ新しいスキルを身につけることで、自信をもって働けるようになります。自分の支援やサポートが利用者さんの達成感や自信につながれば、仕事にやりがいを感じられるでしょう。
コミュニケーションが難しいと感じる場面もあるかもしれませんが、利用者さんとじっくり向き合うことで、強い信頼関係が築けます。ともに働く利用者さんを支えながら、自分自身の成長も実感できることはモチベーションアップにもつながります。
まとめ:就労継続支援A型とは支援を受けながら働ける場所!安心して働けるようにサポートしよう

就労継続支援A型は、働きたいという意欲をもつ障がい者が、安心して就労経験を積むための障害福祉サービスです。利用者さんは自分に合った仕事に取り組みながら、支援を受けてスキル向上を目指せます。職員は利用者さん一人ひとりの特性やニーズに合わせたサポートを提供し、働く環境を整える役割をしています。障害支援についてもっと学びたい場合は、働きながら専門職の資格を取ることも可能です。利用者さんの社会参加を促進し、よりよい生活の実現をサポートできるでしょう。
【日本全国電話・メール・WEB相談OK】介護職の無料転職サポートに申し込む
スピード転職も情報収集だけでもOK
マイナビ介護職は、あなたの転職をしっかりサポート!介護職専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを行います。
はじめての転職で何から進めるべきかわからない、求人だけ見てみたい、そもそも転職活動をするか迷っている場合でも、キャリアアドバイザーがアドバイスいたします。

SNSシェア














