就労継続支援B型とは?サービス内容や利用の流れ、職員の仕事内容を紹介!
文/中村 楓(介護支援専門員・介護福祉士・介護コラムニスト)
就労継続支援B型は、障害のある人が働く機会を得るための厚生労働省が管轄する障害福祉サービスです。就労継続支援B型では、どんなサービスを受けることができ、どのように利用するのでしょうか。また、どんな人が職員として働いているのでしょうか。
本記事では、就労継続支援B型を利用できる対象者やサービス内容、利用までの流れや利用料金についてお伝えするとともに、就労継続支援B型で利用者さんをサポートする職員の職種や仕事内容、必要な資格や給料について、詳しく解説します。
- 目次
- 1.就労継続支援B型とは
- 就労継続支援B型のサービス内容
- 就労継続支援A型との違い
- 2.就労継続支援B型の対象者とは?
- 3.就労継続支援B型の利用者の仕事内容
- 軽作業
- 農作業
- 清掃作業
- 飲食に関わる作業
- ウエス加工作業
- ポスティング作業
- 芸術工芸作業
- 4.就労継続支援B型でもらえる給料
- 5.就労継続支援B型の利用の流れ
- 主治医に利用したい旨を相談する
- 市町村の窓口で利用申請を行う
- 利用したい事業所と相談支援事業所を探す
- 相談支援事業所に計画書作成を依頼する
- 6.就労継続支援B型の利用料金
- 7.就労継続支援B型で利用者さんをサポートする職員の職種と人員配置
- 管理者
- 職業指導員と生活支援員
- サービス管理責任者
- 8.就労継続支援B型で働く職員の仕事内容
- 管理者
- 職業指導員
- 生活支援員
- サービス管理責任者
- 9.就労継続支援B型の職員に必要な資格・スキル
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 社会福祉主事
- 介護福祉士
- 初任者研修及び実務者研修
- 10.就労継続支援B型で働く職員の給料
- 11.就労継続支援B型で働くには?
- まとめ:就労継続支援B型は利用者さんが障害や体調に合わせて働ける障害福祉サービス
1.就労継続支援B型とは

就労継続支援B型とは、厚生労働省が管轄する障害福祉サービスのうち、自立支援給付の一つです。障害福祉サービスとは、障害や難病がある方に対して、生活や就労、介護のサポートを行う支援のことです。就労継続支援B型は、一般企業や通常の事業所で働くことが難しい障害者を対象に、生産活動を通じて一般就労に必要なスキルや知識などを学べるような支援を行っています。障害や体調に留意して働けるため、自分のペースでゆっくりと社会参加していけるという特徴があります。
就労継続支援B型のサービス内容
就労継続支援B型では、一般企業への就職が難しい障害者のために、軽作業や清掃等の就労訓練や、工作や手芸などの生産活動を通じて働く機会を提供します。事業所内で行う仕事だけでなく、外部の就労先や実習先も確保して、就労の機会や職業訓練を行います。そのほか、日常生活や社会生活をスムーズに行うためのサポートもしています。
就労継続支援B型は、事業所によって利用時間や利用回数などが異なります。自分に合う事業所を選ぶことで、障害や体調に留意しながら、自分のペースでゆっくりと社会参加できるという点も大きな特徴の一つです。
就労継続支援A型との違い
就労継続支援には、A型とB型があります。それぞれの違いは以下のようになっています。
| A型 | B型 | |
| 事業所数 | 4,429件 | 15,588件 |
| 利用者数 | 101,448人 | 406,577人 |
| 特徴 | 雇用契約を結んで働く | 雇用契約を結ばずに働く |
| メリット |
▶雇用契約を結ぶので最低賃金が保証される ▶一般企業への就職者数がB型に比べると多い |
▶労働時間の縛りがなく、負担が少ない ▶年齢上限なし ▶事業所数がA型に比べると多い |
| デメリット |
▶事業所の数がB型に比べて少ない ▶利用の年齢制限がある。 |
▶賃金が安い |
参照:令和4年社会福祉施設等調査の概況「障害福祉サービス等事業所・障害児通所支援等事業所の状況」|厚生労働省
A型とB型の最も大きな違いは、雇用契約を結ぶかどうかです。A型の場合、一般企業などで働くことは難しいものの、雇用契約に基づいて働ける障害者が、事業所と雇用契約を結んで働きます。そのため、賃金も最低賃金は保障されています。ただし、利用者さんの年齢制限があり、原則65歳を超えると利用できなくなります。
一方、B型は事業所との雇用契約は結びません。そのため、最低賃金の保証はありませんが、障害や体調に合わせて自分のペースで利用することができます。B型の場合は年齢制限もないため、A型で年齢制限を超えた人が働くことも可能です。
2.就労継続支援B型の対象者とは?

就労継続支援B型は、就労移行支援事業等を利用したものの、一般企業の雇用に結びつかなかった人のうち、就労の機会等を通じて生産活動にかかる知識や能力の維持向上が期待できる障害者を対象としています。具体的には、以下に該当する人が対象となります。
① 企業等や就労継続支援A型で就労経験がある者のうち、年齢や体力の面で雇用されることが難しくなった障害者
② 50歳に達している、もしくは障害基礎年金1級受給者
③ ①②に該当しない者のうち、就労移行支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者
障害者支援施設に入所する人の場合、相談支援事業者による計画書の作成の手続きを経たうえで、市町村により利用の組み合わせの必要性が認められれば、利用することができます。
(参照:障害福祉サービスについて|障害福祉サービスの内容|15就労継続支援B型(非雇用型)|厚生労働省)
3.就労継続支援B型の利用者さんの仕事内容

就労継続支援B型の利用者さんが行う仕事は、事業所によっていろいろな種類があります。実際に行われている主な仕事について、詳しく見ていきましょう。
軽作業
軽作業は、多くの事業所で取り入れている仕事です。具体的には、部品の組み立てや食品の袋詰め、チラシ折り、箱折り、シール貼りなどの作業があります。事業所が委託を受けて行うケースが多く、事業所内の作業として実施していることがほとんどです。
農作業
野菜栽培や農地管理、園芸なども、就労継続支援B型の仕事内容として、よく行われています。事業所の敷地内に農地を持っているところや、委託先の農地に行って行う場合など、事業所によってさまざまです。利用者さんの能力や体調に合わせて、負担が大きくならないような役割分担を行って、作業できるようにしています。事業所によっては、収穫物の選別や袋詰めなども行います。
清掃作業
清掃作業は、施設外のアパートや店舗などに赴いて、数人で清掃を行います。委託先には、コインランドリーや老人ホームなどの施設もあります。委託先によっては、清掃作業以外にシーツ交換などの作業も実施します。
また、除草作業や草刈り作業なども、就労継続支援B型の仕事内容でよく見られます。近隣の公園や企業の敷地内など、さまざまな場所が委託場所となっています。
飲食に関わる作業
就労継続支援B型では、カフェやレストランを運営しているところや、弁当やパンなどを製造販売しているところもあります。カフェやレストランがある事業所では、接客や調理補助、清掃、皿洗いなどの作業があり、それぞれの能力に応じて仕事を担当します。
食品加工販売を行う事業所では、お菓子やパン、豆腐、弁当などの製造や販売を行います。地域の会社や病院、販売店などに納品や配達するところもあります。
ウエス加工作業
就労継続支援B型でよく行われる仕事に、ウエスの加工や販売があります。ウエスとは、機械の油や汚れをふき取るために使う布で、機械工場や自動車整備工場などに納品されます。一般家庭から回収された古着などのなかから、ウエスに適したものを選別し、適度な大きさに切っていくという作業が行われます。
ポスティング作業
自社や委託先のフリーペーパーなどを各家庭に配布するポスティング作業も、就労継続支援B型ではよく見られる仕事内容の一つです。配布するフリーペーパーやチラシを折る作業も、仕事として行います。
芸術工芸作業
就労継続支援B型では、芸術作品や手芸作品などの作業を行う事業所もあります。絵画や工作、手芸、クラフト作品、織物やフェルト加工など、事業所によって行う作業にはさまざまな特色があります。芸術工芸作業を希望する場合は、利用者さん自身に合うものが実施されているか、しっかり確認すると安心です。
4.就労継続支援B型でもらえる給料

就労継続支援B型で利用者さんがもらえる給料は、工賃と呼ばれます。就労継続支援B型の場合、雇用契約を結ばないため、工賃が安いのが現状です。厚生労働省が行った調査によると、就労継続支援B型の事業所の27.4%は、平均月額が1万円未満となっています。利用者数では全体の28.1%が、1万円以上1万5千円未満です。
(参照:就労継続支援B型に係る報酬・基準について≪論点等≫P8|厚生労働省)
また、工賃には地域差も見られます。最も平均工賃が低いのは山形県で14,037円、最も高いのは徳島県の23,361円となっており、その差は9,324円と大きな差があります。
就労継続支援B型の平均工賃についてみてみると、令和4年度の平均工賃は17,031円、時給にすると243円です。雇用契約を結ぶA型の平均月額賃金は83,551円、時給にして947円と比べると、B型の工賃はかなり低いことが分かります。
ただし、B型の工賃は少しずつ改善傾向にあり、毎年徐々に上がっています。前年の工賃から比べると、月額では524円、時給は10円アップしています。今後も、少しずつ工賃は上がると考えてよいでしょう。
(参照:令和4年度工賃(賃金)の実績について|厚生労働省)
5.就労継続支援B型の利用の流れ
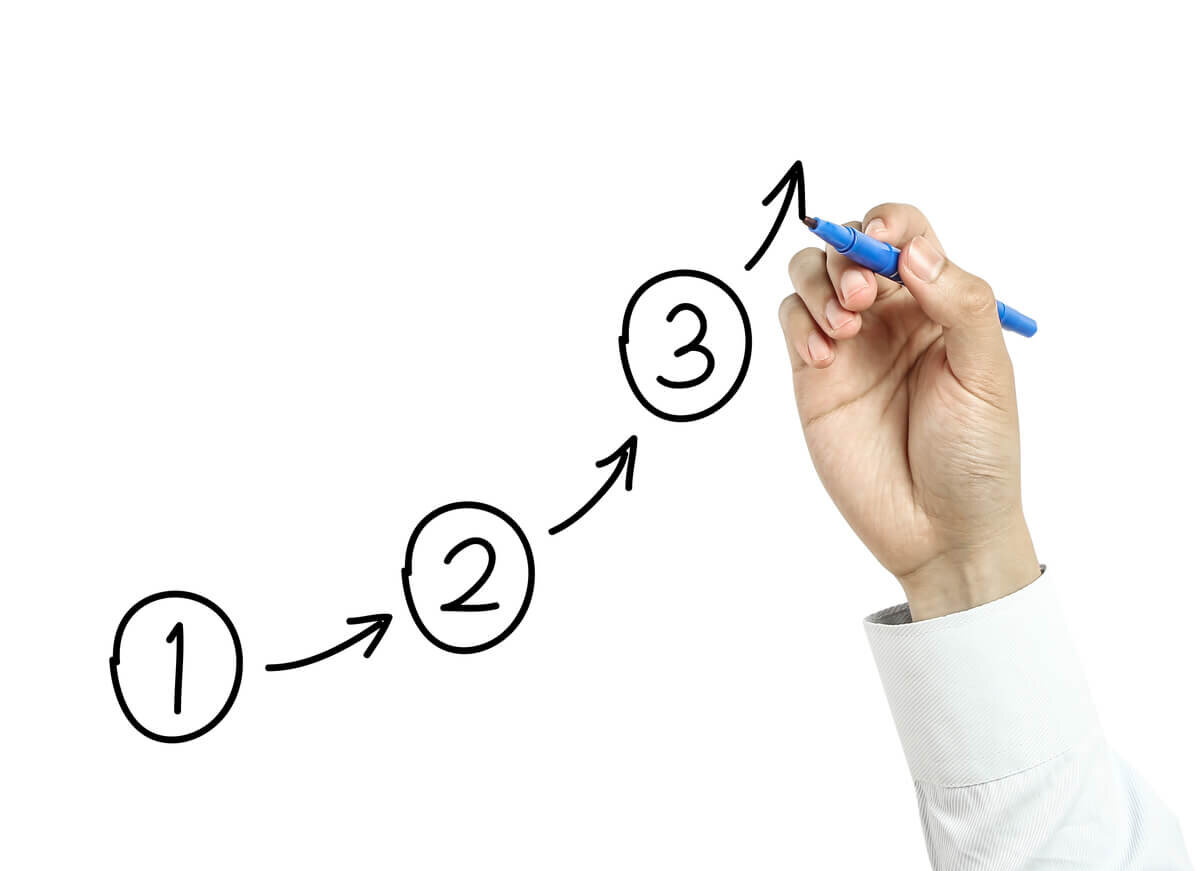
就労継続支援B型を利用するには、どうしたらよいでしょうか。利用の流れについて、詳しく見ていきましょう。
主治医に利用したい旨を相談
就労継続支援B型を利用するためには、主治医に利用したい旨を相談し、就労が可能なのか、サービスを利用する必要性があるかの判断をしてもらわなければなりません。特に障害者手帳を持っていない人の場合、申請時に医師の診断書が必要になるので、事前に主治医への許可を得ておきましょう。
市町村の窓口で利用申請を行う
主治医の許可がもらえたら、市町村の窓口で障害福祉サービスを利用するための申請を行います。申請時に必要な書類は自治体によって異なるものの、一般的には申請書や障害者手帳、世帯収入の申告書などを用意することになるでしょう。障害者手帳がない場合は、医師の診断書が必要です。
申請後は、福祉担当職員から生活状況や心身の状況、生活・就労に関する目標についての認定調査が行われます。認定調査後、1か月ほどで障害福祉サービスを利用するための受給者証が発行されます。就労継続支援B型を利用する際には、受給者証を提示しなければなりません。
利用したい事業所と相談支援事業所を探す
利用申請と同時進行で、利用したい事業所と相談事業所を探します。事業所は見学が行えるところも多いので、気になるところは実際に目で見て雰囲気を確認したり、仕事内容について質問したりしてみましょう。事業所によっては、体験ができるところもあります。
相談支援事業所は、就労継続支援B型を利用するために必要な計画書の作成やサービスの調整などを行う事業所です。どちらの事業所も、役所の窓口で一覧表をもらえることがあるので、申請の際に聞いてみるとよいでしょう。
相談支援事業所に計画書作成を依頼する
利用したい事業所と相談支援事業所が決まったら、相談支援事業所に計画書の作成を依頼しましょう。就労継続支援B型などの障害福祉サービスを利用する際には、担当の相談支援専門員が作成した計画書が必要です。計画書は、利用者さん自身の目標や希望、日常生活の様子、心身の状態などを聞き取ったうえで作成されます。
計画書をもとに利用する事業所を交えたサービス担当者会議が実施され、事業所と契約を交わすと、いよいよ就労継続支援B型を利用できるようになります。
6.就労継続支援B型の利用料金

就労継続支援B型を利用する際には、利用料金が発生します。自己負担額は、利用にかかる費用の1割です。ただし、利用料金には上限額があり、所得に応じて4つに区分されています。上限額を超えた額については、ひと月に利用したサービスの量に関わらず、新たな負担は生じません。
所得別の負担上限月額は以下の通りです。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | |
| 一般1 |
市町村税課税世帯のうち所得割16万円未満 ※20歳以上の入所施設利用者、グループホーム利用者は除く |
9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(参考:障害福祉サービスの利用について|全国社会福祉協議会)
なお、昼食代や交通費などの費用は実費です。ただし、市町村民税課税世帯のうち所得割28万円未満の世帯や非課税世帯の人は、食材費のみが自己負担となる減免措置を受けることができます。
7.就労継続支援B型で利用者さんをサポートする職員の職種と人員配置

就労継続支援B型で利用者さんをサポートする職員には、「管理者」「職業指導員・生活支援員」「サービス管理責任者」がいます。各職種における人員配置基準は、以下の通りです。
| 人員配置基準 | |
| 管理者 |
▶常勤1人必要 ▶業務に支障がない場合はほかの職務との兼務可 |
| 職業指導員及び生活支援員 |
▶総数は常勤換算で利用者数を10で除した数以上、1人以上は常勤 ▶職業指導員と生活支援員はそれぞれ1人以上 |
| サービス管理責任者 |
▶利用者数60人以下では1人以上 ▶利用者数が60人を超えて40またはその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上 ▶1人以上は常勤 |
続いて、それぞれの職員について解説します。
管理者
管理者は、事業所の管理全般を担当するスタッフです。業務に支障がない場合は、ほかの職務と兼務ができます。多くの事業所では、管理者と職業指導員や生活支援員などを兼務していることが多いでしょう。
職業指導員と生活支援員
職業指導員は、利用者さんの希望や適性に合わせて、職業上の技術を習得させるための訓練や指導を行います。生活支援員は、利用者さんの生活援助や訓練、相談援助などを行う職員です。利用者さんに直接関わる機会が多いのが、職業指導員や生活支援員となります。
サービス管理責任者
サービス管理責任者は、障害福祉サービスで支援の総合的な管理を担当する責任者です。障害分野における相談支援業務もしくは直接支援業務の実務経験(3~8年)に加え、研修を修了する必要があります。サービス管理責任者は、5年ごとに資格を更新しなければなりません。
8.就労継続支援B型で働く職員の仕事内容

就労継続支援B型の職員は、どのような仕事を行っているのでしょうか。職種別の仕事内容について、詳しく見ていきましょう。
管理者
管理者は、事業所で働くスタッフの管理や教育、業務状況の把握などを実施します。管理業に支障がない範囲内であれば、ほかの職種と兼務が可能なため、事業所内のほかの職種と兼務している管理者も少なくありません。
職業指導員
職業指導員は、利用者さんの希望や適性に合わせて、作業を通して職業上の技術を習得させるための訓練や指導を行います。また、社会で働くために必要な基本マナーを身に付けるための指導も担当しています。
生活支援員
生活支援員は、職業訓練や健康管理など、日常生活に関する支援を行っています。事業所での人間関係や将来への不安など、困りごとや悩みなどの相談にも対応します。
サービス管理責任者
サービス管理責任者は、利用者さんがそれぞれに合ったサービスを受けられるよう、個別支援計画を作成します。計画作成後も、利用者さんの状況を見ながら、変更すべき点があるのかなどを評価したうえで、必要に応じて見直しも行っています。
9.就労継続支援B型の職員に必要な資格・スキル

就労継続支援B型で働く場合、資格要件は特に必要ありません。しかし、障害を持つ利用者さんに接するという仕事であるため、障害に関する知識や技術を持っていると仕事に役立つでしょう。ここでは、実際に働いている人が持っている資格のなかでも、多いものを5つ紹介します。
社会福祉士
社会福祉士は、相談援助のスペシャリストといわれている福祉職の国家資格の一つです。福祉系大学で所定の科目を履修するなどによって、国家試験の受験資格を得られます。
就労継続支援B型では、利用者さんの指導や生活面の相談に応じる役割として、社会福祉士が多く活躍しています。就労継続支援B型で相談支援もしくは直接支援を経験し、所定の研修を修了すれば、サービス管理責任者になることが可能です。
精神保健福祉士
精神保健福祉士は、福祉職の国家資格で、精神に障害がある方の社会復帰や自立した生活を支援する専門職です。福祉系大学などで所定の科目を履修するなどして、国家試験を受験し合格すると、資格を取得することができます。
就労継続支援B型の利用者さんのなかには、精神に障害がある方もいるため、精神保健福祉士の資格が役立つ場面も多くあります。
社会福祉士と同様に、実務経験を積んで研修を修了することで、サービス管理責任者を目指すことが可能です。
社会福祉主事
社会福祉主事は、社会福祉の業務に関わる任用資格です。社会福祉主事の資格は、大学などで社会福祉に関する科目を収めて卒業するか、養成機関や講習会で課程を修了するなどの方法で、取得することができます。
職業指導員や生活指導員として働き、指導や相談の役割を担えます。社会福祉主事も、社会福祉士や精神保健福祉士と同様に、経験を積んで研修を修了することで、サービス管理責任者を目指すことができます。
介護福祉士
介護福祉士は、介護に関する専門的な知識や技術を持つ専門職で、介護業務に従事する職種のなかでは唯一の国家資格です。養成機関で学ぶか、実務経験を積むことで、国家試験の受験資格が得られます。国家試験に合格すると介護福祉士の資格を取得することができます。
就労継続支援B型では、直接的な介護に携わることは少ないものの、職業指導員や生活支援員として、介護福祉士資格を持つ人も多く活躍しています。経験を積んで研修を修了すれば、前述の資格と同様にサービス管理責任者になることができます。
初任者研修及び実務者研修
初任者研修及び実務者研修は、介護の知識や技術を学ぶ資格です。どちらの資格も受講要件はなく、誰でも取得することができます。実務者研修は、介護福祉士試験の受験要件でもあるため、将来的に介護福祉士資格の取得を視野に入れているのであれば、取得するのをおすすめします。
就労継続支援B型では、初任者研修や実務者研修の修了者は生活支援員や職業指導員として活躍していることが多いでしょう。
10.就労継続支援B型で働く職員の給料

厚生労働省が提供している日本版O-NETによると、生活支援員、就労支援員等の障害福祉施設指導員全体の給与平均月収は、21.5万円です。この額は障害福祉施設指導員全体であるため、夜勤がある施設職員も対象となっています。就労継続支援B型の職員は夜勤がないため、給与平均月収は少し下がる可能性があります。管理者やサービス提供責任者の場合は、手当がつく事業所が多いでしょう。
ただし、介護職の処遇改善については障害分野も同様に行われているため、今後も処遇改善は進んでいくと思われます。月収も今後アップする可能性があるでしょう。
(参照:障害者福祉施設指導専門員(生活支援員、就労支援員等)|職業情報提供サイトjobtag、処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)|厚生労働省)
11.就労継続支援B型で働くには?

就労継続支援B型の事業所で働くには、どうしたらよいのでしょうか。就労継続支援B型の事業所では、未経験でも募集がかかっていることがあります。特に、職業指導員や生活支援員は、未経験でも募集されている可能性が高い職種です。
未経験者がこれから就労継続支援B型で働きたいなら、介護資格を取得するのも一つの方法といえます。介護資格の「初任者研修」や「実務者研修」は受講要件がないため、障害分野や福祉分野での経験がない人でも取得しやすい資格です。就労継続支援B型での就労を考えている場合は、初任者研修や実務者研修の取得に挑戦してみてはいかがでしょうか。
一方、日中活動系や施設系など障害福祉サービスの別分野での経験や、初任者研修や実務者研修などの介護系資格があると、採用試験時のアピールポイントになるでしょう。障害分野以外でも、病院や介護施設などで働いた経験が、採用時に有利に働くケースもあります。
まとめ:就労継続支援B型は利用者さんが障害や体調に合わせて働ける障害福祉サービス

就労継続支援B型は、利用者さんの障害や体調に合わせて無理なく働ける障害福祉サービスです。職員は、利用者さんの希望や適正に合わせて、職業訓練や指導だけでなく、生活面の相談などを担います。就労継続支援B型では、利用者さんの働きたいという意欲を引き出すための支援が行えるため、やりがいも感じられるのではないでしょうか。就労継続支援B型は、未経験者の募集がある事業所もあります。これから障害福祉分野で活躍したいのであれば、就労継続支援B型の事業所も検討してみるといいでしょう。
【日本全国電話・メール・WEB相談OK】介護職の無料転職サポートに申し込む
スピード転職も情報収集だけでもOK
マイナビ介護職は、あなたの転職をしっかりサポート!介護職専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを行います。
はじめての転職で何から進めるべきかわからない、求人だけ見てみたい、そもそも転職活動をするか迷っている場合でも、キャリアアドバイザーがアドバイスいたします。

SNSシェア














