障害者グループホームとは?種類や条件、対象者などを徹底解説!
文/中村 楓(介護支援専門員・介護福祉士・介護コラムニスト)
障害者グループホームとは、障害を持つ人が共同生活を行う住居のことです。利用者が集団生活を送りながら、自立した生活を行うために必要なトレーニングを実施します。障害者グループホームでは、主に夜間職員から必要なサービスを受けますが、日中も受けられるところやホーム内で介護サービスを受けられるところもあります。
本記事では、障害者グループホームの概要や利用するメリット・デメリット、利用に向いている人についてお伝えするとともに、障害者グループホームの種類や利用条件、費用について解説します。加えて、障害者グループホームで働く職員の仕事内容や必要なスキルについて紹介します。
- 目次
- 1.障害者グループホームとは?
- 障害者グループホームを利用するメリット・デメリット
- 障害者グループホームの利用が向いている人
- 2.障害者グループホームの種類
- 介護サービス包括型
- 日中サービス支援型
- 外部サービス利用型
- サテライト型
- 3.障害者グループホームの利用条件
- 入居制限
- 利用の流れ
- 4.障害者グループホームの対象者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 身体障害者
- 5.障害者グループホームにかかる費用
- 6.障害者グループホームで働く職員の仕事内容
- 世話人
- サービス管理責任者
- 生活支援員
- 7.障害者グループホームの業務で役立つスキルや経歴、資格
- 業務で役立つスキルや経歴
- 業務で役立つ資格
- まとめ:障害者グループホームは障害者の自立を支援するサービス
1.障害者グループホームとは?

障害者グループホームとは、障害のある人が自立した生活を送るために必要な支援を受けながら共同生活を送る施設です。障害福祉サービスの1つで、正式名称は「共同生活援助」といいます。
障害者グループホームでは、相談や日常生活上の援助のほか、必要に応じて介護を受けることもできます。住居には、戸建てタイプやアパート・マンションタイプ、同性専用型や男女混合型があり、それぞれに以下のような設備が設けられています。
- 個室住居
- 居間・食堂
- トイレ
- 風呂
入居者数は、4名程度の小規模のものから、10名以上の大規模なものまでさまざまです。障害者グループホームを利用するメリットやデメリットにはどのようなものがあるでしょうか。また、どのような人が障害者グループホームに向いているのでしょうか。それぞれについて、詳しくみていきましょう。
障害者グループホームを利用するメリット・デメリット
障害者グループホームを利用するメリットには、以下のようなものがあります。
- ほかの利用者と関わることができる。
- 自立を目指したサポートが受けられる。
- 金銭の管理のサポートが受けられる。
- 服薬管理をしてもらえる。
- 食事の提供を受けられる。
一方で、グループホームを利用する際のデメリットには、以下のようなものがあります。
- 共同生活におけるルールを守らなければならない。
- 環境に適応できないことがある。
- 利用料金がかかる。
障害者グループホームを利用する場合は、メリットとデメリットを把握し、自身に合った住居環境を検討することが大切です。
障害者グループホームの利用が向いている人
障害者グループホームのメリット・デメリットを踏まえると、利用が向いているのは、以下のような人となります。
- 一人暮らしを検討しているが、いきなりの一人暮らしに不安がある人
- 自立に向けて訓練したい人
- ルールが守れて他者と協力できる人
- 住み慣れた地域から離れたくない人
- 仲間や友人を作りたい人
障害者グループホームの利用には向き・不向きがあります。そのため、自身の性格や目的を明確にしてから、障害者グループホームを利用するかを検討しましょう。
2.障害者グループホームの種類

障害者グループホームには、以下の4種類があります。
介護サービス包括型
介護サービス包括型の障害者グループホームは、主に夜間や休日に相談や介護、日常生活上の援助を提供する施設です。介護が必要な利用者さんについては、グループホームの従業者が介護サービスを提供します。
厚生労働省の「共同生活援助(介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型)に係る報酬・基準について」によると、令和2年4月サービス提供分実績では、介護サービス包括型の事業者数は7,718件、利用者数は114,554人で、最も多いグループホームとなっています。
日中サービス支援型
日中サービス支援型の障害者グループホームは、昼夜を通じて1人以上の職員が配置されており、夜間だけでなく日中も相談や介護、日常生活上の援助を提供する施設です。介護が必要な利用者さんについては、グループホームの従業者から常時介護サービスを受けることができます。
日中サービス支援型の事業者数は、令和2年4月サービス提供分実績では182件、利用者数は2,344人と最も少なくなっています。ただし、日中サービス支援型は平成30年4月に施行された障害者総合支援法の改正に伴った創設されたものです。そのため、事業者数はまだまだ少ないものの、今後広がりが期待されるといえるでしょう。
外部サービス利用型
外部サービス利用型の障害者グループホームは、主に夜間や休日に相談や日常生活上の援助を提供する施設です。日中は、利用者さんの就労先や日中活動サービスなどの外部の事業所を利用します。
介護サービスが必要な場合は、委託契約を結んだ介護事業所のヘルパーが介護サービスを提供するため、グループホームの職員が介護サービスに従事することはありません。
外部サービス利用型の事業者数は、令和2年4月サービス提供分実績では1,321件、利用者数は15,551人となっています。
サテライト型
地域生活への移行を目指している障害者や、すでにグループホームを利用している人の中には、単身での生活を望んでいる人もいます。一人で暮らしたいというニーズにもこたえたのが、サテライト型の障害者グループホームです。そのため、サテライト型は単身での生活が可能な人が対象となっています。
サテライト型は、一人暮らしに近い形態で、居間や食堂などの設備は本体住居の設備を利用します。そのため、サテライト型のグループホームは、本体住居からおおむね20分以内で移動ができる距離に住居があります。
厚生労働省「障害者の居住支援について」によると、2019年10月1日現在のサテライト型の事業所数は1,551件となっています。
3.障害者グループホームの利用条件

障害者グループホームは、障害支援区分に関わらず利用が可能です。ただし、自治体によっては、利用条件が設定されているところもあります。障害者グループホームの入居制限や利用の流れについて、詳しくみていきましょう。
入居制限
障害者グループホームには、入居制限は原則ありません。ただし、事業所によっては、一部入居期限などを設けているところもあります。実際に利用を検討する場合は、希望する事業所に制限について確認するようにしましょう。
利用の流れ
障害者グループホームを利用する流れは次のようになります。
1. 障害者福祉サービスの支給の申請
障害者グループホームは障害福祉サービスの1つであるため、障害者福祉サービスの申請をする必要があります。市区町村の窓口に申請をし、障害者福祉サービスの受給者証を発行してもらいましょう。グループホームの場合、障害支援区分の認定が必要になることもありますので、申請の際に確認し、必要であれば区分認定を受けましょう。
2. 入居を希望する障害者グループホームの検討
受給者証の発行と区分認定が出るまでには時間がかかるため、その間に入居を希望する障害者グループホームの検討をしましょう。気になるグループホームは、実際に見学して施設の雰囲気を確認しておきます。見学の際には、費用やサービスについて具体的に聞いておきましょう。
3. 個別支援計画の作成
グループホームの利用には個別支援計画の作成が必要です。相談支援事業所に依頼して、相談支援専門員に計画書を作成してもらいましょう。
4. 障害者グループホームと契約
計画書が作成されると、いよいよ障害者グループホームとの契約になります。契約が済むと、入居が可能となります。
4.障害者グループホームの対象者
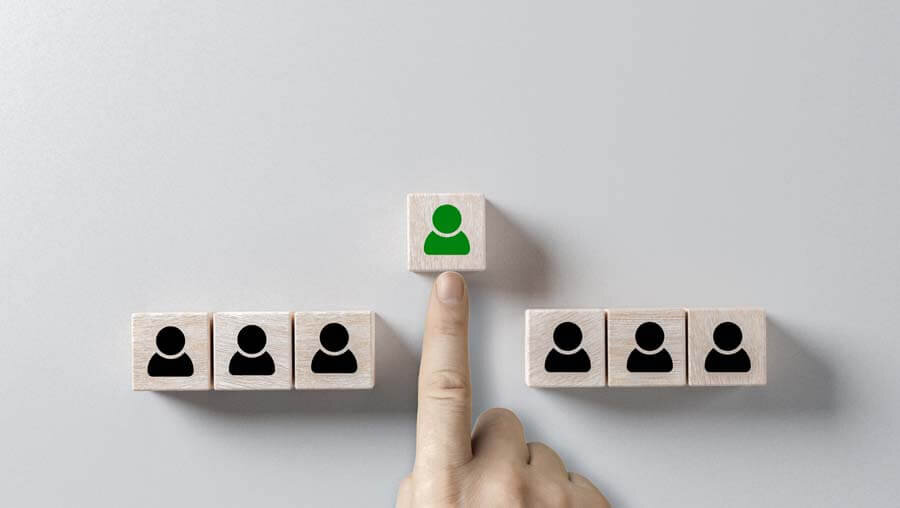
障害者グループホームの対象者には、知的障害者、精神障害者、身体障害者が該当します。身体障害者の場合、65歳未満の人、もしくは65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス、もしくはこれに準ずるものを利用したことがある人に限られています。ここでは、対象者ごとの利用状況について詳しくみていきましょう。
知的障害者
知的障害者とは、金銭管理や読み書き、計算など、日常生活において頭脳を使う知的行動に支障があり、特別な支援や配慮が必要な状態にある人のことをいいます。独立行政法人福祉医療機構が行った「2021年度共同生活援助に関するアンケート調査」によると、知的障害によって施設を利用している人数は、障害者グループホームすべてを合算し、5,864人が利用との回答でした。介護サービス包括型の約8割が知的障害者となっています。
精神障害者
精神障害者とは、精神疾患のために精神機能に障害が生じて、日常生活や社会参加に困難をきたしている状態にある人をいいます。「2021年度共同生活援助に関するアンケート調査」では、精神障害によって施設を利用している人数は、1,074人でした。障害者グループホームのうち、外部サービス利用型はほかの分類に比べ精神障害者の割合が多くなっています。
身体障害者
身体障害者とは、身体上の障害がある人のことをいいます。身体障害者福祉法によると、以下に掲げる身体上の障害がある18歳以上で、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた人となっています。
① 視覚障害
② 聴覚または平衡機能の障害
③ 音声機能、言語機能または咀嚼機能の障害
④ 肢体不自由
⑤ 内部障害
「2021年度共同生活援助に関するアンケート調査」によると、身体障害によって施設を利用している人数は567人で、知的障害者や精神障害者より少なくなっています。
5.障害者グループホームにかかる費用

障害者グループホームを利用する場合には、以下のような費用がかかります。
- 障害者総合支援法による利用者負担額
- 運営主体が定めた入居料
- 食費
- 日用品費
- 光熱水費
このうち、利用者負担額は、生活保護もしくは低所得の場合0円、その他の場合は37,200円が月額上限額となります。入居料については、利用者1人あたり月額1万円を上限に家賃助成を受けることができます。
食費は、月額が決まっている施設と1食あたりの金額提示の場合があり、月額料金であっても食事数で計算しているグループホームもあります。日用品や光熱水費についても、実費または月額での請求があり、グループホームによってさまざまです。詳細については、実際に入居する施設に確認するようにしましょう。
6.障害者グループホームで働く職員の仕事内容

障害者グループホームでは、以下のような職種の人が働いています。
世話人
世話人とは、障害者グループホームの利用者さんに日常生活上の援助や人間関係の調整を行う職種です。日常生活上の援助では、主に以下のような支援を行います。
- 食事の提供
- 家事のサポート
- 金銭管理
- 健康・服薬管理
- 生活相談
- 余暇利用・地域活動への助言
利用者間の人間関係の調整では、以下のような支援が実施されます。
- 入浴の順番や夕食時間等の生活面の共同ルールを利用者同士の合意で決めるよう誘導
- 利用者さん同士の対人関係トラブルへの介入・調整
なお、世話人は介護には従事しません。
世話人は、障害者グループホームの種類によって配置規定があります。介護サービス包括型の場合は利用者6人に対し1人以上、外部サービス利用型の場合も同様ですが、当面は10人に対し1人でも可能となっています。日中サービス支援型の場合は利用者5人以上に対し1人以上が必要です。
参照:共同生活援助(介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型)に係る報酬・基準について|厚生労働省
参照:障害者グループホーム世話人|厚生労働省
サービス管理責任者
サービス管理責任者は、障害者グループホームで個別支援計画の作成やアセスメント、日中活動先との連絡調整などを行う職種です。サービス管理責任者になるためには、障害における実務経験が5~10年あり、所定の研修を修了しなければなりません。障害者グループホームでは、利用者さん30人に対し1人以上のサービス管理責任者が必要です。
参照:障害福祉サービスにおけるサービス管理責任者について|厚生労働省
生活支援員
生活支援員とは、障害者グループホームの利用者さんに対して介護を行う職種です。障害者グループホームでは、利用者さんの障害支援区分に応じて利用者さん2.5~9人に対し1人以上の生活支援員が必要となります。ただし、外部サービス利用型の場合、介護は外部の事業所に委託となるため、人員配置基準はありません。
参照:生活支援員|WAM-NET
参照:共同生活援助(介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型)に係る報酬・基準について|厚生労働省
7.障害者グループホームの業務で役立つスキルや経歴、資格

障害者グループホームの職員のうち、世話人や生活支援員は特段の資格は必要ありません。しかし、次のような経験やスキルがあると、仕事に生かすことができます。
業務で役立つスキルや経歴
障害者グループホームでは、調理や洗濯、掃除等の家事全般を行うことが多いため、これらが苦にならない人や、家事に一定のスキルがある人のほうがよいでしょう。また、障害のある人が利用する施設であるため、障害者に関する知識や理解が必要です。介護や福祉に関する経歴があると、仕事がしやすいでしょう。具体的には、介護や障害分野における介護職や生活支援員としての経歴があると役立ちます。
業務で役立つ資格
障害者グループホームの業務に役立つ資格には、以下のようなものがあります。
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 看護師
- 介護福祉士
- 初任者研修
- 実務者研修
- 特別支援学校の教員
サービス管理責任の資格取得を目指す場合は、障害者の保健・福祉・就労・教育の分野における直接支援や相談支援などの業務における実務経験が5~10年、相談支援従業者初任者研修とサービス管理責任者研修の2つの研修を修了する必要があります。
まとめ:障害者グループホームは障害者の自立を支援するサービス

障害者グループホームは、障害を持つ人が自立した社会生活を送るためのトレーニングを、集団生活を送りながら行う障害福祉サービスです。障害者グループホームの世話人や生活支援員は、資格や経験がなくても働けます。障害者の自立支援に興味がある人は、障害者グループホームの職員になることも検討してみてはいかがでしょうか。
スピード転職も情報収集だけでもOK
マイナビ介護職は、あなたの転職をしっかりサポート!介護職専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを行います。
はじめての転職で何から進めるべきかわからない、求人だけ見てみたい、そもそも転職活動をするか迷っている場合でも、キャリアアドバイザーがアドバイスいたします。

SNSシェア















