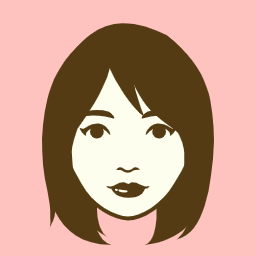産業カウンセラーと精神保健福祉士の違い|仕事内容や資格を解説
構成・文/介護のみらいラボ編集部 監修/渡辺有紀
現代社会はストレス社会とも呼ばれており、多くの人が心に悩みや不安を抱えています。そして、仕事や人間関係、金銭問題といったさまざまなストレスから、精神に不調をきたす人も、決して少なくありません。
そうしたなか、精神に不調を持つ人たちに寄り添い、適切なメンタルケアを行う専門職の必要性が増しており、活躍の場も徐々に広がっています。例えば、産業カウンセラーや精神保健福祉士も、注目度が高まっている専門職の1つ。精神保健福祉士というと、病院や行政機関(保健所、福祉事業所、精神保健福祉センターなど)に勤務するイメージが強いかもしれませんが、近年は企業でメンタルケアやサポートを行う精神保健福祉士も増えています。
そこで今回は、役割や仕事内容が混同されやすい産業カウンセラーと精神保健福祉士をピックアップし、具体的な仕事内容や資格取得の方法などを解説します。資格取得を目指している方や、メンタルケアの専門職に興味のある方は、ぜひご覧ください。
1.産業カウンセラーと精神保健福祉士の違いは?
競争の激しい現代社会において、仕事にストレスは付き物です。しかし、仕事へのプレッシャーや職場の人間関係などによる過度なストレスは、メンタル不調の引き金にもなりかねません。そのため近年は、産業カウンセラーや精神保健福祉士が果たす役割に関心を寄せる企業や学校、役所なども増えています。
産業カウンセラーと精神保健福祉士は、どちらも精神に不調をきたした人のサポートが主な業務となるため、混同されやすい傾向にありますが、両者の仕事内容や資格の取得方法には違った特徴があります。
まずは、それぞれの仕事内容について詳しく解説しましょう。
産業カウンセラーの仕事内容
産業カウンセラーは、「一般社団法人日本産業カウンセラー協会」が認定する民間資格およびその有資格者です。活躍の場は、企業の他に、学校や役所、病院、診療所、各種団体など、多方面にわたります。
産業カウンセラーの活動領域は、主に以下の3つに分けられます。
・メンタルヘルス対策
産業カウンセラーの基本業務です。個別のカウンセリングや監督者への研修などを通して、仕事の質・量、ハラスメントといったさまざまなストレスに対する予防方法やコントロール方法の提案を行います。
・キャリア形成
近年は、働く人たちの仕事意識や働き方が多様化しており、キャリア形成に対する支援の必要性も高まっています。そのため、「上質な職業生活(Quality of Working Life)を実現する」という視点から、進路や職業の選択、キャリアビジョンなどに悩む相談者を支援することも、産業カウンセラーの役割となります。
・人間関係開発・職場環境改善
働きがいのある職場、働きやすい職場を作るには、人間関係の開発や職場環境の改善も必須の要素です。産業カウンセラーは、個々の成長を促す人間関係育成の援助を行ったり、組織診断に基づいた職場環境の整備を提案したりすることで、いきいきと働ける組織作りに貢献します。
(出典:一般社団法人日本産業カウンセラー協会「産業カウンセラーとは」)
精神保健福祉士の仕事内容
精神保健福祉士は、精神保健福祉士法に基づく国家資格です。「精神的な障害や心の病・悩みを抱えた人たちの日常生活や社会復帰を援助すること」が主な役割で、障害の特性や周囲の環境を踏まえながら、課題を解決するための情報提供や助言・指導、社会資源(制度、施設など)との連携、必要な訓練などを行います。
活躍の場は医療機関や障害者施設、自立訓練事業所、保健センターなど幅広く、約半数が相談員や指導員として働いています。
(出典:厚生労働省「精神保健福祉士について」)
なお、企業で働く精神保健福祉士は、「産業ソーシャルワーカー」と呼ばれます。主な仕事内容は従業員のメンタルケアで、仕事や職場環境・人間関係によるストレスや、ワークライフバランス、プライベートについての相談を受けたり、アドバイスを行ったりします。
2.産業カウンセラー・精神保健福祉士になるには?
産業カウンセラーや精神保健福祉士になるには、それぞれ資格が必要です。2つの資格の大きな違いは、産業カウンセラーが民間資格であるのに対して、精神保健福祉士は国家資格である点です。ここでは、それぞれの資格の取得方法について、詳しく解説します。
産業カウンセラー資格の取得方法
産業カウンセラーの資格試験を受けるには、以下の受験資格を満たす必要があります。
・産業カウンセラーの養成講座を修了
・大学院で心理学か心理学隣接諸科学、人間科学、人間関係学のいずれかの課程を修了、特定の科目を取得
※社会人経験がある場合、必要となる科目数が減る
・4年制大学で特定の科目の単位を取得後、卒業
(出典:一般社団法人日本産業カウンセラー協会「産業カウンセラー試験」)
産業カウンセラーの養成講座は、講義動画の視聴による理論学習と、スクーリングによる体験学習の二本立てです。理論学習ではカウンセリングの理論や方法、心理学、精神医学といった基礎的な内容から、産業カウンセラーの活動領域までを幅広く学び、体験学習ではカウンセリングの演習などを行います。
(出典:一般社団法人日本産業カウンセラー協会東関東支部「産業カウンセラーになりませんか?」)
なお、2022年度における資格試験の合格率は、学科試験が65.0%、実技試験が61.1%、総合すると58.4%でした。例年同程度の合格率となっているため、学科と実技はそれぞれ65%前後、総合すると60%前後と考えておくと良いでしょう。
(出典:一般社団法人日本産業カウンセラー協会「合否結果について」)
精神保健福祉士資格の取得方法
精神保健福祉士の資格試験を受けるには、以下の5つのルートがあります。
保健福祉系の大学・短大等のルート
・4年制大学等で指定科目を履修
・短大等の場合は指定科目履修後、在学期間と合わせて4年になるように相談援助実務にあたる
福祉系の大学・短大等のルート
・4年制大学で基礎科目を履修後、短期養成施設で指定科目を修得(6カ月以上)
・短大等の場合は基礎科目履修後、在学期間と合わせて4年になるように相談援助実務に就き、短期養成施設等で指定科目を修得(6カ月以上)
一般大学・短大等のルート
・4年制大学を卒業後、一般養成施設等で基礎科目と指定科目を修得(1年以上)
・短大等の場合は卒業後、在学期間と合わせて4年になるように相談援助実務に就き、一般養成施設等で基礎科目と指定科目を修得(1年以上)
社会福祉士登録者のルート
短期養成施設等で指定科目を修得(6カ月以上)
4年以上の実務経験者のルート
一般養成施設等で基礎科目と指定科目を修得(1年以上)
(出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「精神保健福祉士国家試験」)
2022年3月に行われた精神保健福祉士の国家試験の合格率は、65.6%でした。ここ数年は62〜65%ほどで推移しており、合格ラインは「問題の総得点の60%程度を基準として、問題の難易度で補正した点数(ただし、受験したすべての試験科目群で得点が必要)」とされています。
(出典:厚生労働省「第24回精神保健福祉士国家試験の合格発表を実施します」)
3.産業カウンセラーと精神保健福祉士、どちらを目指すべき?
企業で働く産業カウンセラーと精神保健福祉士は、「従業員のメンタルヘルスの維持や改善をサポートする」という点で共通していますが、アプローチの方法が異なります。ポイントとなるのは、産業カウンセラーが相談者の気持ちに寄り添う「心理的支援」をメインとしているのに対して、精神保健福祉士は具体的なトラブルの解決による「生活課題に対する支援」がメインである点です。
もし、どちらかの資格の取得を考えているのなら、仕事内容や働き方はもちろん、資格取得のしやすさも考慮する必要があるでしょう。
社会人でも資格が取りやすいのは産業カウンセラー
社会人でも資格が取りやすいのは、国家資格の精神保健福祉士よりも、民間資格の産業カウンセラーです。精神保健福祉士は国家資格であるがゆえに受験資格が複雑で、学歴によっては資格を得るまでに数年の時間を要するため、受験のハードルは決して低くありません。
一方の産業カウンセラーは、企業で働きながら資格取得を目指す方も多く、精神保健福祉士より気軽に挑戦できます。そのハードルの低さから、資格取得よりも傾聴などの技能習得を目的として、勉強に取り組む方も少なくありません。ただし、大学や大学院で特定の科目を取得していない場合は、受験資格を得るために養成講座の受講が必須となります。
産業保健分野で幅広く活躍するには精神保健福祉士
企業などで働く産業カウンセラーのメイン業務は、労働者の心理的サポートです。一方、精神保健福祉士の仕事内容は、より多岐にわたります。その1つが、2015年に施行された、企業におけるストレスチェックの「実施者」としての業務です。
ストレスチェックの制度は、厚生労働省の法令によって定められており、産業カウンセラーは実施者になれません。精神保健福祉士が産業医(医師)や保健師(看護師)と並んで実施者に認定されたのは、医療や福祉の現場で活躍してきた実績によるもので、今後も産業保健の現場に、精神保健福祉士ならではの役割が設けられる可能性があります。
ダブルライセンスのメリット
産業カウンセラーと精神保健福祉士の資格を両方取得すれば(ダブルライセンス)、それぞれの資格の強みをより活かすことができるため、精神的な不調を抱えた相談者を多角的に支援できるでしょう。
ストレスチェックについても、実施者は精神保健福祉士に限られますが、実施後の面談や相談対応といった補助的業務は産業カウンセラーが行います。ダブルライセンスがあれば、実施から事後対応に至るまで、ストレスチェックを1人で担当できるため、企業や各種団体においてより貴重な人材となれるでしょう。
まとめ
企業に所属する精神保健福祉士と産業カウンセラーの主な仕事は、従業員の心理的サポートです。ただし、産業カウンセラーは「心理面」に強く、精神保健福祉士は「生活面」の支援に強いという点に特徴があります。また、産業カウンセラーは民間資格、精神保健福祉士は国家資格であるため、資格を取得する方法も異なります。どちらの資格にも、大きな魅力とメリットがあるため、ダブルライセンスを検討してみるのもおすすめです。
「介護のみらいラボ」では、介護の仕事に役立つ知識やスキルアップのノウハウ、職場におけるお悩み相談など、介護の現場で活躍する人たちに日々有益な情報を提供しています。介護の仕事をするなかで、困ったことや気になること、知りたいことがあれば、ぜひ「介護のみらいラボ」をチェックしてください。
※当記事は2022年7月時点の情報をもとに作成しています
【日本全国電話・メール・WEB相談OK】介護職の無料転職サポートに申し込む
スピード転職も情報収集だけでもOK
マイナビ介護職は、あなたの転職をしっかりサポート!介護職専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを行います。
はじめての転職で何から進めるべきかわからない、求人だけ見てみたい、そもそも転職活動をするか迷っている場合でも、キャリアアドバイザーがアドバイスいたします。

SNSシェア