介護福祉士国家試験の内容は?新出題基準・実技試験免除の条件・合格ポイントも詳しく解説
文/福田明(松本短期大学介護福祉学科教授)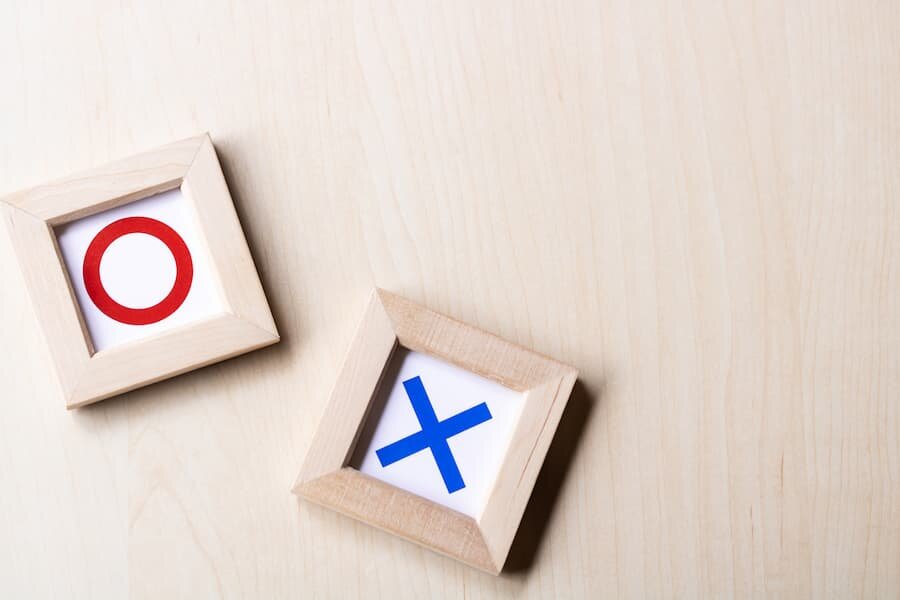
介護福祉士は、日本で唯一の介護系の国家資格です。ここでは、介護福祉士国家試験の全体像を紹介したうえで、筆記試験と実技試験の内容、実技試験免除の条件、筆記試験の新出題基準、合格するためのポイントなどを解説していきます。
- 目次
- 1.介護福祉士国家試験の全体像
- 介護福祉士とは?
- 介護福祉士国家試験の内容
- 2.介護福祉士国家試験の筆記試験
- 筆記試験の内容
- 筆記試験に適用された新出題基準
- 試験科目別に見る新出題基準のポイントとは? 追加・強化された内容を確認しよう!
- 3.介護福祉士国家試験の実技試験
- 実技試験の内容
- 実技試験当日の流れ
- 4.実技試験が免除になる条件とは? 4つの資格取得ルートごとに確認しよう!
- ① 養成施設ルート
- ② 実務経験ルート
- ③ 福祉系高校ルート
- ④ 経済連携協定(EPA:Economic Partnership Agreement)ルート
- 5.介護福祉士国家試験の合格基準
- 筆記試験の合格基準 2つの条件とは?
- 実技試験の合格基準
- 6.介護福祉士国家試験の合格率と難易度
- 7.介護福祉士国家試験に合格するためのポイントとは?
- 筆記試験の合格に向けた5つのポイント
- 実技試験の合格に向けた6つのポイント
- まとめ
1.介護福祉士国家試験の全体像
介護福祉士とは?
国家資格である介護福祉士は、専門的知識・技術をもって一人ひとりの利用者の状況に応じた介護を提供する専門職です。介護が必要な高齢者の増加、あるいは家族介護の限界といった介護問題が浮上するなか、「社会福祉士及び介護福祉士法」にもとづいて、1987(昭和62)年に創設されました。介護福祉士の資格があれば、就職・転職が有利になるだけでなく、給与アップも期待できます。ただし、介護福祉士になるためには、介護福祉士国家試験に合格して登録手続きを行う必要があります。
介護福祉士国家試験の内容
介護福祉士国家試験は、1989(平成元)年に第1回試験が実施され、以後、毎年1回実施されています。介護福祉士国家試験には筆記試験と実技試験がありますが、受験資格の取得方法(資格取得ルート)によっては実技試験がなく、筆記試験のみで合否が決まります。また、実技試験は筆記試験が合格基準に達した場合に受験することが可能です。
介護福祉士国家試験の試験科目と試験時間
| 試験の種類 | 筆記試験 | 実技試験 |
|---|---|---|
| 試験日 | 1月下旬 (日曜日) | 3月上旬 (日曜日) |
| 試験地 | 全国35試験地 ※第36回 | 東京都 ・ 大阪府 |
| 試験科目 | 13科目 | 介護等に関する専門的技能 |
| 試験時間 | 午前問題100分 / 午後問題120分 | 5分以内 |
| 総得点 | 125点 | 100点 |
| 受験申し込み受付期間 | 試験前年の8月上旬~9月上旬 | |
| 受験手数料 | 18,380円 ※第36回 | |
| 合格発表 | 3月下旬 | |
公益財団法人社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験 試験概要をもとに筆者作成。
2.介護福祉士国家試験の筆記試験
筆記試験の内容
筆記試験は、午前と午後に分かれており、5領域13科目から計125問が出題されます(1問1点で計125点満点)。午前は「人間と社会」「こころとからだのしくみ」「医療的ケア」の3領域から63問、午後は「介護」「総合問題」の2領域から62問が出題されます。特に「介護の基本」「コミュニケーション技術」「生活支援技術」「介護過程」の4科目から構成される「介護」領域は全体の40%(50問)を占めており、合否を左右する重要な領域といってよいでしょう。なお、「総合問題」では長文4事例が出題され、各領域の知識・技術が横断的に問われます。
筆記試験では、人間の尊厳や人権、介護保険制度、障害者総合支援法などの法制度、心身の仕組みや発達段階、認知症といった病気・障害のこと、介護福祉士の役割とその支援方法など、問われる内容が多岐にわたります。問題には図や表、グラフが用いられる場合もあります。
出題形式は5肢択一を基本とするマークシート方式です。具体的には問題を読み、5つの選択肢のなかから「最も適切なもの」「適切なもの」「正しいもの」「最も優先すべきもの」を1つ選ぶタイプの設問方法となります。
介護福祉士国家試験の概要
| 試験時間 | 領域 | 試験科目 | 出題数 | |
|---|---|---|---|---|
| 午前問題 計63問 10:00~11:40(100分) | 人間と社会 | 1 | 人間の尊厳と自立 | 2問 |
| 2 | 人間関係とコミュニケーション | 4問 | ||
| 3 | 社会の理解 | 12問 | ||
| こころとからだのしくみ | 4 | こころとからだのしくみ | 12問 | |
| 5 | 発達と老化の理解 | 8問 | ||
| 6 | 認知症の理解 | 10問 | ||
| 7 | 障害の理解 | 10問 | ||
| 医療的ケア | 8 | 医療的ケア | 5問 | |
| 午後問題 計62問 13:35~15:35(120分) | 介護 | 9 | 介護の基本 | 10問 |
| 10 | コミュニケーション技術 | 6問 | ||
| 11 | 生活支援技術 | 26問 | ||
| 12 | 介護過程 | 8問 | ||
| 総合問題 | 13 | 総合問題 | 12問 | |
公益財団法人社会福祉振興・試験センター「第36回介護福祉士国家試験『受験の手引き』をもとに筆者が作成。
筆記試験に適用された新出題基準
2023(令和5)年1月に実施された第35回試験からは、2019(令和元)年に導入された介護福祉士養成課程の新カリキュラムの内容を踏まえた、新たな出題基準が適用されています。
なかでも、介護職の中核的な存在としての素養を高めることを目的に、「人間関係とコミュニケーション」にリーダーシップやフォロワーシップ、PDCAサイクル、コンプライアンス、OJT(On the Job Training)といった、チームマネジメントに関する内容が追加されたことは注目に値するでしょう。
また、新出題基準では、「生活支援技術」のなかで福祉用具の位置づけが格上げされています。そのため、杖や歩行器、車いすだけでなく、スライディングボートや段差解消機、移乗台、浴槽設置式リフト、床走行式リフトなど、多種多様な福祉用具に関する出題を想定しておくのがよいでしょう。
ちなみに新出題基準の詳細は、公益財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページで確認できます。
試験科目別に見る新出題基準のポイントとは? 追加・強化された内容を確認しよう!
ここでは、新出題基準で追加または強化された内容を確認するため、試験科目別に出題基準の主な異同状況(変更された点と同じ点)を示します。以前の出題基準と何が変わったのかを把握し、筆記試験対策に活用してください。
試験科目別に見る新出題基準のポイント
| 試験科目 | 出題基準の主な異同状況 |
|---|---|
| 人間の尊厳と自立 | ほぼ同じ➡ノーマライゼーション、QOL、自立、アドボカシー、権利擁護等 |
| 人間関係とコミュニケーション | 追加➡グループダイナミクス、対人関係とストレス、相談面接の基礎(マイクロカウンセリング、感情の転移・逆転移等) 追加➡チームマネジメント(介護実践とマネジメント、福祉サービス提供組織の機能と役割、コンプライアンス、業務課題の発見と解決の過程、リーダーシップ、フォロワーシップ、OJT、Off-JT、SDS、ティーチング、コーチング等) |
| 社会の理解 | 強化➡地域共生社会の実現に向けた制度や施策(地域福祉、ソーシャル・インクルージョン、多文化共生社会、地域包括ケア等) 追加➡社会保障の実施運営体制(社会福祉事務所、保健所等)、社会保障費用の適正化・効率化、地方分権、社会保障構造改革 追加➡高齢者福祉の動向(高齢者の現状、支援者の状況) 強化➡介護保険制度の財源と利用者負担、サービス事業者・施設、地域支援事業、地域包括支援センター、地域ケア会議、ケアマネジメントと介護支援専門員等 追加➡障害者の定義(障害児・者の法的定義、障害別の法的定義) 強化➡障害者総合支援法のサービス事業者・施設、地域生活支援事業、地域での実態体制(協議会等)、ケアマネジメントと相談支援専門員等 追加➡児童虐待防止法、DV防止法 強化➡地域生活を支援する制度(バリアフリー法、高齢者住まい法、日常生活自立支援事業、災害時要配慮者支援等) 追加➡薬剤耐性対策、生活困窮者自立支援法 |
| 介護の基本 | 追加➡介護福祉士資格取得者の状況 強化➡ストレングス、アクティビティ・サービス、就労支援、多職種連携・協働、チームアプローチ 追加➡薬剤の取り扱いに関する基礎知識と連携(服薬管理の基礎知識、薬剤耐性の知識) |
| コミュニケーション技術 | 強化➡介護職チーム内のコミュニケーション、多職種チームとのコミュニケーション |
| 生活支援技術 | 追加➡シーティング、アドバンス・ケア・プランニング、デスカンファレンス 追加➡福祉用具(福祉用具が活用できる環境整備、個人と用具のフィッティング、福祉用具利用時のリスクマネジメント、福祉用具と介護保険制度・障害者総合支援法、移動支援機器、介護ロボット等) |
| 介護過程 | ほぼ同じ(介護過程の意義・目的、介護過程の展開、ケアプラン、サービス担当者会議等) |
| こころとからだのしくみ | 追加➡健康の概念(WHOの定義)、アドバンス・ケア・プランニング |
| 発達と老化の理解 | 強化➡老化に伴う心身の変化の特徴(予備力、防衛力、回復力、適応力、恒常性機能、フレイル等) 追加➡サクセスフルエイジング、プロダクティブエイジング、アクティブエイジング |
| 認知症の理解 | 追加➡認知症のある人の数の推移 強化➡認知症に伴う生活への影響と認知症ケア(認知症のある人の生活のアセスメント、センター方式、ひもときシート、意思決定支援、バリデーション等) 強化➡連携と協働(地域包括ケアシステムから見た多職種連携・協働、認知症疾患医療センター、認知症初期集中支援チーム、認知症ケアパス、認知症ライフサポートモデル等) |
| 障害の理解 | 強化➡障害のある人の生活と障害の特性に応じた支援(障害のある人の特性を踏まえたアセスメント、身体障害・知的障害・精神障害・発達障害・高次脳機能障害・難病のある人の生活理解と支援、合理的配慮等) |
| 医療的ケア | ほぼ同じ➡喀痰吸引、経管栄養等 |
| 総合問題 | ほぼ同じ➡各領域の知識・技術を横断的に問う問題を長文4事例で出題 |
公益財団法人社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験 科目別出題基準をもとに筆者が作成
3.介護福祉士国家試験の実技試験
実技試験の内容
実技試験では、提示された課題に対して、利用者の状況に応じた介護が適切に行えるかどうかが問われます(実際には、利用者に扮したモデルを相手に必要な介護を行います)。受験する年によって出題内容は異なりますが、筋力が低下した利用者への体位変換、片麻痺の利用者への杖歩行時の支援、視力を失った利用者への食事介護、車いすを使用する利用者への衣服の着脱介護などについて、実践的な能力が求められる点は同じです。
実技試験当日の流れ
実技試験当日の流れは、①受付→②待機室で待機→③控え室で課題を確認(10分程度)→④試験会場で実技試験(5分間以内)となります。控え室で初めて課題が提示されるため、しっかりと内容を確認し、試験会場に呼ばれるまでの間、「どのような介護を行えばよいのか?」について、頭のなかでシミュレーションしておきましょう。
4.実技試験が免除になる条件とは? 4つの資格取得ルートごとに確認しよう!
介護福祉士国家試験では、一定の条件を満たすことで実技試験が免除され、筆記試験のみとなります。ただし、受験資格の取得方法(資格取得ルート)によって、実技試験が免除となる条件は異なります。詳細は、公益財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページで確認してください。
ここでは、4つの資格取得ルートごとに、実技試験が免除される条件を確認しておきます。
① 養成施設ルート
養成施設ルートでは、実技試験がなく筆記試験のみとなります。受験資格を取得するには大学、短期大学、専門学校などの介護福祉士養成施設に入学し、介護福祉士に必要な知識・技術を修得して卒業する必要があります。
① 実務経験ルート
実務経験ルートの場合も、実技試験がなく、筆記試験のみとなっています。ただし、このルートで受験資格を得るには、従業期間3年(1095日)以上かつ従業日数540日以上介護などの業務に従事し、「介護福祉士実務者研修」を修了するか、「介護職員基礎研修」と「喀痰吸引等研修」の両方を修了する必要があります。
③ 福祉系高校ルート
福祉系高校の場合、2009(平成21)年度以降に入学して新カリキュラムを学んで卒業した人は、実技試験が免除されます。一方、2008(平成20)年度以前に入学して卒業した人は、「介護技術講習」「介護過程」「介護過程Ⅲ」のいずれか1つを修了または履修すれば、実技試験が免除となります。
④ 経済連携協定(EPA:Economic Partnership Agreement)ルート
経済連携協定のもと、日本で介護福祉士の資格取得を目指して働いている外国人(インドネシア人、フィリピン人、ベトナム人)は、「介護技術講習」「介護過程」「介護過程Ⅲ」「実務者研修」のいずれか1つを修了または履修すれば、実技試験が免除となります。
5.介護福祉士国家試験の合格基準
筆記試験の合格基準 2つの条件とは?
筆記試験に合格するためには、次の2つの条件を両方とも満たさなければなりません。第1の条件は、総得点(125点)の60%程度にあたる合格基準点をクリアすることです。ただし、合格基準点は問題の難易度によって補正されるので、毎年同じというわけではありません。問題数が120問から125問に変更となった第29回試験から第35回までの合格基準点は、72~78点の間で推移していましたが、第36回ではじめて67点を記録しました。
70点台では、「受かっているか? それとも?」といった不安な気持ちで合格発表を待つことになるため、少なくとも80点以上を獲得し、合格基準を確実にクリアしておきたいところです。
問題数が125問に変更となった第29回からの筆記試験の合格基準点
| 回 | 実施年 | 合格基準点 |
|---|---|---|
| 第36回 | 2024(令和6)年 | 67点 |
| 第35回 | 2023(令和5)年 | 75点 |
| 第34回 | 2022(令和4)年 | 78点 |
| 第33回 | 2021(令和3)年 | 75点 |
| 第32回 | 2020(令和2)年 | 77点 |
| 第31回 | 2019(平成31)年 | 72点 |
| 第30回 | 2018(平成30)年 | 77点 |
| 第29回 | 2017(平成29)年 | 75点 |
出典:厚生労働省「介護福祉士国家試験の合格基準及び正答について(第36回・第35回・第34回・第33回・第32回・第31回・第30回・第29回)
第2の条件は、第1の条件を満たしたうえで、以下の①~⑪の11科目群すべてで得点することです。つまり、1つの科目群に0点であった場合、ほかの科目群がすべて満点であったとしても、不合格となってしまうわけです。「医療的ケア」は5問しかないため、特に注意しましょう。
また、「人間の尊厳と自立」と「介護の基本」、「人間関係とコミュニケーション」と「コミュニケーション技術」については、セットになっている2つの科目の合計が0点であった場合、不合格となります。
筆記試験の11科目群
①「人間の尊厳と自立」(2問)+「介護の基本」(10問)
②「人間関係とコミュニケーション」(4問)+「コミュニケーション技術」(6問)
③「社会の理解」(12問)
④「生活支援技術」(26問)
⑤「介護過程」(8問)
⑥「こころとからだのしくみ」(12問)
⑦「発達と老化の理解」(8問)
⑧「認知症の理解」(10問)
⑨「障害の理解」(10問)
⑩「医療的ケア」(5問)
⑪「総合問題」(12問)
出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験 合格基準」
実技試験の合格基準
実技試験に合格する条件は、実技試験の総得点(100点)の60%程度を基準とし、課題の難易度によって補正した点数以上の得点を獲得することです。過去の合格基準点を踏まえれば、実技試験では60点以上を目指す必要があるでしょう。
第29回からの実技試験の合格基準点
| 回 | 実施年 | 合格基準点 |
|---|---|---|
| 第36回 | 2024(令和6)年 | 53.33点 |
| 第35回 | 2023(令和5)年 | 53.33点 |
| 第34回 | 2022(令和4)年 | 53.33点 |
| 第33回 | 2021(令和3)年 | 53.33点 |
| 第32回 | 2020(令和2)年 | 46.67点 |
| 第31回 | 2019(平成31)年 | 46.67点 |
| 第30回 | 2018(平成30)年 | 60.00点 |
| 第29回 | 2017(平成29)年 | 53.33点 |
出典:厚生労働省「介護福祉士国家試験の合格基準及び正答について(第36回・第35回・第34回・第33回・第32回・第31回・第30回・第29回)
6.介護福祉士国家試験の合格率と難易度
介護福祉士国家試験の合格率を確認すると、過去7回(第29回~第35回)の平均合格率は73.4%となっています。第34回までは70%前後で推移しているものの、新出題基準が適用された第35回は84.3%に急上昇しており、この点は注目に値するでしょう。新出題基準の適用に伴い、合格率が今後どのように推移していくのかについても、注視したいところです。
なお、合格率が高いか低いかだけで難易度を判断することはできないため、ここでは同じ国家資格である社会福祉士国家試験と比較してみます。社会福祉士国家試験の過去7回(第29回~第35回)の平均合格率を調べてみると、31.4%となっていました。これを踏まえるなら、介護福祉士国家試験の難易度は決して高くないといえそうです。
第29回からの介護福祉士国家試験の合格率
| 回 | 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 第36回 | 2024(令和6)年 | 74,595人 | 61,747人 | 82.8% |
| 第35回 | 2023(令和5)年 | 79,151人 | 66,711人 | 84.3% |
| 第34回 | 2022(令和4)年 | 83,082人 | 60,099人 | 72.3% |
| 第33回 | 2021(令和3)年 | 84,483人 | 59,975人 | 71.0% |
| 第32回 | 2020(令和2)年 | 84,032人 | 58,745人 | 69.9% |
| 第31回 | 2019(平成31)年 | 94,610人 | 69,736人 | 73.7% |
| 第30回 | 2018(平成30)年 | 92,654人 | 65,574人 | 70.8% |
| 第29回 | 2017(平成29)年 | 76,323人 | 55,031人 | 72.1% |
出典:厚生労働省「介護福祉士国家試験の受験者・合格者の推移」
7.介護福祉士国家試験に合格するためのポイントとは?
筆記試験の合格に向けた5つのポイント
これまでの筆記試験の傾向を踏まえたうえで、合格するためのポイントを5つ示しておきます。
●ポイント1
介護福祉士国家試験は出題範囲が広く、11科目群すべてで得点しなければならないため、各科目をバランスよく学習することが求められます。過去問題と類似・関連した内容が全体の7割程度出題される傾向にあるため、最低でも過去5年分の問題を繰り返し解くようにしましょう。
●ポイント2
試験科目のなかでは「生活支援技術」が26問と最も多く、その正答率が合否を左右する可能性があります。環境整備、移動、衣服の着脱、食事、口腔ケア、入浴・清潔、排泄、洗濯、調理などの生活支援技術から幅広く出題されるため、まずは基本となる知識・技術をしっかりと身につけましょう。また、介護福祉士養成校での演習や介護現場での実習・実践といった経験が正答に結びつく場合も多いため、それらの取り組みも重要です。
●ポイント3
「総合問題」はもちろん、全科目を通じて事例問題が出題されるため、日頃から事例文を読み、理解力・読解力を鍛えておく必要があります。事例問題を苦手とする人は、まず過去問題を繰り返し解き、事例問題への抵抗感をなくしましょう。
●ポイント4
「最も適切なものを1つ選びなさい」という出題形式が多いことも、介護福祉士国家試験の特徴です。なかには、選択肢を2つくらいまでは絞れるものの、最終的にどれを選べばよいのか迷う問題もあります。年々、状況の判断や課題の解決を求める問題が増えているため、日頃から多くの問題に挑戦して知識量を増やすほか、演習・実習・実践で得た知識・技術についてもきちんと整理しておくとよいでしょう。
●ポイント5
5つの選択肢のなかから「最も適切なもの」「適切なもの」「正しいもの」を1つ選ぶのは、誤っている選択肢を4つ見つける作業でもあります。消去法を駆使することも、正解にたどりつく有効な方法といえるでしょう。
実技試験の合格に向けた6つのポイント
実技試験で合格するためには、過去の課題に取り組み、実技の練習を積み重ねる(場数を踏む)必要があります。その際、以下の6つのポイントを押さえるようにしましょう。
●ポイント1
個人の尊厳に配慮しましょう。「〇〇さん」と名前で呼ぶこと、利用者を上から見下ろさず、目線を合わせてコミュニケーションを図ること、丁寧な言葉遣いをすることなどをきちんと心がけてください。
●ポイント2
介護の内容については事前に利用者に説明し、同意を得たうえで実施に移すことが大事です。車いすの移動を介護する場合なら、最初に「これから車いすの移動を介護しますが、よろしいでしょうか?」と説明し、同意を得るようにしましょう。
●ポイント3
健康状態の確認も大事なポイントです。介護の実施前、体位変換のとき、車いすへの移乗時、杖歩行時、衣服の着脱時、介護の実施後などには、「体調は大丈夫ですか?」「気分は悪くないでしょうか?」といった声かけを行い、体調を確認する必要があります。
●ポイント4
利用者の意向を確認しないまま、自己判断で勝手に物事を決めてしまわないように注意してください。例えば、これから着る上衣を選択する場合、「Aの服とBの服、どちらがよろしいでしょうか?」と尋ね、利用者が自ら選択・決定できるように配慮しましょう。
●ポイント5
自己決定の尊重に加えて、残存能力の活用も自立支援の重要な要素となります。例えば、右片麻痺の方が衣服を脱ぐ場合、すべてを介護するのではなく、「左手を使ってボタンを外せますか?」と問いかけ、動かせる左手の活用を促すことが大切です。
●ポイント6
最後のポイントは、安全・安楽です。特に、杖歩行時やベッドから車いすへの移乗時、座位から立位への体位変換時などは、転倒・転落・強打が起きないように注意してください。
まとめ
介護福祉士国家試験には筆記試験と実技試験がありますが、受験資格の取得方法(資格取得ルート)によっては実技試験が免除され、筆記試験のみで合否が決まります。
筆記試験の出題範囲は幅広く、5領域13科目から計125問が出題されます。特に、「生活支援技術」「介護過程」など4科目から構成される「介護」の領域は全体の40%(50問)を占めるため、正答率が合否を左右する可能性があります。また、2023(令和5)年の第35回試験からは新出題基準が適用され、チームマネジメントなどの出題項目が新たに追加されています。筆記試験では、11科目群すべてで得点することに注力しつつ、125点中80点以上を目指すようにしましょう。
一方、実技試験では、提示された課題に対して、5分間以内に利用者の状況に応じた介護が適切に行えるかどうかが問われます。試験当日は、控え室で初めて課題が提示されるため、試験会場に呼ばれるまでの間、どのような介護を行えばよいのか、頭のなかでシミュレーションしておきましょう。
介護福祉士国家試験に挑戦するにあたっては、やみくもにテキストを読んだり過去問を解いたりしても、十分な効果は期待できません。介護福祉士国家試験の全体像を把握したうえで、それぞれの試験の内容やポイントをしっかりと押さえ、計画的・継続的に試験対策に取り組むことが合格への近道となるでしょう。
【日本全国電話・メール・WEB相談OK】介護職の無料転職サポートに申し込む
スピード転職も情報収集だけでもOK
マイナビ介護職は、あなたの転職をしっかりサポート!介護職専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを行います。
はじめての転職で何から進めるべきかわからない、求人だけ見てみたい、そもそも転職活動をするか迷っている場合でも、キャリアアドバイザーがアドバイスいたします。

SNSシェア















