介護職のボーナスはいくら?経験年数やサービス別の平均額
構成・文/介護のみらいラボ編集部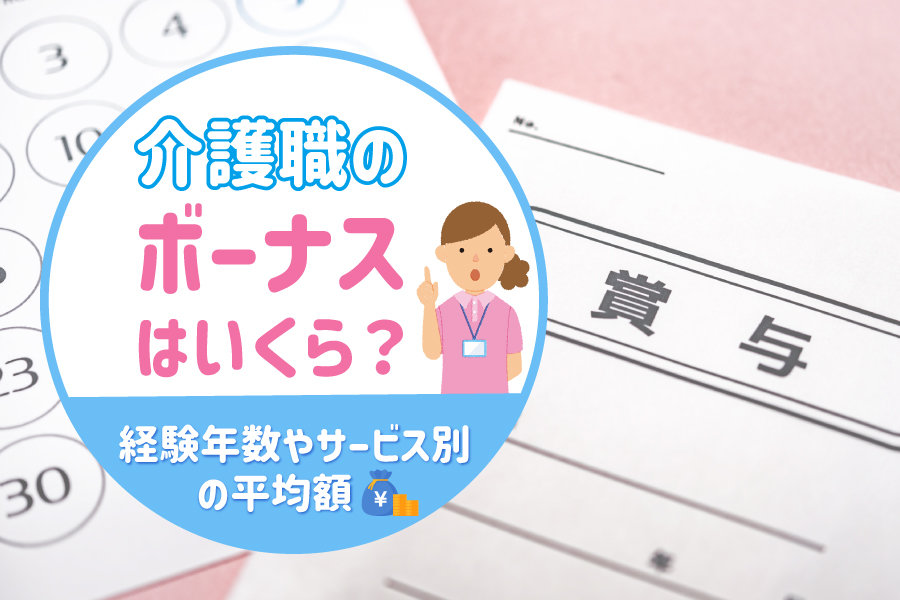
介護の仕事はやりがいの大きな仕事ですが、長く続けていくには、給与やボーナスといった収入面を安定させることも大切です。しかし、職場や年齢などによってはボーナスの支給額が少なかったり、ボーナスの支給そのものがなかったりするケースもあるため、経済的な不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
当記事では、介護職におけるボーナスの平均額について、勤務地や年齢、経験年数、施設の種別などの条件別に紹介します。併せて、介護職のボーナスが支給される方法やタイミング、ボーナス額を上げるための方法も解説するので、収入アップを目指す際の参考にしてください。
1.介護職のボーナス平均額はいくら?
厚生労働省「令和3年賃金構造基本統計調査」によると、介護職におけるボーナス支給額(年間)の全国平均は、男女全体で約52.1万円でした。夏と冬など年2回のボーナス支給がある場合は、1回あたりの支給額の平均が約26万円となります。
また、男女別の年間のボーナスは、男性が約57.3万円、女性が約49.2万円となっています。資格の有無や経験年数などによっても異なりますが、男性の方がやや高い傾向にあると言えるでしょう。
介護職のボーナス支給額に影響を与える要素には、性別以外にどのようなものがあるのでしょうか。ここでは、「都道府県」「年齢」「経験年数」「職種」「サービス」の5つの要素別に、介護職のボーナス事情を確認していきましょう。
【都道府県別】介護職のボーナス
一般的に、労働者の給与やボーナスは勤務エリアの物価や地価などを踏まえた金額となっていると言われています。介護職のボーナス支給額は、勤務する都道府県によってどのように変動するのでしょうか。
| 都道府県 | ボーナス支給額 |
|---|---|
| 北海道 | 約57.6万円 |
| 青森県 | 約43.1万円 |
| 岩手県 | 約53.3万円 |
| 宮城県 | 約50.4万円 |
| 秋田県 | 約52.9万円 |
| 山形県 | 約47.3万円 |
| 福島県 | 約63.4万円 |
| 茨城県 | 約50.5万円 |
| 栃木県 | 約46.4万円 |
| 群馬県 | 約62.1万円 |
| 埼玉県 | 約44.1万円 |
| 千葉県 | 約50.9万円 |
| 東京都 | 約51.4万円 |
| 神奈川県 | 約51.0万円 |
| 新潟県 | 約57.5万円 |
| 富山県 | 約67.1万円 |
| 石川県 | 約63.2万円 |
| 福井県 | 約84.5万円 |
| 山梨県 | 約71.3万円 |
| 長野県 | 約55.5万円 |
| 岐阜県 | 約56.5万円 |
| 静岡県 | 約40.7万円 |
| 愛知県 | 約54.8万円 |
| 三重県 | 約57.0万円 |
| 滋賀県 | 約59.8万円 |
| 京都府 | 約64.9万円 |
| 大阪府 | 約48.0万円 |
| 兵庫県 | 約42.9万円 |
| 奈良県 | 約46.2万円 |
| 和歌山県 | 約47.2万円 |
| 鳥取県 | 約58.5万円 |
| 島根県 | 約44.2万円 |
| 岡山県 | 約61.6万円 |
| 広島県 | 約53.1万円 |
| 山口県 | 約47.3万円 |
| 徳島県 | 約51.1万円 |
| 香川県 | 約48.1万円 |
| 愛媛県 | 約51.3万円 |
| 高知県 | 約61.7万円 |
| 福岡県 | 約51.1万円 |
| 佐賀県 | 約39.2万円 |
| 長崎県 | 約48.0万円 |
| 熊本県 | 約47.8万円 |
| 大分県 | 約56.2万円 |
| 宮崎県 | 約45.2万円 |
| 鹿児島県 | 約48.4万円 |
| 沖縄県 | 約32.3万円 |
(出典:厚生労働省「令和3年賃金構造基本統計調査」)
※表は、厚生労働省「令和3年賃金構造基本統計調査」における介護職員(医療・福祉施設)のデータをもとに作成しています。
上の表から、平均支給額が最も高い都道府県と、最も平均支給額が低い都道府県では、50万円以上の差があることが分かります。これを踏まえて、介護職のボーナス平均支給額は、都道府県によって大きく異なる場合があることに注意しましょう。自身のボーナス支給額について考える際は、勤務しているエリアの相場を目安にすることが大切です。
【年齢別】介護職のボーナス
給与やボーナスの支給額を決定する一般的な要素として、給与、ボーナスを受け取る従業員の年齢が挙げられます。介護職のボーナス支給額は、年齢によってどのように変動するのでしょうか。
| 年齢 | ボーナス支給額 |
|---|---|
| ~19歳 | 約10.1万円 |
| 20~24歳 | 約37.0万円 |
| 25~29歳 | 約48.8万円 |
| 30~34歳 | 約57.5万円 |
| 35~39歳 | 約59.0万円 |
| 40~44歳 | 約59.4万円 |
| 45~49歳 | 約60.0万円 |
| 50~54歳 | 約53.8万円 |
| 55~59歳 | 約53.9万円 |
| 60~64歳 | 約40.7万円 |
| 65~69歳 | 約28.1万円 |
| 70歳~ | 約21.6万円 |
(出典:厚生労働省「令和3年賃金構造基本統計調査」)
※表は、厚生労働省「令和3年賃金構造基本統計調査」における介護職員(医療・福祉施設)のデータをもとに作成しています。
入職したばかりの介護職は、ボーナスの平均支給額が約10.1万円と低めの水準にありますが、20~40代にかけて増加する傾向にあります。ボーナスの平均支給額のピークは、責任のある役職につく方が多い40~49歳頃です。50歳以降に減少傾向となるのは、役職定年を迎えたり、定年後の再雇用で契約職員に切り替わったりすることによると考えられます。
【経験年数別】介護職のボーナス
介護業界は、ライフステージの変化やスキルアップ、キャリアチェンジといった理由で転職する方が多い業界です。介護業界内だけでなく、一般企業など業界外からの転職も少なくありません。そのため、給与やボーナスの支給額は、年齢だけでなく経験年数、勤続年数によっても変動する可能性があります。
| 経験年数 | ボーナス支給額 |
|---|---|
| 0年 | 約9.6万円 |
| 1~4年 | 約41.5万円 |
| 5~9年 | 約51.4万円 |
| 10~14年 | 約57.6万円 |
| 15年以上 | 約69.5万円 |
(出典:厚生労働省「令和3年賃金構造基本統計調査」)
※表は、厚生労働省「令和3年賃金構造基本統計調査」における介護職員(医療・福祉施設)のデータをもとに作成しています。
上のデータから、介護職は、経験年数に応じてボーナス平均支給額が増加する傾向にあると言えます。介護職として働き始めて間もない方は、経験年数を重ねることでボーナス支給額が上がる可能性があるため、気になる場合は就業規則などで確認してみると良いでしょう。
【職種別】介護職のボーナス
介護業務に携わる職業をまとめて「介護職」と呼ぶのが一般的ですが、「介護職」には複数の職種が含まれています。また、職種によって勤務体系や仕事内容、必要な資格などが異なるため、ボーナス支給額も違ってきます。
| 職種 | ボーナス支給額 |
|---|---|
| 介護職員 | 約52.1万円 |
| 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 約64.9万円 |
| 訪問介護従事者 | 約43.1万円 |
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、一定の実務経験を得た上で実務研修受講試験に合格し、実務研修を受講・修了しなければ資格を取得することができません。取得するために時間や努力が必要となることや、より専門性の高い知識・スキルを身に付けていることから、ボーナス支給額もやや高い水準になると考えられます。
なお、訪問介護従事者は介護職員と比べて、夜勤や残業が少ない傾向にあります。訪問介護従事者と介護職員のボーナス平均支給額に差が生じているのは、そうした勤務体系の違いによるものでしょう。
【施設・サービス別】介護職のボーナス
介護職の勤務体系や仕事内容は、介護施設のサービス形態によっても異なります。そのため、提供する介護サービスの種類で、ボーナスの支給額に違いが見られます。
| サービス | ボーナス支給額 |
|---|---|
| 訪問介護 | 463,724円 |
| 訪問入浴介護 | 297,385円 |
| 訪問看護 | 744,741円 |
| 通所介護 | 498,991円 |
| 通所リハビリテーション | 620,827円 |
| 短期入所生活介護 | 461,976円 |
| 特定施設入居者生活介護 | 530,738円 |
| 地域密着型通所介護 | 416,455円 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 617,178円 |
| 認知症対応型通所介護 | 560,121円 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 445,088円 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 493,628円 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 405,578円 |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 529,152円 |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 623,134円 |
| 居宅介護支援 | 609,409円 |
| 介護老人福祉施設 | 807,779円 |
| 介護老人保健施設 | 727,013円 |
| 介護医療院(介護療養型医療施設) | 647,012円 |
(出典:公益財団法人介護労働安定センター「令和2年度介護労働実態調査 事業所における介護労働実態調査結果報告書」)
介護老人福祉施設や介護老人保健施設といった、比較的大人数の利用者さんを24時間体制でケアしている施設は、ボーナスの平均支給額が高い傾向にあります。訪問看護や通所リハビリテーションなど、医師・看護師といった医療従事者と連携する機会が多い施設も、ボーナスの平均支給額が高い水準にあると言えるでしょう。
2.介護職のボーナスはいつどのように支給される?
介護職におけるボーナスの支給時期は、一般的な民間企業や公務員と同様に、夏(6~8月ごろ)と冬(12月ごろ)の年2回である場合が多い傾向にあります。支給額は、冬の方がやや高くなるのが一般的です。
なお、介護職のボーナス支給額は、基本的に月給(基本給)をベースに算出されます。年齢や経験年数によって昇給がかなえば、連動してボーナス増加も期待できるでしょう。
しかし、勤務先の事業状況によっては、ボーナスが減額されたり、支給されなかったりする場合もあるので注意が必要です。また、欠勤や遅刻が多い方には、事業者側のボーナス査定でマイナスの評価がつく場合もあります。日頃から就業規則を守り、欠勤・遅刻をしないように心がけましょう。
3.介護職のボーナス支給額を上げる方法
介護職におけるボーナスの平均支給額や算定基準を理解した上で、自身のボーナス支給額に満足できない場合には、スキルアップやキャリアアップを目指すことをおすすめします。
ここでは、介護職がスキルアップ・キャリアアップするための3つの方法を紹介します。自分に合った方法を選んで、収入アップを目指しましょう。
介護関連の資格を取得する
介護職の給与・ボーナスは、保有資格の有無や種類によって支給額が変動する場合があります。介護関連の資格を取得することで、資格手当がついたり査定で有利になったりする可能性もあるため、介護スキルやキャリアの向上を兼ねて資格取得を目指すと良いでしょう。
介護職の経験が浅い方は、介護士としての基本を学べる「介護職員初任者研修」「介護職員実務者研修」の取得から始めることをおすすめします。十分な介護経験を持つ場合は、キャリアプランに合わせて「介護支援専門員」「介護福祉士」「社会福祉士」など、専門性や難易度の高い介護資格を検討してみましょう。
管理職や責任者のポジションに就く
現在の勤務先でステップアップを重ね、「主任」「サービス提供責任者」「リーダー」といった責任のあるポジションに就くことでも、ボーナス金額のアップが期待できます。役職に就けば「役職手当」も加算されるため、ボーナスだけでなく毎月の給与額アップも狙えるでしょう。
また、施設内で責任のあるポジションを経験すれば、さらなる昇進を目指せる可能性もあります。
基本給の高い職場に転職する
基本給の高い職場に転職することも、ボーナスの金額をアップさせる手段のひとつです。介護職のボーナス支給額は基本給をベースとして算出される場合が多いため、転職して基本給自体がアップすれば、支給されるボーナスの金額も高くなることが期待できます。
ただし、転職する際には基本給やボーナスの金額だけでなく、勤務日数や勤務時間、福利厚生(社会保険完備・交通費支給など)といった待遇・制度を確認することも大切です。求人の内容・勤務条件を総合的に判断した上で転職に踏み切りましょう。
まとめ
介護職におけるボーナスの平均支給額は、勤務地や年齢、施設の種別などによって異なります。平均支給額や自分の勤務状況などを踏まえて、現在のボーナス支給額に不満を感じている場合は、介護職としてのスキルアップ・キャリアアップを図ると良いでしょう。その際は、資格取得や役職就任、転職など、キャリアプランに合った方法を選ぶことが大切です。
マイナビ介護職が提供する「介護のみらいラボ」では、介護の現場で活躍する方に役立つ情報を豊富に取り扱っています。「介護現場の情報を集めたい」「介護職に関する知識を身につけたい」といった際には、ぜひご覧ください。
※当記事は2022年6月時点の情報をもとに作成しています
【日本全国電話・メール・WEB相談OK】介護職の無料転職サポートに申し込む
スピード転職も情報収集だけでもOK
マイナビ介護職は、あなたの転職をしっかりサポート!介護職専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを行います。
はじめての転職で何から進めるべきかわからない、求人だけ見てみたい、そもそも転職活動をするか迷っている場合でも、キャリアアドバイザーがアドバイスいたします。

SNSシェア















