傾眠とは?介護職が知っておきたい原因や対策も解説
文/中村 楓(介護支援専門員・介護福祉士・介護コラムニスト)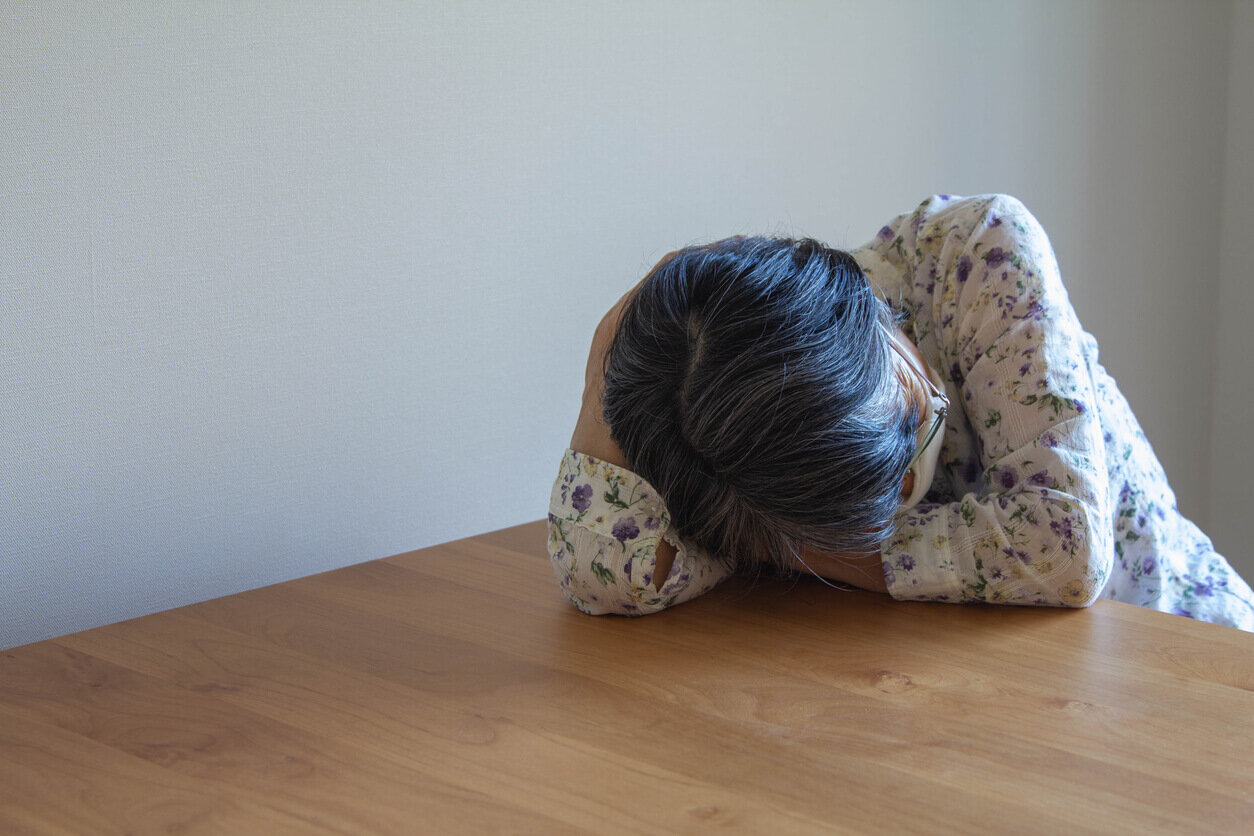
高齢者によくみられる「傾眠」は、介護現場でもよく耳にする言葉です。しかし、経験の浅い介護職にとっては馴染みのない言葉であり、傾眠がどのような状態なのか、どんな対策が必要なのかわからない人もいるかもしれません。そこで、今回は介護職が知っておきたい知識として、傾眠の概要や原因、対策方法について詳しく紹介します。
1.「傾眠」とは最も軽い意識障害

傾眠(けいみん)とは、高齢者によくみられる意識障害のことです。意識障害というと、声をかけても全く反応がないような状態を思い浮かべる人が多いかもしれません。しかし、実際には、意識障害にはいくつかレベルがあり、最も軽い状態なのが傾眠です。
介護現場で、気が付くと利用者さんがうとうとしているという場面に遭遇することがよくあります。介護記録には、「傾眠傾向」とよく書かれているのを見る人もいるのではないでしょうか。ぱっと見は、うとうとしていたり、うたた寝をしているような状態で、肩をトントンとたたいたり、声をかけたりするなど、わずかな刺激で覚醒します。しかし、刺激がなくなると、またすぐに寝入ってしまいます。
傾眠がたびたびみられたり、続いたりする場合には、何らかの病気が関係していることもあります。普段はしっかり覚醒しているような人が、急にうとうとすることが増えたときには、看護師に相談したうえで、注意深く観察する必要があります。
2.傾眠と他の意識障害の違い

先にもお伝えしたように、意識障害には、いくつかの段階があり、大きく4つに分けられます。最も軽度なのが傾眠で、次に昏迷、半昏睡、昏睡と続きます。また、意識障害と似た状態でよく知られているのが失神です。傾眠の状態を理解するうえで、昏迷、半昏睡、昏睡、失神の特徴を知り、傾眠との違いを確認しておきましょう。
昏迷(こんめい)
昏迷とは、肩をたたいたり、声をかけた程度では全く起きないものの、体をゆすったり、大声で呼びかけたりすると、少しだけ目を開けて反応するような状態です。傾眠が少しの刺激でしっかり覚醒するのに対し、昏迷は強い刺激で短時間だけ反応する状態と覚えておきましょう。
昏迷は、傾眠よりも意識を失っているレベルは過度に深いため、無反応の状態が長く続きます。やっと覚醒したかと思っても、話が通じないことや、意味がわからないことを話すといったことも少なくありません。覚醒していても本人の意志が正しく伝えられない状態といえるでしょう。
半昏睡(はんこんすい)
昏迷よりも、さらに意識障害が深くなった状態を、半昏睡といいます。半昏睡は昏迷よりも強く刺激して、ようやく刺激を避けようとするしぐさや、顔をしかめたりする反応がみられるような状態です。昏迷のように目を開けることはあるものの、覚醒しているとはいえず、わずかな反応がみられるような状態にあるのが特徴です。
傾眠と比べると、半昏睡は、明らかに意識障害を起こしているようにみえるでしょう。
昏睡(こんすい)
昏睡は、外部からいくら刺激しても反応しない状態です。最も重い意識障害脳状態で、何をしても目を閉じたまま反応がありません。昏睡状態はすぐに医療措置が必要な状態です。速やかに看護師や先輩を呼び、指示に従いましょう。
傾眠を含め、意識障害は、病気やけがなどで脳の機能が損傷もしくは低下することで起きる症状です。重度になるほど、速やかな医療措置が必要であることを念頭に置き、いざというときに慌てずに対応できるようにしておきましょう。
失神(しっしん)
利用者さんが突然意識を失ったけれど、少し横になったらいつも通りに戻った、という場面に遭遇した人もいるかもしれません。このように、一時的に意識を失う状態を失神といいます。失神は、意識障害ではなく、意識消失の一種です。何らかの原因で、脳全体に一時的に血液が行かなくなることで生じます。
具体的には、長時間立っていた、トイレで力んだ、急に立ち上がったなど、血圧が急激に低下するような場面が代表的です。失神を起こした場合は、横になってもらっている間に血圧が正常に戻るため、その後は自然に目が覚めて元の状態に戻ります。
傾眠はじわじわと眠ってしまうような状態であるのに対し、急に意識がなくなるような状態から、しばらくすると自然に元に戻るのが失神だと覚えておきましょう。
3.傾眠になってしまう5つの原因

傾眠に陥ってしまうのは、さまざまな要因が関係しています。なかでも、高齢者に多い5つの原因について、詳しく解説します。
加齢による社会活動の減少や睡眠の質の低下
高齢になると、気力が低下したり、体の動きが鈍くなったりして、活動量が低下しがちです。利用者さんから「いろいろと面倒になってきて外に出るのがおっくうになった」、「膝が痛いから買い物に出かける回数を減らしている」といった声を聞くことが多い介護職もいるのではないでしょうか。
活動量が低下すると、社会交流の機会も減っていきます。人と話すことは人間にとって刺激的な活動の1つであるため、社会交流が減ると日常生活のなかで刺激が少なくなってしまいます。年齢を問わず、何もすることがないと眠くなることがあるように、刺激がない時間が増えることで、日中であっても眠気を感じることが増えていきます。結果として、傾眠状態に陥りやすくなってしまうことがあります。
また、睡眠の質も傾眠に影響します。高齢になると、体内時計が変化し、早く目が覚めるようになったという人や、夜中に何度もトイレで目が覚めるという人もいます。それにより、日中に眠気が生じてうとうとするため、夜は眠れなくなり、睡眠の質が低下するという悪循環が起きやすく、そのまま日常的な傾眠状態に発展します。
脱水によるもの
高齢者の脱水は、傾眠を引き起こす原因の1つです。脱水状態になると、ぼんやりする時間が増えたり、頻繁に傾眠状態に陥ってしまったりすることがあります。
高齢になると、のどの渇きを感じにくくなるため、水分摂取量が減りがちです。また、活動量が減っていると、お腹もあまり空かなくなり、食事量が減ってしまいます。その結果、必要な水分量がとれておらず、気付かないうちに脱水状態に陥ってしまうことも少なくありません。特に、体調を崩しているときには状態が悪化しやすく、あっという間に脱水の症状が出てしまうケースもあります。
介護現場では、適切に水分摂取や食事がとれるように心がけることが大切です。また、ぼーっとする時間が増えた、いつ見ても傾眠しているようなときには、脱水対策を試みるとよいでしょう。
認知症の影響によるもの
認知症の人は、他の高齢者に比べて傾眠状態に陥りがちです。認知症になると、無気力状態になりやすく、昼夜逆転してしまう人もいます。過度に眠気を感じてしまう人も少なくありません。
認知症の影響により傾眠状態になりやすい人は、こまめにコミュニケーションを取ったり、レクリエーションに参加を促したりするなど、活動量を上げていくことが大切です。加えて、睡眠リズムが整うような対策を、スタッフ一丸となって考えてみましょう。
薬の影響によるもの
薬のなかには、眠気が出やすいものや、鎮静が過度に効いてしまうようなものがあります。高齢者の場合、複数の薬を飲んでいる人が多いため、薬の影響が出やすい傾向があります。薬が変わった後で傾眠することが増えた場合には、薬の影響が考えられます。傾眠状態に陥りやすい利用者さんがいる場合には、薬の内容についてかかりつけ医や看護師に相談し、検討してもらうのもよいでしょう。
血糖値の変動によるもの
傾眠は、血糖値の変動でも起こることがあります。例えば、低血糖症状を起こした場合、徐々に傾眠状態に陥り、その後、けいれんや昏睡状態になってしまいます。早めの対処が必要となるため、糖尿病がある利用者の場合は、よく観察するようにしましょう。
また、糖尿病の場合、高血糖でも昏睡状態になる糖尿病性昏睡が起こる可能性もあります。糖尿病のある高齢者については、普段からよく観察を行い、傾眠傾向がみられるときには、速やかに看護師やかかりつけ医に相談します。そのうえで、早急に対応できる体制を整えておきましょう。
4.介護職ができる3つの傾眠対策

高齢者の傾眠に対し、介護職にはどのようなことができるでしょうか。介護職ができる傾眠対策を3つ紹介します。
日中の活動量を増やす工夫をする
利用者さんが傾眠状態に陥る回数を減らすためには、日中の活動量を上げる工夫をすることが大切です。最も簡単な方法は、普段のあいさつや声掛けをする機会を増やすことです。あいさつや声掛けは会話のきっかけとなり、覚醒する時間を増やすことにつながります。また、コミュニケーションが増え、利用者さんのことをよく知る機会にもなるので、関係性の構築にも役立つでしょう。
加えて、体を動かすレクリエーションを増やし、刺激を与えるのもよいでしょう。天気の良い日には、日向ぼっこや散歩がおすすめです。太陽に当たることは、体内時計の調整にも役立つので、朝カーテンを開けて日の光を部屋に入れるといった工夫も取り入れてみてください。
こまめに水分摂取ができる体制を整える
脱水にならないよう、こまめに水分摂取ができる体制を整えるのも、傾眠対策として効果があります。お茶タイムを多めに設けたり、飲み物の種類を変えたりして、飽きることもなく自然に水分が取れるようにするとよいでしょう。食事の際には、テーブルごとにお茶を置いて、自由に飲めるようにすると、利用者さんが気を使うこともなく水分摂取がしやすくなります。施設によっては、浄水ポットを設置して、いつでも自由に飲めるような対応をしているところもあります。
薬の調整をしてもらう
薬の影響で傾眠に陥りやすくなっている場合には、薬の調整が必要な場合があります。傾眠傾向になって心配な利用者さんがいる場合には、いつから傾眠がみられているのか、頻度はどれくらいなのか、傾眠している時間などを記録することから始めましょう。そのうえで、看護師やかかりつけ医に、薬の調整が可能かを相談するとよいでしょう。
まとめ:傾眠に関する知識を身に付け、仕事に役立てよう

普段から利用者さんを観察することは、介護職にとって大切な仕事の1つです。傾眠は、体調不良の前触れであるケースもあるため、介護職としてしっかり理解しておく必要があります。傾眠についての知識を身に付け、日頃の仕事に役立てていきましょう。
【日本全国電話・メール・WEB相談OK】介護職の無料転職サポートに申し込む
スピード転職も情報収集だけでもOK
マイナビ介護職は、あなたの転職をしっかりサポート!介護職専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを行います。
はじめての転職で何から進めるべきかわからない、求人だけ見てみたい、そもそも転職活動をするか迷っている場合でも、キャリアアドバイザーがアドバイスいたします。

SNSシェア















