ケアハウスと有料老人ホームは何が違う?介護職員が知っておきたいそれぞれの特徴
文/笑和(社会福祉士、介護福祉士)
ケアハウスと有料老人ホームの違いについて、ご存じでしょうか? どちらも高齢者が入居する介護施設という点で共通しますが、それぞれに特徴が異なります。同じ介護分野であっても施設によって、提供できるサービス内容や働き方が変わるため、勤務先となる施設の特徴をしっかり理解しておくことが大切です。 この記事では、ケアハウスと有料老人ホームそれぞれの特徴を解説するとともに、仕事内容について詳しく紹介します。
- 目次
- 1.ケアハウスと有料老人ホームの概要
- ケアハウスとは
- 有料老人ホームとは
- 2.ケアハウスと有料老人ホーム、それぞれの種類
- ケアハウスの種類
- 有料老人ホームの種類
- 3.ケアハウスと有料老人ホームの入居条件の違い
- ケアハウスの入居条件
- 有料老人ホームの入居条件
- 4.ケアハウスと有料老人ホームのサービスの違い
- ケアハウスで提供するサービス、介護サービス
- 有料老人ホームで提供するサービス、介護サービス
- 5.デケアハウスと有料老人ホームの費用の違い
- ケアハウスの入居費用の目安
- 有料老人ホームの入居費用の目安
- 6.ケアハウスと有料老人ホームの介護職員の仕事内容
- ケアハウスで働く介護職員の仕事内容
- 有料老人ホームで働く介護職員の仕事内容
- それぞれの施設における人員配置の違い
- 非常時の対応
- 7.ケアハウスと有料老人ホームで働くメリット・デメリット
- ケアハウスに勤務するメリット・デメリット
- 有料老人ホームに勤務するメリット・デメリット
- 8.ケアハウスと有料老人ホームの仕事に就くうえで必要な資格
- 介護職員初任者研修
- 介護福祉士実務者研修
- 介護福祉士
- 9.ケアハウスと有料老人ホームのQ&A
- 特別養護老人ホームとはどう違うの?
- シルバーマンションとの違いは?
- 有料老人ホームは閉鎖される可能性はある?
- まとめ:ケアハウスと有料老人ホームの違いを理解し、転職に役立てよう
1.ケアハウスと有料老人ホームの概要

ケアハウスと有料老人ホームは、いずれも高齢者が入居する施設という点では共通しています。しかし、それぞれに特徴や入居対象、提供するサービスなどが異なります。まずは各施設の概要を確認してみましょう。
ケアハウスとは
ケアハウスとは、老人福祉法で定められた軽費老人ホームの1つで、主に社会福祉法人が運営する福祉施設です。軽費老人ホームC型とも呼ばれます。
ケアハウスには、一般型と介護型の2種類があり、主に家族からの援助が得られないなどの理由によって、居宅で自立した生活を送るのに不安がある高齢者が入居します。ケアハウス職員は、入居者への食事の提供や掃除・洗濯などの生活支援サービスを中心に、介護型ケアハウスでは介護サービスも提供されます。
●関連記事:ケアハウスとは?提供されるサービス内容とかかる費用を紹介
有料老人ホームとは
有料老人ホームとは、老人福祉法に定められた施設で、入居する高齢者に対して食事、介護、家事、健康管理のサービスのうち、いずれか1つ以上を提供している施設が該当します。
民間企業が設立・運営している施設が多く、入居者は自身のニーズに応じて選んで入居できるのが大きな特徴です。
有料老人ホームは、「介護付き有料老人ホーム」、「住宅型有料老人ホーム」、「健康型有料老人ホーム」の3種類に分類されます。
厚生労働省の資料「特定施設入居者生活介護(参考資料)」によると、有料老人ホームの数や入居者数は年々右肩上がりに増加中です。高齢化の進行によってニーズが高まっています。
2.ケアハウスと有料老人ホーム、それぞれの種類

ケアハウス、有料老人ホームはそれぞれに種類があります。種類ごとに特徴が異なるため、整理しながら理解していきましょう。
ケアハウスの種類
先述のとおり、ケアハウスは一般型・介護型の2種類に大別でき、それぞれの施設の特徴は表のとおりです。
| 一般型ケアハウス | 介護型ケアハウス | |
| 施設の種別 | 軽費老人ホームC型 | 軽費老人ホームC型であり、介護保険法上の特定施設入居者介護でもある。 |
| 入居時の契約 | 施設との契約によって入居 | 施設との契約によって入居 |
| 食事の提供 | あり | あり |
| 生活支援サービス | あり | あり |
| 介護サービス | なし ※外部サービスを利用 | あり |
一般型ケアハウスに勤務する職員は、入居する高齢者に対して、食事の提供や生活支援サービスを提供しますが、介護サービスは提供しません。一方、介護型ケアハウスにおいては、食事の提供や生活支援サービスに加えて、食事、入浴、排泄などの介助を含む介護サービスを提供します。
有料老人ホームの種類
前述したとおり、有料老人ホームは介護付き、住宅型、健康型の3種類に分かれており、それぞれの施設の特徴は次のとおりです(入居条件などの詳細は後述)。
●介護付き有料老人ホーム
主に介護を必要とする高齢者が入居し、職員は食事、入浴、排泄の介助や、生活上の身の回りの世話を行う。
●住宅型有料老人ホーム
自立~軽度の要介護高齢者が入居し、職員は食事の提供や、掃除、洗濯などの生活上のサポートを行う。
●健康型有料老人ホーム
自立した生活を送ることのできる高齢者が入居し、職員は充実した余暇時間を過ごしてもらうためレクリエーション、サークル活動などが行える環境を提供する。
3.ケアハウスと有料老人ホームの入居条件の違い

ケアハウス、有料老人ホームには、それぞれ異なる入居条件が設けられています。どのような点に違いがあるのでしょうか。以下、詳しく見ていきましょう。
ケアハウスの入居条件
ケアハウスは次のような理由で、居宅において自立した生活を送ることが難しい高齢者が入居できます。ただし、施設によって独自の条件を設けている場合もあります。
- 身寄りがない、家族からの援助が受けられない
- 加齢による心身機能の低下が原因で、居宅において自立した生活に不安がある
- 住宅事情によって1人で住むことが困難
- 原則として60歳以上であること(介護型ケアハウスの場合は、65歳以上でかつ要介護認定で要介護1以上と判定された者)
- ケアハウスに入居する方の配偶者や三親等内の親族であれば、60歳未満の方でも一緒に入居することができる(特別な事情と認められる場合)。
なお、一般型ケアハウスは、原則として要介護状態の高齢者は入居できません。入居したあとに要介護状態になった場合は、退去(別の施設・病院への転院)を求められる場合があります。
有料老人ホームの入居条件
有料老人ホームは、介護付き、住宅型、健康型の各施設によって入居条件が設けられています。施設によって詳細は異なりますが、一般的には次のような条件が見られます。
| 介護付き 有料老人ホーム | 住宅型 有料老人ホーム | 健康型 有料老人ホーム | |
| 年齢 | 原則65歳以上 | おおむね60歳以上 | おおむね60歳以上 |
| 要介護度 | 要介護1~5 | 自立~軽度の要介護 | 自立~要支援 |
| 認知症の入居可否 | 可 | 軽度であれば可 | 原則不可 |
上記はあくまで、一般的な目安です。有料老人ホームの多くは民間企業が設置して運営しており、運営元が独自の入居条件を定めることができます。施設によって入居条件が異なるため、一律ではないことを理解しておきましょう。
4.ケアハウスと有料老人ホームのサービスの違い

ケアハウス、有料老人ホームではどのようなサービスが提供され、どのような点に違いがあるのでしょうか。提供する職員の視点で見ていきましょう。
ケアハウスで提供するサービス、介護サービス
一般型ケアハウス、介護型ケアハウスでは提供するサービスが異なります。
●一般型ケアハウスの場合
一般型ケアハウスに勤務する職員は、入居する高齢者に対し、食事の提供や掃除、洗濯などの生活支援サービスを提供します。加えて、入居者からの各種の相談に応じ、緊急時の対応なども行いますが、入居者に対する身体介護(食事介助、入浴介助、排泄介助など)サービスは提供しません。もし、入居者が介護サービスを利用する場合には、外部の介護保険サービス提供事業所(訪問介護事業所、通所介護を提供する施設など)と契約することになります。
●介護型ケアハウスの場合
介護型ケアハウスに勤務する職員は、入居する高齢者に対し、食事の提供、生活支援サービスなどを提供するとともに、身体介護(食事・入浴・排泄の介助、移動の介助など)のサービスや、機能訓練のサービスを提供します。介護型ケアハウスは、介護保険法上の「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設であるため、職員は入居者に対して介護サービスを提供できます。介護サービスを提供できる点が、一般型との大きな違いです。
有料老人ホームで提供するサービス、介護サービス
有料老人ホームにおける、介護付き、住宅型、健康型それぞれが提供しているサービスは以下のとおりです。
| 介護付き 有料老人ホーム | 住宅型 有料老人ホーム | 健康型 有料老人ホーム | |
| 食事の提供 | ○ | ○ | ○ |
| 掃除、洗濯などの 生活支援サービス | ○ | ○ | ○ |
| 介護サービス(食事、入浴、排泄の介助) | ○ | × ※外部サービスを利用 | × |
| レクリエーション | ○ | ○ | ○ |
| 安否確認、 緊急時の対応など | ○ | ○ | ○ |
そのほか、施設によっては、コンシェルジュやフロントを設置し、来訪者応対のほか、電話・郵便物・宅配便の取次や配車手配を行うなどのサービスを提供しているところもあります。
5.ケアハウスと有料老人ホームの費用の違い

ケアハウス、または有料老人ホームに入居した場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。入居希望者から質問されることもあるため、職員として大まかな費用の内訳を把握しておきましょう。
ケアハウスの入居費用の目安
ケアハウスでは、月々9万円~15万円程度の利用者負担が生じます。ただし、前年の収入額に応じて異なるため、あくまで目安です。
一般型ケアハウスの場合、具体的には次のような内訳で費用がかかります。
- サービス提供費(主に事務費、入居者の収入に応じて異なる)
- 生活費(食事代、共用部分の水道光熱費など)
- 居住費(賃料や施設管理費、居室の水道光熱費など)
- その他の費用(外部事業者の介護保険サービスを利用した場合などの本人負担分)
このほか、入居時に必要な費用として、保証金または入居一時金を設定している施設があります。
また、介護型ケアハウスも、基本的な費用負担は、一般型ケアハウスと大きな差はありません。ただし、介護保険サービスにかかる、自己負担分(原則1割、収入によって2・3割)が別途必要です。この費用は、入居者の要介護度や利用したサービスの量によって、個々に異なります。
ケアハウスは老人福祉法に定められた老人福祉施設であるため国から補助金が出ています。入居者にとっては費用を抑えて入居できる施設として人気が高く、結果として多くの待機者問題を抱えています。
有料老人ホームの入居費用の目安
介護付き、住宅型、健康型、いずれかの有料老人ホームに入居する高齢者は、月額費用として15~30万円程度を負担します。内訳は施設によって異なりますが、一般的には次のような項目が挙げられます。
- 居住費用(入居時費用、家賃相当額など)
- 月額利用料金(管理費、サービス費、生活支援サービス費など)
- 食費、光熱水費など
なお、「平成 28 年度老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)高齢者向け住まい及び住まい事業者の運営実態に関する調査研究報告書」によると、介護付き、住宅型、各施設の平均利用料金は次のとおりでした。
- 介護付き有料老人ホーム:238,378円/月
- 住宅型有料老人ホーム:112,431/月
※上記金額には、介護保険サービスや医療にかかる自己負担分は除く。
※同報告書には健康型有料老人ホームの費用に関する記載なし。
6.ケアハウスと有料老人ホームの介護職員の仕事内容
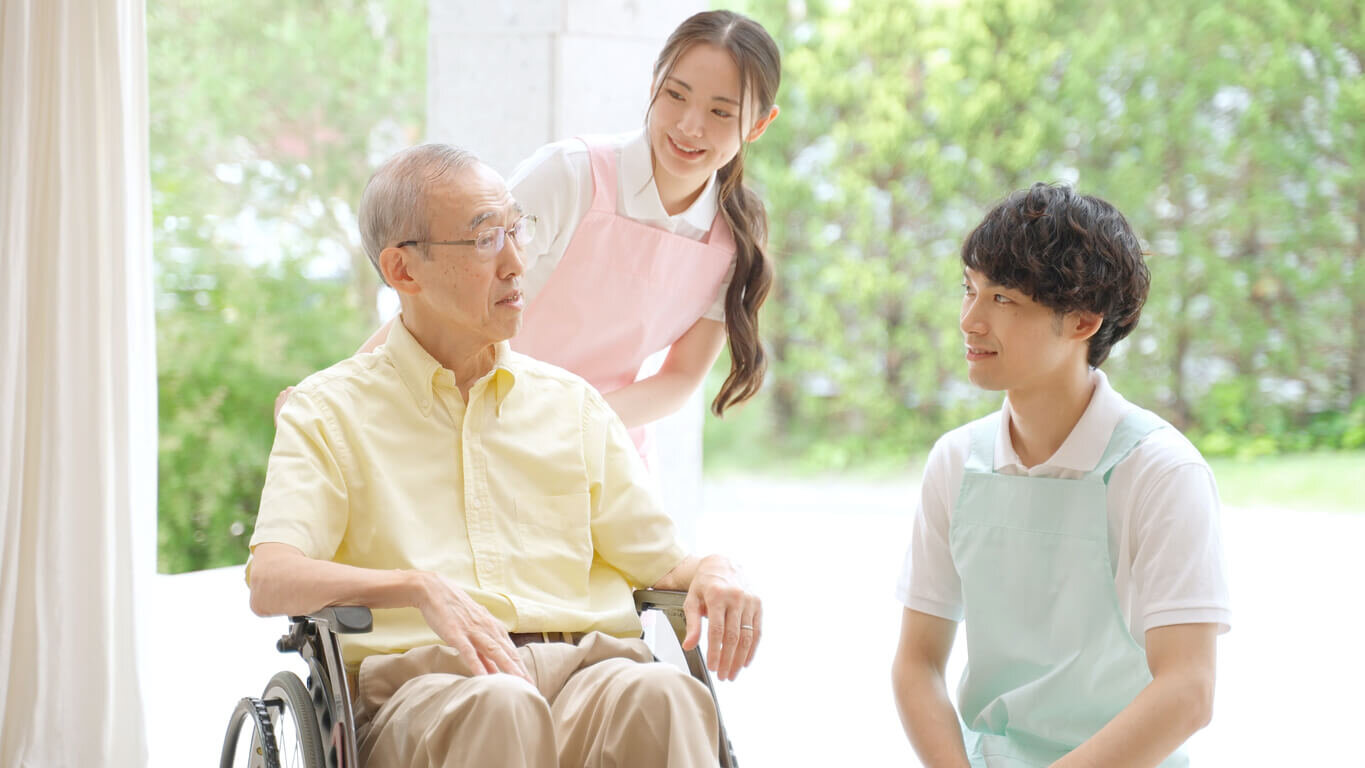
ここからはケアハウス、有料老人ホームに勤務する介護職員の仕事内容について見てみましょう。
ケアハウスで働く介護職員の仕事内容
ケアハウスでの業務は、一般型、介護型のいずれかによって仕事内容がやや異なります。それぞれの特徴は以下のとおりです。
●一般型ケアハウス
職員は、入居者の生活支援サービス(掃除や洗濯、食事の提供、各種相談の対応など)が業務の中心となります。また、夜間帯では巡回やナースコールへの対応、緊急時の対応なども行います。
●介護型ケアハウス
介護型ケアハウスでは、一般型ケアハウスで提供するサービスに加えて、入居者に対する日常生活上の介護サービス・機能訓練を提供します。具体的には次のようなものです。
- 食事、入浴、排泄などの介助
- 移動時の介助、整容・更衣の介助
- 起床や就寝時の介助、リネン交換とベッドメイキング
- 夜間帯の巡回、就寝時の体位変換、ナースコール対応など
有料老人ホームで働く介護職員の仕事内容
有料老人ホームで働く介護職は、施設の種類によって仕事内容が異なります。
●介護付き有料老人ホーム
要介護状態の高齢者が入居しているため、食事、入浴、排泄介助などの介護サービスを提供します。入居者の介護度やニーズは異なるため、1人ひとりに合った介護の提供が求められます。その他、入居者の身の回りの世話、レクリエーション、機能訓練などのサービスも提供します。
●住宅型有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームよりも介護度が低い方を入居の対象としているため、職員が介護サービスを提供することはありません。よって、職員は入居者に食事を提供するとともに、居室の掃除や洗濯などの身の回りの世話、緊急時の対応などを行います。その他、レクリエーション、サークル活動の場の提供を行います。
●健康型有料老人ホーム
入居者は日常生活上で自立した高齢者であるため、職員は食事の提供、居室の掃除や洗濯などの身の回りの世話、レクリエーションやサークル活動の場の提供を行います。また、入居者と何気ないコミュニケーションを取ったり、健康相談を受けたりして、彼らが充実した日々を送ることができるような環境づくりを行います。
それぞれの施設における人員配置の違い
ケアハウスの人員配置基準は次表のとおりです。
| 一般型ケアハウス | 介護型ケアハウス | |
| 施設長 | 1人 | 1人 |
| 生活相談員 | 入居者120人に1人 | 入居者100人に1人 |
| 看護師 | - | 入居者30人に1人 |
| 介護職員 | 入居者30人に1人 | 入居者3人に1人 |
| 栄養士 | 1人以上 | - |
| 機能訓練指導員 | - | 1人以上 |
| 介護支援専門員 | - | 1人以上 |
参考:「自立した、尊厳のある生活を支える軽費老人ホーム・ケアハウス」 公益社団法人 全国老人福祉施設協議会
一方、介護付き有料老人ホームについては法令で細かい人員配置が定められています。住宅型・健康型については、設置者がサービス内容に応じて配置人員を決めることができるため一律に定められているわけではありません。ただし詳細は施設によって異なります。
| 介護付き 有料老人ホーム | 住宅型・健康型 有料老人ホーム | |
| 管理者(施設長) | 1人 | 1人 |
| 生活相談員 | 1人以上 | 必要数 |
| 看護師 | 入居者30人に1人 | 必要数 |
| 介護職員 | 入居者3人に1人 | 必要数 |
| 機能訓練指導員 | 1人以上 | - |
| 介護支援専門員 | 以上 | - |
参考:「特定施設入居者生活介護」厚生労働省 社保審-介護給付費分科会 第179回(R2.7.8)
非常時の対応
ケアハウス、有料老人ホームいずれも緊急時対応の内容は大差ありません。主に次のような対応を行います。
| 項目 | 内容 |
| 初期対応 | 施設内職員への周知、緊急救急搬送の連絡など |
| 応急手当て | 必要に応じて心肺蘇生、AED操作、止血などの処置 |
| 記録 | 傷病者の状況を記録する(呼吸の有無、反応の有無、これまでの経緯) |
| 救急隊の案内 | 救急車、隊員を患者のところへ案内 |
| 救急車に同乗 | 必要に応じて医療機関への搬送に付き添う |
| 事後対応 | 施設内職員との情報共有 |
多くの施設では緊急時対応のマニュアルを整備しています。介護職には、そのマニュアルに沿って迅速かつ冷静に対応することが求められます。
7.ケアハウスと有料老人ホームで働くメリット・デメリット

ここからは、ケアハウスと有料老人ホームに勤務するうえでのメリット、デメリットについて説明します。施設によってそれぞれの違いがあるため、自分に合った働き方ができるかどうかチェックしておきましょう。
ケアハウスに勤務するメリット・デメリット
ケアハウスの場合、以下のようなメリット・デメリットがあります。
【メリット】
●介護職未経験も就業可(一般型ケアハウスの場合)
一般型ケアハウスにおいて職員の主な仕事は、生活支援サービスです。そのため、介護職未経験者でも就業しやすいという特徴があります。また、職員は入居者に対して介護サービスを提供することはなく、身体的負担は少ないといってよいでしょう。
●介護スキルの向上が期待できる(介護型ケアハウスの場合)
介護型ケアハウスの場合、職員は入居者に対して介護サービスを提供します。経験を積めば介護のスキルを向上させることができます。「介護の実務経験が○年以上」というキャリアは、転職活動時に有利に働くでしょう。
●社会福祉法人が運営するため安定している
ケアハウスの代表的な運営元は、社会福祉法人です。社会福祉法人は公益性の高い法人であり、国から補助金が出ていることから組織として安定しています。つまり、倒産のリスクが低いといえるため、職員は安心して仕事に従事できるでしょう。
【デメリット】
●夜間勤務(夜勤)がある
一般型、介護型ケアハウスいずれも夜間勤務(夜勤)があります。夜間帯の仕事内容には、入居者の就寝準備、巡回、就寝時の体位変換、ナースコールの対応、緊急時対応などがあります。夜勤帯は、昼間帯と比べて職員の数が少なくなるため、勤務する職員の担う役割が多くなってしまう点がデメリットであるといえます。
●身体的負担が大きい(介護型ケアハウスの場合)
介護型ケアハウスに勤務する場合、職員は入居者に対して介護サービスを提供するため、介護業務に伴う身体的負担があります。特に介護職の職業病といわれる腰痛に不安がある方は注意が必要です。
有料老人ホームに勤務するメリット・デメリット
続いて、有料老人ホームに勤務する際のメリット・デメリットを見てみましょう。
【メリット】
●福利厚生が充実している傾向
施設によって異なりますが、特に大手企業が設置・運営する有料老人ホームでは福利厚生(賃金以外の報酬、例:住宅手当、社員食堂、レジャー施設利用時の割引など)が充実している傾向にあります。うまく利用すれば、休日を有意義に過ごせます。
●身体的負担が少ない(住宅型、健康型有料老人ホームの場合)
住宅型、健康型有料老人ホームの職員が提供するサービスは、生活支援サービスが主となるため、働くうえで身体的な負担が少ないでしょう。
●接遇スキルが身につく
有料老人ホームは施設によって入居費用の設定がさまざまで、それぞれに入居者の求めるニーズが異なります。特に、入居費用を高額に設定している施設では品質の高い接遇が求められることがあります。こうした環境で働いていると、高い接遇スキルが身につきやすく、新たに転職する際に保有スキルとしてPRできるでしょう。
●資格取得サポートがあるところも多い
上記の福利厚生と関連しますが、有料老人ホームを運営する企業のなかには、職員の資格取得を応援し、サポートする体制を整えているところがあります。ステップアップを目指す場合には、こうした支援体制がある施設で働くと、モチベーションも高まります。具体的には次のような例です。
| 初任者研修 | 実務者研修 | |
| A有料老人 ホーム | 職員が、同研修を修了して入職した場合、1年間勤続したら研修費用を全額キャッシュバック。 | 勤務する職員が同研修を受講する場合、受講費用の半額を補助する。また、優先してシフトの調整を行う。 |
| B有料老人 ホーム | 施設自体が同研修を開講し、勤務する職員がこれを受講した場合、研修費用が無料。かつ、優先してシフトを調整してくれる。 | 勤務する職員が同研修を受講する場合、研修費用の2/3を補助する。また、上司が修了試験に向けた対策講座を実施してくれる。 |
【デメリット】
●高度なニーズに対応するスキルが求められる
有料老人ホームの入居者はケアハウスと比べて倍以上の費用を払っていることになります。そのため、提供されるサービスや接遇に高い品質を求める入居者も少なくありません。職員は普段から対応品質の向上を図るための研修・訓練を受ける必要があり、入居者のニーズに対応することになるでしょう。こうした接遇面において、ストレスが発生しやすいかもしれません。
●介護スキルを身につけることが難しい(健康型有料老人ホームの場合)
前述のとおり、健康型有料老人ホームにおいては介護を必要としない自立した高齢者が入居しています。そのため、職員が介護サービスに従事することはありません。介護スキルを身につけたい、向上させたいと考えている方は、健康型有料老人ホームでの仕事は向かないでしょう。
8.ケアハウスと有料老人ホームの仕事に就くうえで必要な資格

介護型ケアハウスや介護付き有料老人ホームで働く際、介護に関わる資格を持っていた方が有利です。転職活動に向けて、介護系資格の取得をおすすめします。ここでは、施設で介護職として仕事に就くうえで持っておいた方がよい資格を紹介しましょう。
介護職員初任者研修
介護職員初任者研修(以下、初任者研修)は、介護系資格のなかで最も基本となる資格です。介護業務が未経験の人でも、基礎から学ぶことができ、これから介護分野で働きたいと思う初心者にとって最適な資格だといえるでしょう。
受講期間は、自治体によって異なるものの、一般的に130時間以上の講習受講が必要です。最短1ヶ月程度で取得できるコースがあり、あまり時間をかけずに取得できる場合もあるため、確認してみましょう。この資格があれば、介護型ケアハウスや介護付き有料老人ホームだけでなく、訪問介護事業所や通所介護を行っている施設でも働くことができます。
介護福祉士実務者研修
介護福祉士実務者研修(以下、実務者研修)は、初任者研修の上位とされる資格です。介護職未経験であっても受講でき、初任者研修と比べると学習に費やす時間が増えますが、基本から応用まで学べる研修です。
受講期間は、450時間・6ヶ月以上と定められています。ただし、受講者が既に持っている資格(初任者研修修了やホームヘルパー2級等)によって、受講する科目の一部が免除されるため、人によって実際の受講期間は異なります。
一般的には通信教育を受けて学習を進め、一部を通学して学ぶスタイルです。詳細は、自治体や実施期間によって異なるため、事前に確認しておきましょう。なお、通学に要する期間は6日〜9日間で済むので、仕事をしている人でも受講・修了が可能です。
介護福祉士
介護福祉士は、介護分野におけるプロフェッショナルと国が認める国家資格です。
前述の初任者研修や実務者研修の上位に位置し、介護系資格のなかで最上位資格であるといえます。この資格があれば、介護型ケアハウス・介護付き有料老人ホームなどで働くことができるだけでなく、介護職をまとめるリーダー的な役割を担う役職に就くことができます。施設で提供する介護の質を担保する役割といってよいでしょう。
介護福祉士の国家試験には、受験資格があります。ここでは代表的な2つのルートを紹介します。
1. 養成校ルート
介護福祉士養成施設(専門学校や短期大学など)へ通学し、専門知識や技術を学び、決められたカリキュラムを履修して、卒業と同時に介護福祉士国家試験の受験資格を得るルートです。入学してから卒業までにかかる期間は2年〜3年、卒業年度の1月末に「受験資格取得見込み」として、初めて国家試験を受験できます。受験後、合格すれば資格を得られます。
2. 実務経験ルート
専門学校などの養成校に通わずに、実務経験を積みながら受験資格を得るルートです。受験資格取得の要件は、実務経験3年+実務者研修の修了です。介護の実務経験を積みながら、ちょうど3年を迎える頃に実務者研修の修了を目指すとよいでしょう。
要件を満たす、もしくは満たす見込みで介護福祉士国家試験の受験を申し込み、合格して資格取得という流れです。社会人として仕事をしながら国家資格の取得を目指している方にとっては、このルートが最適です。
なお、介護福祉士国家試験は年1回実施され、例年であれば、毎年1月末の日曜日に全国で試験が行われます。合格率は近年では約70~80%台で、合格しやすい国家資格の1つです。
9.ケアハウスと有料老人ホームのQ&A

ここからは、ケアハウスや有料老人ホームに関するよくある質問を紹介します。職員として質問されたときに適切に回答できるよう、知識を深めておきましょう。
特別養護老人ホームとはどう違うの?
特別養護老人ホームとは、介護保険法の定める施設で、自宅での生活が難しい要介護3以上の高齢者が入所する施設です。入所者の多くは認知症や重度の要介護状態の方で、これまで紹介したケアハウスや有料老人ホームとは異なる性質を持った施設であるといえます。ターミナルケア(看取り、終末期ケア)に対応しているのも特徴といえるでしょう。
勤務する介護職員は、入居者に対して食事、入浴介助、排泄の介助のみならず、更衣や口腔ケア、清拭(身体を拭いて清潔に保つ)などのサービスを提供します。
シルバーマンションとの違いは?
有料老人ホームのなかには、施設名に「シルバーマンション」や「高齢者下宿」といった名称で運営されているところがあります。名称が異なると印象が変わるため、別の施設のように思われるかもしれません。しかし、こうした名称を使っていたとしても、老人福祉法の定義に該当する施設(入居する高齢者に対して食事、介護、家事、健康管理のサービスのうち、いずれか1つ以上を提供している)であれば、有料老人ホームに該当します。
ただし、「シニア向け分譲マンション」については、まったく状況が異なります。一般的な分譲マンションの対象を高齢者向けとしているだけで、介護施設ではありません。老人福祉法の定義に該当しない、一般住宅を指します。
有料老人ホームは閉鎖される可能性はある?
有料老人ホームの多くは民間事業者が運営するため、事業の採算が取れないと倒産・撤退する恐れがあります。公的な施設とは異なり、利用者がいたとしても、閉鎖になる可能性があるでしょう。
東京商工リサーチの「コロナ禍と物価高で急増 「介護事業者」倒産は過去最多の143件、前年比1.7倍増~ 2022年「老人福祉・介護事業」の倒産状況 ~」の資料によると、2022年における「老人福祉・介護事業」の倒産件数が143件で、過去最高となりました。このうち、有料老人ホームの倒産件数は12件で、数は決して多くはないものの、リスクがゼロではありません。
まとめ:ケアハウスと有料老人ホームの違いを理解し、転職に役立てよう

ケアハウスは自立した生活を送ることが難しい高齢者が入所し、食事の提供、生活支援サービス、場合によって介護サービスを提供します。ケアハウスは有料老人ホームよりも安い費用で入居できるものの、待機者が多い傾向にあります。
一方の有料老人ホームは、ケアハウスよりも入居費用は高めですが、ケアハウスほど待機者はおらず、すぐに入居できる施設もあります。また、食事の提供、生活支援サービス、介護サービスを提供のほか、施設によってはコンシェルジュなどの付加価値の高いサービスが提供されています。ケアハウスと有料老人ホームのそれぞれの特徴や違いを理解したうえで、自分に合った職場を探してみましょう。
スピード転職も情報収集だけでもOK
マイナビ介護職は、あなたの転職をしっかりサポート!介護職専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを行います。
はじめての転職で何から進めるべきかわからない、求人だけ見てみたい、そもそも転職活動をするか迷っている場合でも、キャリアアドバイザーがアドバイスいたします。

SNSシェア















