防災介助士とは?学習内容と資格取得のメリット・流れ
構成・文/介護のみらいラボ編集部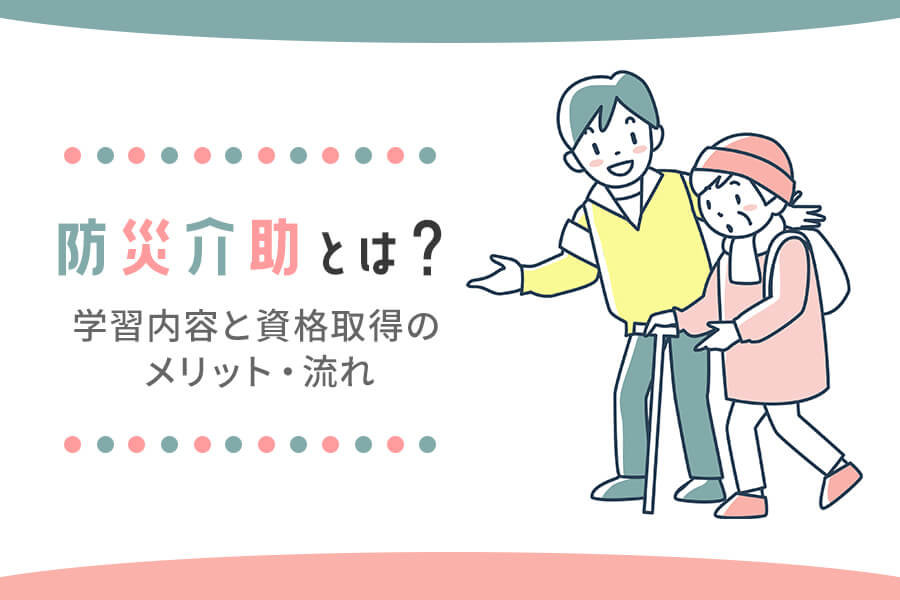
日本は、災害大国と言われるほど、自然災害に見舞われやすい国です。そして、大規模な災害が発生した際、高齢者や障害者をはじめとした迅速な避難が難しい人たちは、特に被害を受けやすくなります。
介護職員として働く人の中には「たった今災害に巻き込まれたら、自分は目の前の命を守れるだろうか」と不安に思うこともあるでしょう。いつ起こるか分からない非常事態への備えとして、必要な知識を学べる資格が防災介助士です。
この記事では、防災介助士の概要と資格取得によって得られるメリット、資格取得方法を解説します。
1.防災介助士とは?
防災介助士とは、災害発生時における要配慮者・避難行動要支援者への対応方法を身につけ、日頃からどのようなリスク対策を行うべきかを学んだ介助者のことです。
自然災害の頻発に加えて人為的な災害も懸念される昨今では、防災・減災に対する意識の高まりを受け、地域行政や企業でさまざまな対策が練られ、訓練が行われています。しかし、多くは健常者の使用や行動を前提としており、高齢者や障害者をはじめとする支援が必要な人への配慮は、まだまだ十分とは言えません。
災害発生時には、高齢者や障害者の多くが逃げ遅れたり、不便な避難生活を強いられたりする確率が高くなります。また、健常者でも災害発生に伴い、ケガや病気に直面するケースは珍しくありません。
有事の際、すべての命を円滑に救助するためには、社会のバリアフリー・ユニバーサル化を防災・減災の観点からも考えることが大切です。なお、防災介助士は国家資格ではなく、公益財団法人:日本ケアフィット共育機構が創設した民間資格制度の1つとなります。
また、主に高齢者や障害を持つ人が、年齢や障害に関係なく社会に参加できるようサポートするための「サービス介助士」という資格も、災害発生後のケアに有効活用できます。
●サービス介助士とは?学べる内容・資格取得のメリット・取得方法
防災介助士の資格取得で学べる内容
防災介助士は、"防災・災害におけるバリアフリー・ユニバーサルデザイン化"を、「知る」「守る」「助ける」の3つの視点から学ぶ資格です。
・知る
知る視点からは、災害と防災の基礎知識を学びます。地震や台風といった自然災害だけでなく、大規模事故発生やテロ行為といった人為災害に至るまで、あらゆる災害の特徴を包括的に学ぶことが重要です。災害で発生する被害や混乱状態で人が直面する脆弱性、連鎖的に起こり得る事態などを知っておくことで、非常時の被害を最小限に抑えるために何が必要かを理解できるでしょう。
・守る
守る視点からは、防災意識の重要性を学びます。災害発生時に必要となる防災グッズは、常日頃からストックすることが大切です。またいざというときの避難経路や救助用品のありかは、平時からしっかりと頭に叩き込んでおかなければ、とっさに使用することができません。日常生活の中でも、折につけ防災を意識し周囲にも注意喚起し続けることは、災害発生時により多くの人を守れる可能性を高めます。
・助ける
助ける視点からは、実際に災害と遭遇した際に取るべき行動を学びます。災害発生時における高齢者・障害者の介助方法に加え、止血などの基本的な応急手当の方法、自力での避難が難しい状態に陥った人の搬送方法などを学ぶ項目です。
防災介助士は、上記3つの視点をもとに通常の防災対策や防災訓練ではカバーしきれない、避難行動要支援者への対応に重点を置いて学びます。
(出典:公益財団法人 日本ケアフィット共育機構「防災介助士とは?」)
2.防災介助士の資格を取るメリット
防災介助士の資格を得ることで、以下のようなメリットが得られます。
・災害発生時に冷静な行動ができる
・リーダーシップが身につく
・責任ある役割を任されやすくなる
・転職・就職時のアピールに使える
災害発生時に少しでも多くの命を助けて安全を確保するためには、周囲のパニックに飲まれることなく、正確な知識を持って冷静に対処しなければなりません。災害発生時にどのようなことが起こるか、どのように対処すべきかを学んでおくことで、万が一のときにも冷静な判断と行動が可能となります。
また、防災介助士の講座では、現場におけるチーム作りの基本となるICS( Incident Command System)を学びます。周囲との情報共有や外部との連携、効率的なチームの運営方法は、災害時のみならず仕事にも利用できる知識です。
災害時に冷静さを保てる人や、チーム運営の知識を持っている人は、平常時にも重宝されます。職場で重要な役割を任されるようになったり、転職・就職時のアピール材料として利用できたりといった点も、防災介助士の資格取得者となるメリットと言えるでしょう。
3.防災介助士の資格取得の流れ
防災介助士資格取得には、テキストによる自宅学習と課題提出、および実技教習の受講が必要です。実技教習受講後に行われる筆記試験で合格点を取れば、資格の登録申請ができます。なお、実技教習開始までに救急救命講習の修了が必要です。
以下では、防災介助士の資格取得に至るまでの流れを4つのステップに分けて解説します。
STEP1:申し込み
防災介助士資格取得講座申し込みは、公益財団法人:日本ケアフィット共育機構が運営する、防災介助士公式サイトから行えます。申し込みフォームに必要事項を記入し、受講料を支払えば受講開始です。受講に必要な資格・条件などはありません。
防災介助士資格申し込みの概要は、下記の通りです。
| 受講対象 | 申込者全員 | |
|---|---|---|
| 受講料 | 27,500円(消費税10%込) | |
| 支払方法 | 払込取扱票 |
・コンビニ ・郵便局 |
|
クレジットカード (1回払いのみ) |
・VISA ・MASTER ・JCB ・AMEX ・ダイナース |
|
(出典:公益財団法人 日本ケアフィット共育機構「取得の流れ・料金」)
STEP2:自宅学習・課題提出
受講申し込み受付後に、テキストと課題が1部ずつ送られてきます。テキストをもとに自宅で学習し、事前課題を提出しましょう。事前課題は100問、70点未満の場合は再提出が必要です。ただし、実技教習を受講するまでに、救急救命講習を受講しておかなければなりません。
救急救命講習は、全国の消防署および日本赤十字社が開く講習会です。開催場所・日時の詳細は、管轄の消防署もしくは最寄りの日本赤十字社支部へ問い合わせてください。防災介助士の実技教習には、下記4講習のいずれかが必要です。
| 消防署 | 「普通救命講習 I」または「普通救命講習 II」 |
|---|---|
| 日本赤十字社 | 「救急法一般講習」または「基礎講習」 |
講習内容がAEDのみの場合は受講したと見なされないため、注意しましょう。
(出典:公益財団法人 日本ケアフィット共育機構「取得の流れ・料金」)
STEP3:実技教習・筆記試験
提出課題で70点以上獲得し、救急救命講習の受講が済んだら、実技教習・筆記試験へ進みます。教習会場は東京・大阪・福岡の3か所、専用フォームから申し込む事前予約制で、時間割はどの会場でも同じです。
| 実技教習 | 9:30〜16:00 |
|---|---|
| 筆記試験 | 16:00〜17:00 |
実技教習では、災害の理解や地域安全、共育的リーダーシップのためのワークをはじめ、災害発生時を想定した実践的な救急・介助技術を学びます。筆記試験では50問が出題され、100点満点中70点以上獲得で合格です。合格率は80%を超えており、比較的難易度は低めとされています。
(出典:公益財団法人 日本ケアフィット共育機構「取得の流れ・料金」)
STEP4:登録申請・認定授与
筆記試験の合否連絡は、2~3週間ほどで届きます。合格通知が来た人は、防災介助士資格の登録申請を行い、認定状と認定証を受け取りましょう。なお、試験が70点未満で不合格となった場合も再受験が可能です。
| 再受験料 | 3,300円(消費税10%込) |
|---|
また、資格取得後は、3年ごとに更新手続きを行わなければなりません。
| 資格更新料 | 3,300円(消費税10%込) |
|---|
全カリキュラムを履修し資格試験合格に至るまでには、平均して2〜3か月かかります。受講期間に12か月の制限があるものの、特段の理由が認められる場合は防災介助士受講期間延長申請フォームから期間延長を申し込むことが可能です。
| 延長申請料 | 2,200円(消費税10%込) |
|---|
(出典:公益財団法人 日本ケアフィット共育機構「取得の流れ・料金」)
まとめ
防災介助士は、災害発生時に取り残されがちな高齢者や障害者といった、要配慮者・避難行動支援者への対応方法を身につけられる資格です。また、バリアフリー・ユニバーサル化へ平常時から取り組むことの社会的必要性を広く訴えるために有効な知識も学べます。
「介護のみらいラボ」では、介護業界の最新ニュースやスキルアップの方法といった、有益な情報を多数掲載中です。介護福祉の担い手として今よりもっと活躍したいと考える人は、ぜひ「介護のみらいラボ」をご利用ください。
※当記事は2022年3月時点の情報をもとに作成しています
【日本全国電話・メール・WEB相談OK】介護職の無料転職サポートに申し込む
スピード転職も情報収集だけでもOK
マイナビ介護職は、あなたの転職をしっかりサポート!介護職専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを行います。
はじめての転職で何から進めるべきかわからない、求人だけ見てみたい、そもそも転職活動をするか迷っている場合でも、キャリアアドバイザーがアドバイスいたします。

SNSシェア















