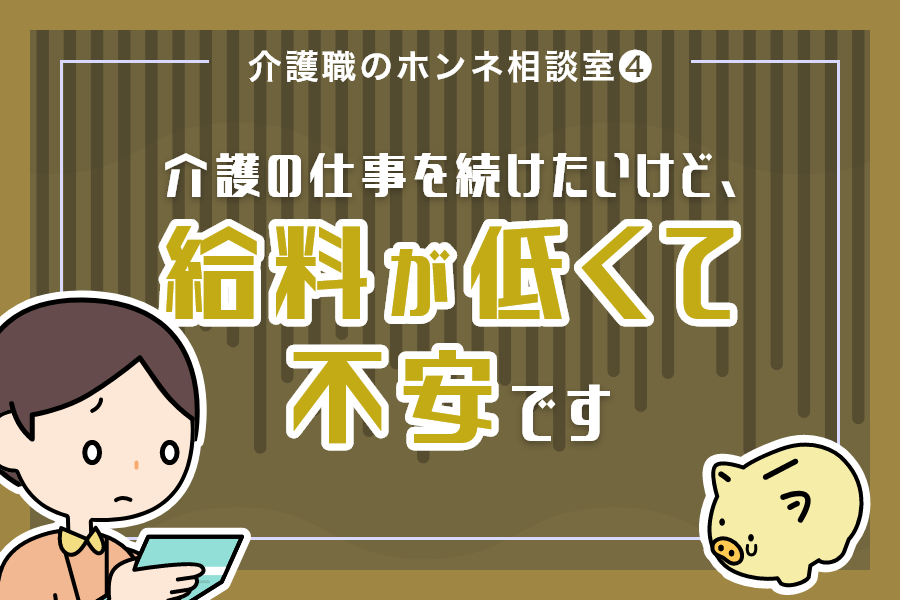医療ソーシャルワーカーに向いているのはどんな人? 実際の仕事内容や必要なスキルを紹介
文/倉元せんり
医療ソーシャルワーカー(以下、MSW)は、医療機関で患者さんやご家族の困りごとに対して、必要な支援を行う相談援助職です。もしかしたら、みなさんのなかにも「医療ソーシャルワーカーとして働いてみたい」「でも、自分にできるだろうか」と思っている方がいらっしゃるかもしれませんね。
そこでこの記事では、MSWに向いている人の特徴や必要なスキルを紹介します。MSWになりたい方や興味がある方は、ぜひ参考にしてみてください。
1.医療ソーシャルワーカーの仕事内容
MSWの仕事の仕事内容は、以下の6つに大別されます。
- 療養中の心理的・社会的問題の解決、調整援助
- 退院援助
- 社会復帰援助
- 受診・受療援助
- 経済的問題の解決、調整援助
- 地域の保健医療福祉システムづくりに参画する地域活動
参考:『医療ソーシャルワーカー業務指針』(厚生労働省健康局長通知)
仕事の多くは、病気の発症や後遺症によって発生した困りごとに対する相談援助で、MSWは「利用できる制度を知りたい」「入院費を払えるか不安」などの悩みを解決する役割を担います。
所属する医療機関によって名称は異なるものの、MSWは「医療相談室」や「地域医療連携室」などの部署に在籍しています。これらの部署の求人募集は、社会福祉士や精神保健福祉士の有資格者を条件とするケースがほとんどで、MSWは福祉の専門知識が求められる仕事と言えるでしょう。
2.医療ソーシャルワーカーに向いている人
MSWとして活躍するには、患者さんや家族の話をよく聞き、課題を引き出し、支援を進めていく力が必要です。ここでは、MSWに向いている人の特徴を具体的に紹介します。
複数の仕事を丁寧に進められる人
MSWは常に複数の患者さんを担当し、同時に支援を進めなければなりません。筆者は、急性期・回復期リハビリテーション病棟のある医療機関に約8年間勤務しましたが、そのときは常に30名以上の患者さんを担当していました。
急性期病棟は病気を発症したばかりの方が治療をする病棟で、回復期リハビリテーション病棟は治療を終えた方がリハビリをする病棟です。そのため、入院間もない方に高額療養費の説明をした直後に、退院間近の方に介護保険サービスの説明をしたり、入所先の施設を紹介したりすることも多くありました。
そうした環境で働く場合、忙しくなると画一的な対応になりがちですが、患者さんによって、抱える感情や生活状況はさまざまです。そのため、患者さん1人ひとりと丁寧に向き合い、必要な支援を見極められる人はMSWに向いているでしょう。
感情に流されず冷静に対応できる人
医療機関に入院・通院する患者さんは、さまざまな不安を抱えているため、MSWは自身の感情をコントロールし、適切に患者さんやご家族に向き合う必要があります。
身体の不調はもちろん、経済的な不安や社会的役割の喪失など、抱えている不安は人それぞれです。面接の場面では、患者さんやご家族が涙を流したり、怒りをあらわにしたりするケースも少なくありません。そして、目の前で感情をぶつけられると、MSWもさまざまな感情を抱いてしまいます。
しかし、MSWは患者さんやご家族の感情表現を受容し、共感しながら、それぞれの状況を冷静に判断しなければなりません。MSWが感情的になってしまうと、課題の本質を見極められなくなるからです。
MSWは常に「平常心を保てているか」「今抱いている感情は誰の感情か」を自分に問いかけ、冷静に対応する必要があるでしょう。
患者さんにとっての「よりよい支援」を常に考えられる人
MSWは丁寧に話を聞いた上で、患者さんやご家族にとっての「よりよい支援」を考える必要があります。
筆者がMSWだったとき、脳梗塞を発症して入院された方がいらっしゃいました。その方は重い後遺症が残ったため、病状説明で「家には帰れないので、長期療養型病院へ転院を」と伝えられ、MSWの私と面接することになりました。
しかし、面接に臨まれたご家族は何かに引っかかっている様子。聞いてみると、「家での生活がとても好きな人なので、何とかして自宅に戻らせたいんです」とのことでした。
患者さんはすべてに介助が必要で、立位もままならない状況でしたが、そうした場面にこそ、「よりよい支援」が求められます。そのため、私は他職種に介助指導を依頼したり、介護保険サービスの利用調整を行ったりと、できるだけの支援を行いました。結果、その方は無事に退院することができ、自宅へと帰られました。
もちろん、このようなケースばかりではなく、関係機関の判断や身体状況によっては、患者さんの希望通りに進められない場合もあります。しかし、希望や思いを丁寧に聞かなければ、患者さんにとっての「よりよい支援」はできません。それだけに、MSWは「病気になってもその人らしく生きるための支援」をいちばんに考える必要があるでしょう。
3.医療ソーシャルワーカーに向いていない人
ここからは、MSWに向いていない人の特徴について、詳しく紹介したいと思います。
自分のペースで仕事を進めたい人
MSWは医師や看護師、リハビリ職といった他職種との連携が必須です。例えば、患者さんの退院支援をする際は、治療方針やリハビリの進捗状況に加えて、退院後の希望や生活環境を把握しなければ支援が進められません。そのため、MSWには患者さんやご家族の思いを聞き取り、チームと共有する役割が求められます。加えて、外部の地域包括支援センターや、関連施設と情報を共有する場面も少なくありません。
このように、MSWは単独での支援ができないことから、他職種や他機関とのチームワークが重要になります。小まめな連絡・報告や情報共有が苦手な人、自分のペースで仕事を進めたい人は、MSWに向いていない可能性があるでしょう。
細かいことに気づくのが苦手な人
MSWは、患者さんやご家族の小さな変化に気づき、潜在的なニーズを汲み取って支援につなげる必要があります。そして、そのためには患者さんの言葉だけでなく、表情や雰囲気をよく観察しなければなりません。
例えば、相談内容が「施設を探してほしい」というものだったとしても、言葉の端々や表情から「家に帰りたい」という思いが読み取れる場合もあります。
MSWは患者さんの本当の思いを引き出し、その思いに寄り添いながら支援を行うことが重要です。言葉だけを頼りにせず、患者さんの細かな変化に常に目を向ける。これが苦手な人は、MSWに向いていないかもしれません。
4.医療ソーシャルワーカーになるために必要なスキル
繰り返しになりますが、MSWになるためには以下のスキルが必要です。
- コミュニケーションスキル
- 変化に気づくスキル
MSWの仕事においては、患者さんやご家族との信頼関係が欠かせません。だからこそ、相手の気持ちを傾聴し、受容しながら適切に会話できるコミュニケーションスキルは非常に重要です。
また、MSWには患者さん1人ひとりの変化に気づき、臨機応変に対応できるスキルが求められます。ときには、患者さんの意向が変化したことで、支援の方向性が変わる場合もあります。
MSWはそうした変化を敏感に察知し、受容しながら「よりよい支援」を考える必要があるでしょう。
5.医療ソーシャルワーカーはきついって本当?でもやりがいもある!
インターネット上には「MSWはきつい」といったクチコミが見られます。そうしたクチコミが広まる背景には、以下のような状況が影響しているのではないでしょうか。
- 病院と患者さんの板挟みに合う
- 多くの患者さんを担当するため忙しい
- 支援内容が複雑である
MSWは病院と患者さん側の意見の違いに悩まされる場合があります。最も多いのは、医師から「早期退院」と指示があったにもかかわらず、患者さん側に「退院したら不安」という思いがあるケースです。
また、病気の発症に伴って、経済面などのさまざまな問題が浮き彫りになるケースや、一度の面接では問題が解決しないケースもけっして少なくありません。
加えて、MSWは常に多くの患者さんを担当しています。そうしたさまざまな要素が重なって、「MSWはきつい」というクチコミにつながっているのでしょう。
確かにMSWの仕事は、慣れないと「きつい」と感じる場面が多いかもしれません。しかし、MSWは病院のなかで患者さんの視点に立って仕事をする唯一の福祉職です。そして、適切な支援につなげられるかはMSWにかかっています。もちろん大変なケースも多くありますが、患者さんと一緒に課題を解決できたときは、何ものにも代えがたいやりがいを感じるはずです。
まとめ:医療ソーシャルワーカーは大変だけど専門性の高い仕事! 迷っているなら飛び込んでみよう
MSWは医療機関で働く唯一の相談援助職です。医学的なサポートはできませんが、丁寧に話を聞いたり、患者さんにとっての「よりよい支援」を考えたりできる人であれば、MSWに向いていると言えるでしょう。
MSWには福祉の専門家として適切な判断と支援が求められるため、悩む場面も数多くあります。しかし、患者さんからの「ありがとう」の言葉は何よりうれしいものです。大きなやりがいを感じられる仕事なので、MSWに興味のある方は、ぜひ挑戦してみてください。
●関連記事:医療ソーシャルワーカー(msw)とは?仕事内容・必要な資格・給与事情
【日本全国電話・メール・WEB相談OK】介護職の無料転職サポートに申し込む
スピード転職も情報収集だけでもOK
マイナビ介護職は、あなたの転職をしっかりサポート!介護職専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを行います。
はじめての転職で何から進めるべきかわからない、求人だけ見てみたい、そもそも転職活動をするか迷っている場合でも、キャリアアドバイザーがアドバイスいたします。

SNSシェア