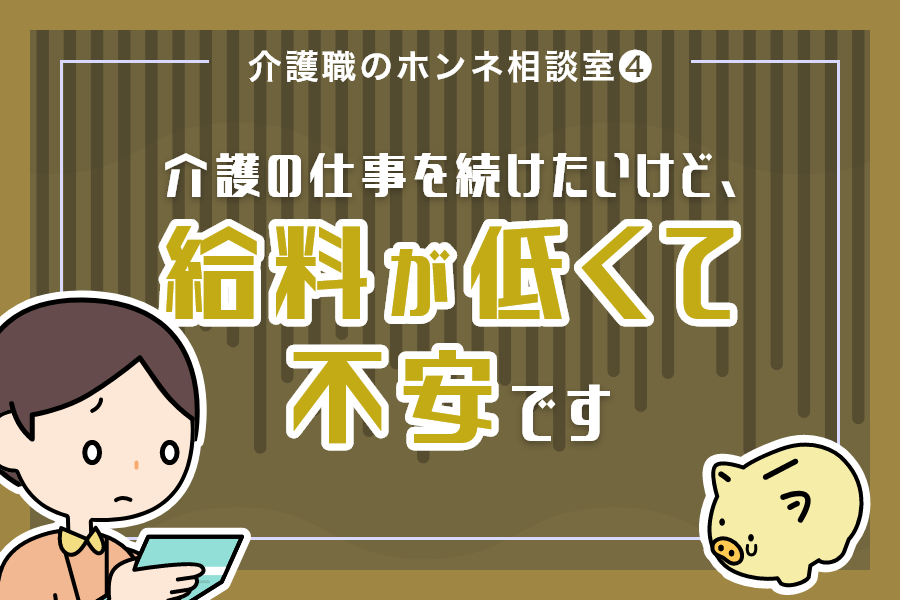「全部がうまくいかない!」仕事や人生で疲れたらどうしたらいい?
構成・文/介護のみらいラボ編集部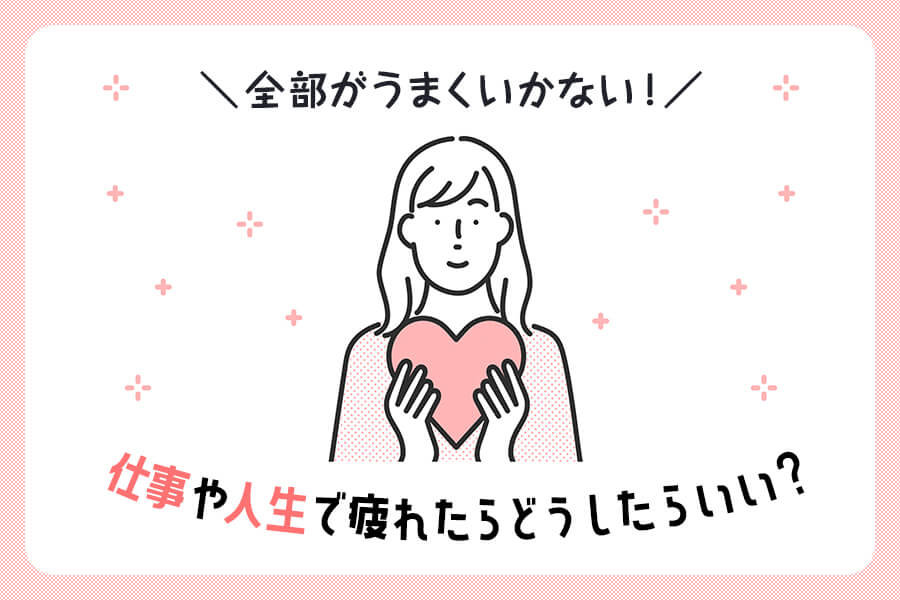
何をやっても失敗したり裏目に出たりと、すべてうまくいかないと思うようなときがあります。しかし、考え方や行動を変えれば悪い流れを断ち切ることができるでしょう。
当記事は、うまくいかないことが続く原因と、取るべき対処法について解説します。スランプを抜け出したい、前向きな気持ちになりたいという人は必見の内容です。
1.うまくいかないことが続く原因とは?
すべてがうまくいかないと感じるときは、以下の2つが原因となっている可能性があります。
・他人と比べて自分のミスを責め続けている
何かあるたびに、他人と自分を比べる人は少なくありません。「〇〇さんは優秀なのに、どうして自分はダメなんだろう」と考えた経験がある人もいるでしょう。物事を他人と比較することは適切でないものの、視野が狭くなっているときは悪い面ばかりが目につく傾向にあります。
・失敗を引きずってマイナス思考に陥っている
失敗ばかりが続くと自信を失い、最終的に「何をやっても、どうせうまくいかない」というマイナス思考に陥ります。負の連鎖をもたらし、なかなか抜け出せません。「次も失敗したらどうしよう」と考えているうちは、よい流れを引き寄せることは困難です。
2.「うまくいかない」を変える! 考え方のコツ3つ
周囲の反応を気にして、自分の考え方を変えることに怖さや抵抗を感じる人もいるでしょう。しかし、うまくいかない状況を打破するために、考え方を変えることは大切です。ネガティブな感情を払拭するために、「うまくいく考え方のコツ」を押さえておきましょう。
成長できる機会だと前向きに捉える
「失敗してうまくいかない=成長している途中」と、前向きに捉えることが大切です。成功者はいずれも、苦しいときでも行動をやめることがありません。諦めてしまえば、自分自身が成長できないことを理解しているためです。
仕事をしていると、困難だと感じる場面が少なくありません。介護職なら利用者やその家族から理不尽な扱いを受けたり、認知症利用者とうまく付き合えなかったりと、心が折れそうになることがあります。しかし、「きっと乗り越えられる」と考えて困難にチャレンジすれば、成長につながります。失敗を成長の糧にできるかは、自分の考え方次第です。
自分のことを客観的に見直す
うまくいかないときは、主観的になっている傾向があります。流れを変えるためには、客観的に自分を見直すことが必要です。客観的とは「第三者の視点で自分を見ること」であり、冷静に物事を捉えて正しい判断ができます。
過去を振り返れば、「自分の受け止め方や、判断がまちがっていた」と思い当たる人もいるでしょう。客観的に自分を見るためには、行動や会話を記録して「他者の目線」で観察することが有効です。ビデオ・レコーダー・スマートフォンなどを使って実践してみましょう。
家族や職場の人たちに、自分のイメージを詳しく聞いてみる方法もおすすめです。自分が知らなかった癖や考え方に気付いたら、素直に受け止めて改善することが大切です。
できないことは、できないと認める
世の中には、自分の力だけではコントロールできないこともあります。成長するためには努力や行動が欠かせない一方で、状況によっては「できない」と認めることも必要です。ありのままを受け入れれば気持ちが楽になり、失敗を恐れなくなります。
まずは自分のできる範囲で目標を立てて、小さな成功体験を積み重ねていくことが重要です。例えば「利用者を笑顔にする」「スムーズな移乗介助を覚える」などの目標であれば、短期間で実現しやすいでしょう。
やると決めたことが達成できれば大きな自信になり、さらなる目標に向けて行動できるようになります。日々の積み重ねによって、自分に対する周囲の評価も自然と変わってきます。
3.うまくいかない日々から脱却する4つの行動
自分の行動を変えるだけで、うまくいかない日々から抜け出せる可能性があります。すぐに考え方を変えられないという場合でも、意識的に行動することは比較的容易です。
では、どのような内容を実践することが望ましいでしょうか。4つの項目に分けて解説します。
しっかり食べて運動してぐっすり寝る
前向きな気持ちを取り戻すためには、健康的な食事を摂ることが欠かせません。厚生労働省の「食事生活指針」では、脳や身体のエネルギー摂取を適正に保つために、ごはんなどの穀類を毎食摂ることを推奨しています。
野菜・果物・乳製品などを組み合わせて、ビタミンやミネラルなどの栄養素をバランスよく摂る必要性も挙げています。
(出典:厚生労働省「食生活指針について」)
また、日常生活に運動を取り入れて、気持ちのリフレッシュを図ることも必要です。
(引用:厚生労働省「健康づくりのための身体活動基準2013」)
運動はランニングやサイクリング、ダンスなどの「有酸素運動」が適切です。体力に自信がなければ、近所を散歩することから始めてもよいでしょう。1日20分を目安に、続けられる範囲で行うことがポイントです。
ぐっすり眠るためには、睡眠環境を整えなくてはなりません。身体への負担が少ない寝相を保てるように、自分に合った寝具を選びましょう。規則正しい睡眠習慣を身に付けるために、日光浴を行うことも重要です。
(出典:厚生労働省 e-ヘルスネット「健やかな睡眠と休養」)
普段はしない新しいことにチャレンジする
日常生活における刺激やときめきが不足すると、うつむくことが多くなります。新しいことにチャレンジすれば、気持ちが切り替わりうまくいかない日々を脱却できるでしょう。
何かを始めるといっても、内容にこだわる必要はありません。地域の活動やイベントに参加したり、習い事に通ってみたりと方法はさまざまです。思い立ったら、すぐに始めてみましょう。知識や経験が増えれば、思いもよらない場面で役立つ可能性があります。
新しいことを始める程の精神的な余裕がなければ、いつもと違うルートで通勤してみたり、行ったことのないカフェに立ち寄ってみたりするだけでも十分です。なお、新しいことにチャレンジする際には、挫折して落ち込まないように、ハードルを低めに設定することがポイントです。
自分の好きなことに徹底的に打ち込む
仕事やプライベートでのストレスを完全になくすことは難しく、マイナス思考に陥る前に対策する必要があります。自分が好きなことに徹底的に打ち込み、気持ちのリフレッシュを図りましょう。
ぼんやりと景色を見たり、ゆっくりお風呂に入ったりと、忙しい中でもリラックスできる時間を作ることが有効です。好きな音楽を聴くこともリフレッシュにつながります。なお、お酒にもリラックス効果が期待できるものの、アルコールは睡眠の質を低下させるため、飲みすぎには注意しましょう。
(出典:厚生労働省「みんなのメンタルヘルス」)
没頭していれば、憂鬱なことなど考えている暇がありません。好きなことでスケジュールを埋め尽くして、小さな失敗をしてもクヨクヨしない仕組みを作りましょう。
どうしてもつらいときは誰かに相談する
つらい気持ちを一人で抱え込むことは、事態を深刻化させます。つらいと感じたときは、信頼できる人に相談してみましょう。人に相談することで、自分だけでは見つけられなかった対処法が発見できる可能性があります。会話をする中で「なぜ、小さなことで悩んでいたのだろう」と気付く場合もあるでしょう。
惨めな気持ちを打ち明けることに抵抗感がある場合は、ただの雑談でもかまいません。天気やテレビの話題など、ちょっとした会話でも気持ちの切り替えにつながります。
(出典:厚生労働省「こころもメンテしよう」)
身近に相談相手がいない場合は、公的機関の専用窓口を利用しましょう。厚生労働省は悩みを持つ人や困っている人に向けて、電話やSNSで気軽に相談できる窓口を案内しています。いずれも専門家が対応するため、適切な意見や助言がもらえます。
(出典:厚生労働省「まもろうよ こころ」)
まとめ
あらゆることがうまくいかない原因は、他人と比べて自分のミスを責め続けている、失敗を引きずりマイナス思考に陥っていることが挙げられます。自分の考え方を変えれば、状況は必ず好転します。すぐに実現することが難しい場合は、まずは行動を変えてみましょう。
「介護のみらいラボ」は、介護現場で役立つ情報を掲載しています。介護職の基礎知識からキャリアアップの方法まで、内容はさまざまです。ぜひ、日常的な情報収集にご活用ください。
【日本全国電話・メール・WEB相談OK】介護職の無料転職サポートに申し込む
スピード転職も情報収集だけでもOK
マイナビ介護職は、あなたの転職をしっかりサポート!介護職専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを行います。
はじめての転職で何から進めるべきかわからない、求人だけ見てみたい、そもそも転職活動をするか迷っている場合でも、キャリアアドバイザーがアドバイスいたします。

SNSシェア