高齢者向け【紙コップ】レクリエーション!工作やゲームを紹介

有料老人ホームやデイサービスといった高齢者施設では、さまざまなレクリエーションが行われています。レクリエーションは、利用者さんにとって大きな楽しみの一つですが、その一方で、「レクリエーションの企画を考えるのが大変」と悩んでいる介護職員の方も少なくありません。
日々の業務を遂行しながらレクリエーションの企画を考え、準備のために買い出しに行くのは、非常に大きな負担となります。できることなら、時間と手間があまりかからず、それでいて、利用者さん全員が楽しめる室内レクリエーションを開催したいですよね。
そんな時におすすめなのが、紙コップを活用したレクリエーションです。そこで今回は、紙コップを使った高齢者向けの工作レクリエーション・ゲームレクリエーションを紹介します。高齢者レクリエーションの企画・進行を担当している方は、ぜひ参考にしてください。
1.紙コップが高齢者レクリエーションに適している理由
時間と手間があまりかからず、それでいて利用者さんが楽しめるレクリエーションを企画したい----。そんな時に大活躍するのが紙コップです。
紙コップが高齢者レクリエーションに適している最大の理由は、レクリエーション担当者の手間が少なくてすむことでしょう。紙コップは、コンビニやスーパー、ホームセンターなどさまざまな店舗で売られているため手に入りやすく、しかも安価です。また、わざわざ買い出しに行かなくても、施設内に大量にある場合もあります。
加えて、紙コップは軽く軟らかいため、多少雑に扱ったり落としてしまったりしても、利用者さんがけがをする危険性がほぼありません。切ったり着色したり、積み重ねたりといった作業も容易なので、特に工作レクリエーションには向いています。
2.紙コップを使った高齢者向け工作レクリエーション
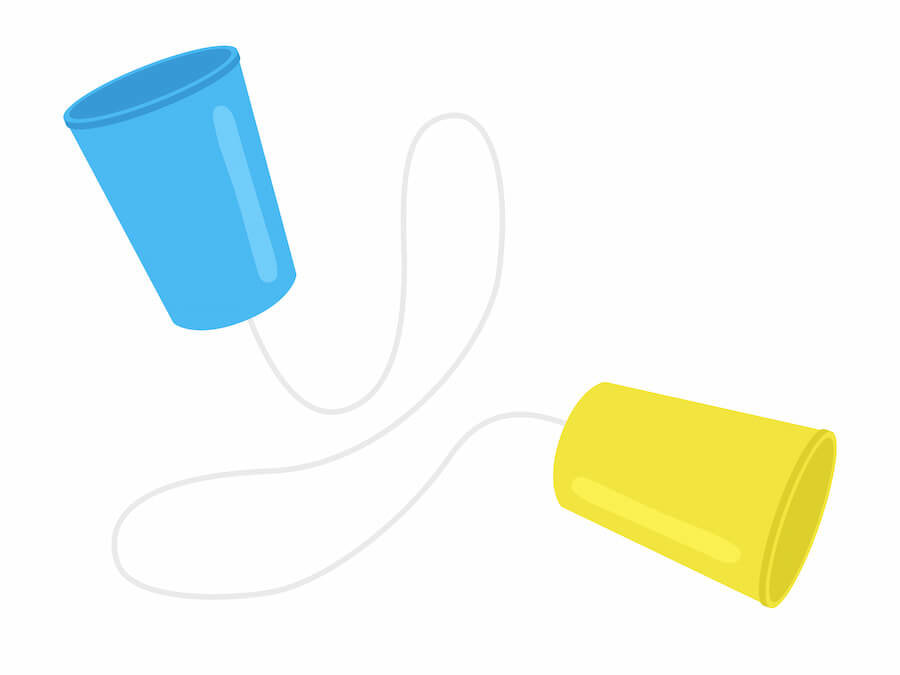
紙コップには、軟らかく加工しやすいという特性があります。そのため、工作にはもってこいのアイテムといえるでしょう。
●関連記事:「高齢者 レクリエーション 工作」
ここからは、紙コップを使った高齢者向けの工作レクリエーションを4種類紹介します。
糸電話
糸電話は昔ながらの工作遊びです。2つの紙コップを糸でつなぐだけなので、高齢者施設の利用者さんも気軽に取り組むことができるでしょう。完成後には、「子どもの頃に遊んだことがある」「懐かしい!」と、思い出話に花が咲くかもしれません。
<準備するもの>
● 紙コップ(2個で1セット)
● 糸(好みの長さにカットしておく)
● きりまたはつまようじ
● はさみ
● テープ
<作り方>
| (1) | 紙コップの底の中心部に、きり、またはつまようじで穴を開ける。もう1つの紙コップにも同様に穴を開ける |
|---|---|
| (2) | 紙コップの穴の外側から内側に向かって糸を通す。通した糸は2cmくらいの長さを残してはさみでカットし、抜けないようテープで留める |
| (3) | もう一方の紙コップにも同様に糸を通す。糸を内側の底にテープで留めたら完成 |
糸電話が完成したら2人1組になって、糸電話を楽しんでもらいましょう。1人は紙コップを耳にあて、もう1人は紙コップにむかって話しかけて、電話のように会話をします。
利用者さんが大勢いる場合は複数のチームに分け、糸電話を使って「伝言ゲーム」をして楽しむのも良いでしょう。なお、糸電話を使用して何かを話す場合は、糸をピンと張らせておくのがポイントです。
風車
風を受けて回転する風車を、紙コップで作ってみましょう。糸電話に比べて工作の難易度はやや高くなりますが、その分、完成した時の達成感もアップします。
<準備するもの>
● 紙コップ
● きり
● つまようじ
● はさみ
● 曲がるタイプのストロー
● 割り箸1本分
● ボンド
<作り方>
| (1) | 紙コップの底の中心部に、きりまたはつまようじで穴を開ける |
|---|---|
| (2) | 風車の「羽根」の部分を作る。紙コップの飲み口から底に向かって、筒部分が6等分になるように、はさみで切り込みを入れる。この時、切り込みは底の少し手前で終わるようにしておく |
| (3) | 紙コップを底が上になるように立てる。(2)で切って作った部分を、根元からやや斜めに谷折りにして羽根を作る。残りの5カ所も同様に折る |
| (4) | (1)で開けた穴にボンドを塗り、つまようじを紙コップの外側から内側に向かって差し込んで固定する。つまようじの外側に突き出た部分に、ストローの飲み口側を差し込む |
| (5) | ストローを折り曲げ、ストローの下の穴から割り箸を差し込む |
完成した風車は、息を吹きかけたり、手に持って歩いたりして、羽根が回る様子を楽しみます。(3)の工程を終えたら、カラーペンなどで羽根や底の部分に絵や模様を描いてもらうのも良いでしょう。一人ひとりの個性が見えて、コミュニケーションの活性化にもつながります。
なお、(4)の工程が終わったところで、つまようじの頭の部分(みぞが彫られている部分)をソフト粘着剤などで覆っておくとより安全です。
パペット
「パペット」は「操り人形」の総称ですが、一般的には「手指で操る人形」を指します。軟らかく加工しやすい紙コップを使って、パペットを作ってみましょう。紙コップのパペットは、作る過程を楽しむだけでなく、完成品で遊ぶことでコミュニケーションの活性化が期待できる点も魅力です。
<準備するもの>
● 紙コップ
● 画用紙や折り紙
● はさみ
● のり
● カラーペン
<作り方>
| (1) | 紙コップの飲み口側から底に向かって、はさみで切り込みを入れる。この切り込みと向かい合う位置に、もう1つ切り込みを作る |
|---|---|
| (2) | (1)で2等分された筒部分を外側に向かって開く。この時、底に折り目ができるので、折り目に沿って底を半分に折る(半分に折った底の部分がパペットの「口」になる) |
| (3) | 紙コップのパペットに、カラーペンや画用紙、折り紙を使って動物やキャラクターをデザインする |
| (4) | (2)で半分に折った底の部分に、口の色を表す赤色やピンク色の画用紙を貼る、もしくは、カラーペンで色を塗る |
完成した紙コップパペットは、「口」の部分を後ろ側から手でつかみ、手を閉じたり開いたりすることでパクパクとさせて遊びます。パペットを用いて会話をしたり、パペットの口にハンカチなどを加えさせて綱引きをしたりして遊ぶのもおすすめです。
ロケット
下から上に垂直に飛び立つロケットも、輪ゴムと紙コップを使えば簡単に作れます。
<準備するもの>
● 紙コップ(2個で1セット)
● 輪ゴム(2つで1セット)
● はさみ
● テープ
● カラーペン
<作り方>
| (1) | まずはロケットを作る。片方の紙コップの飲み口側に、はさみで0.5~1cm程度の切り込みを入れる。十字になるように4カ所に切り込みを入れるのがポイント |
|---|---|
| (2) | 輪ゴムを2つつなげて、(1)の切り込みに十字形にかける。紙コップの側面部分の輪ゴムは、テープで貼って固定する |
| (3) | (2)の紙コップに、カラーペンで絵などを描いたら完成 |
発射台になる紙コップ(手を加えていないほうの紙コップ)に、輪ゴムのついた紙コップをかぶせ、一気に手を離せば、紙コップロケットが飛び跳ねます。
切り込みの位置や深さ、輪ゴムの長さ、重ねる力加減によって飛び跳ね方が異なるので、利用者さん全員でロケットを飛ばして飛距離を競うのも一つの楽しみ方です。
3.紙コップを活用!高齢者向けゲームレクリエーション
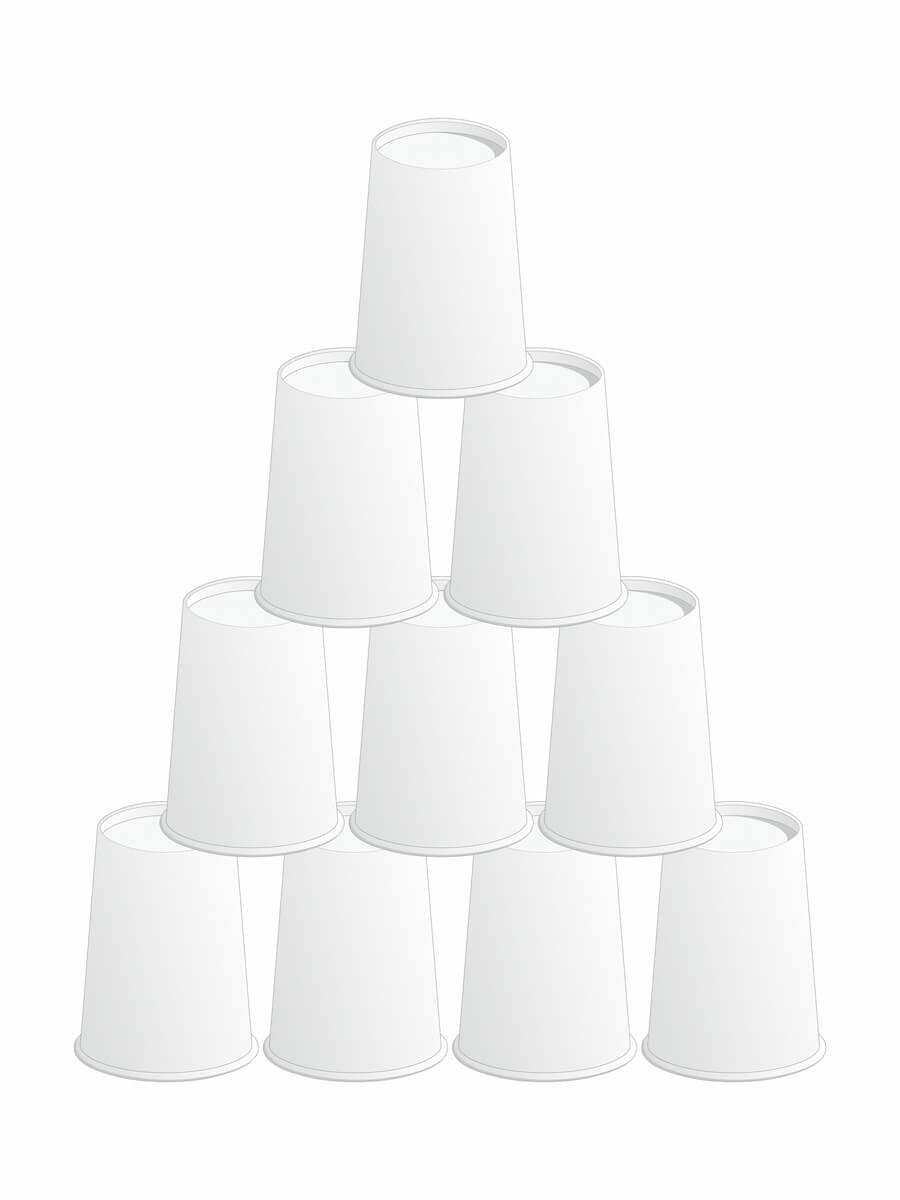
ここまで、紙コップの工作レクリエーションを紹介してきましたが、ここからは、紙コップをそのまま活用して楽しめる、高齢者向けゲームレクリエーションを紹介します。工作と違ってはさみやきり、つまようじなどを使わないため、より安全に楽しむことができます。
紙コップボーリング
紙コップボーリングは、紙コップをボーリングのピンに見立てて遊ぶゲームレクリエーションです。チーム戦にすれば利用者さん全員で楽しめ、非常に盛り上がるでしょう。
<準備するもの>
● 紙コップ(偶数個)
● テープ
● 新聞紙
<ゲームの流れ>
| (1) | 2つの紙コップの飲み口側を合わせたら、テープで固定してボーリングの「ピン」を作る。ピンの本数はお好みでOK。床にピンを並べる |
|---|---|
| (2) | 新聞紙をしっかり丸めてボールを作る |
| (3) | 参加者はピンに向かってボールを投げる |
| (4) | 倒したピンの数が多かった人の勝利 |
紙コップボーリングは、チーム戦で行うのがおすすめです。車いすの方がいる場合は、ピンまでの距離を変えるなどして、すべての利用者さんが平等に楽しめるよう配慮しましょう。また、難易度を少し上げたい場合は、(1)の工程で紙コップの中にビー玉やゴムボールを入れて重さをつけてみるのも良いでしょう。
紙コップ積み
紙コップ積みは、紙コップを積み上げて高さを競うゲームレクリエーションです。積み上げる形は「ピラミッド形」が基本で、紙コップを倒さないように慎重に積み上げていきます。チーム戦でも、個人対抗戦でも実施できますが、ここではチーム戦でのやり方を紹介しましょう。
<準備するもの>
● 大量の紙コップ(チームごとに色分けすると良い)
● 大きめのテーブル・人数分のイス
<ゲームの流れ>
| (1) | 2~3人1組のチームを作り、参加者は椅子に座る。各チームに同じ数の紙コップを配る |
|---|---|
| (2) | レクリエーション担当者のかけ声とともに、チームで協力しながらテーブルの上に紙コップをピラミッド形に積み上げていく |
| (3) | 倒してしまった場合は最初からやり直し、制限時間内に最も高く積み上げられたチームが勝利 |
レクリエーション担当者はゲームを行う前に、利用者さんの目の前で実際に紙コップを積みながら、やり方を説明すると良いでしょう。利用者さんが慣れてきたら、積み方をピラミッド形以外のものに変えるのもおすすめです。
なお、高く積み上げていくうちに夢中になり、椅子から立ち上がる利用者さんもいるかもしれません。利用者さんが体勢をくずしたり、転倒したりしないよう注意深くチェックしておきましょう。
紙コップすくい
紙コップすくいは、無造作に横向きに置かれた紙コップを棒ですくうゲームレクリエーションです。ルールが簡単な上に勝敗が分かりやすいので、盛り上がることうけあいです。また、上半身や腕、手の機能訓練になるというメリットもあります。
<準備するもの>
● 紙コップ(10個程度)
● 棒(人数分。めん棒程度がちょうど良い)
● すくった紙コップを入れる箱(人数分)
<ゲームの流れ>
| (1) | 床もしくはテーブルの上に、紙コップを横向きにして無造作に置いておく |
|---|---|
| (2) | レクリエーション担当者のかけ声とともに、参加者は紙コップを棒ですくって箱に入れていく |
| (3) | 制限時間内に最も多く紙コップをすくい上げた人が勝利 |
紙コップすくいも、チーム戦で行うことができます。レクリエーションの難易度を高めたい時は、色のついた紙コップを用意してレクリエーション担当者がすくう色を指定するなど、オリジナルルールを採用すると良いでしょう。
紙コップ陣取り
紙コップ陣取りは、箱の中に並べた紙コップに、遠くからボールを投げ入れるゲームレクリエーションです。「紙コップシュート」とも呼ばれ、腕や手の機能訓練になる他、集中力の向上にも効果的なレクリエーションとなっています。
<準備するもの>
● 紙コップ(箱にぴったり入る程度の個数を用意)
● 大きめの箱(ダンボール箱やお菓子箱でOK)
● 新聞紙
● イス
<ゲームの流れ>
| (1) | 大きめの箱に、紙コップをすき間なく入れる |
|---|---|
| (2) | 新聞紙をしっかり丸めて、片手で握れる程度のボールにする |
| (3) | 参加者は、箱から1~2m程度離れた場所に座る |
| (4) | レクリエーション担当者のかけ声とともに、参加者は紙コップに向かってボールを投げる |
| (5) | 制限時間内に紙コップに最も多くボールを投げ入れた人が勝利 |
上記では個人戦のやり方を紹介しましたが、チーム戦で行うのもおすすめです。その場合は、カラーボールを使うと勝敗がわかりやすくなります。
腕を使って投げるのが困難な利用者さんが多い場合は、新聞紙を丸めたボールの代わりに、軽くてバウンドしやすいピンポン玉を使うと良いでしょう。なお、レクリエーション中は、夢中になった利用者さんが転倒したりする恐れもあるため、注意深く見守るようにしてください。
まとめ
紙コップを用いた高齢者レクリエーションは、紙コップを使って糸電話や風車などを作る工作レクリエーションと、紙コップそのものを使うゲームレクリエーションに大別できます。どちらも準備にそれほど時間と手間がかからないため、利用者さんが楽しめて、なおかつ担当者の負担を軽減できるレクリエーションを探している方におすすめです。紙コップは軽くて軟らかいので、利用者さんがけがをしてしまうリスクも抑えられます。
「介護のみらいラボ」では、当記事の他にも、介護を行う上でためになる有益な情報や介護レク素材を豊富に提供しています。介護業界で活躍する方や、家族の介護を行う方は、「介護のみらいラボ」をぜひご覧ください。役に立つ情報がきっと見つかるはずです。
※当記事は2022年5月時点の情報をもとに作成しています
●関連記事:介護施設のレクリエーション32選!高齢者が盛り上がるレク例と企画のコツ
【日本全国電話・メール・WEB相談OK】介護職の無料転職サポートに申し込む
スピード転職も情報収集だけでもOK
マイナビ介護職は、あなたの転職をしっかりサポート!介護職専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを行います。
はじめての転職で何から進めるべきかわからない、求人だけ見てみたい、そもそも転職活動をするか迷っている場合でも、キャリアアドバイザーがアドバイスいたします。

SNSシェア














