脳科学者 篠原菊紀さんに聞く/高齢者が「脳トレ」に取り組むメリットと効果的な実施方法とは?
解説:公立諏訪東京理科大学工学部情報応用工学科 篠原菊紀教授 取材・文:小川裕子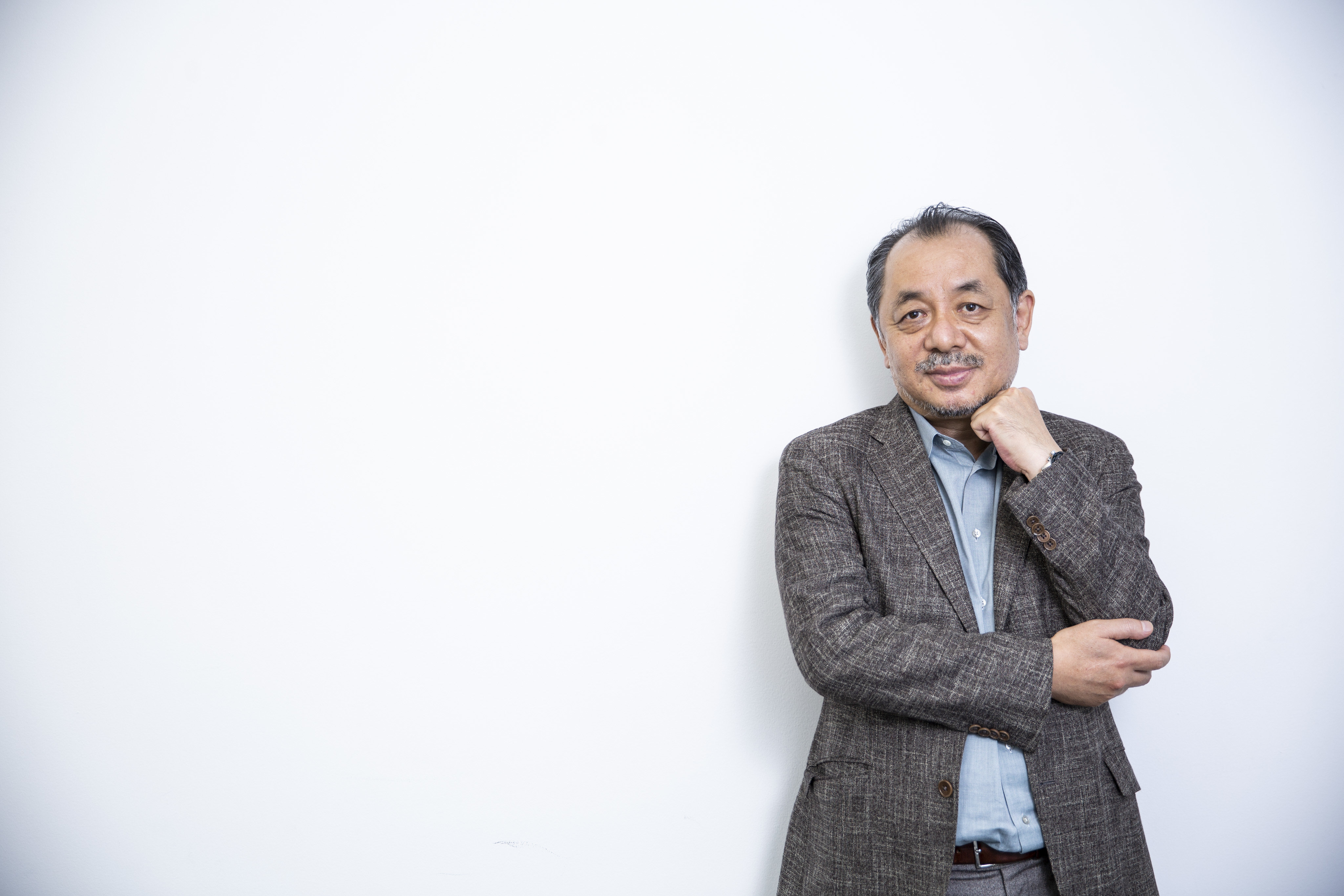
介護施設ではさまざまな高齢者向けのレクリエーションが行われていますが、なかでも人気なのが「脳トレ」です。
みなさんも、レクリエーションの一環として脳トレを実施した経験があるのではないでしょうか。とはいえ、「脳トレは何を目的に行うべきか」「脳のどんな機能が鍛えられるのか」「認知症予防に本当に効果があるのか」など、その目的やメリットまできちんと考えたり、教わったりする機会は少ないもの。
そこで今回は、脳科学者で、脳トレ問題の制作・監修も行う篠原菊紀先生に、脳トレの目的からメリット、効果的な実施方法まで、さまざまな疑問に答えていただきました。
脳トレがワーキングメモリの働きを高める
まずは、「脳トレによって、脳のどの部分が鍛えられるのか?」についてお聞かせください。
篠原 年を重ねるにつれてからだが衰えるように、脳の働きも衰えます。なかでも、とくに老化しやすいのがワーキングメモリ。何かの作業(ワーキング)をするために、必要な情報を一時的に脳に記憶(メモリ)しておく能力です。
たとえば誰かと会話しているとき、私たちは相手の発言を一時的に覚えておいて、返事をしたり、行動したりしますが、この「相手の発言を一時的に覚えておく」ときに機能するのがワーキングメモリです。ワーキングメモリは、いわば「脳のメモ帳」のようなもので、会話以外にも、料理、仕事、読み書きや計算など、さまざまな場面に関わっています。
ワーキングメモリの機能は、おもに脳の「前頭前野※1」と呼ばれる領域が担っていますが、その働きは18~25歳でピークを迎え、40~50代で衰えはじめます。年をとるにつれて物忘れが増えたり、物をなくしやすくなったりしますが、それは前頭前野が衰えてワーキングメモリの機能も低下するからです。
世間一般で行われている脳トレの目的は、そうした機能低下を防ぐためにワーキングメモリを鍛えることにあります。簡単にいえば、ワーキングメモリを鍛えることで前頭前野の働きを活性化させ、ひいては脳全体の働きを改善しようとしているのです。
※1 おでこのすぐ後ろにある部位のこと。ワーキングメモリ以外にも、「考える」「感情をコントロールする」「判断する」など多くの機能を担っており、「脳の司令塔」ともいえる存在です。
脳トレの効果には科学的な根拠があるのでしょうか。また、「認知症の予防にもつながる」ともいわれていますが、本当ですか?

脳トレは「認知的トレーニング」とも呼ばれ、その効果を検証するさまざまな研究が行われています。よく知られているのが、2832人の高齢者(平均年齢73.6歳)を対象としたアメリカの研究で、そこでは認知的トレーニングを行ったグループと行わなかったグループにわけて、それぞれを10年間追跡調査しました。すると、認知的トレーニングを受けたグループは認知機能が改善し、しかも、その効果は10年後も維持されていることがわかったのです。
また、ほかの多くの研究からも、脳トレはとくにワーキングメモリの働きを改善する効果が高いことがわかっています。これらのことから、「脳トレは脳の機能維持や機能改善に効果がある」といえるでしょう。
次に、脳トレと認知症の関係についてですが、こちらはさまざまな議論があり、現時点では「脳トレが認知症の予防につながる」とは断言できません。ただし、WHO(世界保健機関)が2019年に発表した「認知機能低下および認知症のリスク低減のためのガイドライン」では、対策のひとつとして認知的トレーニングが推奨されています。加えて、多くの認知症テストで、ワーキングメモリの働きをチェックする項目が設けられています。
さきほどお話したとおり、脳トレはワーキングメモリのトレーニングとして有効ですから、脳トレをすれば、認知症テストの成績が上がる可能性が高い。よって、認知症予防のひとつの手段として脳トレに取り組むことを、私はおすすめしています。
ぬり絵やなぞり書きなどで手を動かしたり、集中したりすることも、脳トレと同様のメリットが得られますか?
ぬり絵やなぞり書きの効果を検証した研究はあまりありません。しかし、ぬり絵やなぞり書きをしているときの脳の活動の様子を調べると、ワーキングメモリの中核である前頭前野を中心に脳が活性化しています。ですので、脳トレと同様のメリットを期待しても問題ないでしょう。
加えて、ぬり絵やなぞり書きは、肩や手、指のリハビリにもなります。認知機能の低下にともない指先のコントロールも衰えてくるので、身体的なトレーニングとしても役立ちます。
脳トレは"楽しく行うこと"が何よりも大事!

認知的トレーニングは、どのくらいの頻度で行えばいいのでしょうか。
「脳は筋肉と同じで、鍛えないと衰える」といわれることもありますが、実は、トレーニングの効果が出るのは脳のほうが断然早いんです。たとえば、いまこの記事を読んで「そうなんだ、なるほど」と思った瞬間にも脳は変化しています。
なかでもワーキングメモリはトレーニング効果がきわめて出やすく、その効果が長期間持続するという特徴があります。70代の高齢者に月に1回、60分ほどの認知的トレーニングを半年間受けてもらったところ、効果が5年後まで続いたという報告があるほどです。しかも、その研究では認知的トレーニングを受けていないグループも、ワーキングメモリの機能向上が見られました。なぜかわかりますか?
実は、認知的トレーニングを受けていないグループも、認知的トレーニングを受けているグループとの違いを調べるために、ワーキングメモリの働きを調べるための"テスト"を半年に1度受けていました。つまり、テストそのものがトレーニングとなって、そのおかげでワーキングメモリ系の成績が改善したわけです。そのくらい脳----とりわけワーキングメモリの機能は、トレーニングの効果が出やすいのです。
そうしたことをふまえてトレーニングの頻度を考えるならば、認知的トレーニングは半年に1回でも効果が期待できます。ただし、ほかの研究をみてみると、1回15分、週3~4回の認知的トレーニングで効果が出たという報告が多いため、1回15分、週3~4回を目安に継続的に行うといいでしょう。
脳トレ以外にも、おすすめのトレーニングはありますか?
運動でからだを動かすことです。さまざまな研究から、運動には身体機能の向上だけでなく、認知機能の改善にも役立つことがわかっています。
高齢者向けの運動としておすすめなのは、ゆっくり歩くのと、速く歩くのを交互に繰り返すインターバル速歩です。速歩の合計時間は1日15分以上が目安。これを週4回、5か月継続すると、身体機能の改善や認知機能の変化が期待できるでしょう。
なお、さきほどお話したWHOの「認知機能低下および認知症のリスク低減のためのガイドライン」では、運動のほかに、「禁煙」「高血圧や糖尿病のコントロール」「栄養バランスのいい食事」なども推奨されています。いうまでもなく、脳もからだの一部。脳の老化を食い止めたいのであれば、からだの健康も意識することが大切なのです。
レクリエーションとして脳トレを行う際に、介護従事者が心がけるべきこと、気をつけることについても教えてください。
まず心がけてほしいのは、「脳トレを強制しないこと」です。大脳の奥には線条体という部位がありますが、この部位は「やる気」と密接に関わっていて、楽しいこと、ワクワクするようなことをしているときに活性化し、やる気が出ます。そして、線条体が活性化している状態で脳トレを行うと、脳トレの効果もアップします。しかし、相手が嫌々取り組んでいるような状態で脳トレを行うと? 線条体は活性化せず、効果も上がりません。
だからこそ、脳トレは楽しく行うことが大切です。介護従事者の方は、高齢者が「楽しそう」「やってみたい」と思えて、自主的に取り組みたくなるような雰囲気をつくってください。たとえば、脳トレに取り組んだもののなかなか解けないような人には、「うまくできなくてあがいているときのほうが、脳のトレーニングになっているんですよ」と伝えてみる。また、「この部分はとっても上手にできましたね」という具合に、うまくできたところをほめるのも有効です。いずれにしても、意欲を失わないように配慮するようにしましょう。
なお、「うまくできなくてあがいているときのほうが、脳のトレーニングになっている」というのは本当のことで、脳は「ちょっとめんどくさい」くらいのことをやっているときのほうが活性化します。反対に、何の問題もなくスムーズに作業しているときは鎮静化するので、脳トレをすらすらと解いてしまう人がいたら、問題の難易度を上げてみるといいでしょう。そのほうが、脳は鍛えられますよ。
プロフィール

篠原菊紀(しのはら きくのり)
公立諏訪東京理科大学工学部情報応用工学科教授
地域連携研究開発機構 医療介護・健康工学部門長
「快感・楽しさ」をキーワードに脳活動の研究をするかたわら、教育、介護などの分野で使える教材やレクリエーション活動の監修・開発も行う。『脳の老化予防に効く! 懐かしの昭和探し脳トレ2』(扶桑社)、『むずかしいけど楽しい! 超めんどい脳活まちがいさがし 日本の地理編』(主婦の友社)など、監修本・著作多数。
●関連記事:介護施設で盛り上がるレク32選!企画のコツも
【日本全国電話・メール・WEB相談OK】介護職の無料転職サポートに申し込む
スピード転職も情報収集だけでもOK
マイナビ介護職は、あなたの転職をしっかりサポート!介護職専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを行います。
はじめての転職で何から進めるべきかわからない、求人だけ見てみたい、そもそも転職活動をするか迷っている場合でも、キャリアアドバイザーがアドバイスいたします。

SNSシェア













