介護過程とは?4つのプロセス・目的を解説
構成・文/介護のみらいラボ編集部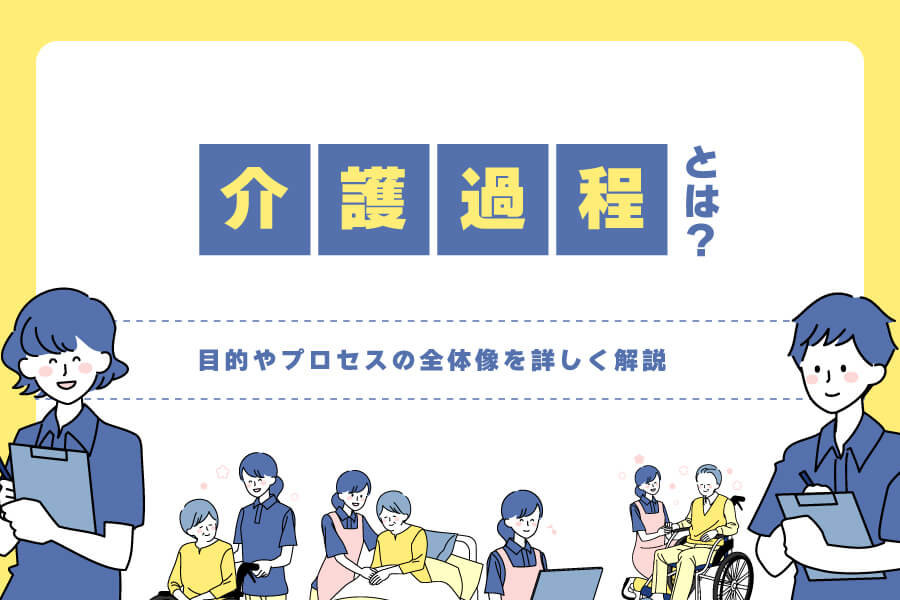
介護の現場で働き始めて間もない人のなかには、「介護過程」や「介護計画書」といった介護関連の専門用語に、とまどいを感じている人も多いのではないでしょうか。介護の現場では、そうした専門用語が使用されるケースも少なくありません。業務を的確に行うためにも、専門用語の意味や目的をきちんと理解しておきましょう。
当記事では、介護職が押さえておきたい「介護過程」の言葉の意味や、実践するにあたっての目的、ケアプランとの違いについて解説します。介護過程を構成する4つのプロセスや、介護過程を学ぶ方法もあわせて紹介するので、きちんと理解して日々の業務に生かしましょう。
1.介護過程とは?取り組む目的も解説
介護関連の職種に就きたい方や介護の実務に携わっている方のなかには、「介護過程についてよくわかっていない」「内容を詳しく知りたい」と考えている方も多く見られます。まずは介護過程の意味と取り組む目的、介護過程の必要性について解説しましょう。
介護過程とは
介護過程とは、「利用者さんが自分らしい生活を送るためには、どういった課題を改善・解決すればいいのか、どのような介護が必要なのかを検討し、実践に移す道筋」です。
介護職員は、介護サービスを提供するプロフェッショナルです。だからこそ、その場の思いつきで介護するのではなく、目的や根拠を持って介護サービスを実施する必要があります。それを踏まえるなら、介護過程は科学的根拠や専門性に基づく介護サービスを、利用者さん一人ひとりに提供するためのプロセス・考え方だと言えるでしょう。
介護過程では、介護サービス提供後の振り返りも必要になるため、プロセスを言語化して記録に残しておくことも重要です。記録を残すことで、利用者さんやその家族、他職種の人にも、実施している介護サービスが科学的根拠と専門性に基づいていることを客観的に示せます。
介護過程に取り組む最大の目的は、介護過程の記録を振り返り、尊厳の保持や自立といった利用者さんのQOL(生活の質)の向上につなげることです。介護過程が根拠と専門性に基づいていれば、他職種と連携したチームアプローチが容易になり、利用者さんのQOL向上という目的が達成しやすくなるでしょう。
また、介護職員が介護過程の展開の仕方について学び、介護に関する専門性を高めることは、人手不足・教育不足などの課題解消にもつながります。そのため、介護に携わる一人ひとりが介護過程の意味や意義を理解しておくことは、非常に重要だと言えます。
(出典:厚生労働省「介護過程-実践事例集」)
介護過程の必要性
先に紹介したように、介護過程は「利用者さんが、自分らしい生活を送るために課題を改善・解決すること」を目的としています。
介護を経験や勘に頼って実践すると、サービスの質にばらつきが生まれ、利用者さんの抱える課題を解決するのが難しくなります。だからこそ、介護過程を展開し、個別の介護の方針や内容を具体的に定め、介護の質の均一化を図ることが大切なのです。
また、介護過程を展開する際は、介護サービスの提供後に振り返りや検証を行うことも重要です。繰り返しになりますが、介護過程のプロセスの言語化・記録を行えば、利用者さんやその家族および他職種に、専門性に基づいた介護サービスを提供していると客観的に示せるでしょう。
2.介護過程における介護計画とケアプランの違い
介護過程では、介護職員が個別の「介護計画」を作成します。介護計画と似た言葉に「ケアプラン」がありますが、介護計画とケアプランでは内容が異なります。
「ケアプラン(施設サービス計画書)」は、ケアマネジャーが作成する計画であり、利用者さんの状態やニーズにあわせて、介護サービスの種類、内容、利用頻度などを定めるものです。一方、「介護計画」は、ケアマネジャーが作成したケアプランをもとに、利用者さん一人ひとりにどのような介護サービスを実施するかを決めたもので、「個別介護計画」「個別支援計画」とも呼ばれます。
介護計画を作成するにあたってはケアプランが不可欠なため、ケアプランは介護過程の一部と考えてよいでしょう。
3.介護過程の4つのプロセス
介護過程は、「アセスメント」「介護計画の立案」「実施」「評価」の4つのプロセスで構成されています。介護過程の4つのプロセスは、介護におけるPDCAサイクルだと考えると、わかりやすいかもしれません。
以下では、それぞれの内容について詳しく解説します。
アセスメント
介護におけるアセスメントとは、利用者さんやその家族から話を聞いたり、利用者さんの性格、言動などを観察したりして情報を集めることです。アセスメントで集めた情報をもとに、利用者さんが自分らしい生活を送るために必要な取り組み、課題などを見つけ出し、目標を設定します。
アセスメントは、以下の3つのポイントを押さえて実施することが大切です。
・情報を集める
利用者さんやその家族から話を聞くことはもちろん、家族構成や病歴、日常生活動作能力といった情報も集める必要があります。アセスメントを行う際は、どの項目を誰に聞くのかをあらかじめ決めておくと、スムーズに進められるでしょう。
・情報の把握・分析・解釈・判断を行う
集めた情報をもとに、利用者さんが生活のなかで何に困っているかを把握し、さらに必要な情報を集めます。その後、チームの意見や理論、知識、経験などを踏まえながら、得た情報がどのような意味を持つのかを分析・解釈・判断します。
・課題を明確にする
今後発生する可能性がある課題を明確にします。課題の見落としがないように複数人でチェックを行い、多様な意見を取り入れるとよいでしょう。
介護計画の立案
アセスメントで明らかになった課題を解決するために、介護計画を作成するプロセスです。介護計画の立案は、基本的に以下の流れで実施します。
| 1 | 目標設定を行う |
|---|---|
| 2 | 目標達成のために必要な介護ケアの内容・方法・頻度などを決める |
| 3 | 利用者さんやその家族、関係者と情報共有を行う |
介護計画は介護職だけで決めるのではなく、利用者さんやその家族の意向を反映することが大事です。なお、介護計画には厚生労働省の定めた様式がありますが、各施設が自分たちにあった様式を作っても問題ありません。
(出典:福祉医療機構「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準課目の提示について」)
実施
立案した介護計画に基づいて、介護ケアを提供するプロセスです。介護計画の実施においては、それぞれのケアを行う理由を現場の職員が共通認識として持ち、常に意識することが重要になります。
また、実施した内容や結果を今後につなげられるように、以下のポイントを記録しておくことも大切です。
・利用者さんからどのような反応を得られたか
・介護ケアの内容が利用者さんのニーズにマッチしていたか
上記のほかに、ケアを実施するなかで気づいたことがあれば、随時記録を取ってチーム内で共有するとよいでしょう。
評価
介護ケアの実施後は、どのような結果が得られたかを客観的に評価することが大切です。
なお、評価の結果、新たな課題や達成できなかった目標が見つかるケースも少なくありません。そうした場合は、もう1度アセスメントを実施し介護計画を見直した上で、利用者さんの希望に添った介護に近づけていきましょう。
介護過程の評価に際しても、利用者さん本人やその家族の意見に耳を傾けることが大切です。利用者さんやその家族にとって満足のいく結果が得られなかった場合も、アセスメントからのやり直しが必要となるでしょう。
4.介護過程を学ぶ2つの方法
介護過程について理解するためには、介護系の資格取得や講座の履修を通して、介護過程の知識・スキルを身につけるのも有効です。興味のある方は、介護過程が受講科目となっている「実務者研修」や、介護過程に関する内容が出題される「介護福祉士試験」の学習に取り組んでみてはいかがでしょうか。
ここでは、「実務者研修」「介護福祉士」の概要や研修内容、試験内容を解説します。
●実務者研修
実務者研修は国家資格ではないものの、質の高い介護の知識・スキルを身につけていることを証明できる資格です。介護に関する研修には「初任者研修」もありますが、初任者研修が介護の基礎を学ぶのに対して、実務者研修はより専門的な内容を学びます。実務者研修を修了することで、介護福祉士養成施設での到達目標と同水準の介護提供能力を修得できるとされています。
実務者研修を修了するためには、次のような研修内容(450時間)を学ぶ必要があります。
■実務者研修における主な研修内容
・社会福祉制度(介護保険など)
・医療の知識
・認知症の理解
・障害の理解
・介護技術
・介護過程 など
(出典:厚生労働省「制度改正の概要」)
●介護福祉士
介護福祉士は、介護に関する幅広い知識と技術があることを証明する国家資格です。介護福祉士は、支援を必要とする利用者さんの身体介護や生活援助を行うほか、利用者さん本人やその家族からの相談にも対応します。また、介護職員のリーダーとして教育や助言、指導を行うのも介護福祉士の大切な仕事です。
介護福祉士になるためには、筆記試験と実技試験からなる介護福祉士国家試験に合格する必要があります。試験では介護過程をはじめ、介護に関するさまざまな領域の問題が出題されるため、事前に十分な準備を行いましょう。
介護福祉士国家試験の受験資格を得るための道筋は、「実務経験ルート」「養成施設ルート」「福祉系高校ルート」「経済連携協定(EPA)ルート」の4つです。それぞれの特徴を理解して、自分にあったものを選びましょう。
(出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験」)
(出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター「受験資格(資格取得ルート図)」)
(出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター「試験概要」)
(出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター「過去の試験問題」)
5.介護過程の勉強方法
介護過程は、「介護の基本」や「生活支援技術」などの科目で、基礎知識を身につけてから取り組むことが大事です。また、介護過程の意義や目的を問う問題は、出題される可能性が非常に高いため、「なぜ根拠に基づいて介護を行う必要があるのか」については、テキストや問題集で繰り返し学習しておくのがおすすめです。
事例問題では、ボリュームのある長文が出題されることも多く、読解力が求められます。さらに、実際の場面をイメージする想像力も必要です。過去問題集や予想問題で事例問題を何度も解き、読解力と想像力を向上させることが、正解にたどりつくための近道と言えるでしょう。長文問題を解く際は時間配分も重要になるので、時間を計りながら勉強するようにしてください。
(出典:厚生労働省「介護教員講習会の専門分野に関すること」)
(出典:日本介護福祉士会「介護過程の教授方法についての研究」)
6.介護福祉士試験で出題される介護過程の問題例
介護福祉士試験では、介護過程に関する問題が毎年出題されます。過去問題集などを使って内容を理解し、正しく回答できるようにしておきましょう。
ここでは、過去の介護福祉士試験で出題された介護過程の問題を、いくつか紹介しておきます。
【第35回(2023年)/問題106】
介護過程を展開する目的として、最も適切なものを 1つ選びなさい。
1 業務効率を優先する。
2 医師と連携する。
3 ケアプランを作成する。
4 画一的な介護を実現する。
5 根拠のある介護を実践する。
(出典:社会福祉振興・試験センター「介護過程」)
この問題の解答は「5」です。介護過程は、「なぜその介護ケアを行う必要があるか」という根拠に基づき、利用者さんにより効果的な介護サービスを提供するために実践します。
【第34回(2022年)/問題64】
介護過程における目標の設定に関する次の記述のうち、適切なものを 1つ選びなさい。
1 長期目標の期間は、 1か月程度に設定する。
2 長期目標は、短期目標ごとに設定する。
3 短期目標は、生活全般の課題が解決した状態を表現する。
4 短期目標は、抽象的な内容で表現する。
5 短期目標は、長期目標の達成につながるように設定する。
(出典:社会福祉振興・試験センター「介護過程」)
この問題の解答は「5」です。長期目標の期間は6~12か月程度に設定されます。また、長期目標は、複数の短期目標に対して1つ設定されるのが一般的です。一方、短期目標とは具体的な活動目標のことであり、数値目標なども含めて具体的に記載する必要があります。短期目標は利用者さんが達成できる内容で設定し、最終的には長期目標を達成することにつなげていきます。
【第35回(2023年)/問題110】
次の事例を読んで、問題について答えなさい。
〔事 例〕
Lさん(76 歳、女性、要介護 1)は、自宅で娘と暮らしている。軽度の認知症(dementia)と診断されたが、身体機能に問題はなく、友人との外出を楽しんでいる。ある日、外食の後、自宅近くで保護されたとき、「ここはどこなの」と言った。その後、自宅から出ようとしなくなった。心配した娘が本人と相談して、小規模多機能型居宅介護を利用することになった。
利用開始時に、Lさんの短期目標を、「外出を楽しめる」と設定した。 2 週間が過ぎた頃、Lさんから、近くのスーパーへの買い物ツアーに参加したいと申し出があった。
当日、他の利用者や介護福祉職と笑顔で買い物をする様子が見られた。買い物が終わり、歩いて戻り始めると、笑顔が消え、急に立ち止まった。
介護福祉職が声をかけると、「ここはどこなの。どこに行くの」と不安そうに言った。
問題
Lさんの状況から、短期目標と支援内容を見直すためのカンファレンス(conference)が開かれた。
担当する介護福祉職の提案として、最も優先すべきものを 1 つ選びなさい。
1 外出先から帰れなくなる不安への対応が必要である。
2 表情がかたくなったときは帰り道を変更する。
3 外出する意欲を持つ必要がある。
4 歩くために身体機能の改善が必要である。
5 事業所をなじみの生活空間にする。
(出典:社会福祉振興・試験センター「介護過程」)
この問題の解答は「1」です。上記の事例において、Lさんは外出先から帰れなくなることへの不安を訴えています。そのため、介護福祉職の仕事としては、「1」が最優先だと言えるでしょう。
まとめ
介護過程とは、科学的根拠や専門性に基づいた介護ケアを、利用者一人ひとりに提供するプロセスを指します。介護の現場では、介護過程における一連の取り組みの意義や目的を十分に理解した上で、介護ケアにあたることが大切です。実務者研修や介護福祉士などの資格取得を通して介護過程を学び、介護現場でのスキルアップを目指しましょう。
「介護のみらいラボ」では、介護の現場で活躍する人に向けたお役立ち情報を数多く掲載しています。介護の仕事について気になることや知りたいことがあれば、ぜひ「介護のみらいラボ」を参考にしてください。
※当記事は2024年8月時点の情報をもとに作成しています
●関連記事:
・介護のモニタリングとは?目的や実施時の注意点、確認事項を解説
【日本全国電話・メール・WEB相談OK】介護職の無料転職サポートに申し込む
スピード転職も情報収集だけでもOK
マイナビ介護職は、あなたの転職をしっかりサポート!介護職専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを行います。
はじめての転職で何から進めるべきかわからない、求人だけ見てみたい、そもそも転職活動をするか迷っている場合でも、キャリアアドバイザーがアドバイスいたします。

SNSシェア














