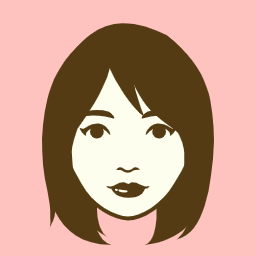介護施設で実施できる医療行為は?一覧で紹介
構成・文/介護のみらいラボ編集部 監修/渡辺有紀
介護士として働き始めると、「これは医療行為にあたるのだろうか?」と迷う場面に出くわすこともあるでしょう。施設の入居者さんに適切なケアを行うためには、まず介護士としてできること・できないことを把握しておく必要があります。
当記事では、介護施設で実施できる医療行為の概要と、介護士ができる医療行為を紹介します。あわせて、「介護士にはできないけれど、看護師にはできる医療行為」についても解説しますので、これからの業務にお役立てください。
1.介護施設でできる医療行為は?
高齢者施設などの介護施設では、介護士や看護師が定められた範囲の医療ケア(日常生活に必要な医療的な生活援助)や医療行為を行うことができます。また、医師が勤務している施設では、必要に応じて診察や簡単な医療処置を行うこともあります。
利用者さんに安全で適切なサービスを提供するためにも、介護施設で行われる医療行為のうち、「介護士が対応可能なもの」を把握しておくようにしましょう。
介護施設の種類による人員配置の違い
介護施設のなかには、要件として医師や看護師の配置が義務づけられているところもありますが、どの介護施設にも医師や看護師が配置されているわけではありません。
職員の人員配置基準は介護施設の種類によって異なるため、まずは介護施設の種類による人員配置の違いを知っておきましょう。ここでは一例として、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と介護付き有料老人ホームの人員配置基準をご紹介します。
| 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 介護付き有料老人ホーム | |
|---|---|---|
| 医師の配置 | 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 | -- |
| 看護師の配置 | 入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上 | 入所者30人までは1人以上、それを超える場合は50人ごとに1人追加 |
| 介護士の配置 |
入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上 ※ただし、看護師との合計で計算する |
入所者3人に対して1人以上 ※ただし、看護師との合計で計算する |
(参考:厚生労働省「介護老人福祉施設(参考資料)」)
(参考:厚生労働省「特定施設入居者生活介護(参考資料)」)
前述したように、この他の介護施設にもそれぞれに基準があり、専門職員配置の有無や割合が定められています。また、医療行為を行える範囲は、医師や看護師、介護士の立場で異なるため、その点にも注意が必要です。
2.介護士ができる医療行為・医療ケアの一覧
介護士は医療従事者ではないため、基本的には医療行為が認められていません。しかし、社会情勢や介護現場の状況に合わせて法制度の見直しが進み、現在は介護士も定められた範囲の医療ケア・医療行為を行えるようになっています。
サービス利用者さんの生活に寄り添い、サポートする介護士にとって、医療ケア・医療行為の知識は欠かせません。自身が実施できる範囲については、しっかりと把握しておくようにしましょう。
医療行為の対象ではない医療ケア
介護現場におけるケアのなかには、過去に医療行為だったものが、医療・介護サービスのあり方の変化などを背景に、医療行為の対象からはずれたケースがあります。現在、「医療行為の対象ではない」とされている処置は以下の通りです。
医療行為の対象ではない医療ケア
・体温計による体温測定
・自動血圧測定器による血圧測定
・パルスオキシメーターの装着(新生児以外かつ入院治療不要の場合のみ)
・擦り傷、やけどなど、専門的判断や技術を必要としない処置
・医薬品を使用するときの介助
(湿布の貼付、目薬の点眼、鼻腔粘膜への薬剤噴霧、服薬介助、坐薬の挿入)
(出典:厚生労働省「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」)
「医薬品を使用するときの介助」については、医師や看護師の指導のもと、以下の内容を満たすことで介護士による介助が認められています。
・利用者さんに治療や入院が必要なく、安定した容態であること
・投薬量の調整等や副作用の危険性により、医師および看護師による経過観察が連続的に必要な場合ではないこと
・内服薬服用における誤嚥や座薬の挿入における出血の可能性など、当該医薬品の使い方について専門の配慮が必要ではないこと
規制対象外の医療行為
医師法や保健師助産師看護師法などで医療行為とされているものの、法律の規制対象外として扱われる処置もあります。
以下の医療行為は規制対象外となっているため、介護士による対応が可能です。
規制対象外の医療行為
・爪切り、爪やすり
・歯ブラシや綿棒による口腔ケア
・耳垢の除去(耳垢閉塞の場合を除く)
・ストーマ装置のパウチにたまった排泄物の除去
・自己導尿を補助するためのカテーテル準備、体位保持
・市販の浣腸器を用いた浣腸
(出典:厚生労働省「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」)
ただし、上記の行為であっても、利用者さんの病状が不安定なときなど医学的な管理が必要な場合は、医療行為に該当する可能性があります。必要に応じて、医師や看護師に「医学的管理が求められるかどうか」の確認を行い、自身が行える行為かを正しく把握するようにしましょう。また、利用者さんの体調や病状の変化があった場合は、速やかに報告を行うことが大切です。
条件付きで可能な医療行為
介護の現場で行われる医療行為のなかには、条件付きで介護士に認められているものがあります。2012年4月より、「特定行為業務事業者」の認定を受けた介護士は、新たに以下の処置ができるようになりました。
条件付きで可能な医療行為
・口腔内の喀痰吸引
・鼻腔内の喀痰吸引
・気管カニューレ内部の喀痰吸引
・胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
・経鼻経管栄養
上記行為が可能となる条件
・登録喀痰吸引等事業者として登録を受けた事業所の介護福祉士が行う場合
・登録特定行為事業者として登録を受けた事業所の介護職員が行う場合
(出典:秋田市介護保険課「介護職員ができる医療行為の範囲について」)
上記の業務を行う1つの要件として、「喀痰吸引等研修」を受講・修了することが挙げられます。これは、喀痰吸引が必要な方や、口から食事ができず経管栄養により栄養をとる必要がある方を支えるための資格(研修)で、研修修了後、各都道府県に申請を行うことで「特定行為業務従事者」の認定を受けられます。
なお、介護福祉士の場合は、国家試験に合格した後に実地研修や都道府県への申請を行うことで、「登録喀痰吸引等事業者」に認定されます。ただし、平成28年度以前に介護福祉士になった方は、「喀痰吸引等研修」の受講・修了が必要です。
(出典:厚生労働省「平成24年4月から、介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引・経管栄養)についての制度がはじまります。」)
ただし、認定を受けて医療行為を行える場合でも、利用者さん本人や家族の同意が必要であることを理解しておきましょう。また、医療行為は医師や看護師の指示監督のもと行うという、基本的なルールを守ることも重要です。
3.介護士ができない医療行為の一覧
介護における医療行為のなかで、介護士が実施できるものは限られています。そのため、対応できない処置を依頼された場合は、利用者さんや家族に丁寧な説明を行い、お断りする必要があります。また、そうした際に安全かつ適切な判断ができるように、「介護士が対応できない行為」をきちんと把握しておくことも大切です。
ここでは、介護士が対応できない医療行為について、「看護師にはできるもの」と「医師にしかできないもの」に分類して、一覧で紹介します。
介護士はできないが看護師にはできるもの
看護師は医療資格を保有しているため、法律で認められている医療行為の範囲も広がります。以下のような医療行為が必要な場合は、自分で行うのではなく、看護師に対応してもらいましょう。
・インスリン注射
・褥瘡の処置
・中心静脈栄養(IVH)
・在宅酸素療法
・ストーマの貼り替え
・カテーテルの交換
・人工呼吸器の管理 など
利用者さんの様子が気になるときに、施設の看護職員と適切な連携を図れるよう、普段から看護師が対応できる医療行為を把握しておくことが大切です。
医師にしか認められていないもの
以下は、医師にしか認められていない医療行為となります。
・診察および経過観察
・注射や点滴
・処方箋の交付
・応急処置 など
医療体制や設備が整った施設では、医師による人工透析などが行われるケースもあります。しかし、介護施設で行える医療行為の範囲は、医療施設で行えるものと比べると限定的です。高度な医療行為が必要になったときでも、外部の医療機関に迅速で的確な報告・相談ができるように、医療行為や医療体制についてきちんと理解しておきましょう。
また、医療行為は専門的な知識がないまま実施すると、違法行為になったり、命を左右する医療事故につながったりする可能性があります。利用者さんを危険にさらさないためにも、迷ったときには自己判断せず、医師や看護師に相談しましょう。
4.介護士は医療行為を含む医療知識への理解を深めることが大切
高齢化の影響で、介護現場ではさらに医療ニーズが高まることが予想されます。介護士として業務の幅を広げたい場合は、喀痰や経管栄養に関する研修の受講を検討するのもおすすめです。
また、介護施設で利用者さんが安全に過ごすためには、介護士をはじめとする介護職員の正しい判断が欠かせません。日頃から医療行為や医療関連の知識を深め、利用者さんの状態を適切に把握し、必要な対応を考えることを心がけましょう。
今後は、介護士が対応できる医療行為の範囲が、拡大される可能性もあります。制度改正などの情報も欠かさずチェックしておきましょう。
まとめ
介護士が施設で働く場合、自身が対応できる医療行為と対応できない医療行為を把握して、適切な判断を行うことが求められます。今後、介護現場における医療行為のニーズがさらに高まることも予想されるため、医療行為に関する知識・理解を深め、介護士としてのスキルや専門性を向上させるように努めましょう。
「介護のみらいラボ」では、介護の現場で活躍する方の仕事や日常生活に有益な情報を掲載しています。スキルアップや悩み解決、健康、マネー情報など、さまざまな視点から情報をお届けしていますので、ぜひ「介護のみらいラボ」を参考にしてください。
※当記事は2022年8月時点の情報をもとに作成しています
【日本全国電話・メール・WEB相談OK】介護職の無料転職サポートに申し込む
スピード転職も情報収集だけでもOK
マイナビ介護職は、あなたの転職をしっかりサポート!介護職専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを行います。
はじめての転職で何から進めるべきかわからない、求人だけ見てみたい、そもそも転職活動をするか迷っている場合でも、キャリアアドバイザーがアドバイスいたします。

SNSシェア