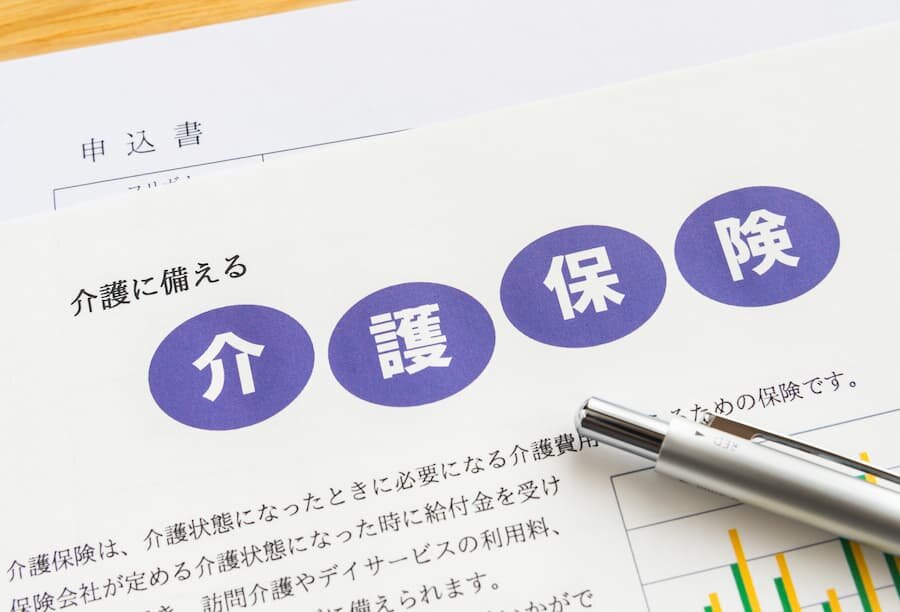訪問介護とは?働き方、できること、できないこと、一日の流れ
文:吉田 匡和 (よしだ まさかず) 社会福祉士・介護支援専門員(ケアマネジャー)・社会福祉主事
2015年の法改正により、特別養護老人ホームの入所条件が「原則要介護3~5の者に限る」と改正されました。これによって条件を外れた多くの要介護者が在宅サービスを利用するようになりました。
そうした背景を受けて要介護者宅に出向いて介護を行う「訪問介護(ホームヘルパー)」の需要が高まっています。訪問介護の基本から現状、一日の流れなどを紹介します。
訪問介護とは
介護保険法によると、訪問介護とは「訪問介護員(ホームヘルパー) 等が、利用者(要介護者等)の居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事等を提供するものをいう」と定義されています。
近年では、住み慣れた場所で自分らしい生活を最期まで送れるようにサポートしあう「地域包括ケアシステム」が国によって推進されており、訪問介護の存在が重要視されています。
訪問介護事業者の82.4%が「ヘルパー不足」と回答
介護を必要とする高齢者の数が年々増加する一方で、介護の担い手は大幅に不足していることが社会問題になっています。厚生労働省の発表によると、2019年度のホームヘルパーの有効求人倍率は13.1倍に上昇。
同省の「平成29年度 介護労働実態調査」でも訪問介護事業者の82.4%が「ヘルパー不足」と回答するなど、深刻な人手不足が続いています。しかし見方を変えれば、求人件数が多く採用されやすい職種といえるでしょう。
訪問介護員(ホームヘルパー) になるには
訪問介護員(ホームヘルパー)として働くためには、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、旧介護職員基礎研修修了者、旧訪問介護員1級または旧2級課程修了者など、いずれかの資格が必要になります。それぞれの資格取得方法をまとめました。
介護福祉士になるには
大学や短大、専門学校などの養成校を経由する「養成施設ルート」、3年間の実務経験と実務者研修などを要する「実務経験ルート」のほか、「福祉系高校ルート」、「経済連携協定(EPA)ルート」など、4つのルートがあります。
養成施設ルート及び実務経験ルート、福祉系高校ルートの新カリキュラムについては実技試験が免除されていますが、養成施設ルート以外は筆記試験を受験しなくてはなりません。
実務者研修修了者(旧ヘルパー1級)になるには
幅広い利用者に対する基本的な介護提供能力の修得を目的に創設され、実務経験者が介護福祉士資格試験を受験する場合には実務者研修の修了が義務付けられています。研修時間は450時間で、仕事と両立できるよう通信教育が活用されています。
介護職員初任者研修修了者(旧ヘルパー2級)になるには
介護に携わるうえで最低限の知識と技術、それを実践する際の考え方を身につけることで基本的な介護業務ができるようにすることを目的とされています。旧ホームヘルパー2級に該当するもので、2013年の制度変更により名称が変更されました。講義・演習が一体的に実施され、研修時間は130時間。特別養護老人ホーム等の介護職員等として実務経験がある場合には、研修の一部が免除されます。
旧介護職員基礎研修修了者、旧訪問介護員1級又は旧2級課程修了者については、すでに改定されており、実務者研修を受けることによって更新が可能です。修了者については実務者研修を受ける際に受験費用や受講時間の短縮等を受けることができます。
訪問介護員(ホームヘルパー)の仕事内容
訪問介護員(ホームヘルパー)は、利用者の自宅などに訪問し、利用者に対して主に「身体介護」、「生活援助」、「通院等乗降介助」の3つを業務の基本として対応します。条件によっては移動時間も業務範囲内ですが、「自由利用が可能な時間」と判断される場合には、賃金に加算されないため注意が必要です。
また、介護保険制度の目的に定められた業務以外のサービスを行ってはいけません。加えて、サービスの対象は介護を必要とする人のみであり、同居している家族に対して行うことは禁じられています。訪問介護員(ホームヘルパー)としての働き方を考えるうえで、できることと、できないことがあることを理解し、自身が取り組む業務についてしっかり確認しておく必要があるでしょう。具体的な「原則提供可能なサービス」、また「原則提供が禁止されているサービス」は以下のとおりです。
訪問介護で原則提供可能なサービス
身体介護
- 体位変換・移動介助・食事介助など
- 経管栄養剤の準備・経管栄養中の観察
- トイレ誘導・排泄介助・おむつ交換
- パウチにたまった排泄物の処理
- 体温測定や血圧測定、爪きり、目薬点眼、簡単な傷ややけどの処置
- たんの吸引(H28年合格以降の介護福祉士・研修後など条件あり)
- 経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻経管栄養)(H28年合格以降の介護福祉士・研修後など条件あり)
生活援助
- 利用者が使う部屋の掃除・洗濯
- 利用者の食事の用意
通院等乗降介助
- 通院のための車両の運転
- 通院やデイサービスの送迎などの乗降介助
訪問介護で原則提供が禁止されているサービス
身体介護
生活援助
- 同居人が使う部屋の掃除・洗濯
- 同居人の食事の用意
- 日常生活の範囲を超えるサービス
- 利便のためだけのサービス
- 趣味に関するサービス
通院等乗降介助
- 通院以外を目的とした車両の運転。途中で買い物などに立ち寄ることも不可。
訪問介護員(ホームヘルパー)の仕事の一日の流れ
訪問介護員(ホームヘルパー)は、事業所で当日の利用者訪問の準備を行い、車両を運転して各訪問先に向かいます。一日4、5件ほど担当し、身体介護、生活援助、通院等乗降介助などを行うほか、時には同僚のヘルパー、ケアマネージャーとの情報交換や報告、連絡、相談、書類の作成なども行います。
移動時間も含め終業は17時~18時頃となるケースが多く、訪問先から直帰することもあれば、必要に応じて事務所に戻ることもあります。訪問介護員(ホームヘルパー)の一日を時系列にした一例を紹介します。
9時00分
サービス提供責任者などを交えてスタッフ間で申し送りを行います。この申し送りにおいて利用者の近況や注意事項などが報告されます。
<ここがポイント>
申し送りにおいては、特に新規の利用者に訪問する場合は、ケアマネージャーらとの念入りな情報交換を行います。勤務時間や勤務形態は事業所によって異なり、事業所に出勤せず直接利用者宅に訪問することもあります。
9時10分~10時00分
デイサービスを利用するAさんのお宅を訪問し、着替えや持ち物の準備を補助するなど、送り出しの支度を行います。デイサービス送迎車が来たら必要事項をスタッフに申し送り、出発を見送りました。
10時30分~11時00分
生活支援が必要なBさんのお宅を訪問し、部屋の掃除や浴室、トイレ、キッチンなどの清掃を行います。
<ここがポイント>
訪問先によって間取りや設備が異なるほか、家庭ごとの独自のルールがある場合など、個別の対応が必要です。また、介護の仕事は、利用者の尊厳を尊重した個別的対応が大切です。
訪問介護員(ホームヘルパー)は訪問先に合わせたマンツーマンの対応を行うため、介護スキルの向上が期待できます。
11時30分~12時00分
事業所に戻って、午前中の業務内容を記録します。
<ここがポイント>
サービス実施記録は、よりよいケアに結びつけるためのツールであるとともに、事故などが起きた場合に原因や対策を検討するうえで重要な資料になるため、サービスごとに作成します。
12時15分~13時00分
身体介助と生活支援が必要なCさんのお宅を訪問し、昼食の準備と昼食介助、おむつ交換を行います。他の訪問介護員(ホームヘルパー)の申し送りで便秘気味と聞いていたため、本人に確認して繊維質の多い食事を提供します。また、便が出ても漏れないように、オムツの交換を丁寧に行いました。
<ここがポイント>
サービスが可能な時間が限られているため、時間を有効に使いながら相手にとって必要な介護を行わなくてはなりません。そのためには利用者個々の情報をしっかりと把握しておくことが必要です。
13時00分~14時00分
事業所または外出先で食事をとります。
14時00分~16時00分
介護支援専門員(ケアマネジャー)から急遽「訪問看護の利用者Dさんの通院に付き添ってほしい」と連絡があったため、予定していた訪問を他の訪問介護員(ホームヘルパー)に変わってもらい、Dさんに同行しました。
<ここがポイント>
このように予定にはないサービスに対応することは少なくありません。
16時00分~17時00分
デイサービスから帰ってくるAさんを迎えうけます。食事を食べてもらい、就寝準備を済ませた後、Aさんと会話をしながら家族の帰りを待ちました。
<ここがポイント>
介護施設ではひとりで多くの利用者を対応しなければなりませんが、こうして一人一人に向き合えるのがホームヘルパーの良い点です。
17時00分~18時00分
事業所に戻り、サービス実施記録を作成したり、他の訪問介護員(ホームヘルパー)と情報交換したりして18時まで過ごしました。これで一日の業務は終了です。
<ここがポイント>
訪問介護は単独業務になることが多いため、施設勤務よりも人間関係のストレスは少ないと言われています。施設勤務の場合、同僚や勤務先での人間関係だけでなく、複数の利用者との関係において、ストレスが生じることがあるからです。
平成29年度「介護労働実態調査(公益財団法人 介護労働安定センター)」によると、「介護関係の仕事を辞めた理由」で最も多かったのが「職場の人間関係に問題があったため」となっています。
同調査において、「今の勤務先で働き続けたいか」という質問に対し、施設等の介護職員の52.0%が「はい」と回答したのに対し、訪問介護員(ホームヘルパー)は65.7%が「はい」と回答していることから、施設等での勤務と比べて、訪問介護員(ホームヘルパー)は働きやすい環境にあるといえるのかもしれません。
「混合介護」の実施でサービス内容の拡大が期待
混合介護は、介護保険サービスに保険外サービスを全額自費で上乗せする新しいシステムです。2018年8月1日から2021年3月31日まで、東京都・豊島区で特区として「選択的介護モデル事業」が進められています。
安倍総理大臣は政府の「全世代型社会保障検討会議」において「ニーズに合わせて保険外のサービス提供と柔軟に組合せができるようルールの明確化を図る」と述べるなど、改めて「混合介護」を推進する考えを表明しており、今後の訪問介護におけるサービスの拡大が期待されています。
混合介護で可能になるサービスの例
- 庭の草むしり、ペットの世話
- 外出に付き添った後に、趣味や楽しみのための場所への同行
- 乗り物の乗降介助など保険内のサービス提供後に、保険外サービスとして院内の付き添いを行うこと
- 同居家族の部屋の掃除や日常生活支援に当てはまらない大掃除、家族のための買い物など
訪問介護は、ワークライフバランスに合わせた働き方にマッチ
訪問介護員(ホームヘルパー)の雇用形態は非常勤が多いため、安定した収入が得られにくいという側面がある一方で、施設への勤務などと比べて勤務時間が柔軟に設定できることから、仕事と家事や育児などを両立しやすいのが利点です。
自身のワークライフバランスに合わせた働き方の1つとしてホームヘルパーとしての勤務を検討してみてはいかがでしょうか。
- 参考URL
- 特別養護老人ホームの入所申込者の状況|厚生労働省
- 在宅医療・介護推進プロジェクト|首相官邸
- 平成29年度 介護労働実態調査|公益財団法人介護労働安定センター
- 訪問介護職の有効求人倍率13倍に上昇 人材確保急務に|NHK政治マガジン
- 介護福祉士国家試験|社会福祉試験振興・試験センター
- 介護職員基礎研修について|厚生労働省
- 介護人材の確保について|第4回社会保障審議会福祉部会|福祉人材確保専門委員会|厚生労働省
- 介護サービスの生産性向上に向けた取組|厚生労働省
【日本全国電話・メール・WEB相談OK】介護職の無料転職サポートに申し込む
●関連記事:訪問介護で行う生活援助とは?介護保険適応サービスと保険外サービスの違いを理解しよう
SNSシェア