かんたき(看護小規模多機能型居宅介護)とは?施設の特徴は?
構成・文/介護のみらいラボ編集部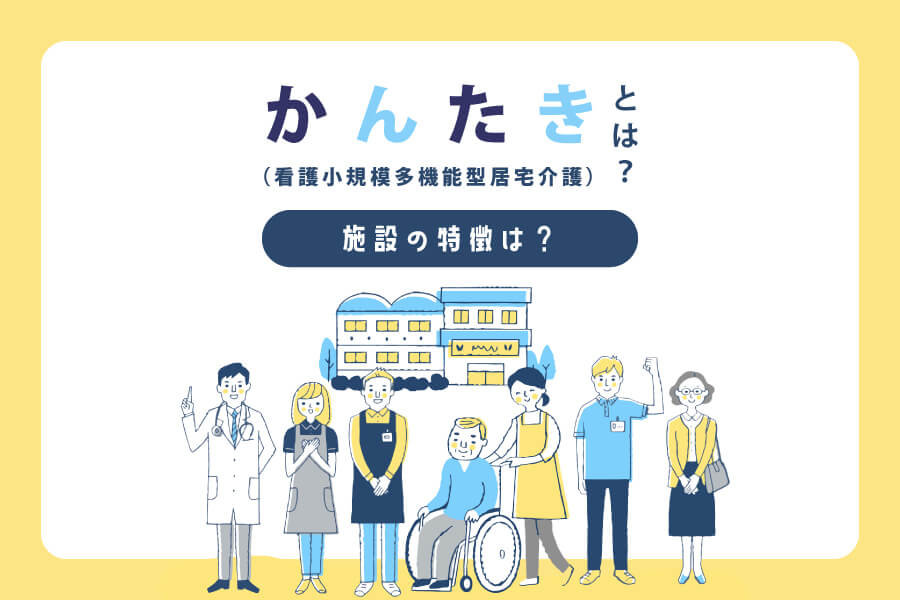
「かんたき」は看護小規模多機能型居宅介護の略称であり、高齢化が進むわが国において、その需要は右肩上がりの状況です。だからこそ、かんたきのサービス内容を詳しく知っておけば、自身の活躍の場を広げることができるでしょう。
当記事では、かんたきの概要や特徴、創設された経緯について解説します。介護職がかんたきで働くメリットとデメリットも紹介するので、「予備知識として持っておきたい」「職場選びの検討材料にしたい」という方は、ぜひ参考にしてください。
1.かんたきとは?どんな特徴がある?
かんたき(看護小規模多機能型居宅介護)とは、看護と介護を一体的に提供するサービスです。退院後の在宅生活への移行を支援するだけでなく、利用者さまが住み慣れた地域で暮らしていけるように、複数のサービスを組み合わせて対応します。
かんたきは介護保険適用サービスであり、利用者さまの多くは要介護3以上の方たちです。利用料金は基本的に月額定額制となっており、大きく分けて3つの特徴があります。
(出典:厚生労働省「看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)について」/)
「通い」「泊まり」「訪問」を利用できる
かんたきでは、下記の3つのサービスを提供します。
<かんたきのサービス>
・通い(通所介護)
食事や入浴、レクリエーションのほか、主治医の指示のもとで医療ケアやリハビリを提供。利用時間・曜日については、利用者さまやご家族の都合に合わせて柔軟に対応するのが特徴です。利用者さま3人に対して1人以上の保健師や看護師(准看護師)を配置するなど、人員基準が明確に定められています。
・泊り(短期入所)
夜間対応のスタッフが配置されており、利用者さまは施設に泊まって必要なケアを受けることができます。日頃から利用する施設であるため、気兼ねせずに過ごせるのがポイントです。宿泊可能な人数は、通いサービス利用定員の3分の1から9人までとなっています。
・訪問(訪問看護/訪問介護)
訪問看護:看護師が利用者さまの自宅に直接訪問し、主治医の指示のもとで体調チェックや血糖値測定などを行います。
訪問介護:介護士などが、利用者の自宅に出向いて食事や入浴の介助、調理や掃除などの生活支援を行います。
かんたきは在宅療養を総合的に支えるだけでなく、家族の介護負担の軽減や不安解消にも大きく貢献します。
(出典:厚生労働省「看護小規模多機能型居宅介護」)
医療依存度が高い方にも24時間365日対応している
医療機関と密接に連携しながら、昼夜を問わず毎日対応を行うこともかんたきの特徴です。利用者さまのなかには末期がんや脳卒中、認知症などの疾患を患っている方や、脊髄小脳変性症、パーキンソン病といった、難病を抱えている方もいらっしゃいます。そのため、現場では下記のような医療ケアを実施します。
<かんたきにおける医療ケア>
・胃ろうや腸ろうによる栄養管理
・カテーテル管理
・喀痰吸引
・酸素療法
・ストーマのケア
・気管切開のケア
・人工呼吸器の管理
・インスリン注射
・静脈内注射
・疼痛管理
上記の他、利用者さまが自宅で自分らしい最期を迎えられるように、看取りに対応するケースも少なくありません。
(出典:厚生労働省「看護小規模多機能型居宅介護」)
サービスが変わっても同じスタッフが担当する
デイサービスやショーステイ、訪問介護など複数のサービスを利用した場合、担当するスタッフはサービスによって異なります。一方、かんたきはすべてのサービスにおいて同じ施設のスタッフが担当します。常になじみのあるスタッフが担当することで、利用者さまは安心感を得られるでしょう。定員人数も最大29人までとなっているため、一人ひとりと向き合ったサービスが提供できるのも大きなポイントです。
なお、かんたきは他の居宅サービスと併用することができず、利用にあたっては各事業所専属のケアマネジャーに依頼する必要があります。とはいえ、それが利用者さまにとってマイナスになることはなく、「面倒な手続きが1カ所で済ませられる」「一貫性のあるサービスが受けられる」といったメリットのほうが大きいでしょう。
2.かんたき(看護小規模多機能型居宅介護)が創設された経緯
在宅療養を希望しているものの、看護力や介護力が足りないために、なかなか実現できないケースは多くあります。また、単身世帯や高齢者のみの世帯が増えていることから、今後はそうしたケースが増加すると予想されます。
そんななか、医療依存度の高い人の在宅療養を支えることを目的に、2012年に創設されたのがかんたきです。当初「複合型サービス」という名称だったかんたきは、サービス内容をイメージしやすくするため、2015年に「看護小規模多機能型居宅介護」に改称されました。
同年には、訪問看護体制強化加算が新設され、中重度の要介護者の医療ニーズに重点的な対応をしている事業所が評価される仕組みになりました。また、2018年には医療ニーズに対応可能な介護職員との連携体制の構築、ターミナルケア体制の整備が行われるなど、看護体制の強化を推進。サテライト型の事業所でも、サービスを提供できるようになりました。
かんたきの請求事業所数は、2019年時点で531事業所となっており、毎年約80の事業所が増えています。今後も同様の流れが続くと予想されますが、同時に制度自体の細かな見直しが行われる可能性があります。
(出典:厚生労働省「看護小規模多機能型居宅介護」)
(出典:日本看護協会「看護小規模多機能型居宅介護の創設の経緯」)
3.「かんたき」と「しょうたき」の違い
かんたきとよく似た名称のサービスに、「しょうたき」(小規模多機能型居宅介護)があります。ここでは、かんたきとしょうたきのサービスの違いについて確かめておきましょう。
しょうたきとは、要介護者(要支援者)の様態や希望に応じて、「通い」を中心に「訪問」「泊まり」を組み合わせるサービスです。一見すると、かんたきと同じサービス内容のように思えますが、決定的な違いとして「医療的処置が必要な方の受け入れ可否」が挙げられます。
しょうたきのサービスは、身体介助、生活介助、機能訓練といった内容にとどまりますが、かんたきはこれに加えて医療ケアを行います。2006年に創設されたしょうたきは、かんたきの基盤となったサービスであり、「しょうたきの機能に訪問看護の機能を加えたのが、かんたき」だと認識しておくと混同を避けられるでしょう。
(出典:厚生労働省「看護小規模多機能型居宅介護」)
(出典:厚生労働省「小規模多機能型居宅介護」)
4.介護職がかんたきで働くメリット・デメリット
かんたきで働きたいと考えている方は、メリットとデメリットについても把握しておきましょう。
<メリット>
・豊富な知識や経験が得られる
介護だけでなく医療分野のサービスも提供しているため、一般的な介護現場で働く場合と比べて、多くの知識や経験を得ることができます。臨機応変に対応しなくてはならない場面も多いため、適応力や判断力も身に付くでしょう。
・利用者さま一人ひとりとじっくり向き合える
かんたきは少人数制であることから、利用者さまのニーズに応えやすい環境です。温かい心の交流は、仕事のモチベーションにもつながるでしょう。
・キャリアアップを目指しやすい
かんたきには、ケアマネジャーも在籍しています。実務経験を積みながら受験資格を得られることはもちろん、条件次第ではそのままケアマネジャーとして活躍できるチャンスがあるかもしれません。そうやって慣れた職場でキャリアアップを目指せる点は、大きな魅力です。
<デメリット>
・業務範囲が広い
多様なサービスを提供するかんたきでは、覚えなくてはならない業務がたくさんあります。訪問のみ、通いのみなど、特定の介護サービスに従事してきた方は、とまどう場面も少なくないでしょう。経験値にかかわらず、慣れるまでには相応の時間が必要だと考えるのが妥当です。
・変則的な働き方になる
24時間365日対応をするかんたきでは、夜勤や宿直があります。生活のリズムを安定させるには、ある程度決まったパターンでシフトを組んでもらうなどの対策が必要です。
医療依存度の高い方が在宅で暮らせるように、介護と看護を一体的に提供することが、かんたきの特徴であり強みです。「もっと多角的に利用者さまをサポートしたい」と考えている介護職の方なら、これまで以上のやりがいを実感できるでしょう。また、スキルアップやキャリアアップを目指している方にとっても、かんたきは重要な選択肢の一つとなるはずです。
まとめ
かんたきは、看護と介護を一体的に提供するサービスです。利用者さまやご家族のニーズに合わせて「通い」「泊まり」「訪問」を選択できる他、医療ケアを中心に24時間365日対応していることが主な特徴です。介護職がかんたきで働く場合は、「幅広い知識と経験が得られる」「キャリアアップを目指しやすい」などのメリットがあります。
「介護のみらいラボ」では、介護分野の最新ニュースや高齢者レクリエーションのやり方など、介護職として働く上で役立つ情報を幅広く掲載しています。日々の情報収集に、ぜひご活用ください。
※当記事は2022年5月時点の情報をもとに作成しています
【日本全国電話・メール・WEB相談OK】介護職の無料転職サポートに申し込む
スピード転職も情報収集だけでもOK
マイナビ介護職は、あなたの転職をしっかりサポート!介護職専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを行います。
はじめての転職で何から進めるべきかわからない、求人だけ見てみたい、そもそも転職活動をするか迷っている場合でも、キャリアアドバイザーがアドバイスいたします。

SNSシェア















