要介護5とは?認定基準や受けられるサービス、ケアの注意点まで解説
文/中谷ミホ(介護福祉士・ケアマネジャー・社会福祉士)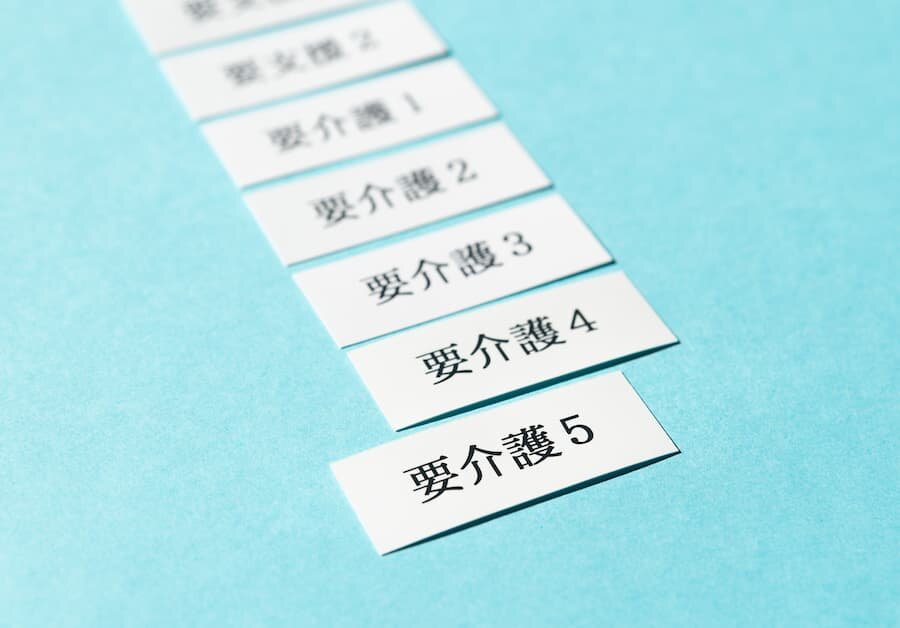
実際の介護現場では、要介護度の軽い方から重度の方まで、さまざまな利用者さんのケアにあたります。そのため、介護職として働くにあたっては、要介護度ごとに心身の状態やケアの方法、介護保険制度に関する知識をきちんと身につけておきたいものです。
そこで、今回は要支援・要介護区分のなかで最も重度な「要介護5」を取り上げ、認定基準や受けられるサービス、ケアする際の注意点などを詳しく解説していきます。これから介護職を目指す方や介護職として働く予定のある方は、ぜひ参考にしてください。
1.要介護5とは
要介護5は、介護なしに日常生活を送ることがほぼ不可能な状態です。立ち上がりや歩行が難しく、1日の大半をベッドの上で過ごすようになります。
寝たきりの状態になると、関節の動きに制限が起こる拘縮や褥瘡(床ずれ)のリスクが高まります。そのため、これらを予防するための専門的な介護が必要です。
さらに要介護5になると、咀嚼(かむ)や嚥下(飲み込む)などの口腔機能が低下して、窒息や誤嚥性肺炎を起こしやすくなります。
そのため、食事の際は介助、見守りなどの支援を受けて嚥下食を食べる方もいれば、口から食事を取ることが困難となり、経鼻経管栄養や胃ろうを通して栄養を摂取する方もいます。
認知機能面では、理解力や思考力が低下し、意思疎通が難しくなります。自分で動けない方が多いため、徘徊はほとんど見られませんが、異食や不潔行為などの行動・心理症状(BPSD)が見られることがあるでしょう。
要介護5の認定基準
要介護度認定を行う基準の1つに、厚生労働省が定める「要介護認定等基準時間」があります。
要介護認定等基準時間とは、「介護に要する時間(介護の手間)」を時間に換算して評価したもので、要介護5では「110分以上」とされています。
要介護認定等基準時間で算出する介護の内容は次のとおりです。直接生活介助は、食事、排泄、移動、清潔保持にわけて推計されます。
• 直接生活介助:入浴や排泄、食事などの介助
• 間接生活介助:洗濯や掃除などの家事援助など
• BPSD関連行為:徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末など
• 機能訓練関連行為:歩行訓練や日常生活訓練などの機能訓練
• 医療関連行為:輸液の管理、褥瘡の処置などの診療などの補助
(出典:厚生労働省『介護認定審査会テキスト』)
厚生労働省が定める要支援・要介護度の区分別の「要介護認定等基準時間(1日あたり)」は次のとおりです。
| 区分 | 要介護認定等基準時間 |
|---|---|
| 要支援1 | 25分以上32分未満 |
| 要支援2、要介護1 | 32分以上50分未満 |
| 要介護2 | 50分以上70分未満 |
| 要介護3 | 70分以上90分未満 |
| 要介護4 | 90分以上110分未満 |
| 要介護5 | 110分以上 |
(出典:厚生労働省『介護認定審査会テキスト』)
なお、要介護認定等基準時間は、あくまでも介護の必要性をはかる「ものさし」として時間を定めたものです。実際のケアにかかる時間を示すものではないので、注意しましょう。
要介護5と要介護4の違い
要介護4と要介護5は、どちらも日常生活のほとんどに介護を必要とする状態です。しかし、両者を比較すると残存機能や意思の疎通などの点に違いがあります。
例えば、要介護5が寝たきりの状態であるのに対し、要介護4では全面的な介助があれば、歩行や立ち上がりが可能です。また、支えがあれば座ることもできます。
食事や排泄、入浴などの日常生活動作に目を移すと、要介護5ではほとんどの動作で介助を必要としますが、要介護4では介助があれば自分でできる動作もあります。
認知機能面では、どちらも理解力の低下や認知症による行動・心理症状(BPSD)が見られます。
意思疎通は、要介護5だと日常生活全般にわたって難しいことが多いですが、要介護4では状況に応じてある程度可能です。
2.要介護5で受けられるサービス・制度
要介護5になると、日常生活のほぼすべてに介助を必要とするため、さまざまな種類の介護サービスが受けられます。
ここからは、要介護5の方が受けられる介護サービスと、利用できる制度を見ていきましょう。
訪問型サービス
訪問型サービスとは、自宅で受けられるサービスのことです。一般的には、ホームヘルパーや看護師などが自宅を訪問して、身体介護や家事援助、看護、リハビリテーションなどのサービスを提供します。
要介護5の方が利用可能な訪問型サービスは、次の6種類です。
• 訪問介護(ホームヘルプ)
• 訪問入浴
• 訪問看護
• 訪問リハビリテーション
• 夜間対応型訪問介護
• 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
通所型サービス
日帰りで施設に通い、介護やリハビリテーションなどを受けるサービスです。要介護5では、次の5種類が利用できます。
• 通所介護(デイサービス)
• 通所リハビリテーション
• 地域密着型通所介護
• 療養通所介護
• 認知症対応型通所介護
施設に短期入所して受けるサービス
施設に短期間の宿泊(短期入所)ができるサービスです。短期入所には、一般型と医療型の2種類があり、いずれも1泊2日から連続30日を上限に利用できます。
• 一般型:短期入所生活介護(ショートステイ)
• 医療型:短期入所療養介護
訪問・通所・短期入所を組み合わせたサービス
1つの事業所と契約し、訪問介護・看護、通い(通所介護)、宿泊(短期入所)の3つのを柔軟に組み合わせて利用するサービスです。
サービスには、次の2種類があります。
• 小規模多機能型居宅介護
• 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
施設に入所して受けるサービス
要介護5の方は、次の7種類の施設が利用できます。
• 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
• 介護老人保健施設
• 介護医療院
• 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホームなど)
• 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
• 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
• 地域密着型特定施設入居者生活介護
福祉用具をレンタル・購入するサービス
介護保険では、福祉用具のレンタルや購入も可能です。要介護5の方がレンタルできる福祉用具は、次の13品目です。
• 特殊寝台
• 特殊寝台の付属品
• 床ずれ防止用具
• 体位変換器
• 手すり
• スロープ
• 車いす
• 車いすの付属品
• 歩行器
• 歩行補助つえ
• 移動用リフト
• 徘徊感知機器
• 自動排泄処理装置
要介護5の場合は、上記の福祉用具が1割負担(場合によっては2割または3割)でレンタルできます。
衛生面などの理由でレンタルに向かない福祉用具は、特定福祉用具販売に指定されており、介護保険を使った購入が可能です。同一年度で購入できる福祉用具は10万円までで、介護保険の利用者負担の割合に応じて、購入費の7~9割が払い戻されます。
福祉用具販売の対象用具は、次の6品目です。
• 腰掛け便座
• 自動排泄処理装置の交換可能部品
• 排泄予測支援機器
• 入浴補助用具
• 簡易浴槽
• 移動用リフトのつり具の部品
住宅改修の保険給付
自宅をバリアフリーに改修工事をする際、保険給付が受けられます。支給額の上限は、1人につき20万円です。
高額介護サービス費制度
1か月間に支払った介護サービスの利用者負担額の合計が負担限度額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。課税所得の金額、あるいは生活保護を受給しているかなどの条件によって、上限額が決まっています。
障害者控除
障害者手帳の交付を受けていなくても、市町村長や福祉事務所長などから認定を受けていれば、障害者控除が適用される場合があります。
3.要介護5でかかる費用
最重度である要介護5では、介護サービスの利用頻度が高まるため、介護費用が高額になりやすい傾向にあります。
ここでは、在宅介護の場合と、施設に入居した場合にかかる費用の目安を見ていきましょう。
在宅介護の場合
訪問介護、訪問看護、ショートステイ(介護型)、ベッドレンタルを利用した場合の月額料金の目安は次の通りです。
| サービス内容 | 利用回数/月 | 利用詳細 | 自己負担額 (1割の場合) |
|---|---|---|---|
| 訪問介護(身体介護) | 28回 | 30分以上1時間未満 | 11,088円 |
| 訪問看護 | 8回 | 30分以上1時間未満 | 6,568円 |
| 短期入所療養介護(介護老人保健施設) <従来型個室>【療養型】 | 8回 | 1泊2日を8回 | 9,048円 |
| 特殊寝台(ベッド)貸与 | 1,000円/月 | ||
| 合計 | 27,704円 | ||
※金額は、各種加算や別途費用を除いた試算額です。
(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造」(令和3年))
施設入居の場合
施設に入居する場合、公的な施設と民間の事業者が運営している施設とで、1か月の利用料(利用者負担額)は異なります。
ここでは、要介護5の方が入居できる施設のなかから、公的な施設である「介護老人福祉施設」と、民間の施設である「介護付き有料老人ホーム」の月額利用料の一例を紹介しましょう。
| 施設の種類 | 入居一時金 | 月額利用料 (利用者負担額) |
|---|---|---|
| 介護老人福祉施設 (ユニット型個室) | なし | 約14万円 |
| 介護付き有料老人ホーム | あり | 前払い方式(※)の場合約18万円 月払い方式の場合:約20万円 |
※前払い方式とは、入居時に一括して終身の家賃等の全部、あるいは一部を支払う方法のことです。
(出典:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」)
公的な介護保険施設には、介護老人福祉施設や介護老人保健施設、介護医療院があり、いずれも入居一時金はかかりません。月額利用料(利用者負担額)は利用する居室のタイプによっても異なりますが、相場は一例で示したとおりです。これらの施設では、世帯所得などに応じて、さまざまな減免制度も用意されています。
一方、民間の事業者が運営する介護付き有料老人ホームの場合、入居一時金や月額利用料は、施設ごとに金額が異なります。
4.要介護5の区分支給限度額
居宅サービスを利用するにあたっては、1か月で利用できる限度額が設定されています。要介護5の支給限度額は、1か月あたり362,170円です。
支給限度額は、要介護度の区分ごとに設定されています。支給限度額を超えた場合、超過分は全額利用者負担となります。
要介護度別の支給限度額は次の通りです。
| 区分 | 支給限度額 |
|---|---|
| 要介護1 | 167,650円 |
| 要介護2 | 197,050 円 |
| 要介護3 | 270,480円 |
| 要介護4 | 309,380 円 |
| 要介護5 | 362,170円 |
要介護5の方は、1か月間に362,170円までであれば、介護保険の適用内で介護サービスが受けられることになります。支給限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1~3割が利用者負担です。
「介護度が最重度なため、介護サービスを利用する量が増える」という観点から、要介護5は要介護度の区分のなかで、最も高い支給限度額となっています。
5.要介護5の利用者さんをケアする際の注意点
要介護5の方のケアで、特に注意したいのが褥瘡です。寝たきりの方は褥瘡ができやすいため、予防や対策が必須です。
日頃のケアでは、定期的な体位交換だけでなく、皮膚の摩擦やずれ、汚れ、湿り気、低栄養などにも気をつける必要があるでしょう。
褥瘡の予防・対策では、シーツや衣類のしわをしっかりと伸ばし、クッションなどを使用して身体がずれないようにポジショニングを行うことが大切です。また、おむつ交換の際には、排泄物をきれいに拭き取って皮膚の清潔を保ちましょう。皮膚に赤みなど異常が見られたら、早めに医師や看護師に報告してください。
また、拘縮や麻痺などがある方の場合、更衣介助で痛みを感じるケースが少なくないため、ゆっくりと介助することが大切です。脱健着患を意識して、脱ぐときは動かしやすい健側(健康なほうの腕や足)から、着るときは麻痺やけがなどがある患側から介助を行いましょう。
食事介助では誤嚥に注意が必要です。誤嚥とは、飲み込んだ際に、食べ物や飲み物、唾液が食道ではなく気管に入ることです。
食事を行う際の姿勢が悪いまま食事介助をすると、誤嚥性肺炎を引き起こすリスクが高まるため、食事の際には上半身をしっかりと起こすなど、正しい姿勢の確保を心がけてください。
なお、利用者さんが意思疎通の難しい方であっても、介助者のペースで黙ってケアを行うのではなく、利用者さんに対する声かけを必ず行いましょう。
例えば、介助の開始時に行う「これから食事をしましょう」といった声かけもその1つです。そうした声かけは、利用者さんに安心感を与え、尊厳を守ることにもつながるので、ぜひ実践してください。
まとめ
要介護5は、要介護度で区分されている5段階のなかで最も重度な状態です。寝たきりの状態が多く、意思疎通が困難な方がほとんどです。
日常生活のすべての場面で介護を必要とするため、介護保険ではさまざまな種類の介護サービスが利用できます。また、多くの介護サービスを利用できるように、介護保険の支給限度額もいちばん高い設定となっています。
介護職が要介護5の方のケアにあたるときは、専門的な知識や技術が必要となる場面が多くなります。意思疎通が困難な利用者さんであっても、コミュニケーションを積極的にとり、尊厳を守るケアを行うように心がけましょう。
●関連記事:
・介護度とは? 要介護区分の内容と介護保険の申請方法
・日常生活自立度(寝たきり度)とは?詳しい評価基準と内容
【日本全国電話・メール・WEB相談OK】介護職の無料転職サポートに申し込む
スピード転職も情報収集だけでもOK
マイナビ介護職は、あなたの転職をしっかりサポート!介護職専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを行います。
はじめての転職で何から進めるべきかわからない、求人だけ見てみたい、そもそも転職活動をするか迷っている場合でも、キャリアアドバイザーがアドバイスいたします。

SNSシェア















