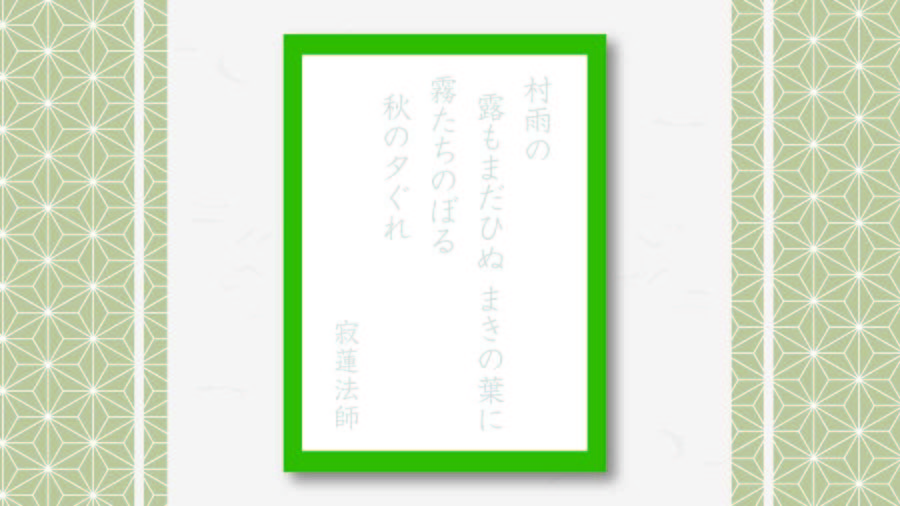【なぞり書き百人一首】夏の歌③ ほととぎす 鳴きつる方を ながむれば ただありあけの 月ぞ残れる
構成・文/介護のみらいラボ編集部
夏の歌の第3回目にピックアップしたのは、後徳大寺左大臣の作品。歌意や作者の解説なども掲載しておきますので、情景や詠み手の思いを感じながら、ゆっくりと文字をなぞってみましょう。
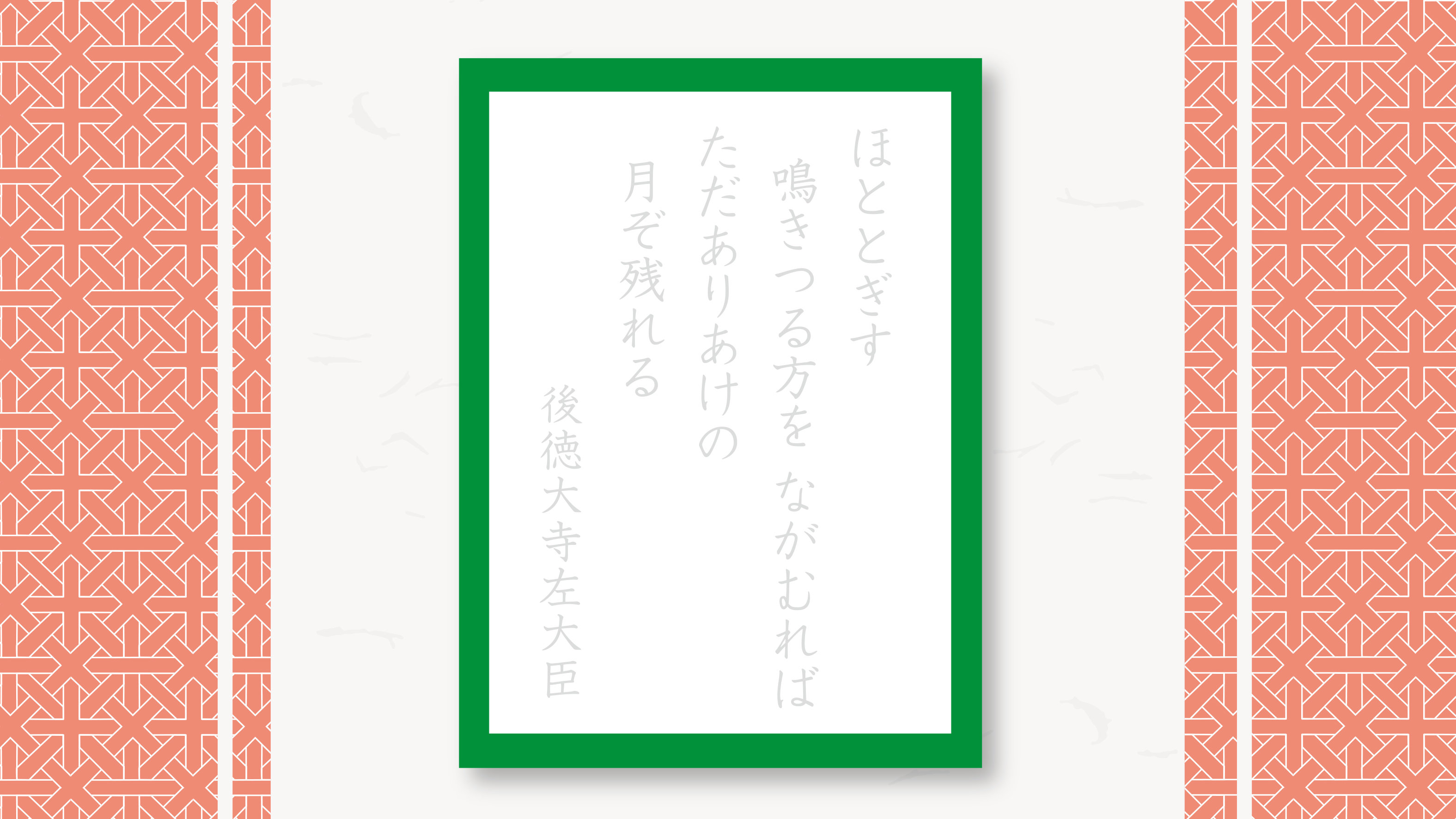
歌の意味と作者について
歌番号81番は、後徳大寺左大臣が詠んだ一首。夏のはじめに飛来するホトトギスは、平安貴族の間で「夏の訪れを告げる鳥」とされており、その初音(季節に初めて鳴く声)を聴くのはとても優雅なことだったそうです。
ほととぎす 鳴きつる方を ながむれば
ただありあけの 月ぞ残れる
小倉百人一首 歌番号(81番) 後徳大寺左大臣
歌意
ほととぎすが鳴いた方角を眺めやると、もうほととぎすの姿はなくて、ただ有明の月が、ひっそりと空に残っているだけだった。
ことば
●ほととぎす:5月ごろ渡来し、秋には南に去っていく渡り鳥。日本の夏を代表する風物として、古くから愛されていました
●鳴きつる方:「鳴いた方角」の意味
●ありあけの月:夜が明ける頃になっても空に残っている月のこと
作者
後徳大寺左大臣(ごとくだいじのさだいじん):本名は藤原実定で、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての公卿・歌人。百人一首の撰者である藤原定家は、いとこにあたります。
[参考]
『全訳読解古語辞典 第五版』(三省堂)
『百人一首(全) ビギナーズ・クラシックス 日本の古典』(角川ソフィア文庫)
『解説 百人一首』 (ちくま学芸文庫)
スピード転職も情報収集だけでもOK
マイナビ介護職は、あなたの転職をしっかりサポート!介護職専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを行います。
はじめての転職で何から進めるべきかわからない、求人だけ見てみたい、そもそも転職活動をするか迷っている場合でも、キャリアアドバイザーがアドバイスいたします。

SNSシェア