介護離職とは?原因やメリットデメリット・離職以外の選択肢も
文/佐藤正幸(長岡崇徳福祉専門学校 介護福祉学科 専任教員)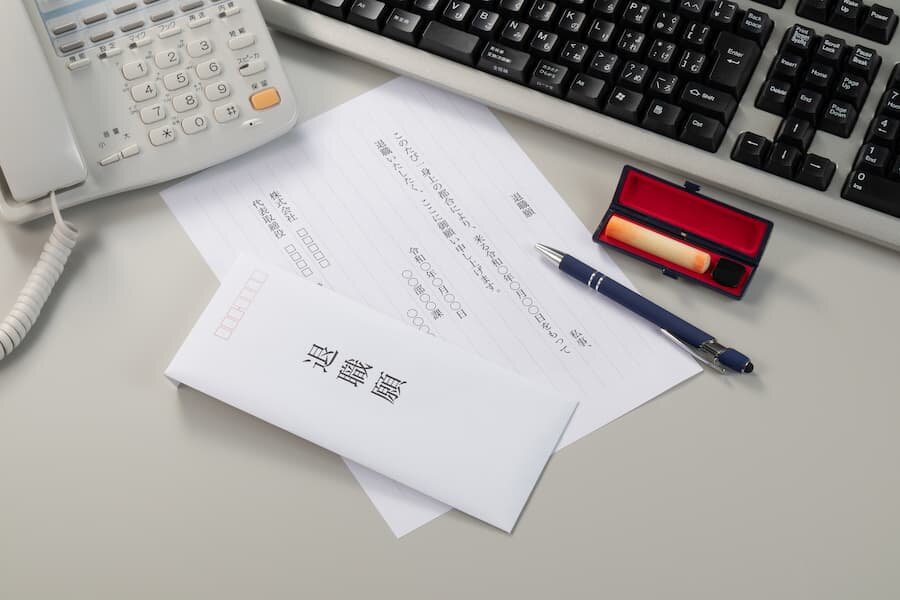
介護離職とは、家族の介護を理由に仕事を辞めることをいいます。
社員の離職は会社側にとって大きな痛手ですが、なかには仕事がなくなることで、介護者とその家族も経済的に苦しくなるケースがあります。離職という選択をせずに、仕事と介護を両立することはできないのでしょうか。
仕事との両立を目指すには、制度をうまく活用して、経済的な基盤を維持しながら介護を続けることが大切になります。そして、そうした方法が結果的には、介護者と介護を受けている家族の心身の健康維持にもつながるでしょう。
この記事では、介護離職の現状とその原因、介護離職を防ぐための具体的な方法などを紹介していきます。
1.介護離職の現状
厚生労働省の過去10年間のデータから介護離職者数の平均を計算すると、男女合わせて年間約9万人となっています。また、男女比を見てみると、男性よりも女性のほうが2.9倍多い数値です。
女性の介護離職者数が多いのは、同居している介護者の約65%が女性であることが影響していると考えられます。

「雇用動向調査結果の概況」(厚生労働省)<2012年~2021年>を元に筆者作成
2.介護離職に至る理由
NTTデータ経営研究所が、介護離職経験者2,000人を対象に行った調査によると、介護離職の原因として多かったのは次の5つでした。
1. 仕事と介護の両立が難しい職場だった 59.4%
2. 介護をする家族・親族が自分しかいなかった 17.6%
3. 自分の心身の健康状態が悪化したため 17.3%
4. 介護に専念したかった 15.4%
5. 施設へ入所できず介護の負担が増えた 15.0%
「仕事と介護の両立が難しい職場だった」が60%近くを占めることから、職場の理解がいかに重要かがわかります。
さらに、「介護をする家族・親族が自分しかいなかった」という回答も17.6%におよんでおり、助けてくれる人・サービスの存在があれば、離職せずに済む可能性も見えてきます。
3.介護離職のメリット・デメリット
先の調査によると、「介護離職後の自身の変化に関する精神面・肉体面・経済面」に関する回答は次の通りでした。
〇精神面
非常に負担が増した 30.2%
負担が増した 26.1%
変わらない 14.8%
負担が減った 12.6%
かなり負担が減った 9.9%
〇肉体面
非常に負担が増した 24.0%
負担が増した 27.5%
変わらない 16.4%
負担が減った 15.2%
かなり負担が減った 10.8%
〇経済面
非常に負担が増した 34.1%
負担が増した 35.0%
変わらない 19.0%
負担が減った 3.7%
かなり負担が減った 1.6%
5割以上の人が、精神的にも肉体的にも負担が増したと回答し、約7割もの人が経済面の負担が増したと回答しています。
介護離職によって経済的な負担が増すのは、ある意味想像どおりといえますが、注目すべきは、「軽くなる」と考えられていた精神的な負担が増していることです。
このことから、介護離職は経済的な負担を重くするだけでなく、精神的な負担が重くなることも多いため、家族の状況を悪化させる危険性が非常に高いといえるでしょう。
4.知っておきたい介護離職以外の選択肢
では、介護離職をしないためにはどうすればよいのでしょうか。ここでは、仕事と介護を両立するために、活用してほしい制度などを見ていきます。
介護休業
「育児・介護休業法」は、仕事と育児・介護の両立を支援するために作られた法律で、そのなかには介護休業についての定めもあります。
これは、「要介護状態(※)にある対象の家族を介護する場合は、介護休業が取得できる」というもので、対象家族1人につき、通算93日まで取得することが可能です。また、介護休業は3回まで分けて取得することもできます。
※負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態を指します。
つまり、家族の介護のために、複数の介護者が同時に介護休業を取得したり、自分が3か月、配偶者が3か月、子どもが3か月と、日をずらして取得したりもできるわけです。
介護休暇を取得する場合は、原則2週間前までに事業主に申し出ることになっています。また、介護休業は看取りのために取得することも可能です。
ちなみに対象家族とは、「労働者の配偶者」「父母」「子」「配偶者の父母」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」のことをいいます。本人の祖父母、兄弟姉妹を介護する場合にのみ介護休業の取得が可能で、配偶者の祖父母や兄弟姉妹は対象外です。
介護休業給付金
介護が大変になると、仕事を一時的に休業しないといけないこともあります。また、その場合、介護者は収入が減ってしまい生活が成り立たなくなることも考えられます。そうしたときに利用したいのが、介護休業給付金です。
介護休業給付金の支給対象は、家族の介護のために休業した雇用保険の一般被保険者で、介護休業を開始した日より前の2年間に、雇用保険の加入期間が12か月以上あることが条件となります。
なお、厚生労働省では12か月間の基準について、「介護休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を1か月とする」と定めています。
給付金を受給するには、事業主に介護休業開始日の2週間前までに申請する必要があり、支給額は、休業開始時賃金×支給日数×67%です。つまり、給与の67%を受け取ることができるわけです。そして、休業期間が終わると職場に復帰することができます。
介護休暇
介護休暇とは、要介護状態にある対象家族の介護や、その他の世話(通院の付き添いや施設への送迎など)をするために取得できる休暇のことで、こちらも育児・介護休業法に定められています。
介護休暇は、要介護状態にある対象家族1人につき1年に5日、対象家族が2人以上の場合は1年に10日まで取得することができます。また、時間単位で取得することも可能です。
働き方の見直し
育児・介護休業法では、介護休業や介護休暇のほかにも、短時間勤務などの措置(短時間勤務、フレックスタイム制度、時差出勤)や所定外労働の制限(残業免除)、時間外労働の制限、深夜業の制限などを定めているため、一度、会社に相談してみるとよいでしょう。そうした相談は、都道府県労働局でも受け付けています。
5.介護保険サービスのことで困ったときの相談窓口
介護離職後に負担が増えないようにするためには、「介護を1人で抱え込まない」「介護をしすぎない」「深刻に捉えすぎない」という3点が大切です。そして、そのためには介護保険サービスを上手に活用して、自分の時間を確保しながら介護に向き合う必要があります。
介護保険サービスの利用に関することは、最寄りの地域包括支援センターに相談しましょう。すでに介護サービスを利用している場合は、担当のケアマネジャーに相談してみてください。
抱えている問題を専門家に話すことで気持ちが楽になったり、もらったアドバイスが介護のヒントになったりするかもしれません。また、介護保険サービスの利用は、それを必要とする人だけでなく、家族のレスパイト(休息)にもなります。共倒れにならないためにも状況に合ったサービスを活用し、心身の健康維持に努めましょう。
また、要介護状態の家族が自宅での生活を維持するためには、手すりを取り付ける、床の段差をなくす、開きやすい扉に交換するなど、居住環境を整えることも大切です。それによって自立度が向上すれば、けがや事故を減らすことができるでしょう。
介護保険では20万円を上限として、そのうちの1割自己負担で工事を行うことができます。
※当記事は2023年11月時点の情報をもとに作成しています
まとめ:1人で抱え込まずに必ず相談を
介護離職を防ぐためには、1人で抱え込まないことが重要です。先にお伝えしたように、離職したからといって必ずしも楽になるわけではなりません。場合によっては、負担が増えるケースも考えられます。
まずは専門家や会社に相談をし、育児・介護休業法や介護保険制度をきちんと活用しながら、仕事と介護の両立を目指していきましょう。
●関連記事
・介護問題とは?9つの問題とその背景
・介護疲れの原因は?疲れを軽減する方法・対策を紹介
スピード転職も情報収集だけでもOK
マイナビ介護職は、あなたの転職をしっかりサポート!介護職専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを行います。
はじめての転職で何から進めるべきかわからない、求人だけ見てみたい、そもそも転職活動をするか迷っている場合でも、キャリアアドバイザーがアドバイスいたします。

SNSシェア















