障害福祉サービスとは?種類や対象者、利用の流れなどを解説!
文/中村 楓(介護支援専門員・介護福祉士・介護コラムニスト)
障害を持つ利用者さんを対象としたサービスは、障害福祉サービスといいます。障害を持つ人それぞれに合ったサービスを提供するため、介護の仕事と似たようなサービスもあれば、障害福祉サービス独自のものもあります。
本記事では、障害福祉サービスの概要や種類、対象者について解説するとともに、利用料や利用の流れ、障害福祉サービスで働くために必要な資格やスキルについて、わかりやすく解説していきます。
1.障害福祉サービスとは?

障害福祉サービスとは、障害がありサポートを必要としている人に対し、障害の程度や社会活動、介護者、居住などの置かれている状況を踏まえたうえで、必要な支援を提供するサービスです。サービスには、「障害福祉サービス」と「地域生活支援事業」があります。「障害福祉サービス」は介護給付と訓練等給付に、「地域生活支援事業」は実施する主体によって2種類に分けられています。
■サービスの種類
| 項目 | |
|---|---|
| 障害福祉サービス | 介護給付 |
| 訓練等給付 | |
| 地域生活支援事業 | 市区町村が行う支援事業 |
| 都道府県が行う支援事業 |
それぞれのサービスには、期限があるものとないものがあります。期限があっても、必要に応じて期間の延長や更新を行うことができる場合もあり、サービスによってさまざまです。
2.障害福祉サービスの対象者

障害福祉サービスの利用対象となる人は、以下の通りです。
- 身体障害者
- 知的障害者
- 発達障害者を含む精神障害者
また、治療方法が確立していない疾病やそのほかの特殊な疾病であり、政令で定めるものによる障害程度が内閣総理大臣および厚生労働省大臣が定める指定難病となっていることが要件です。2024年4月時点での指定難病は、341種類あります。
そのほか、サービスによって対象者が細かく決められているものがあります。例えば、重度訪問介護の場合は、障害支援区分が区分4以上で以下のいずれかに該当することが必要です。
- 二肢以上に麻痺があり、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている
- 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者
3.障害福祉サービスの種類

障害福祉サービスには、どのような種類があるのでしょうか。それぞれの特徴について、種類ごとに解説します。
介護給付
障害福祉サービスの自立支援給付のうち、介護の支援を受けるものを「介護給付」といいます。介護給付には、「訪問系介護給付」「日中活動系介護給付」「施設系介護給付」の3種類があります。
①訪問系介護給付
訪問系介護給付は、事業所の職員が自宅に訪問して介護等のサービスを行うものです。訪問系介護給付には、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援があります。重度訪問介護以外は、障害児も利用できます。
| サービス | 概要 | |
|---|---|---|
| 居宅介護 | 対象者 |
|
| サービス | 自宅で入浴・排泄・食事の介護等を行うこと | |
| 重度訪問介護 | 対象者 |
以下により行動上著しい困難を有し常に介護を必要とする人
|
| サービス |
|
|
| 同行援護 | 対象者 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人 |
| サービス | 外出する時に必要な情報提供や介護を行うこと | |
| 行動援護 | 対象者 | 自己判断力が制限されている人 |
| サービス | 行動する時に、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行うこと | |
| 重度障害者等包括支援 | 対象者 | 介護の必要性がとても高い人 |
| サービス | 居宅介護等複数のサービスを包括的に行うこと | |
②日中活動系介護給付
日中活動系介護給付は、自宅で生活する人が施設等へ通うことで受けられるサービスです。短期入所・療養介護・生活介護があります。短期入所のみ障害児の利用も可能です。
| サービス | 概要 | |
|---|---|---|
| 短期入所 | 対象者 | 常に介護を必要とする人 |
| サービス | 介護者が病気の場合などに、短期間、夜間も含めた施設で、入浴・排泄・食事の介護等を行うこと | |
| 療養介護 | 対象者 | 医療と常時介護を必要とする人 |
| サービス |
|
|
| 生活介護 | 対象者 | 常に介護を必要とする人 |
| サービス | 昼間の入浴・排泄・食事の介護 創作的活動・生産活動の機会の提供 | |
③施設系介護給付
施設系介護給付は、施設に入所する障害者を対象としており、主に夜間の支援を行います。サービスには施設入所支援があり、常時介護が必要な施設入所者は、日中の支援を行う「日中活動系介護給付」の「生活介護」と組み合わせて利用することが多いでしょう。
| 概要 | ||
|---|---|---|
| 施設入所支援 | 対象者 | 施設に入所している障害者 |
| サービス |
主に夜間
|
|
訓練等給付
自立支援給付のうち、訓練等の支援を受けるものを「訓練等給付」といいます。障害者のみを対象としたサービスで、「居住支援系訓練等給付」と「訓練系・就労系訓練等給付」の2種類があります。
①居住支援系訓練等給付
居住支援系訓練等給付は、日常生活を送るための訓練を行うサービスです。居住支援系訓練等給付には、自立生活援助と共同生活援助の2種類があります。
| 概要 | |
|---|---|
| 自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行うこと |
| 共同生活援助 | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴・排泄・食事の介護、日常生活上の援助を行うこと |
②訓練系・就労系訓練等給付
訓練系・就労系訓練等給付は、障害のある方が自立した生活を送るために必要な訓練や、就労を目指すための訓練を行うサービスです。自立訓練給付と就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援があります。
| サービス | 概要 |
|---|---|
| 自立訓練(機能訓練) | 障害を持つ人に対し、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーション(以下、リハビリ)、日常生活や社会生活に関する相談、助言などを行うこと |
| 自立訓練(生活訓練) | 障害のある人が自立して日常生活や社会生活ができるよう、生活能力を身に付けるために必要な支援、訓練を行うこと |
| 就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する障害を持つ65歳未満の人に、就職に必要な知識やスキル向上の支援を行うこと |
| 就労継続支援(A型) | 障害がある人に働く機会を提供するとともに、一般企業などで働くために必要な訓練を行うこと。事業所と雇用契約を結ぶため、最低賃金が保障される。 |
| 就労継続支援(B型) | 一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会や生産活動の場を提供し、働くために必要な知識やスキルを身に付けるために必要な訓練や支援を行うこと |
| 就労定着支援 | 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題を解決して長く働き続けられるよう支援すること |
地域生活支援事業
地域支援生活支援事業とは、障害のある人が自立した日常生活や社会生活が送れるよう、地域の実情に応じたサービスを提供する事業です。実施主体には、市町村と都道府県があり、それぞれ異なる事業が実施されています。
①市区町村が行う地域生活支援事業
市町村が主体となって行う地域生活支援事業には、以下のようなものがあります。それぞれ、対象者や利用料などが異なります。
| 概要 | |
|---|---|
| 理解促進研修・啓発 | 地域住民に向けて、障害者に対する理解を深めるための研修や啓発事業を行う |
| 自発的活動支援 | 障害者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動(ボランティアやピアサポートなど)を支援する |
| 相談支援 | 障害のある人やその保護者などからの相談に応じ、必要な情報提供や権利擁護などの必要な援助を行う 基幹相談支援センター等の機能強化も実施 |
| 成年後見制度利用支援 | 知的障害者や精神障害者が成年後見制度を利用する際に、補助を受けなければ成年後見制度の利用が難しいと認められた場合に、費用の全部もしくは一部を助成する |
| 成年後見制度法人後見支援 | 市民後見人を活用した法人後見を支援するために行われる研修や支援を実施する |
| 意思疎通支援 | 聴覚・言語機能・音声機能・視覚等の障害があり、意思疎通を図ることに支障がある人のために、手話通訳者や要約筆記者等を派遣して、コミュニケーションの円滑化を図る |
| 日常生活用具の給付・貸与 | 障害のある人が日常生活や社会生活をより円滑に営めるよう、必要となる自立生活支援用具等、日常生活用具の給付や貸与を行う |
| 手話奉仕員養成研修 | 聴覚障害のある人との交流活動の促進や市町村の広報活動などの支援を目的として、日常会話程度の手話を習得した手話奉仕員を養成する |
| 移動支援 | 屋外での移動が困難な障害のある人に対し、ガイドヘルパーが付き添って外出支援を行う |
| 地域活動支援センター | 障害のある人が通い、創作的活動や生産活動の提供、社会との交流の促進、相談受付などの支援を行う |
参考:「障害福祉サービスの利用について|全国社会福祉協議会」
市町村の地域生活支援事業には、上記のほかに任意事業があります。任意事業では、福祉ホームの運営や訪問入浴サービス、日中一次支援などが実施されています。
②都道府県が行う地域生活支援事業
都道府県が主体となって行う地域生活支援事業には、以下のようなものがあります。市区町村主体の地域生活支援事業と同様に、サービスによって対象者や利用料などが異なります。
| サービス | 概要 |
|---|---|
| 専門性の高い相談支援 | 障害のある人が自立した生活を営めるよう、特に発達障害、高次脳機能障害などの専門性の高い相談について、必要な情報提供等を行う |
| 広域的な支援 | 市町村粋を超える広域的な支援に対し、相談支援に関するアドバイザーを配置して相談支援体制の整備を推進する事業や、精神障害者を対象とした専門性が高い相談支援や緊急対応を目的とする事業 |
| 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成・派遣 | 手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、失語症向け意思疎通支援者を養成することや派遣などを行う事業を実施 |
| 意思疎通支援を行う者の派遣にかかる連絡調整 | 手話通訳者、要約筆記者を派遣する際の市町村相互間の連絡調整を行う |
参考:「障害福祉サービスの利用について|全国社会福祉協議会」
上記以外にも、オストメイト社会適応訓練や音声機能障害者発声訓練、発達障害者支援体制整備などの事業や、サービス・相談支援者、指導者などへの研修事業等が実施されています。
4.障害福祉サービスの利用の流れ
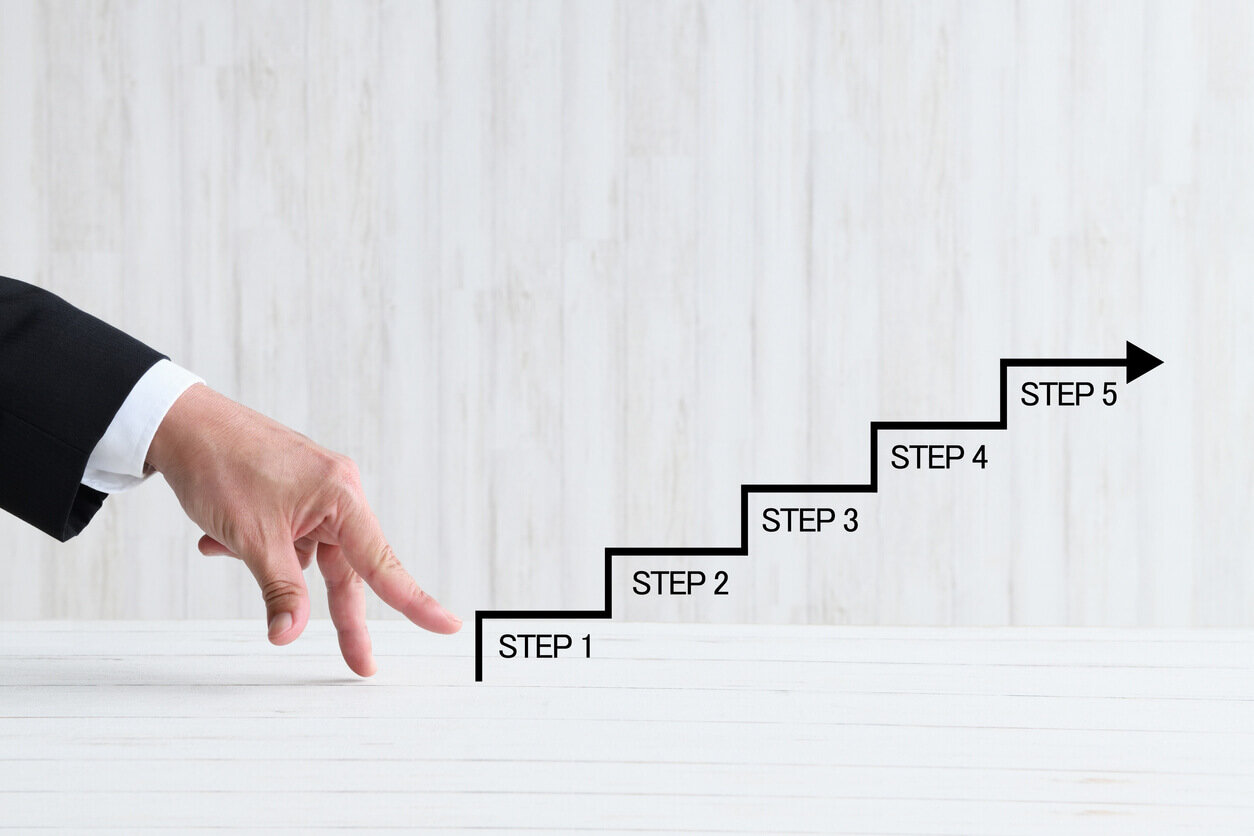
障害福祉サービスは、どのように利用すればよいのでしょうか。申請から利用開始までの流れを詳しく見ていきましょう。
申請
障害福祉サービスの利用を希望する際には、まずお住いの市町村の窓口に申請しましょう。障害福祉サービスを利用する時には、指定特定相談支援事業者に連絡してサービス等利用計画案を作成してもらう必要があります。指定特定相談支援事業者は、申請時にもらう事業者一覧から自分で選んだ事業所を選んで連絡します。
障害支援区分の認定
障害福祉サービスのうち、自立支援給付の介護給付を受ける場合には障害支援区分の認定を受ける必要があります。訓練等給付の場合は、基本的に障害支援区分の認定は不要です。ただし、同行援護を希望する場合は、同行援護アセスメント調査票の基準を満たさなければなりません。また、共同生活援助を希望する場合は、障害支援区分の認定が必要なケースがあります。
障害福祉サービスの支給の決定
障害支援区分の認定調査が終わると、市町村に提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえ、支給の可否が決まります。支給決定となると、指定特定相談支援事業者の相談支援専門員が作成した計画書を基に、利用したい事業所が集まってサービス担当者会議が開催されます。
サービス利用の開始
サービス担当者会議が開催された後は、サービス事業所等との連絡調整が行われます。事業所ごとに作成されるサービス等利用計画を基に、各事業所と契約書を交わすと、希望するサービスの利用が開始となります。
5.障害福祉サービスの利用料

障害福祉サービスを利用する場合の利用料金は、どのようになっているでしょうか。利用者が自己負担する障害福祉サービスの利用料は、所得に応じて負担上限額が4つに分けられています。具体的な区分設定は以下の通りです。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く |
9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
上記の区分については、ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の負担は生じません。所得を判断する際の世帯範囲は障害児と障害者で異なり、18歳以上の障害者の場合、障害者とその配偶者が対象となります。
障害児の場合は、保護者の属する住民票基本台帳での世帯が世帯範囲となります。同一世帯であれば利用者の人数に関係なく、自己負担額は上限までとなります。
障害福祉サービス利用時の減免措置
障害福祉サービスを利用する際には、かかる費用負担を減らす減免措置が利用できる場合があります。障害福祉サービスで利用できる減免措置について、詳しく見ていきましょう。
①療養介護を利用する場合の減免措置
療養介護を利用する場合には、医療費と食費の減免が受けられます。この減免措置では、自己負担相当額と医療費、食事療養費を合算して上限が設定されます。20歳以上の施設入所者の場合、低所得の人は少なくとも25,000円は手元に残るような形で、利用者負担額が減免されるようになっています。
②世帯での合算額が基準額を上回る場合の減免措置
障害福祉サービスの負担額が基準額を超えた場合には、高額障害福祉サービス等給付費の対象となります。世帯での合算額となるため、障害者の場合、配偶者の利用するサービス料を含めた金額を合算します。
障害児の場合は、障害総合支援法に基づくサービス、児童福祉法に基づく障害児通所支援、障害児入所支援のうち2つ以上を利用している場合、それぞれのいずれか高い額を超えた部分について、高額障害福祉サービス費等が支給されます。
③食費等実費負担の減免措置
食費等の実費負担についても、減免措置があります。
20歳以上の入所者の場合は、食費と光熱水費の実費負担において、54,000円を限度として施設ごとに金額が設定されます。低所得者に対する給付の場合は、費用の基準額を54,000円と設定したうえで、食費や光熱水費の実費負担をしたとしても、手元に少なくとも25,000円が残るように補足給付されます。
就労等で得た収入がある場合は24,000円までは、収入として認定しません。24,000円を超えた額については、超えた額の30%は収入として認定しないことになっています。例えば、25,000円の収入があった場合、24,300円は収入として認定しません。
通所利用の場合には、低所得および一般1に該当する場合、利用料負担は食材料費のみです。減免前と比べると、実際にかかる額のおよそ3分の1の自己負担で済みます。なお、食材料費は、施設ごとに異なった設定となっています。
④グループホーム利用者の減免措置
グループホームの利用者については、家賃の助成があります。具体的には、家賃が1万円未満の場合は実費額が、家賃が1万円以上の場合は1万円の補足給付が行われます。
⑤そのほかの減免措置
そのほかの減免措置としては、生活保護への移行防止策があります。この減免措置は、負担軽減額を講じても自己負担額や食費等実費を負担することによって生活保護の対象となる場合に、生活保護の対象とならない額まで自己負担の上限額等の引き下げを行うものです。
6.障害福祉サービスで働くために必要な資格・スキル

障害福祉サービスは、利用者さんのニーズに合わせて多種多様なサービスがあり、それぞれのサービスごとに必要とされる職種は異なります。障害福祉サービスで役立つ主な資格やスキルを見ていきましょう。
介護福祉士・初任者研修・実務者研修
障害福祉サービスでは、入所施設や居宅介護、重度訪問介護など、身体介護を行うサービスが多くあるため、介護系資格が役立ちます。未経験から障害福祉サービスの仕事に就きたいのであれば、介護の資格は取得しやすいのでおすすめです。
初任者研修や実務者研修は受講要件がないため、これから障害福祉サービスに携わりたい人にとっても、取得しやすい資格といえるでしょう。なかでも実務者研修は、介護福祉士の受験要件となっているため、将来的に介護福祉士を目指すのであれば、実務者研修を受講するのがおすすめです。ただし、介護福祉士の資格を取得するには、実務者研修のほかに、実務経験が3年以上必要です。
看護師
障害福祉サービスの利用者さんは、持病を持っている人や体調管理が難しい人も多く、看護師の資格が役立ちます。具体的には、利用者さんの体調管理や医療的ケアが必要な人の介助、緊急時対応などの支援を行います。看護師になるには、大学の看護学科や看護専門学校を卒業し、国家試験に合格する必要があります。
保育士
障害福祉サービスには、障害児を対象としたサービスも多くあるので、保育士の資格が役立ちます。特に、児童発達支援や放課後等デイサービスでは、以下のような配置基準があり、保育士の存在が重宝されています。
-
児童発達支援
利用定員10名までは2名以上、11~15名までは3人以上、16~20名は4名以上の児童指導員または保育士が必要 -
放課後等デイサービス
2名以上の児童指導員もしくは保育士が必要
保育士の資格を取得するには、専門学校や大学等を卒業するか、学校を出ていない場合は実務経験2年以上を経てから保育士試験を受験して合格する必要があります。
精神保健福祉士・社会福祉士・社会福祉主事
精神保健福祉士や社会福祉士、社会福祉主事は、障害を持つ人の相談や手続等の支援などを行う職種です。障害福祉サービスでは、生活支援員や相談支援専門員、就労支援事業所や自立訓練事業所など、多方面で活躍することができるでしょう。
精神保健福祉士と社会福祉士の資格は、福祉系大学等で所定の科目を履修するなど、一定の要件を満たしたのち、国家試験に合格することで取得できます。社会福祉主事は、大学等で社会福祉に関する科目を修了するなどの方法で取得可能です。
公認心理士師・臨床心理士
障害者の通所施設や入所施設、相談機関などでは、公認心理師や臨床心理士の募集がかかっていることがあります。公認心理師や臨床心理士は、カウンセリングや心理査定、心理支援の実施、関係機関との連携、障害者の家族の相談、援助などを行います。
公認心理師は国家資格であるため、大学や大学院に通って所定の科目を修了した後で実務経験を積み、国家資格に合格しなければなりません。臨床心理士は大学や大学院で学んだ後、試験に合格すると資格が取得できます。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
障害を持つ人にとって、リハビリは今の状態を維持・向上するために欠かせません。そのため、障害福祉サービスではリハビリ職が活躍できる職場もたくさんあります。
理学療法士は身体機能の回復や維持向上のためのリハビリを、作業療法士は日常生活における作業や動作を用いてのリハビリを、言語聴覚士は言葉や口腔機能のリハビリを主に行う職種です。理学療法士や作業療法士、言語聴覚士になるには、専門学校や大学で学び、国家試験に合格する必要があります。
まとめ:これから障害福祉サービスに就くなら介護の資格を取得しよう

障害福祉サービスには、いろいろなサービスがありさまざまな職種が活躍しています。未経験から障害福祉サービスに挑戦したい、訪問系や施設で働いてみたいという人には、介護の資格は取得しやすく就職にも有利になるでしょう。障害福祉サービスに興味があるのなら、ぜひ介護の資格に挑戦してはいかがでしょうか。
スピード転職も情報収集だけでもOK
マイナビ介護職は、あなたの転職をしっかりサポート!介護職専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを行います。
はじめての転職で何から進めるべきかわからない、求人だけ見てみたい、そもそも転職活動をするか迷っている場合でも、キャリアアドバイザーがアドバイスいたします。

SNSシェア















