介護度とは? 要介護区分の内容と介護保険の申請方法
文/笑和(社会福祉士、介護福祉士)
介護度とは、介護を必要とする状態を指標化したもので、高齢者等が日常生活のなかでどの程度の介護を要するのか、その程度を表したものです。要介護認定によって、介護を必要とする程度が軽度であれば要支援と判定され、逆に重度の状態で多くの介護が必要であれば要介護と判定されます。 この記事では、要支援・要介護における区分ごとの状態を説明するとともに、関連する要介護認定の申請方法について解説します。
1.介護度とは

介護度とは、高齢者等が介護を必要とする度合いを指標化したものです。要介護認定を受けることによって、ご本人の身体や精神の状態に応じ「要支援1・2」または「要介護1~5」の7区分のいずれかに判定されます。
これは介護保険制度によって定められた全国一律の基準で、どの市町村・都道府県に住んでいても、この指標に基づいて介護度が判定されます。ただし、実際の要介護状態の程度だけでなく、障害や認知症の有無、持病や既往歴を基に判定されるものなので、同じ病気や障害を持っていたとしても、同じ介護度になるとは限りません。
介護保険とは
介護保険とは、2000年にスタートした介護保険法に基づく公的な制度で、介護が必要な被高齢者が介護サービスを利用する際、一部の費用負担のみで受けることができる仕組みです。介護度を確認するには、利用者が在住地の市町村窓口に要介護認定の申請をすることから始まります。要介護認定の結果、判定された介護度によって利用できる介護サービスの量・内容が異なるため、実際にどの介護度に判定されるのかが重要な鍵となります。
2.要介護認定の申請方法
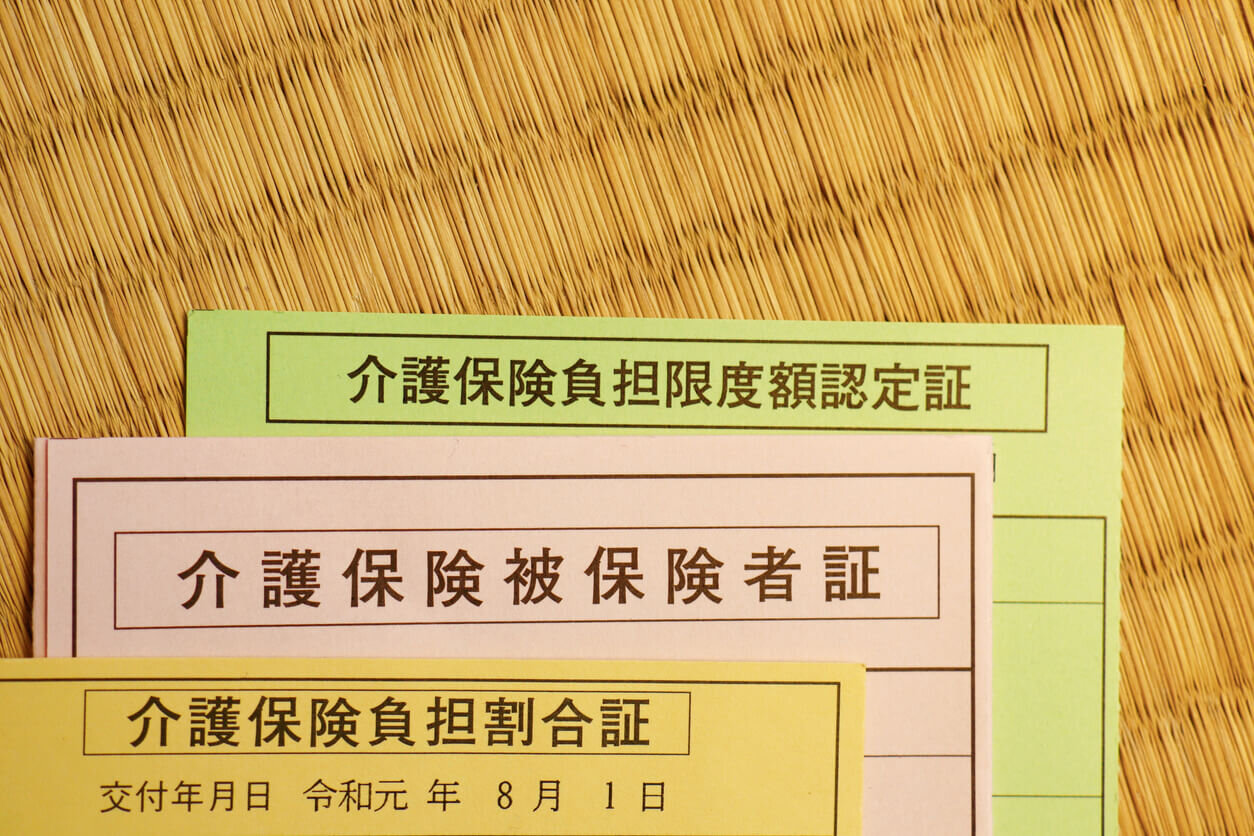
被保険者は住所のある市町村の窓口に、要介護認定の申請を行います。申請に必要なものは、市町村によって異なりますが、基本的には次の書類が必要です。
・要介護認定・要支援認定の申請書
・介護保険被保険者証
・その他(申請者の身元確認書類、被保険者のマイナンバーが確認できる書類等)
申請は原則として、介護サービスを利用しようとする被保険者本人が行いますが、特別な事情があれば、家族や介護支援専門員(ケアマネジャー)が代理で申請することもできます。
3.要介護区分(介護度)の判定

市町村による要介護認定の結果、利用者は要支援1・2または要介護1~5のいずれかの区分に判定されます。以下、要支援・要介護区分ごとの状態を説明します。
要支援1・2
要支援1~2は、後述の要介護と較べると軽度であるものの、見守りや一部介助が必要な状態です。介護保険制度では、介護予防給付というサービスを利用できます。
| 区分 | 状態 |
|---|---|
| 要支援1 | 基本的な日常生活動作(食事・排泄・入浴)は一人で行うことが可能ですが、起き上がりや立ち上がりの能力が低下している状態です。また、手段的日常生活動作(買い物や金銭管理等)の一部で、見守りが必要な状態です。 |
| 要支援2 | 要支援1に加え、歩行・立ち上がりで見守りが必要な状態であり、今後の健康状態によっては、介護が必要になる恐れがあります。 |
要介護1~5
要介護は1~5まであり、5が最も重度で常時介護が必要な状態です。介護保険制度では、介護給付というサービスを利用できます。
| 区分 | 状態 |
|---|---|
| 要介護1 | 要支援2よりも起き上がり、立ち上がりの能力が低下している状態で、片足での立位、日常での意思決定、買い物等が難しく、部分的な介助が必要となる状態です。 |
| 要介護2 | 日常生活動作において部分的な介護(歩行、洗身等)が必要となり、かつ、手段的日常生活動作では、金銭の管理や簡単な調理が難しく、一部介助が必要になる状態です。利用者によっては認知症の症状が見られ、日常生活にトラブルが起こる恐れがあります。 |
| 要介護3 | 要介護2よりも認知機能・身体機能が低下し、寝返り、トイレ、歯磨き、衣類の着脱が一人では難しく、全面的な介助が必要な状態です。また、自立歩行が困難で、利用者によっては杖や歩行器、車いすを利用します。 |
| 要介護4 | 要介護3以上に、生活上のあらゆる場面(移乗、移動、洗顔、整髪)での介助が必要です。座位保持、両足での立位が困難で、移動には車いすが必要となります。常時の介助がなくては日常生活を送ることが難しい状態です。また、認知機能の低下が著しく、やっと会話が行える状態です。 |
| 要介護5 | 生活のあらゆる場面で常時介護が必要な状態です。重度の認知症や麻痺があり、日常生活動作の全てにおいて常時の介助がなくては生活することが困難な状態です。外出の頻度は著しく減り、ほぼ寝たきりの状態で、意思の伝達が困難です。 |
4.介護度によって異なる利用可能なサービスの種類とケアプラン作成

要介護度によって利用できるサービスの種類は次のとおりです。詳しい内容は後述します。
| 区分 | 利用できるサービス | ケアプランの作成 |
|---|---|---|
| 要支援1・2 |
介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス 例:介護予防訪問入浴介護・通所リハビリテーション等 |
地域包括支援 センター |
| 要介護1~5 |
介護サービス(居宅・施設・地域密着型サービス) 例:訪問介護、通所介護、施設への入所等 |
居宅介護支援 事業所 |
要支援1・2が利用できるサービス
要支援は、介護が必要な状態にならないための介護予防サービスを利用します。以下、一例を示します。
-
介護予防訪問入浴介護
自宅の浴槽では入浴するのが難しい高齢者等のお宅を訪問し、事業者があらかじめ準備しておいた特殊浴槽を使って入浴の介護を行います。 -
介護予防通所リハビリテーション
利用者が通所リハビリテーションの施設などに通い(送迎あり)、介護が必要な状態にならないためのリハビリテーションを受けることができます。日帰りで利用でき、筋力トレーニングや、栄養改善の指導、口腔ケア等のサービスを受けます。
なお、実際にサービスを利用する場合は、地域包括支援センターの介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランの作成を依頼します。
要介護1~5が利用できるサービス
要介護の場合は、身体介護を含めた日常生活上の世話などの介護サービスを利用します。代表的なものは次のとおりです。
-
訪問介護
自宅で生活する高齢者等に対して、介護福祉士やホームヘルパーが自宅に赴き、身体介護や生活援助等を行います。 -
通所介護
自宅で生活する利用者が、食事、入浴、レクリエーション等のサービスを日帰りで受けることができます。自宅からデイサービスまでの送迎は事業所側が行うことが一般的です。 -
施設サービス
介護老人福祉施設などに入所して、身体介護・日常生活における身の回りのお世話を受けることができます。施設によっては「介護度3以上の人」といった入所要件を定めているところがあります。
なお、ケアプランの作成は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼します。
介護支援専門員(ケアマネジャー)とは
介護支援専門員は、介護サービスに関する専門知識を持つ専門職です。利用者が自宅や施設で生活を送るうえで相談に応じ、解決に向けてのアドバイス、関係機関との連絡・調整等をしてくれます。
介護支援専門員は、利用者が困っていること・受けたいサービス等の希望を聞いて、ニーズに則したケアプランを作成する役割を担います。また、介護職員等と相互に連絡を取りながら、プランに沿った介護サービスが提供されているかチェックすることも重要な業務の一つです。そのため、介護職側は利用者の介護度や介護サービスの内容に関して疑問・質問がある場合には、介護支援専門員に問い合わせてみましょう。介護支援専門員は、該当する介護度に至った経緯や、提供する介護の根拠を教えてくれます。
5.利用者の介護度を知るために

介護度は、利用者の心身の状況、抱える疾病や障害、既往歴等を基に判定されます。今回紹介した要支援1・2、要介護1~5の状態は、あくまでも標準的な状態を表しているものであり、利用者の状態によって個人差がある点には注意が必要です。また、利用者の心身状況が悪化すれば、再度要介護認定を受けて介護度を更新することができます。利用者の介護度を知ることは、利用者理解につながり、提供する介護の質的向上にもつながるものです。介護職は、利用者の介護度の把握を怠ることなく、ケアプランに基づいた介護を提供できるよう意識を高めましょう。
●関連記事:要介護認定とは?認定基準や要介護認定を受けるまでの流れ
【日本全国電話・メール・WEB相談OK】介護職の無料転職サポートに申し込む
スピード転職も情報収集だけでもOK
マイナビ介護職は、あなたの転職をしっかりサポート!介護職専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを行います。
はじめての転職で何から進めるべきかわからない、求人だけ見てみたい、そもそも転職活動をするか迷っている場合でも、キャリアアドバイザーがアドバイスいたします。

SNSシェア















