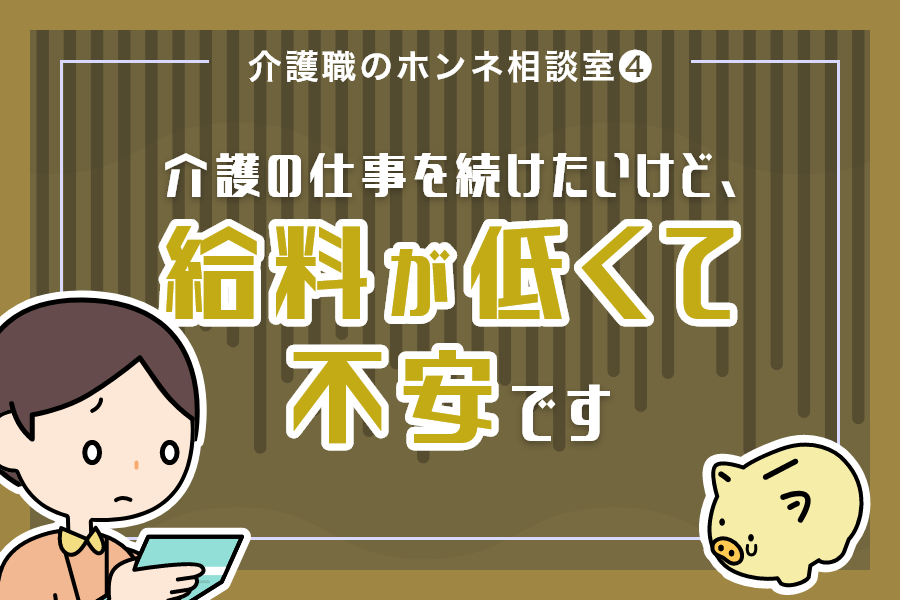社会人から社会福祉士になるには?未経験から資格取得・転職するまで
文/金杉宏敬
福祉業界には、一般企業に働いていた人がこの世界に飛び込んでくる例を数多く見ます。
本記事では、かつて一般企業に勤めていた筆者が、社会福祉士として福祉業界に転職したきっかけや、未経験から資格を取得するまでに行ったことをお伝えします。
一般企業などから福祉業界に転職しようとする方々に、筆者の経験が少しでも参考になれば幸いです。
1.福祉業界に興味を持ったきっかけ
筆者は大学卒業後、一般企業に就職し営業職として仕事をしていましたが、4、5年が経過した頃、漠然とした将来への不安を抱きました。
ちょうど介護保険制度がスタートした時期で、福祉業界に注目が集まった頃でした。
福祉に関する知識はまったくありませんでしたが、介護保険制度について調べるうちに、介護保険制度と同時にスタートした成年後見制度を知り、本気でこの業界に転職してみようと思いました。
以前より法律関係に興味があり、福祉と法律の知識を軸に権利擁護に関わる仕事に就きたかったため、社会福祉士を目指すことになりました。
2.未経験から社会福祉士として転職するまで
福祉業界を知るための情報収集
当時は今のようにSNSなどの情報発信が盛んでなかったため、主に書籍で福祉業界に関する情報収集をしました。
「福祉業界」全体の動向や将来性に関してはSNSではまとまった情報が少ないため、1冊の書籍で内容を確認することが望ましいと個人的には思います。
また、すでに業界で働いている知人がいるのであれば、聞かない手はありません。最もリアルな情報であり、SNSや書籍からは読み取ることができない肌感覚の情報を知ることができます。
●関連記事:【経験談つき】社会福祉士の就職先と選び方|資格を活かせる仕事一覧も
福祉業界の入り口となる資格取得
社会福祉士の資格取得までは最低でも数年間の時間を要するため、最初にホームヘルパー2級(現・介護職員初任者研修)の資格を取得し、企業を辞めて特別養護老人ホームに入職しました。
社会福祉士の資格取得までに福祉業界を知り、さらに資格取得後に業務を行うときに、その経験が役立つのではないかと考えたからです。
ですので、まず業界の入り口となる資格を取得して、福祉業界に入るのも1つです。
以下に、比較的取得しやすい資格を紹介します。
●関連記事:介護職員初任者研修(旧・ホームヘルパー2級)
未経験の方や無資格の方の入門資格です。介護知識やスキルの基本を学ぶことができます。最短1か月程度での取得が可能です。
●関連記事:認知症介護基礎研修
認知症介護の入門で基礎知識や技術を習得します。資格要件は「認知症ケアに携わる介護従事者」の一点のみで、約6時間の講義のため1日で終了します。
●関連記事:福祉住環境コーディネーター
高齢者や障害者が安全かつ円滑に生活できるよう、福祉・医療・建築など幅広い知識を学びます。検定試験の受験の合格で資格取得可能です。
●関連記事:移動介護従事者(ガイドヘルパー)
障害別に資格取得が必要で、主催は各自治体が行っている場合が多いです。「全身性障害」「視覚障害」「知的・精神障害」の3つの障害別に受講が必要です。3~5日程度の研修で取得可能です。
ボランティアへの参加
私はホームヘルパー資格を取得した後、ホームヘルパーの学校の先生の紹介で知的障害者の通所施設にボランティアに行きました。1回きりの参加でしたが、障害がある方の特性や日中にどのような活動を行っているのかを知ることができ、貴重な経験になりました。
ボランティアは登録制のほか、単発での参加が可能な場合もあります。以下の関係機関などから情報を得てみてください。
・介護施設、通所施設
・地域にある社会福祉協議会のボランティアセンター
・自治体の福祉課や地域包括支援センター
・NPO法人 など
同じ志を持つ仲間との情報交換や交流
筆者は、ホームヘルパー資格の学校で知り合った仲間とその後もお会いし、お互いの将来の目標や進みたい道について情報交換を行い、参考になる書籍やボランティア情報などいろいろと教えてもらいました。
未知の世界のことですから常に新鮮で多くを学ぶことができました。また、仲間との交流は将来への不安も和らげてくれます。同じ環境で出会いがあった場合は積極的に仲間をつくることをおすすめします。
3.働きながら社会福祉士通信課程に入学し卒業するまで
筆者はホームヘルパー2級の資格を取得後、特別養護老人ホームに入職し、働きながら社会福祉士の資格を取得しようと、通信課程で学ぶことを決めました。
通信課程専門学校の選定
現在、最短9か月で受験資格取得が可能な「短期養成施設」は全国に約15校あり、1年10か月程度の「一般養成施設」が全国で70校以上あります。(2022年11月時点)
なお短期養成施設は、主に福祉系大学・短大に進学し、厚生労働省が指定する基礎科目を履修した方などが入学対象となり、そうでない方は一般養成施設となります。
多くの養成施設が4月もしくは5月入学で、入学願書受付は10月頃から最終で3月末までの学校もあります。定員があるため、入学を決意した方は早めの資料請求と願書提出が望ましいです。
通信課程とはいえ、年間に数日間学校に通いスクーリングを受ける必要があります。遠距離だと想像以上に負担が大きいため、自宅からアクセスしやすい学校を選んだほうがよいでしょう。勤務している場合、スクーリングで貴重な公休や有給休暇を活用するため、学校での授業以外の負担を可能な限り少なくすることが大事です。
筆者はインターネットで社会福祉士通信課程を検索し、自宅から無理なく通える片道1時間以内の学校を優先的に調べました。
そのなかで決め手となったのは学費と学校の規模。学費(授業料+実習費+教材費)はできるだけ安いところにし、規模は過去の合格者や合格率の実績、生徒の募集人数などを参考にしました。
なお、福祉系の大学で単位取得をしていなかったため、一般養成施設の入学でした。
レポート提出と単位取得
通信課程のカリキュラムの多くは自宅学習です。毎月1~2科目のテキストを使用してレポートを作成します。レポートは一定の基準を満たすと単位を取得できます。ほぼ毎月新たな科目のレポートを提出するため、毎月の学習計画を立てることが必須になります。
筆者は仕事が終わったあとに、平日は2時間程度を勉強に充てていました。ほぼ毎月レポート作成と提出があるため、いつまでにテキストを読み込み、レポートを完成させるかを逆算して月間計画を立てることが重要だと思い、毎月初めに計画立てを行いました。
しかし、本業や家事などがあるなかで時間の確保が難しく、集中して勉強をすることがとても大変でした。夜に勉強しようとテキストを開いたものの睡魔に負けてしまうこともよくありました。そのため朝早く起きて頭がすっきりしている時間帯や通勤電車の中などを活用しました。
スクーリングの参加と現場実習
教室で教員と対面で授業を受けるスクーリングは、通算10日前後を4回程度に分けて実施されます(実習免除の場合は日数が少なくなります)。自宅学習時の不明点などをこの機会に解決することで次のステップに進むことができます。
私はホームヘルパーの学校の先生から、「同じ境遇の仲間をつくってください。仲間がいることでつらいときも相談し合えたり頑張ることができます」とアドバイスをいただきました。
そこで積極的に話しかけたのですが、同じ目標と志す仲間との交流はとても楽しいものでした。当時知り合った仲間とは今も交流があり、スクーリングでは、ぜひ仲間づくりにも取り組んでほしいと思います。
所定の実務経験を満たさない方は、「相談援助実習」が指定の施設で行われます。実務経験がない、もしくは1年未満の方は、一般養成課程は30日間かつ240時間以上の実習が法令で定められています。
特養勤務中に通信課程に通学していた筆者は、実務経験とはならず相談援助実習を受けました。
実習施設は通える範囲の施設を学校側が考慮して決定してくれます。私の実習施設は自宅から1時間程度で通える社会福祉法人でした。
特養の各フロアでの実習や、特養に併設した居宅介護支援事業所、デイサービス、訪問看護で実習を行いました。その日の配属先の担当者の指導を仰ぎながら1日を過ごし、毎日終了前に実習レポートを作成して、総責任者の方に提出します。毎日8時30分から17時の実習は初めての体験ばかりで、新鮮かつとても有意義な時間でした。実習終了後は大変な達成感があり、今でも貴重な体験として記憶に残っています。
ただ、社会福祉士を目指そうと思った方でもこの実習の存在が二の足を踏む一因となる方も少なくないはずです。勤めされている方は、実習参加のための時間確保のために職場の理解を得るよう努めてください。
4.社会人経験は社会福祉士の取得後も活かせる
筆者の学校は1年10か月で卒業するカリキュラムでした。レポート提出、スクーリング、実習を無事終了し卒業できたため、卒業後間もなく行われた1月の国家試験を受験し合格することができました。
合格のコツとして感じたのは次のことです。
・国家試験受験、通信課程卒業までの期間を逆算し学習計画を立てること
・自分自身の得手不得手を把握し、全問正解を目指すのではなく7割程度の正解率でよいと割り切り勉強すること(実際の合格率が例年6割程度のため、あえて7割と設定しました)
・漠然とした目標ではなく、合格後の次のステップをイメージすることで、モチベーションを維持すること
・国家試験までやり切ったと思えるように努力をして、自信を持って試験に臨むこと
豊富な人生経験は支援の際の考えや発想の幅を広げることになります。そのため、社会人から社会福祉士になることはとてもメリットが多いといえます。
社会福祉士のデビューは、何歳からでも可能だと感じています。
●関連記事:社会福祉士の合格率が低い5つの理由と試験勉強のコツ
スピード転職も情報収集だけでもOK
マイナビ介護職は、あなたの転職をしっかりサポート!介護職専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを行います。
はじめての転職で何から進めるべきかわからない、求人だけ見てみたい、そもそも転職活動をするか迷っている場合でも、キャリアアドバイザーがアドバイスいたします。

SNSシェア