【7月】高齢者施設におすすめのレクリエーション・行事8選
構成・文/介護のみらいラボ編集部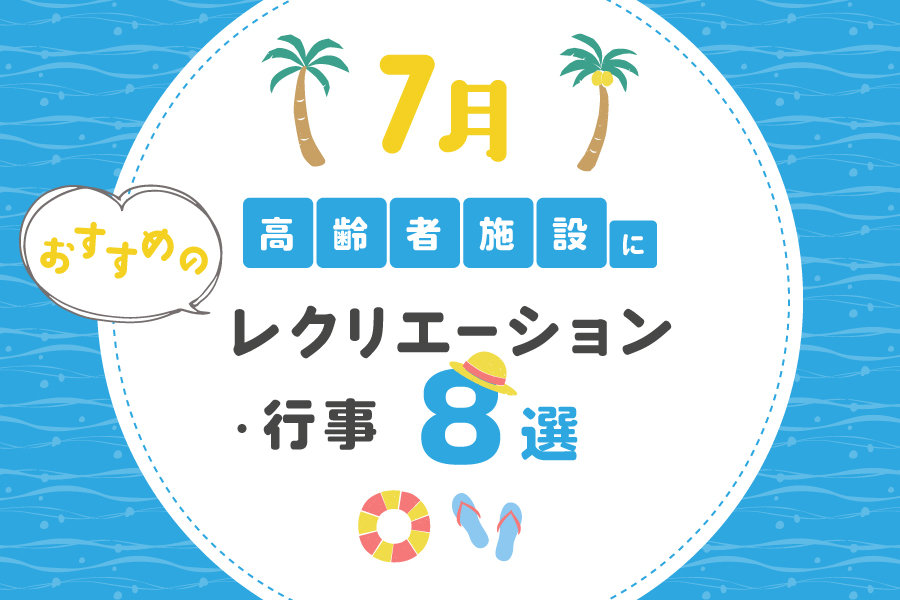
暑い日が続き、夏らしさが増してくる7月。じめじめした梅雨から解放されて気分が上向く一方で、利用者さんの暑さ対策や体調管理が気になる介護職員の方もいるのではないでしょうか。レクリエーションを実施する際は、熱中症をはじめとする病気や不調に十分配慮してください。
暑い時期は、どうしても室内で過ごす時間が多くなりますが、日々の生活に変化をつけつつ、マンネリ化しないレクリエーションを実施するためには、季節のイベントや行事を上手に取り入れるのがおすすめです。当記事では、7月にぴったりの高齢者向けおすすめレクリエーションを詳しく解説していきます。
1.7月にレクリエーションを実施する際のポイント
7月は、二十四節気の小夏・大暑にあたり、本格的な夏が始まる時期です。体がまだ暑さに慣れておらず熱中症の危険性が高まるため、屋外の活動はもちろん室内の活動でも熱中症対策が必要です。レクリエーションを考える時は、熱中症対策も併せて考えるようにしましょう。特に高齢者の方は暑さを感じにくかったり、体温調整がうまくいかなかったりすることもあるので注意が必要です。
熱中症の予防には、水分補給と温度調節が欠かせません。経口補水液をすすめるなどして、こまめに水分、塩分、ミネラルを補給してもらいましょう。
(出典:全国健康保険協会「7月 油断大敵! 熱中症にご用心」)
なお、マスクを着用していると熱中症のリスクが上がると言われています。屋外で周囲との距離が十分に取れる場所では、マスクを外してもらい、熱中症のリスクを低減しながらレクリエーションを行いましょう。
(出典:厚生労働省「「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント」)
2.【7月】高齢者に喜ばれる行事・レクリエーション8選
7月は、七夕や海の日といったさまざまな行事があり、幅広いレクリエーションを実施できます。ただし、体調を崩しやすい時期でもあるため、利用者さまの様子や室温に気を配り、楽しくレクリエーションを行いましょう。
ここからは、7月の行事や風物詩にちなんだレクリエーションを紹介します。
七夕
七夕といえば、真っ先に「天の川」や「七夕飾り」が思い浮かびます。そのため、七夕のレクリエーションでは、短冊に願い事を書く風習をイメージする利用者さまも少なくないでしょう。
もちろん、笹や短冊、七夕飾りを用意して七夕の飾り付けを楽しむだけでもいいのですが、レクリエーションを成功させるためには、利用者さまがポジティブな気持ちで取り組めるように配慮することが大事です。
例えば、折り紙で七夕飾りを作成する場合は、「手指のトレーニングに役立つ」ことを伝え、工作レクリエーションの意義を理解してもらうと良いでしょう。目的に向かって作業をすることで、完成した時の達成感も増すはずです。また、完成した後に利用者さまへ感謝の言葉を伝えると、より前向きに取り組んでもらえるでしょう。
なお、七夕のレクリエーションには、下記のような七夕クイズもおすすめです。
【問題】彦星の仕事は牛の世話ですが、織姫の仕事は次のうちどれでしょうか。
(1)絹糸の選定
(2)機織り
(3)織物の商人
【正解】(2)「機織り」
織姫は天空の偉い神様である天帝の娘で、織物職人です。
【問題】七夕の起源はどこの国でしょうか。
(1)中国
(2)日本
(3)ベトナム
【正解】(1)「中国」
中国の伝説と、裁縫の上達を願う行事が結びついて七夕の行事になりました。
●関連記事:
・七夕がテーマの室内レクリエーション「天の川の戦い」
・【間違い探し】7月:七夕
海の日
海の日のレクリエーションには、海の生き物や水遊び、浜辺の花火などを題材にした壁画作りがおすすめです。折り紙、切り絵だけでなくマスキングテープやモールを用いるとより鮮やかな壁画になります。
海の日の当日には、海にまつわる童謡や歌謡曲を流して、雰囲気を盛り上げましょう。音楽にはムードを高める効果もあるため、レクリエーションのへの導入がスムーズになるはずです。
下記に海の日に関するクイズの例題も紹介しておくので、壁画や音楽などで雰囲気を盛り上げながら、利用者さまに出題するのもいいでしょう。
【問題】アメリカの「海の日」はいつでしょう。
(1)5月22日
(2)6月18日
(3)7月16日
【正解】(1)「5月22日」
1819年5月22日、蒸気船が大西洋横断に成功したことに由来しています。
【問題】「海の日」は2003年から7月第3月曜日と定められましたが、それまでは何月何日だったでしょう。
(1)7月15日
(2)7月20日
(3)8月15日
【正解】(2)「7月20日」
ラジオ体操
ラジオ体操は、全身の筋肉をバランスよく刺激するため、高齢者の運動不足を解消したり、けがや事故を予防したりする効果が期待できます。ただし、その日の体調や気分によって参加したくない利用者さまもいるでしょう。不参加を希望する方には無理強いをせず、その場の雰囲気を味わってもらうだけでも構いません。
体操の際は、利用者さま同士がぶつからないように、両腕を真横に伸ばしても隣同士が接触しないスペースが必要です。ラジオ体操は、座位でも十分に体を動かすことができるため、車椅子の利用者さまにも、可能な範囲で参加してもらうと良いでしょう。車いすの利用者さまが多い施設の場合、介護スタッフも椅子に座って体操すると、動きの見本になります。
かき氷作り
かき氷は、夏祭りなどでも目にする夏の風物詩。手軽に作れるため、7月のレクリエーションにおすすめです。かき氷作りに使うかき氷機には、電動と手動がありますが、それぞれ特徴が異なります。
電動かき氷機は手早く、簡単にかき氷を作れるので、調理に自信のない利用者さまでも無理なく参加できます。一方の手動かき氷機は、自分で作る楽しさがある上に、手や腕の運動にもなるのがメリットです。施設の規模や利用者さまの能力に応じて、電動・手動を使い分けてください。
なお、こうした調理レクリエーションには「作る楽しみ」があるため、利用者さまの達成感や成功体験につながりやすいでしょう。
富士山の山開き
富士山の山開きは、山梨県側のルートが7月1日頃、静岡県側のルートが7月10日頃となっており、7月のレクリエーションの題材にぴったりです。日本人にとって、とてもなじみ深い富士山を工作レクリエーションやクイズに取り入れましょう。
工作レクリエーションは、色紙を用いた手のひらサイズの壁面作りや、紙コップを逆さにしてギザギザの紙を貼付した立体的な富士山の置物作りがおすすめです。作った後は、個性豊かな作品を展示して楽しんでください。
下記は富士山にちなんだクイズです。利用者さまに楽しみながら考えてもらいましょう。
【問題】富士山の高さは何メートルでしょうか。
(1)3,776メートル
(2)3,677メートル
(3)3,767メートル
【正解】(1)「3,776メートル」です。
【問題】富士山の頂上は何県でしょうか。
(1)静岡県
(2)山梨県
(3)どちらでもない
【正解】(3)「どちらでもない」
富士山の8合目から上は「富士山本宮浅間大社」によって御神体として管理されており、県が定められていません。
大暑
大暑は、二十四節季の7月23日頃から8月6日頃のことで、一年で最も暑くなる時期です。大暑はちょうど暑中見舞いを出す時期にあたるため、絵はがきを作成するのもいいでしょう。はがきサイズの厚紙にちぎり絵を貼ったり、色鉛筆で絵を描いたりと、利用者さまのできることや準備できる材料にあわせて作成してください。
作った絵葉書を展示すれば、施設内が夏らしい雰囲気になります。
土用の丑の日
土用の丑の日は、土用(立春、立夏、立秋、立冬の前の18日間)の期間である7月20日頃から8月6日頃までの「丑の日」に、精の付くうなぎを食べて暑気を乗り切る風習です。
土用の丑の日には、うなぎに関わるミニゲームやクイズを行いましょう。新聞紙をうなぎに見立てて細長く切り、ラップの芯などに引っかけて釣る「うなぎ釣りゲーム」は、土用の丑の日にぴったりのレクリエーション。たくさん釣ったチームの勝ち、色の付いたうなぎは高得点などルールを工夫すると、楽しく参加してもらえます。
土用の丑に関わる、下記のようなクイズを出題するのも良いでしょう。
【問題】土用の期間に禁止されている行為は何でしょう。
(1)うなぎ以外の魚介類を食べる
(2)土いじりをする
(3)遊泳などのために川に入る
【正解】(2)「土いじりをする」
土用の期間は、土を汚す行為を慎むべきとされています。
【問題】日本で最も食べられているうなぎの種類は次のうちどれでしょう。
(1)二ホンウナギ
(2)オオウナギ
(3)アメリカウナギ
【正解】(1)「二ホンウナギ」
なお、土用の丑の日は、うなぎを使った献立もおすすめです。最近では、小骨が気にならないように加工された介護食用のうなぎもあるので、安心してうなぎを楽しむことができます。
7月の歌・音楽
歌や音楽のレクリエーションは一年を通して楽しめますが、季節が感じられる曲を取り入れると、より豊かな気持ちになれるでしょう。7月におすすめの童謡は「たなばたさま」「海」「すいかの名産地」など。「星影のワルツ」「見上げてごらん夜の星を」「真っ赤な太陽」「およげたいやきくん」といった歌謡曲も夏のレクリエーションの定番曲です。
歌や音楽のレクリエーションでは、歌体操を一緒に行うのも良いでしょう。5分程度の曲に合わせて楽しく体を動かせば、夏の運動不足の解消につながります。
まとめ
7月には、七夕や海の日、土用の丑といった高齢者の方にも親しみやすい行事が多くあります。レクリエーション実施のポイントは、熱中症や脱水症状に注意しながら無理のない範囲で行うことと、利用者さまが参加しやすい雰囲気を作ることです。一人ひとりの能力に合わせてできることを工夫し、楽しいレクリエーションを計画しましょう。
「介護のみらいラボ」は、介護分野で活躍する方に向けて、役立つ情報を発信しています。季節ごとのレクリエーション情報も掲載しているため、レクリエーションのアイデアを探している方は、ぜひ参考にしてください。
●関連記事
・夏におすすめの高齢者向けレクリエーション7選!夏の行事一覧も
・高齢者向け夏の簡単工作3選! 風物詩で季節の移り変わりを楽しもう
・【8月】高齢者施設のレクリエーションのアイデア8つ
※当記事は2022年6月時点の情報をもとに作成しています
【日本全国電話・メール・WEB相談OK】介護職の無料転職サポートに申し込む
スピード転職も情報収集だけでもOK
マイナビ介護職は、あなたの転職をしっかりサポート!介護職専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを行います。
はじめての転職で何から進めるべきかわからない、求人だけ見てみたい、そもそも転職活動をするか迷っている場合でも、キャリアアドバイザーがアドバイスいたします。

SNSシェア














