地域包括支援センターとは?地域での役割と活躍できる職種
構成・文/介護のみらいラボ編集部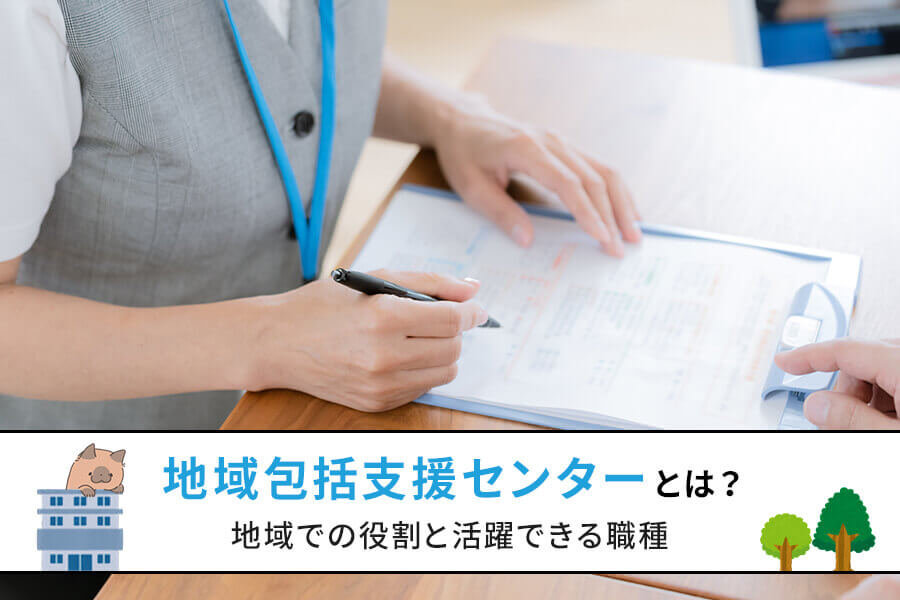
高齢者が年々増加する日本では、医療・介護の需要の高まりに対応する取り組みを推進しています。中でも、地域支援事業を担う「地域包括支援センター」の設置は全国の市町村で進められていることが特徴です。
地域包括支援センターは、高齢者の保健医療の向上や福祉の増進を包括的に支援することを目的とした施設であり、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャー(介護支援専門員)などの配置が義務付けられています。
保有している資格によって地域包括支援センターでの活躍方法もやや異なるため、事前に各職種の働き方を知っておくとよいでしょう。この記事では、地域包括支援センターの概要と各職種の仕事内容を徹底的に解説します。
1.地域包括支援センターとは?
地域包括支援センターとは、高齢者やその家族が、住み慣れた地域で安心した生活を送れるよう、保健医療の向上や福祉の増進を包括的に支援することを目的とした施設です。
いわゆる「地域の高齢者やその家族に何らかの困りごとがあったときに役立つ総合相談窓口」であり、地域包括ケアシステムの実現に向けた中心的な機関として、全国の市町村で設置されています。
2021年4月時点において地域包括支援センターは、全国5,270カ所に設置されています。支所(ブランチ)を含めると7,305カ所です。なお、設置数は年々増加傾向にあります。
(出典:厚生労働省「地域包括ケアシステム」)
地域包括支援センターの業務内容
地域包括支援センターは、「包括的支援事業」「介護予防支援事業」が必須事業とされています。さらに地域包括支援センターによっては任意事業も行っており、各事業で職員はあらゆる業務を担当します。下記は、地域包括支援センターの事業別業務内容です。
〇包括的支援事業
包括的支援事業とは、地域におけるケアマネジメントを総合的に行うことを目的とした事業です。具体的には、下記5つの事業で構成されています。
・介護予防ケアマネジメント事業
・総合相談・支援事業
・権利擁護事業(成年後見制度の活用促進・高齢者虐待防止対応など)
・包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
〇介護予防支援事業
介護予防支援事業とは、要支援者や将来的に介護が必要になる可能性が高い高齢者に対して、要介護状態となることを予防するための支援・サポートを行う事業です。具体的には、介護保険における予防給付の対象者(要支援者)が、指定介護予防サービスなどの利用を適切に行うことを目的とした、予防給付に関するケアマネジメントを行います。
〇任意事業
任意事業とは、地域の実情や特性に応じて市町村が実施主体となり実施する事業です。具体的には、下記のような事業があります。
・介護給付等費用適正化事業
・家族介護支援事業
・地域自立生活支援事業
・成年後見制度利用支援事業 など
背景にある「地域包括ケアシステム」とは?
前述の通り、地域包括支援センターは地域包括ケアシステムの実現に向けた中心的な役割を果たします。地域包括ケアシステムとは、地域の高齢者が、要介護状態・要支援状態になっても、住み慣れた街で最後まで自分らしい生活を送れるよう地域内で支え合うシステムのことです。
地域包括ケアシステムは、第一次ベビーブーム時代(1947〜1949年)に出生した「団塊の世代」の方たちが全員後期高齢者にあたる75歳以上となる2025年を目途に、すべての地域での構築が推進されています。また、単純な地域包括ケアシステム構築だけでなく、地域の主体性にもとづいて、特性に応じて構築することも目標となっています。
地域包括ケアシステムの構築を進めるためには、地域包括支援センターの存在が欠かせません。今後はより多くの市町村で地域包括支援センターが設置され、それに伴って地域包括支援センターで働く職員の需要も高まるでしょう。
(出典:厚生労働省「地域包括ケアシステム」)
2.地域包括支援センターで活躍する職種と仕事内容
地域包括支援センターの人員配置基準は、介護保険法施行規則によって定められています。また、「包括的支援事業に関わる人員配置基準」と「介護予防支援事業に関わる人員配置基準」とで異なる点も覚えておきましょう。下記は、それぞれの人員配置基準です。
|
「包括的支援事業」 に関わる人員配置基準 |
65歳以上の高齢者(第1号被保険者)3,000~6,000人ごとに、下記の職種を最低限各1人 ・保健師 ・社会福祉士 ・主任ケアマネジャー |
|---|---|
|
「介護予防支援事業」 に関わる人員配置基準 |
下記の職種から1名以上の必要な数 ・保健師 ・社会福祉士 ・ケアマネジャー ・看護師(実務経験あり) ・社会福祉主事(3年以上の実務経験あり) |
ここからは、メインとなる包括的支援事業に関わる職種がそれぞれどのような資格なのか、また地域包括支援センターにおいてどのような働き方をするのかを詳しく説明します。最後には介護予防支援事業に関わる職種についても紹介しているので、参考にしてください。
包括支援事業|社会福祉士
社会福祉士は、身体上・精神上に何らかの障がいがあり日常生活に支障をきたしている方を対象に、福祉相談や指導・助言、さらに医療福祉サービスを提供する関係者との連携のうえあらゆる支援を行う職種です。「ソーシャルワーカー」とも呼ばれます。
地域包括支援センターで働く社会福祉士は、相談者・利用者からの介護福祉サービスに関する相談に対応し、適切なサポートを提供することが主な仕事です。保健師や主任ケアマネジャーと連携しながら、高齢者が置かれている状況に応じて適切な医療機関・介護施設・行政サービスを紹介することもあります。
2019年3月に三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社から公表された「地域包括支援センターの業務実態に関する調査研究事業報告書」によると、地域包括支援センターに配置される社会福祉士の数は2.4人でした。ほかの資格の職員よりも最も平均値が高く、多くの地域包括支援センターで求められる人材といえるでしょう。
(出典:三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「地域包括支援センターの業務実態に関する調査研究事業報告書」)
包括支援事業|保健師
保健師は、病気予防や健康維持を目的に、地域住民の健康管理・保健指導を行う職種です。保健師資格を取得するためには看護師資格が必要であることから、包括支援事業の中でも医療知識を要するケースで活躍できます。
地域包括支援センターで働く保健師の主な仕事内容は、医療に関する相談対応や自立支援のサポートから、ケアプラン作成を含む介護予防マネジメントまで多岐にわたることが特徴です。時には、地域住民を対象とした健康づくり教室を企画・開催したり、独居高齢者の家庭を訪問してコミュニケーションをとったりすることもあります。
「地域包括支援センターの業務実態に関する調査研究事業報告書」によると、地域包括支援センターに配置される社会福祉士の数は1.4人でした。医療サービスを必要とする高齢者が多い地域では、保健師の需要がより高まる傾向にあります。
(出典:三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「地域包括支援センターの業務実態に関する調査研究事業報告書」)
包括支援事業|主任ケアマネジャー
主任ケアマネジャーとは、介護支援専門員資格の上位資格である「主任介護支援専門員」の資格を取得したケアマネジャーのことで、医療・介護・福祉サービスの提供に向けたネットワークの構築やケアマネジャーの育成・サポートを行う職種です。
地域包括支援センターで働く主任ケアマネジャーの仕事は、総合相談の支援から介護予防ケアプランの作成、地域の医療・介護問題の発見や解決まで多岐にわたります。地域ケア会議を開催したり、新人ケアマネジャーの育成をしたりすることも、主任ケアマネジャーの重要な仕事です。
「地域包括支援センターの業務実態に関する調査研究事業報告書」によると、地域包括支援センターに配置される社会福祉士の数は1.7人でした。主任ケアマネジャーは幅広いシーンで役割を果たせるため、多くの地域包括支援センターで求められる傾向にあります。
(出典:三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「地域包括支援センターの業務実態に関する調査研究事業報告書」)
介護予防支援に必要な職種
介護予防支援事業に必要な職種には、保健師・社会福祉士・ケアマネジャー・看護師・社会福祉主事の5つが挙げられます。ここでは、包括的支援事業でも必要となる保健師・社会福祉士を除く3つの職種について紹介します。
〇ケアマネジャー
地域包括支援センターにおいてケアマネジャーは、地域が抱える問題や解決策の発見にとりくんだり、介護予防のケアプランをほかの職種と連携して作成したりします。医療・介護面での支援サービスだけでなく、行政サービスや各制度に関するアドバイスも行います。
〇看護師
地域包括支援センターにおいて看護師は、地域住民の相談支援や介護予防ケアプランの作成を行います。保健師と同様、主に介護予防事業の中でも医療知識を要するシーンで大いに活躍できます。
〇社会福祉主事
地域包括支援センターにおいて社会福祉主事は、「ケースワーカー」としてあらゆるサポートを要する高齢者の相談に対応したり、医療機関などの各関係者と連携して必要な支援を提供したりします。ほかの職種とは異なり、社会福祉主事は任用資格となります。
包括的支援事業とは異なり、高齢者が要介護状態となることを予防するための支援・サポートを主に行う介護予防支援事業では、地域の特性や実情のほか、対象となる高齢者の状況や環境を考慮し、アセスメントを行うことが重要です。そのうえで、介護予防ケアプランを作成したり、各機関と連携して適切な支援を受けられるようにしたりすることが基本の業務となります。
まとめ
地域包括支援センターとは、高齢者やその家族が住み慣れた地域で安心した生活を送れるよう、保健医療の向上や福祉の増進を包括的に支援することを目的とした施設です。設置数は年々増加傾向にあり、2021年4月時点において全国5,270カ所に設置されています。地域包括ケアシステムの構築が推進されている近年、2025年を目途にすべての地域で地域包括支援センターを充実させることが目標となっており、設置数は年々増加傾向にあります。
地域包括支援センターでは、主に保健師・看護師・社会福祉士・社会福祉主事・主任ケアマネジャー・ケアマネジャーが活躍できます。保有資格によって業務傾向もやや異なることを覚えておきましょう。
「介護のみらいラボ」では、当記事のほかにも介護業界で活躍する人に有益な情報を数多く掲載しています。現場で役立つ知識を得たいという方は、「介護のみらいラボ」の他記事もぜひご覧ください。
※当記事は2022年3月時点の情報をもとに作成しています
●関連記事: 地域包括ケアシステムとは?5つの構成要素から構築のプロセスまで 地域包括ケアシステムでの自助・互助・共助・公助とは?5つの要素も【国試過去問ドリル第14回】 地域ケア会議とは?目的・機能・運営用法を詳しく解説
【日本全国電話・メール・WEB相談OK】介護職の無料転職サポートに申し込む
スピード転職も情報収集だけでもOK
マイナビ介護職は、あなたの転職をしっかりサポート!介護職専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを行います。
はじめての転職で何から進めるべきかわからない、求人だけ見てみたい、そもそも転職活動をするか迷っている場合でも、キャリアアドバイザーがアドバイスいたします。

SNSシェア















