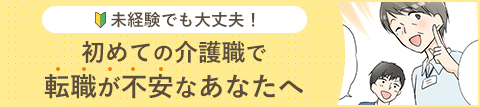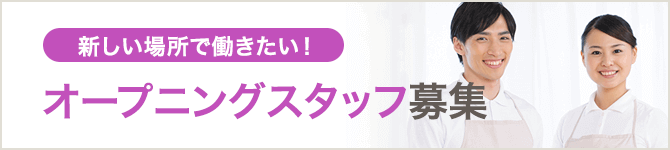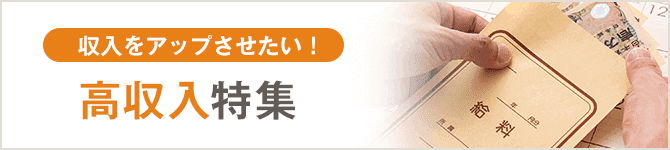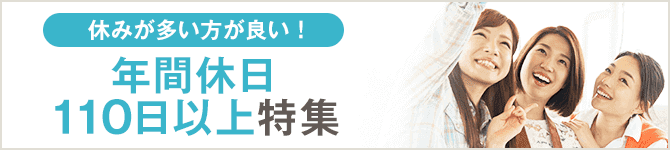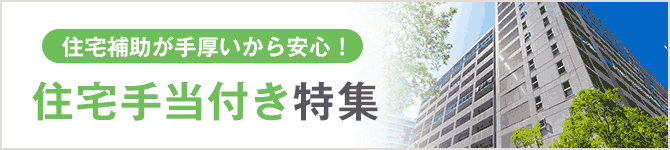社会福祉主事任用資格とはどんな資格?仕事内容や取得方法も解説

福祉サービスに関わる職業で働きたい場合に、社会福祉主事任用資格は役立つ資格です。福祉施設では社会福祉主事任用資格の取得者を歓迎・優遇するケースがあるため、興味を持っている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、社会福祉主事の概要や資格を取得するメリットを解説します。また、資格の取得方法や合格率、活躍できる場所についても紹介します。社会福祉主事任用資格を取得することで、働き方にも幅が生まれます。興味がある方はぜひ参考にしてください。
目次
- 3.社会福祉主事任用資格取得者の仕事内容
- 3-1.福祉事務所で働く場合
- 3-2.身体障害者更生相談所で働く場合
- 3-3.知的障害者更生相談所で働く場合
- 3-4.児童相談所で働く場合
- 3-5.民間の福祉施設で働く場合
- 3-6.民間の医療機関で働く場合
- 5.社会福祉主事任用資格の取得方法
- 5-1.大学・短大で指定科目を3科目以上履修し卒業する
- 5-2.所定の学校の通信課程を修了する
- 5-3.指定養成機関を修了する
- 5-4.都道府県等講習会を受講する
- 5-5.社会福祉士・精神保健福祉士の資格を取得する
- 6.社会福祉主事取得費用の相場
1.社会福祉主事とは
社会福祉主事とは、福祉事務所で家庭訪問や面談、生活指導などを行う職員として働く場合に必要な任用資格です。社会福祉の資格の中でも最も古いものの1つとして知られています。
もともとは、行政の福祉担当部署や福祉事務所に勤める公務員が、専門的な相談を行うために設けられた資格でしたが、現在は公務員に限らず、福祉事務所には社会福祉主事の配置が義務付けられています。また、公務員だけでなく、社会福祉施設の相談員や生活指導員への就職にも有利な資格です。
「主事」とは、公的機関・法人・団体などに設置される事務担当者を意味します。つまり社会福祉主事とは、福祉事務所が社会福祉法に基づいて行う各種事務の担当者です。
福祉事務所の職員として働くためには、社会福祉主事任用資格を取得していることが条件となっています。「任用資格」とは、特定の職業・職位に任用される場合に必要となる資格です。
社会福祉主事任用資格を取得することで、福祉事務所で勤務するための条件を1つ満たすことができます。
ただし、社会福祉主事任用資格とは「社会福祉主事として働ける資格者である」ことを示す資格であり、任用資格の取得だけで社会福祉主事を名乗ることはできません。
資格取得者が公務員試験に合格し、福祉事務所などで働くことにより、初めて社会福祉主事を名乗ることができます。
1-1.社会福祉主事と「社会福祉士・介護福祉士」の違い
社会福祉主事と似ている職業に、社会福祉士と介護福祉士があります。いずれも福祉・介護系の職場で活躍する職業であるものの、活躍する職場や仕事内容は異なるため、違いを正しく把握しましょう。
下記は、それぞれの違いを比較した表です。
| 社会福祉主事 | 社会福祉士 | 介護福祉士 | |
|---|---|---|---|
| 主な職場 | ・行政の福祉事務所 ・行政の各種相談所 |
・行政の福祉事務所など ・社会福祉協議会 ・高齢や障害者、児童などの施設 ・病院 |
・介護が必要とされている人が入所している施設 ・病院 ・ヘルパーステーション |
| 業務の対象者 | ・社会生活を送ることが困難な方 | ・支援を必要とする高齢者 ・障害者 ・児童など |
・介護を必要とする高齢者や障害者など |
| 主な仕事内容 | ・利用者の相談対応 ・生活保護の申請受付 ・現業員(ケースワーカー)の指導監督 |
・利用者の相談対応 ・助言や生活指導 ・援助の実施 |
・利用者への介護業務 ・介護計画の立案 ・家族への介護指導 |
社会福祉主事と名乗るためには公務員である必要があり、就職先の多くは公的施設であることが特徴です。社会福祉士や介護福祉士に比べると事務的な業務が多いものの、社会福祉の現場を支える重要な職業といえます。
「社会福祉士」「介護福祉士」はどんな資格?違いや資格取得方法も
2.社会福祉主事任用資格を取得するメリット
社会福祉主事が働ける職場は豊富にあります。福祉事務所の査察指導員や現業員として働く以外にも、各種相談所の福祉司になったり、社会福祉施設の生活相談員として働いたりすることが可能です。
ここでは、社会福祉主事に興味がある方に向けて、社会福祉主事任用資格を取得する3つのメリットを紹介します。
2-1.社会福祉主事になるための条件を満たせる
社会福祉主事任用資格を取得することで、社会福祉主事になるための条件を満たすことができます。社会福祉主事は働ける職場が多く、社会福祉に関わる職務の経験を積める仕事です。
公務員として公的施設で勤務することにより、比較的安定した収入が得られることや、一般的な介護職よりリストラの心配が少ない点もメリットといえます。
また、日本では生活保護受給者数が多く、生活保護の申請受付などを行う社会福祉主事は将来性も高い仕事です。生活保護被保護実人員数の推移を2019年度・2020年3月・2021年8月で比較すると、下記の通りとなっていました。
| 2019年 | 2020年3月 | 2021年8月 |
|---|---|---|
| 2,073,1171人 | 2,066,660人 | 2,037,800人 |
(出典:厚生労働省「生活保護制度の現状について」/ https://www.mhlw.go.jp/content/12002000/000858337.pdf)
社会福祉主事は社会福祉に助けを求める人と向き合う仕事であり、職業需要は今後も高いことが見込まれています。
社会福祉主事の年収500万円以上の介護職・福祉の求人・転職一覧
2-2.キャリアパスが明確になる
福祉事務所で働く社会福祉主事は、主に現業員または査察指導員の職務に就きます。査察指導員は現業員を監督する職種であり、査察指導員になるには現業員としての経験が必要です。
つまり、社会福祉主事になることで、現業員として働いて査察指導員を目指す、といったキャリアパスが明確になります。
現業員の主な仕事内容は、生活保護の受給申請者に対応することです。福祉事務所を訪れる相談者は高齢・障害・病気などによって生活に困難を抱えているため、現業員は相談内容に応じて必要となる支援を行います。
相談内容によっては、医師などの医療関係者・医療機関や介護福祉施設と連携を取り、相談援助業務を行うこともあるでしょう。
一方、査察指導員の仕事内容は、現業員の指導監督を行うことです。主な仕事内容としては、現業員に対する専門的助言や業務の進行管理などがあり、福祉事務所の業務を滞りなく進行させる役割を担っています。
査察指導員として働くためには、現業員としての勤務経験・キャリア以外に、職場における指導力・リーダーシップも必要です。
2-3.一般的な介護職よりも高給を得られる
社会福祉主事は、一般的な介護職よりも高給を得られるメリットがあります。まず、社会福祉主事の給与について見てみましょう。
社会福祉主事として働く場合、地方自治体の一般職もしくは福祉職として採用されます。そのため、社会福祉主事が受け取る給与額は、公務員給与規定の一般行政職に沿って計算された額です。
以上を踏まえて、公務員の一般行政職が受け取る平均給与月額を見てみると、2021年度で約36万円となっていました。つまり、自治体ごとの特別手当などがあるので一概にはいえませんが、社会福祉主事の平均給与月額も約36万円に自治体ごとの変動を加えた、近い数値になるのではないかと推定できます。
(出典:総務省「令和3年地方公務員給与実態調査結果等の概要」/ https://www.soumu.go.jp/main_content/000784529.pdf)
一方で、介護職員が受け取る平均給与月額は、2021年9月時点で約32万円となっていました。社会福祉主事と介護職員の平均給与月額を比較すると、 社会福祉主事が含まれる公務員一般行政職のほうが約4万円高いことが分かります。
(出典:厚生労働省「令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要」/ https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/21/dl/r03gaiyou.pdf)
社会福祉主事は公務員であるため、福祉・介護系職業の中でも高給で働けることが魅力です。現業員として経験・キャリアを積み、査察指導員に任命されることで給与額の向上も期待できます。
社会福祉に携わりながら、より高い収入を得たい人は、社会福祉主事任用資格の取得を目指してもいいのではないでしょうか。
2-4.就職先の幅が広がる
社会福祉主事任用資格は本来、地方公務員の社会福祉主事として行政機関で働くために、必要となる資格です。しかし、社会福祉主事任用資格は民間の福祉施設で働く場合にも役に立ちます。社会福祉主事任用資格の保有を、相談員や指導員、施設長の採用要件とする求人も少なくないためです。
つまり、社会福祉主事任用資格者は公務員として働くだけでなく、民間の施設でも働ける可能性があり、就職や転職先の選択肢の幅が広げられます。もちろん民間の施設で働く場合にも、社会福祉主事と同様、相談業務などの福祉職に就けるのでキャリアアップが目指せます。
3.社会福祉主事任用資格取得者の仕事内容
社会福祉主事任用資格は、取得後に公務員試験を受けて試験に通れば社会福祉主事として働くのが一般的です。また、民間の施設などで社会福祉関係の仕事に携わる道を選ぶこともできます。
ここでは、社会福祉主事任用資格が役に立つ、代表的な勤務先である6か所について、それぞれの勤務先における働き方や業務内容を解説します。
3-1.福祉事務所で働く場合
福祉事務所は都道府県および市に設置される行政機関です。福祉の相談を受け付ける、地域の相談窓口として機能しています。福祉事務所には、社会福祉主事の配置が義務付けられています。
(出典:厚生労働省「福祉事務所」/ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/fukusijimusyo/index.html)
福祉事務所における社会福祉主事の主な仕事は、相談者の受付や指導、助言です。 困窮者やひとり親家庭、障がいをもつ方や高齢者など、生活に困っている人々の相談を受け、生活保護申請や福祉サービスにつなげ、サポートします。相談内容により、支援の方法は多岐にわたります。
3-2.身体障害者更生相談所で働く場合
身体障害者更生相談所は、身体障害者の自立や社会的活動への参加を促すために、都道府県に設置される機関です。 身体障害に関する専門的な知識や技術によって、身体障害者に対し、障害区分の判定や相談などの支援を行うのが主な仕事です。
身体障害者更生相談所には、身体障害者福祉司の配置が定められています。身体障害者福祉司となるには、社会福祉主事の任用資格を持ち、身体障害者の更生施設などの関連事業に、2年間従事する必要があります。
(出典:高知県「身体障害者更生相談所および知的障害者更生相談所について」/ https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060301/files/2012121900150/2012121900150_www_pref_kochi_lg_jp_uploaded_attachment_73879.pdf)
3-3.知的障害者更生相談所で働く場合
知的障害者更生相談所は、18歳以上の知的障害者に対して、地域による生活支援を目的として、都道府県に設けられている機関です。 知的障害に関する専門的な知識や技術によって、知的障害者に対し、障害区分の判定や療育手帳の発行などが仕事です。
知的障害者更生相談所には、知的障害者福祉司を配置します。知的障害者福祉司となるには、社会福祉主事任用資格を取得したうえで、知的障害者の福祉に関する事業に2年間従事する必要があります。
(出典:高知県「身体障害者更生相談所および知的障害者更生相談所について」/ https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060301/files/2012121900150/2012121900150_www_pref_kochi_lg_jp_uploaded_attachment_73879.pdf)
3-4.児童相談所で働く場合
児童相談所は、児童福祉法によって各都道府県と指定都市に設置が義務付けられている機関です。18歳未満の子どもの健全な成長や発達を目指して、子ども自身やその保護者にまつわる問題を扱います。 非行や不登校、虐待、家庭内暴力といった、さまざまな相談を受け付け、解決のための支援が児童相談所の役割です。
(出典:厚生労働省「第1章 児童相談所の概要」/ https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv11/01-01.html)
児童相談所には児童福祉司を配置する必要があり、児童福祉司になるには社会福祉主事として2年以上児童福祉事業への従事が求められます。
3-5.民間の福祉施設で働く場合
社会福祉主事任用資格取得者は、介護施設や障害者施設などの民間の福祉施設では、生活相談員として働きます。生活相談員の 主な業務は、デイサービスやグループホーム、特別養護老人ホームなどの施設で利用者さんや入居希望者、その家族を対象とした相談支援です。
その他にも、サービス利用・入退居の事務的手続き、窓口業務、電話対応、施設内外の関係機関・役所・病院との連絡調整も行います。
3-6.民間の医療機関で働く場合
社会福祉主事任用資格取得者が民間の医療機関で働く場合、医療ソーシャルワーカーとして働くことになります。 主な仕事内容は、診察や入院治療を受ける患者さん本人やその家族の相談対応です。
入院や退院の手続き、その後の生活や社会復帰に関する支援として介護保険などの制度の情報提供なども行います。地域の医療機関や施設との連携も大切な業務です。医療ソーシャルワーカーとして働く場合、医療機関の他にも保健所や精神保健福祉センターなどで働くこともあります。
4.社会福祉主事の合格率
社会福祉主事任用資格は、介護福祉士資格などと違って国家資格ではなく、取得するための試験がありません。養成機関で指定科目を修学して卒業したり、社会福祉士などの他資格を取得したりすることで取得できる任用資格です。
社会福祉主事任用資格の取得難易度は、取得方法として選んだルートによって異なります。 一例として、専門学校の通信課程で取得を目指した場合は、教育内容をしっかり理解することで取得できる程度です。一般的に、 介護系の国家資格よりも取得しやすいといわれています。
5.社会福祉主事任用資格の取得方法
社会福祉主事任用資格を取得する方法は複数あります。ただし、資格を取ったからといって、すぐに社会福祉主事として働けるわけではありません。社会福祉主事として職務に就くには、社会福祉主事任用資格を得たうえで、公務員試験に合格する必要があります。
ここでは、5つのルート別に社会福祉主事任用資格の資格要件を紹介します。
5-1.大学・短大で指定科目を3科目以上履修し卒業する
大学や短大の卒業者で、社会福祉法で厚生労働大臣が定める科目を3科目以上履修している場合は、社会福祉主事任用資格の取得が可能です。 ただし、指定科目は時代によって科目名が異なるため、自分の履修した科目が指定科目に該当しているか確認することが大切です。
なお、一部の大学を除き、指定科目を3科目以上履修していたとしても資格取得を示す証明書の発行はありません。資格があることを示すには、大学や短大の成績証明書や卒業証明書が必要です。
(出典:厚生労働省「ページ9:社会福祉主事任用資格の取得方法」/ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi1/shakai-kaigo-fukushi9.html)
5-2.所定の学校の通信課程を修了する
すでに社会福祉施設などで働いていて、これから資格を取得したい場合には、通信教育の利用がおすすめです。基本的には自学によるレポート提出が中心となるため、働きながら資格取得を目指せます。 通信教育課程の期間は1年間で、そのうち5日間は対面授業(スクーリング)に参加する必要があります。 スクーリングの日程は土日祝日にも設けられているため、平日に働いていたとしても参加可能です。
なお、通信教育の受講は社会福祉事業の従事者に限定されています。受講期間中に離職すると受講資格がなくなるため、注意しましょう。
(出典:厚生労働省「ページ9:社会福祉主事任用資格の取得方法」/ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi1/shakai-kaigo-fukushi9.html)
5-3.指定養成機関を修了する
指定養成機関とは、介護や福祉系の専門学校のことで全国に指定校があります。 専門学校では全22科目を1,500時間かけて履修するため、最低でも2年以上の通学が必要です。
一般的には、2〜4年課程でカリキュラムが組まれています。指定養成機関を卒業すると、社会福祉主事任用資格に加えて専門学校の卒業資格も得られます。
(出典:厚生労働省「ページ9:社会福祉主事任用資格の取得方法」/ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi1/shakai-kaigo-fukushi9.html)
5-4.都道府県等講習会を受講する
都道府県などの自治体が行う社会福祉主事認定講習は、都道府県か市町村の職員を対象とした講習会です。 資格を持たないまま社会福祉事業に従事している場合に有効です。
ただし、2022年時点で講習を実施している自治体はありません。講習の受講を検討している方は事前に住まいの自治体の情報をよく確認しましょう。
(出典:厚生労働省「ページ9:社会福祉主事任用資格の取得方法」/ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi1/shakai-kaigo-fukushi9.html)
5-5.社会福祉士・精神保健福祉士の資格を取得する
もし社会福祉士か精神保健福祉士の資格を持っている場合、条件なしで社会福祉主事任用資格を取得できます。 ただし、社会福祉士と精神保健福祉士の資格は、社会福祉主事任用資格の上位資格です。国家資格のため国家試験に合格する必要があるなど、資格取得の難易度も上がります。
社会福祉主事任用資格の取得を目的として、社会福祉士や精神保健福祉士の資格を取ることは、あまりないでしょう。社会福祉士か精神保健福祉士の資格に、社会福祉主事の資格が付いてくるイメージです。
(出典:厚生労働省「ページ9:社会福祉主事任用資格の取得方法」/ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi1/shakai-kaigo-fukushi9.html)
精神保健福祉士(PSW)とは?取得メリット・合格率・試験概要
6.社会福祉主事取得費用の相場
社会福祉主事を取得するためには、大学や短大、専門学校に通う必要があります。
社会福祉主事は学部に関係なく、指定された科目を履修すれば取得できるため、学費は学部によって大きく差があります。
下記は、1年間の学費の一例を学校別にまとめた表です。
| 学校 | 学費 |
|---|---|
| 4年制大学・私立 | 約100万~ |
| 国公立 | 約60万~ |
| 短大 | 約40万~ |
| 専門学校 | 約100万~ |
なお、通学だけでなく通信課程を持つ学校もあり、学費は通信課程のほうが安くなります。 自分に合った学校選びをすることが大切といえるでしょう。
まとめ
社会福祉主事は福祉事務所などに勤務する公務員であり、日常生活や社会生活を送ることが困難な方の相談業務を担う、やりがいある仕事です。社会福祉主事は需要が高い仕事であり、キャリアパスが明確になる、一般的な介護職よりも高い収入を得られるといったメリットもあります。
社会福祉主事になるためには、社会福祉主事任用資格の取得が必要です。地方公務員試験に合格する必要もあるため、勉強はしっかり行いましょう。社会福祉主事は活躍できる場所が多いため、介護・福祉業界で働きたい方は取得を目指してみてください。
※当記事は2022年8月時点の情報をもとに作成しています
関連記事

|
資格
| 公開日:2025.04.15 更新日:2025.04.15 |
ホームヘルパーとは?必要な資格や介護福祉士との違いを解説
ホームヘルパーは、高齢者や障害者が自宅で安心して生活できるよう、居宅を...(続きを読む)
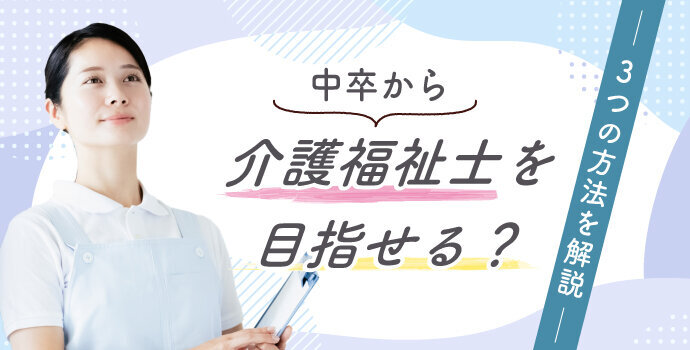
|
資格
| 公開日:2024.12.17 更新日:2024.12.17 |
中卒から介護福祉士を目指せる?3つの方法を解説
介護福祉士の資格を取得するためには、いくつかの条件があります。介護福祉...(続きを読む)

|
資格
| 公開日:2024.08.21 更新日:2024.08.21 |
介護福祉士の資格でできる仕事には何がある?主な転職先について解説
介護の専門資格である介護福祉士を取得することで、無資格の状態に比べて、...(続きを読む)
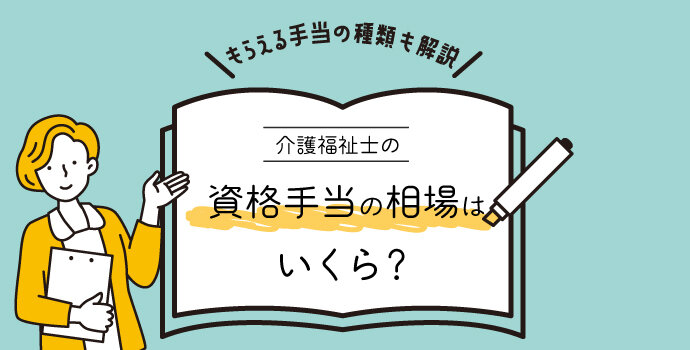
|
資格
| 公開日:2024.08.21 更新日:2024.08.21 |
介護福祉士の資格手当の相場はいくら?もらえる手当の種類も解説
基本給以外の給料アップにつながる手当として、資格手当があります。介護福...(続きを読む)