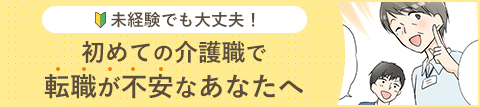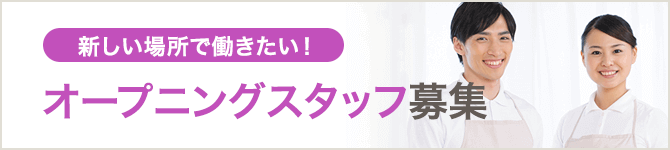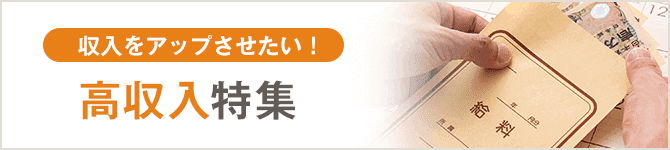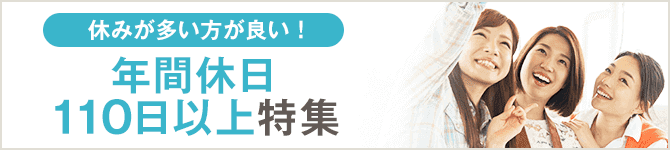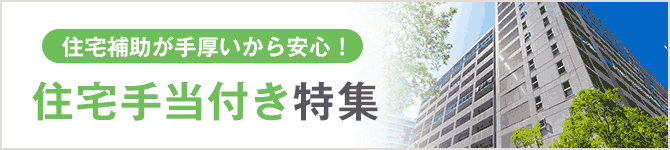社会福祉士はどんな仕事?仕事内容や資格取得方法を解説

社会福祉士は、介護関連の国家資格のひとつです。高齢者や障がいをもつ方をはじめ、日常生活を送ることが困難な方の支援やサポートを行います。福祉や介護、医療に関わる幅広い分野の知識が求められるため、あらゆる現場で活躍することが可能です。
当記事では、社会福祉士の資格内容や、試験の難易度について解説しています。資格の取得方法や必要なカリキュラムについても紹介しますので、社会福祉士の資格取得を目指している方は、ぜひ参考にしてください。
目次
1.社会福祉士とは?
社会福祉士とは、社会福祉士及び介護福祉士法にもとづく国家資格にあたります。
社会福祉士資格を持つ方は「社会福祉士」を名乗り、何らかの理由によって健康的な日常生活を送れない方の相談支援が可能です。
(出典:厚生労働省「社会福祉士・介護福祉士等」/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi1/index.html)
まずは、社会福祉士とはどんな仕事・資格であるかを詳しく解説します。
1-1. 社会福祉士の仕事内容
社会福祉士の主な仕事は、医療福祉分野の専門知識や経験をもとに支援を必要とする高齢者や障がいをもつ方などの相談に乗ることです。 社会福祉士はその他、地域の子ども・生活困窮者・ひとり親世帯などの相談に乗ることもあります。
相談者に適した公的支援制度や社会福祉サービスを特定し、問題解決方法の1つとして提案することも、社会福祉士の仕事です。 相談内容によっては社会福祉士が社会福祉サービスの提供者・医師などに連絡して、調整をサポートすることもあります。
相談者は多くの場合、公的支援や社会福祉サービスに関する専門知識をもっていません。専門知識をもたない方に公的支援などに関する理解を深めてもらうためには、分かりやすい言葉・表現を使用し、基礎知識から伝えることも必要です。
1-2.社会福祉士の勤務先
社会福祉士は対象者の幅が広く、高齢者福祉関係・障害者福祉関係・医療関係・児童福祉関係・行政関係・教育関係などで需要があります。
(出典:厚生労働省「社会福祉士について」/ https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/1.shiryo_1.pdf)
分野ごとの担当業務と勤務先の具体例は、以下の通りです。
- ・高齢者福祉関係
-
高齢者福祉関係の職場で働く社会福祉士は「生活相談員」として、利用者および利用希望者や家族の相談対応・支援計画の作成などを担当します。利用者の状態によっては在宅介護から施設介護(場合によっては、施設介護から在宅介護)への切り替えを助言し、手続きのサポートを行うことも必要です。
〇勤務先の具体例
高齢者福祉施設(設特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、デイサービスなど)
- ・障害者福祉関係
-
障害者福祉関係の職場で社会福祉士は「生活相談員」「サービス管理責任者」として、利用者などの相談対応や自立支援を担当します。サービス管理責任者とはサービスの質向上を図る狙いで関係者に対し、技術的な指導を行う職業です。サービス管理責任者は、スタッフのスキルアップを目的とした研修の企画・実施を担当するケースもあります。
〇勤務先の具体例
身体障害者(知的障害者)更正施設、身体障害者(知的障害者)更正施設、精神障害者生活訓練施設など
- ・医療関係
-
医療現場で社会福祉士は「医療ソーシャルワーカー」として患者さんに寄り添い、経済的な不安や入院生活に関わる問題などの相談に応じます。訪問看護と連携して福祉サービスと調整し、利用者さんの社会復帰を援助することも、社会福祉士の仕事です。
〇勤務先の具体例
医療機関(病院、クリニックなど)
- ・児童福祉関係
-
児童福祉関係の職場で社会福祉士は「児童指導員」として、病気・ケガ・いじめ・虐待などによって不安や悩みを抱える子どもを支援する役割を果たします。非行・虐待への対応や悩みを抱える保護者を支援することも、社会福祉士の役割です。
〇勤務先の具体例
児童福祉施設(児童擁護施設、乳児院、児童自立支援施設など)
- ・行政関係
-
公務員として働く社会福祉士は福祉課や保健福祉課などに配属されて、窓口での相談対応・面談業務を担当します。生活保護課に配属された場合、利用者さんの自宅を訪問して支援する業務を担当することもあるでしょう。
〇勤務先の具体例
都道府県庁、市役所、保健所など
- ・教育関係
-
教育現場で社会福祉士は「スクールソーシャルワーカー」として、直接的支援と間接的支援を担当します。直接的支援とは、子どもが抱える問題を解決する目的で学校や家庭に働きかけたり、関係機関との調整を図ったりすることです。間接的支援とは、子どものサポート体制を整える目的で教職員のサポートにあたる業務を指します。
〇勤務先の具体例
公立の小・中・高等学校、教育委員会など
2.社会福祉士の資格を取得するメリット
社会福祉士の資格は、介護現場に限らず幅広い職場で活かすことができます。介護関連の資格の中でも相談のプロ、スペシャリストと呼ばれており、相談者のあらゆる悩みを解決することが主な仕事内容です。
ここでは、社会福祉士の資格を取得する3つの大きなメリットについて解説します。
2-1.他の専門職からの信頼を獲得できる
社会福祉士の資格があると、介護施設や医療機関など相談援助が必要な現場で役立ちます。社会福祉士は業務独占ではなく名称独占資格であるため、資格がなくても相談援助の職に就くことは可能です。しかし、社会福祉士の資格を取得していれば、他の専門職からの信頼を得られる可能性が高くなります。
また、社会福祉士の仕事は、他の専門職からの認知度が非常に高いため、介護施設や医療機関での信用は抜群です。資格を持っていない方に比べて仕事もしやすく、医師や看護師などの医療職の方とも、仕事をしやすいでしょう。
もちろん、患者や家族など、一般の利用者や関係者からの信頼度も、資格があることで大幅にアップします。
2-2.福祉業界の専門性を高めることができる
社会福祉士の資格を取得するためには、介護や福祉、医療など幅広い分野の専門的知識が必要です。そのため、社会福祉士の資格だけではなく、他の資格と一緒に取得することで、より福祉業界での専門性を高めることができます。
すでに保育士や看護師、介護福祉士、ケアマネージャーなどの資格を有する方が社会福祉士の資格を取得すると、スキルアップに有利です。転職に役立つのはもちろん、介護や福祉、医療のあらゆる相談業務で活躍できる知識が身につくため、専門家として大きな自信となるでしょう。
2-3.相談援助関連の資格の取得に有利となる
社会福祉士の資格を持っていると、相談援助関連の他資格を取得する際に有利です。相談援助関連の資格として、精神保健福祉士を紹介します。
精神保健福祉士は社会福祉士と同様、国家資格のため、資格取得には19科目の筆記試験を受ける必要があります。しかし、社会福祉士の資格があれば、11科目の共通科目が免除されますので、社会福祉士の資格を持っている方は、次に精神保健福祉士を目指す方が多いです。
精神保健福祉士の受験資格を得るためには、社会福祉士の資格取得後、短期養成施設で精神保健福祉士養成課程を学ぶ必要がありますが、一から精神保健福祉士の取得を目指すより難易度が大幅に下がります。
(出典:社会福祉振興・試験センター「精神保健福祉士国家試験」/ https://www.sssc.or.jp/seishin/qa/q_a_all.html#p005)
3.社会福祉士に向いている人
社会福祉士として安定的に長く活躍するためには仕事の適性を正しく判断し、挑戦するかどうかを検討する必要があります。
以下で紹介する社会福祉士に向いている人の性格や行動傾向を把握し、自分自身にとって望ましいキャリアを選択するためのヒントとしていただけたら幸いです。
3-1.相手の立場で物事を考えられる人
社会福祉士は、さまざまな環境要因によって心身ともに傷ついた利用者さんと接する機会が多いです。そのため、自分の都合を押しつけず相手の立場に立って本当に必要な支援策を検討し、問題を抱える人に思いやりをもって行動できる人は、社会福祉士に向いていると言えます。
心身ともに傷ついた利用者さんは見下すような態度を敏感に察知し、心を閉ざす可能性があります。利用者さんと信頼関係を構築して、公的支援の必要性を見極める際の資料をスムーズに収集するためにも、社会福祉士は利用者さんに優しい態度で接することが大切です。
3-2.コミュニケーション能力がある人
社会福祉士の主な業務は相談対応であることから、高度なコミュニケーション能力が求められます。ただし、社会福祉士として活躍するのに、必ずしも高度な能力が必要とは限りません。一般的に、社会福祉士の適性を判断する際には「聞く力」が重要視されます。
社会福祉士の相談業務では、まず利用者さんの話しを注意深く聞き、利用者さんに対して共感を示すことが大切です。会話相手の仕草・表情なども観察しつつ、考えを的確に読み取ることが得意な人は、社会福祉士に向いているでしょう。
3-3.協調性のある人
社会福祉士は関係機関で働く人と連携し、利用者さんの支援にあたることも多くあります。
立場の異なる人とも良好な関係を維持し、利用者さんを適切に支援できる環境を整えるためには、協調性が欠かせません。
多くの場合、社会福祉士が単独で解決できる問題は限定的です。「何でも自分で解決しよう」と考えるあまりに連携を疎かにする態度は、利用者さんの利益につながりません。利用者さんの問題の根本的な解決を図るためにも、社会福祉士は関係機関で働く人に協力を求めて、適切な支援を提供する必要があります。
3-4.学ぶ姿勢を持ち続けられる人
社会福祉士が関わる法律や社会福祉制度は、時代に応じて変化します。社会福祉士として長く活躍するためには常に学ぶ姿勢を持ち、最新の法律や社会福祉制度をフォローしていく努力が必要です。
社会福祉士が最新知識を習得する方法としては、社会福祉会の主催する研修会への参加や、書籍を活用した独学が検討されます。自分に合う勉強方法で常に知識のアップデートを図れる人は、「社会福祉士の適性がある」と言えるでしょう。
3-5.忍耐力のある人
支援対象者の中には周囲の環境や人間関係に悲観して、相談中に感情的になる人もいます。
泣く・怒るなどで感情を示す利用者さんを受け止めて、必要な情報を聞き出すためには、相応の忍耐力が必要です。
また社会福祉士の業務では、時に虐待者の支援などの倫理的に受け入れ難い問題を扱うこともあります。社会福祉士として長く働くためには、個人的な感情に流されず真摯な態度で問題と向き合う冷静さも必要でしょう。
4.社会福祉士の合格率
社会福祉士の合格率は、他の介護関連資格と比べて低いとされています。
直近5年の社会福祉士の合格率は平均28.9%です。
介護福祉士や精神保健福祉士の合格率はおよそ60%以上であるため、難易度は非常に高いことが分かります。
(出典:厚生労働省「第33回社会福祉士国家試験合格発表」/ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17192.html)
社会福祉士の合格率が低い理由は、出題範囲の広さにあります。社会福祉士の試験は19科目から出題され、これは介護関連の資格の中でもかなり多い科目数です。
(出典:社会福祉振興・試験センター「[社会福祉士国家試験]試験概要」/ https://www.sssc.or.jp/shakai/gaiyou.html)
すべての科目で一定の点を取る必要があるため、どの科目もしっかり理解している必要があります。
社会福祉士国家試験に合格するためには、十分な勉強時間を確保してテキスト学習を行うなど、苦手科目を克服することがポイントです。
5.社会福祉士の取得方法
社会福祉士の資格を取得するためには、全部で12ものルートがあります。大きく分けると3つのルートとなりますが、それぞれのルートで流れや必要経験が異なるため、資格取得前に要件を把握しておきましょう。
ここでは、社会福祉士の資格を取得する方法を、3つのルート別に解説します。
- ・福祉系大学もしくは短大で指定科目を履修するルート
-
福祉系の大学もしくは短大で指定科目を履修した場合、最短4年で社会福祉士国家試験の受験資格を得ることが可能です。例えば、福祉系の4年制大学に在籍している方は、4年生の1月に社会福祉士国家試験を受験できます。
- ・短期養成施設などで学ぶルート
-
2年制の福祉系短大で基礎科目のみ履修している場合、受験資格を得るには社会福祉主事養成機関を卒業後相談援助の実務経験が2年以上必要です。児童福祉司・身体障害者福祉司・査察指導員・知的障害者福祉司・老人福祉指導主事としての実務経験が4年以上ある場合は、短期養成施設などで6ヶ月以上学ぶことで受験資格を得られます。
- ・一般養成施設などで学ぶルート
-
一般の大学や短大を卒業した方、相談援助の実務経験が4年以上の場合は、一般養成施設などで1年以上学ぶと受験資格を得られます。
2年制もしくは3年制の短大で学んだ場合は、3年制は1年、2年制は2年の相談援助業務の実務経験が求められます。 実務経験として認められる職種は、児童指導員や生活相談員、介護支援専門員(ケアマネジャー)や医療ソーシャルワーカーなどさまざまです。医療、福祉や介護の幅広い分野で、資格取得のための実務経験を積むことができます。
(出典:厚生労働省「ページ2:社会福祉士の資格取得方法」/ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi1/shakai-kaigo-fukushi2.html)
6.社会福祉士の受験資格
社会福祉士国家試験の受験資格は、以下の通りです。
- ・福祉系大学もしくは短大で指定科目を履修する方
-
4年制の福祉系大学で指定科目を履修している方は、実務経験がなくても社会福祉士国家試験を受験することができます。
同じように指定科目を履修していても、福祉系短大の場合は相談援助業務の実務経験が必要となります。学校の種類と必要な実務経験年数は下記の通りです。福祉系大学:なし
福祉系短大3年:1年
福祉系短大2年:2年
- ・短期養成施設などで学ぶ必要のある方
-
福祉系大学や短大で基礎科目だけ履修している場合、短期養成施設などで学ばなければ、社会福祉士試験の受験資格を得ることができません。
基礎科目を履修した学校の種類によっては、短期養成施設などに入学する際に相談援助の実務経験が必要となる場合があります。社会福祉主事養成機関を卒業している場合は、実務経験があれば短期養成施設などに入学することができます。学校の種類による必要な実務経験年数は下記の通りです。
福祉系大学:なし
福祉系短大3年:1年
福祉系短大2年:2年
社会福祉主事養成機関:2年なお、相談援助の実務経験が4年以上ある児童福祉司と身体障害者福祉司、知的障害者福祉司および老人福祉指導主事は、短期養成施設などで学べば社会福祉士試験の受験資格を得ることができます。
- ・一般養成施設などで学ぶ必要のある方
-
上記2つの条件に当てはまらない場合でも、1年以上の一般養成施設などで学べば、社会福祉士試験の受験資格を得ることができます。しかし、一般養成施設にも入学条件があり、卒業した学校の種類によっては相談援助の実務経験が必要となります。 学校の種類と必要な実務経験年数は下記の通りです。
一般大学:なし
一般短大3年:1年
一般短大2年:2年
なし:4年(出典:社会福祉振興・試験センター「社会福祉士国家試験」/ https://www.sssc.or.jp/shakai/shikaku/route.html)
7.社会福祉士のカリキュラム
社会福祉士の国家試験受験資格を満たすためには、福祉系の大学や短大、養成施設などで専門のカリキュラムを学ぶことが必要です。2020年には、新たな福祉ニーズに対応するために、より実践能力の高い社会福祉士の養成を目的としたカリキュラムが施行されました。
新しくなった社会福祉士の養成カリキュラムでは、医療・心理学・社会学・福祉など幅広い分野の専門科目を学びます。 2024年度からは国家試験の問題も新カリキュラムが対象となることが予定されており、これから受験する方は試験対策の見直しが必須です。
| 社会福祉士養成課程のカリキュラム | |
|---|---|
| 人間と社会およびその関係性の理解 (90時間) |
・医学概論(30時間) 人間の健康や疾病など、身体構造や心身機能を理解して、公衆衛生の観点から健康課題を解決するための対策を学ぶ。 ・心理学と心理的支援(30時間) 人の心の仕組みを理解し、人間の成長段階に生じる心理的課題を理解することが目的。また、心理学にもとづいたアセスメントと支援について学習する。 ・社会学と社会システム(30時間) 現代社会の特性や多様性を学び、社会問題についての理解を深める。 |
| 社会福祉の原理や基盤の理解 (150時間) |
・社会福祉の原理と政策(60時間) 社会福祉の歴史や理論を学び、日本の福祉サービスなどの福祉政策について理解する。 ・社会保障(60時間) 国内外の社会保障について学び、現代社会において必要な社会保障の課題や役割を理解する。 ・権利擁護を支える法制度(30時間) 法律の専門知識を学び、権利擁護を支える民法や憲法、行政法などを理解する。 |
| 複合化・複雑化した福祉課題および 包括的な支援の理解(240時間) |
・地域福祉と包括的支援体制(60時間) ・高齢者福祉(30時間) ・障害者福祉(30時間) ・児童・家庭福祉(30時間) ・貧困に関する支援(30時間) ・保健医療と福祉(30時間) ・刑事司法と福祉(30時間) さまざまな福祉課題について、包括的な支援の方法を学び、各分野の連携に役立てる。 |
| ソーシャルワークの基盤および理論と 方法の理解(240時間) |
・ソーシャルワークの基盤と専門職(30時間) ・ソーシャルワークの基盤と専門職【専門】(30時間) ・ソーシャルワークの理論と方法(30時間) ・ソーシャルワークの理論と方法【専門】(30時間) ・社会福祉調査の基礎(30時間) ・福祉サービスの組織と経営(30時間) 社会福祉調査の意義や目的を理解し、ソーシャルワークの基盤となる考え方や理論を実践的に身につける。 |
| ソーシャルワークの方法および実践の理解(480時間) | ・ソーシャルワーク演習(30時間) ・ソーシャルワーク演習【専門】(120時間) ・ソーシャルワーク実習指導(90時間) ・ソーシャルワーク実習(240時間) これまで学んだ知識を活かし、現場実習を通じて生活支援の技術や実践能力を養う。 |
(出典:厚生労働省「見直し後の社会福祉士養成課程の全体像」/ https://www.mhlw.go.jp/content/000604998.pdf)
新たな社会福祉士養成課程では、ソーシャルワークの相談援助実習指導が強化されています。社会福祉士として求められる役割を理解し、実習で得た具体的な体験を実務に活かせる能力を育てることが目的です。
ソーシャルワーク実習指導担当教員から個別に現場実習指導を受けられるため、実習先でも安心して学ぶことが可能です。
8.社会福祉士取得費用の相場
社会福祉士になるためにかかる費用は、国家試験の受験費用と登録料の他に、学校に通う場合の費用と受験対策にかかる費用があります。
2021年時点で、国家試験の受験料は下記の通りです。
| 試験 | 受験費用 |
|---|---|
| 社会福祉士のみ受験する場合 | 19,370円 |
| 社会福祉士と精神保健福祉士を同時に 受験する場合 |
16,840円 |
| 社会福祉士の共通科目免除により 受験する場合 |
16,230円 |
(出典:厚生労働省「第34回社会福祉士国家試験の施行について」/ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20142.html)
学校別の費用と受験対策費用は、以下の通りです。
- ・福祉系大学または短大の学費
-
福祉系大学に通う場合、1年間に必要な学費は、国立でも年間約60万円が必要です。私立の場合はさらに費用がかかります。
しかし、すでに社会人として働いている場合、仕事を辞めて大学や短大に通うことが難しいという方も少なくありません。大学の通信課程であれば、4年かかりますが実習関連費を除けば1年間に25万円ほどの学費で通うことができます。通学が難しい場合には、大学の通信課程も選択肢のひとつに加えてみてはいかがでしょうか。
- ・養成施設の費用
-
養成施設の学費は、短期か一般かによって異なります。
どちらの場合も、実務経験の年数によって実習が免除されます。免除の条件については各学校に確認しておきましょう。費用は施設によって異なるため、一概には言えませんが、以下目安として参考にしてください。短期養成施設 実習あり:約30万円実習なし:約20万円 一般養成施設 実習あり:約40万円実習なし:約30万円
- ・社会福祉士受験対策費用
-
国家試験の受験対策費用は、書店で参考書や問題集を購入すれば3,000円程度で済みます。しかし、社会福祉士の試験は19科目もあるため、独学では難しいと感じたら通信講座を選ぶことがおすすめです。
ただし、通信講座の費用は約4万円~と、スクールによって大きく異なるため、総合的に判断して自分に合う講座を選びましょう。また、通学での受講は地域が限られます。お住まいの地域に通学講座があるかを確認することも重要です。
9.社会福祉士を仕事で活かす
社会福祉士は、社会福祉施設や行政機関、病院や教育現場など、福祉に関わるすべての場所で活躍することができる専門家です。また、社会福祉士は福祉系資格への汎用性が高く、児童福祉司や児童指導員、生活保護担当査察指導員および身体障害者福祉司は、社会福祉士の資格が欠かせません。
社会福祉士は、あらゆる福祉の現場で働くことができる資格です。 どのような分野で活躍したいのか、どんな社会福祉士になりたいのかを日ごろから考えておくことで、早い段階で自分に合う職場を見つけることができるでしょう。
まとめ
社会福祉士の資格は、福祉や介護、医療などのあらゆる場面で活かすことができます。他の専門職の方と働く際にも、社会福祉士の資格があれば信頼度が高まり、仕事がスムーズに進むなど、大きなメリットが得られるでしょう。
社会福祉士の国家試験は範囲が広いため、長時間の試験対策をおすすめします。今後の社会福祉養成課程のカリキュラム改正をふまえ、最新の知識を身につけておくことが大切です。
当記事の内容を参考に、社会福祉士の資格取得を目指してください。
※当記事は2022年8月時点の情報をもとに作成しています
関連記事

|
資格
| 公開日:2025.04.15 更新日:2025.04.15 |
ホームヘルパーとは?必要な資格や介護福祉士との違いを解説
ホームヘルパーは、高齢者や障害者が自宅で安心して生活できるよう、居宅を...(続きを読む)
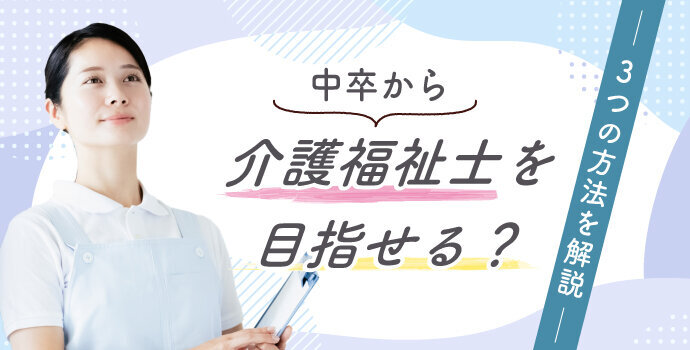
|
資格
| 公開日:2024.12.17 更新日:2024.12.17 |
中卒から介護福祉士を目指せる?3つの方法を解説
介護福祉士の資格を取得するためには、いくつかの条件があります。介護福祉...(続きを読む)

|
資格
| 公開日:2024.08.21 更新日:2024.08.21 |
介護福祉士の資格でできる仕事には何がある?主な転職先について解説
介護の専門資格である介護福祉士を取得することで、無資格の状態に比べて、...(続きを読む)
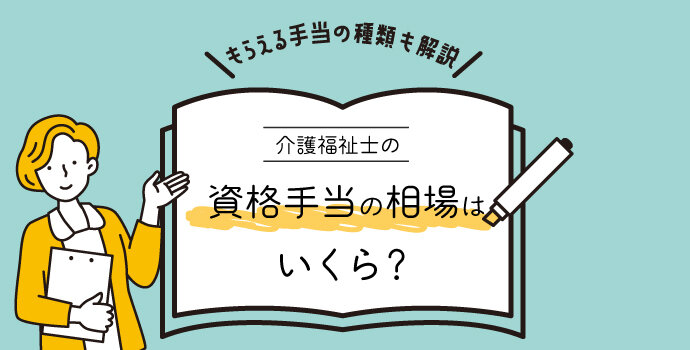
|
資格
| 公開日:2024.08.21 更新日:2024.08.21 |
介護福祉士の資格手当の相場はいくら?もらえる手当の種類も解説
基本給以外の給料アップにつながる手当として、資格手当があります。介護福...(続きを読む)