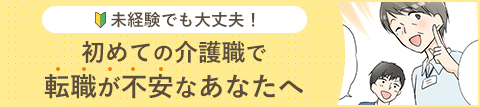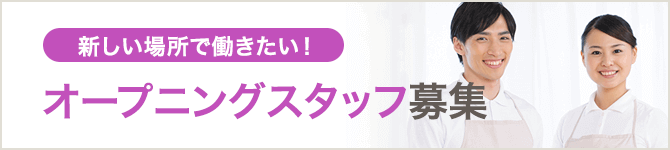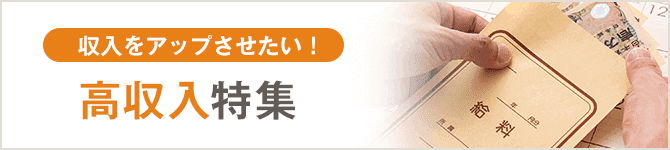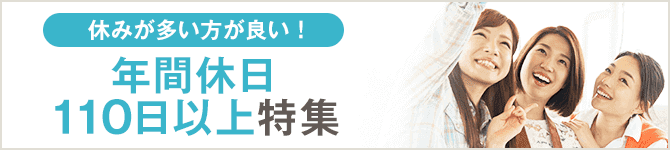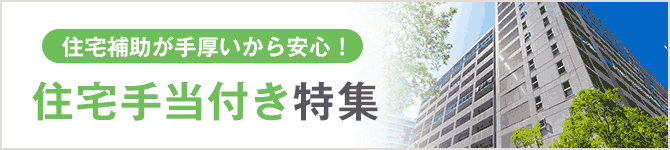ケアマネジャーとは?仕事内容と資格の取得方法を解説

介護職として一定の経験を積んだ後、「より地域の高齢者に貢献できる人材になりたい」と考えて、ケアマネジャー(介護支援専門員)を目指す人もいるでしょう。ケアマネジャー資格を取得するためには一定の時間と労力を要することから、役割や将来性を正しく理解した上で、自分に合う職業かを判断しましょう。
当記事では、ケアマネジャーの仕事内容・資格の取得方法・将来性を解説します。ケアマネジャーに関する理解を深めて、後悔しないキャリアプランを選択したい人は、ぜひ参考にしてください。
目次
1.ケアマネジャー(介護支援専門員)とは
ケアマネジャー(介護支援専門員)とは、介護保険制度におけるケアマネジメントを行うための公的資格で、国家資格ではないものの、信頼性が高く転職にも有利な資格です。
主な仕事内容には、介護を必要とする人への相談援助、介護保険制度を利用するためのケアプランの作成、関係機関との連絡・調整の3つがあります。
ケアマネジャーとなるためには、年1回行われる介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネジャー試験)に合格しなければなりません。その後、介護支援専門員実務研修の全講座を修了することで、登録が可能となります。
登録後の介護支援専門員証発行によって、はじめてケアマネジャーとして働くことが可能です。ケアマネジャーとして業務に就く場合は、5年ごとに更新が必要となります。
(出典:厚生労働省「介護支援専門員(ケアマネジャー)」/ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000114687.pdf)
介護職系の給料・年収について/ケアマネジャー(介護支援専門員)とは
1-1. ケアマネジャーの役割
ケアマネジャーは、介護を必要とする人(以下「利用者」とします。)とその家族の相談に乗り、必要なサポートをマネジメントするプロフェッショナルです。仕事内容は、下記の2つの業務に大別されます。
- ケアプランの作成(ケアマネジメント)
-
利用者の現状及び課題を把握して、適切なケアプラン(居宅・施設・介護予防サービス計画)の作成を行います。実際の介護サービスはケアプランに基づいて行われるため、非常に重要な業務です。ケアプランの作成にあたり、利用者や家族から話を聴き、必要なサービスに結びつけていく分析(アセスメント)や、計画通りにサービス提供がされているかのチェック(モニタリング)なども行います。これら一連の業務を「ケアマネジメント」と呼びます。
- 利用者とサービス事業者の調整
-
介護保険サービスは、訪問介護・通所介護・施設介護などサービス提供形態がさまざまであり、また事業者・施設の数も多くあります。そのため、利用者自身が最適なサービス事業者を選ぶことは難しいことが実情です。
ケアマネジャーは、利用者や家族が必要と感じているサービスを提供できる事業者や施設の情報を提供して、利用者や家族が最適な選択ができる橋渡しを行うことが、業務の一つとなっています。
また、サービス利用開始後にクレームを利用者の代わりに事業者・施設に伝えたり、反対に事業者・施設からの申し出を利用者に伝えたりするといった、調整業務も担当します。
1-2.ケアマネジャーの仕事内容
ケアマネジャーが活躍できる場は数多くありますが、どこの職場においても基本的にはケアマネジメント(ケアプランの作成など)が業務の中心となります。
ここでは、施設形態別にケアマネジャーの具体的な仕事内容について解説します。
- ●居宅介護支援事業者(ケアプランセンター)
-
居宅介護支援事業者で働くケアマネジャーは、自宅で暮らす要介護状態の利用者のために、ケアマネジメント(ケアプランの作成など)を行うことが主な業務内容です。通称「居宅ケアマネ」とも呼ばれています。
ケアマネジメントには、ケアプラン作成だけではなく、定期的に利用者宅を訪問して、心身の状態・生活状況・介護状態などを聴き取るモニタリング及びアセスメントを行うことも含まれます。居宅介護支援事業者は、ケアマネジャーの就職先としては最も多く、独立して業務を行う人もいます。
- ●老人ホーム(特別養護老人ホームや有料老人ホームなど)
-
老人ホームで働くケアマネジャーは、通称「施設ケアマネ」と呼ばれており、入居している利用者のケアマネジメント(ケアプランの作成など)を行います。
施設に常駐しているため、利用者の状態を常時把握できるほか、他の職員との連携も容易であるという業務特性があります。
- ●小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護・グループホーム
-
地域密着型サービスである小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護・グループホームでもケアマネジャーは必要です。利用者のケアマネジメント(ケアプランの作成など)を行います。
2.ケアマネジャー(介護支援専門員)の資格を取得するメリット
ケアマネジャーの資格取得までの道のりは容易ではありませんが、資格を取得することでさまざまなメリットを得ることができます。介護業界でキャリアアップしたい人や、より高いステージで活躍したい人は、ぜひ資格取得を目指すことをおすすめします。
ここでは、ケアマネジャーの資格を取得する主なメリットについて解説しますので、ぜひ参考にしてください。
2-1.給料アップを望める
ケアマネジャーの資格は、多くの職場で評価が高く、給料水準や手当も高い傾向にあります。 資格を取得してケアマネジャーとして転職したり、現職で手厚い手当をもらったりすることが可能です。
資格取得の努力が給料へダイレクトに反映されることは、大きなメリットといえるでしょう。
2-2. 活躍の場が広がる
ケアマネジャーを必要としている福祉の現場は多く、ケアマネジャーの配置義務がある老人ホーム(特別養護老人ホームや有料老人ホーム)や居宅介護支援事業者などからの需要があります。そのため、資格を取得することで、活躍の場を大きく広げることが可能です。
また、介護ニーズならびに事業者が提供する介護サービスの多様化により、今後ケアマネジャーが求められる場所は、さらに増えると考えられます。介護業界で幅広く活躍したい人には、非常におすすめの資格であるといえます。
夜勤がなく自分のペースで働ける
ケアマネジャーが行うケアマネジメント業務は、基本的に日中に行われるため、夜勤がありません。
業務難易度が高く責任も重い仕事ですが、夜勤のある介護現場のような身体的負担や生活リズムへの影響が少なく働けることがメリットです。ケアマネジャーの仕事に慣れてくると、他の介護職種に比べて自分のペースで働くことができるでしょう。
3.ケアマネジャー(介護支援専門員)の合格率
ケアマネジャーの資格を取得しようと考えている人は、試験の合格率について知っておく必要があります。
下記は、近年のケアマネジャー試験における合格率を一覧で示した表となります。
| 試験開催年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 第17回(平成26年) | 174,974人 | 33,539人 | 19.2% |
| 第18回(平成27年) | 134,539人 | 20,924人 | 15.6% |
| 第19回(平成28年) | 124,585人 | 16,281人 | 13.1% |
| 第20回(平成29年) | 131,560人 | 28,233人 | 21.5% |
| 第21回(平成30年) | 49,332人 | 4,990人 | 10.1% |
| 第22回(令和元年度) | 41,049人 | 8,018人 | 19.5% |
| 第23回(令和2年度) | 46,415人 | 8,200人 | 17.7% |
| 第24回(令和3年度) | 54,290人 | 12,662人 | 23.3 % |
(引用:厚生労働省「第24回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について」/ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187425_00008.html)
合格率は毎年変動がありますが、約10~約20%程度の範囲で推移していることが分かります。基本的に、難易度は非常に高い試験であることは認識しておいたほうが良いでしょう。
試験内容は「介護支援分野25問」「保健医療福祉サービス分野35問」の2分野で、合計60問が出題されます。試験の難易度で合格ラインは若干調整されますが、各分野で正答率70%程度が合格ラインとされています。
さらに、ケアマネジャーの試験難易度は毎年上がっているといわれており、これから試験合格を目指す人は、入念な準備を行っておく必要があるでしょう。
4.ケアマネジャー(介護支援専門員)資格の取得方法
ケアマネジャーとして活動するためには、介護支援専門員実務研修受講試験に合格して、その後一定の研修を受けて資格を取得する必要があります。
資格については国家資格ではありませんが、各都道府県により管理されており、公的資格に分類されます。
- ■ケアマネジャー資格取得の流れ
- 1:受験申込(6月上旬~7月上旬の約1ヶ月間・都道府県により異なります。)
2:介護支援専門員実務研修受講試験(毎年10月第2日曜日)
3:合格発表(12月上旬)
4:実務研修(通学・オンライン・eラーニングなど)
5:実務研修修了後、都道府県に登録しケアマネジャーの資格取得
ケアマネジャーの試験を受験するためには、定められた期日内に、受験する都道府県の実施団体に申し込みを行う必要があります。期日を過ぎたり受験する地域を間違えたりすると、無効となるため注意しなければなりません。
年1回しか実施されない試験ですので、試験対策と共に必要書類の準備や申し込みについても入念に調べておく必要があります。
4-1.受験資格
ケアマネジャーの試験を受けるためには、国家資格に基づく業務経験もしくは相談援助業務経験が5年以上、なおかつ従事した日数が900日以上というような実務経験が必要です。
国家資格の保持者と相談援助業務経験者の受験資格には、下記のような違いがあります。
■国家資格に基づく業務経験
下記に該当する資格を持っている人が、その資格本来の業務を行った期間が5年以上あれば、受験資格として認められます。介護福祉士であれば直接的な介護業務が対象となり、営業や事務が主たる仕事の場合は業務経験として認められません。
【該当資格】
- 医師
- 歯科医師
- 薬剤師
- 保健師
- 助産師
- 看護師
- 准看護師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 社会福祉士
- 介護福祉士
- 視能訓練士
- 義肢装具士
- 歯科衛生士
- 言語聴覚士
- あんまマッサージ指圧師
- はり師
- きゅう師
- 柔道整復師
- 栄養士(管理栄養士含む)
- 精神保健福祉士
■相談援助業務経験
施設の相談援助業務に従事している場合は、働いている施設や行っている業務内容によって、受験資格として認められるかどうかが変わります。受験資格が認められる相談援助業務は下記の通りです。
●生活相談員
下記における生活相談員としての業務が対象
- 特定施設入居者生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護予防特定施設入居者生活介護 など
●支援相談員
介護老人保健施設における支援相談員としての業務が対象
●相談支援専門員
計画相談支援、障害児相談支援における相談支援専門員としての業務が対象
●主任相談支援員
生活困窮者自立相談支援事業などにおける主任相談支援員としての業務が対象
(出典:福祉医療機構「介護支援専門員(ケアマネジャー)」/ https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/fukushiworkguide/jobguidejobtype/jobguide_job07.html)
5.ケアマネジャー(介護支援専門員)になるために必要な年数
ケアマネジャーになるためのルートは複数あるものの、いずれを選択するとしても、一定の実務経験が必要です。資格取得を目指す人は自分自身の意思のみですぐに試験を受けられるわけではないことを理解し、計画的に準備しましょう。
以下では、ケアマネジャーの資格を取得するために必要な年数を解説します。
5-1.介護福祉士から目指す場合
介護福祉士がケアマネジャー試験を受けるためには、資格登録後に5年(900日)以上の実務経験が必要です。
(出典:公益財団法人東京都福祉保健財団「令和4年度東京都介護支援専門員実務研修受講試験」/ https://www.fukushizaidan.jp/101caremanager/shiken/)
つまり、介護福祉士からケアマネジャーになるためには最短でも5年かかります。
なお、事務作業など対人業務以外の仕事を担当していた期間は介護老人保健施設や特別養護老人ホームなどに勤務していたとしても、年数に算入できません。資格登録前に居宅介護支援事業所などで働いていた期間も、年数に算入できない点には注意しましょう。
5-2.無資格から目指す場合
無資格からケアマネジャーになるためには、介護福祉士資格の登録後に5年(900日)以上の実務経験を経て、ケアマネジャー試験を受ける必要があります。介護福祉資格を取得するためには、実務経験ルート・養成施設ルート・福祉系高校ルートのいずれかを経て試験を受け、合格することが必要です。
介護職として働きつつ介護福祉士資格の取得を目指す場合は通常、実務経験ルートを選択します。実務経験ルートとは、介護現場で3年以上の実務経験と実務者研修の受講により、試験を受ける資格を得るルートです。介護福祉士資格を取得するための期間・介護福祉資格登録後にケアマネジャーを目指す期間を合わせると、最短でも8年かかります。
より短期間で介護福祉士資格の取得を目指すためには、養成施設ルートも検討しましょう。養成施設ルートとは、養成施設で1〜2年以上修学し、国家試験を受ける資格を得るルートです。養成施設ルートで介護福祉資格を取得するための期間・介護福祉資格登録後にケアマネジャーを目指す期間を合わせると、最短でも6年かかります。
(出典:厚生労働省「介護福祉士資格の取得方法について」/ https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/siryou1_6.pdf)
6. ケアマネジャー(介護支援専門員)資格の取得費用の相場
ケアマネジャーの資格取得までには、ケアマネジャー試験受験費用・実務研修受講料・介護支援専門員登録手数料・介護支援専門員証交付手数料がかかります。
ケアマネジャーの管轄は都道府県となるため、地域によって資格取得費用に差があります。特に実務研修受講料は地域差が大きいので、事前に確認しておきましょう。各費用のおおよその目安については、下記の通りです。
| 費用項目 | 費用相場 |
|---|---|
| ケアマネジャー試験受験費用 | 7,000~9,000円 |
| 実務研修費用 | 20,000~60,000円 |
| 登録手数料・交付手数料 | 2,000~4,000円 |
また、ケアマネジャーは合格率が例年20%を下回ることが多く、難易度の高い資格として知られています。そのため、受験対策講座を行うスクールに通学したり、通信講座を受講したりする人が多いでしょう。学習の仕方によっては、必要な費用がさらにかかります。
●学習にかかる費用
医療福祉系スクールには、通学と通信の2種類があります。受講コースはさまざまで、内容によって費用が異なります。
受講費用は1、2万円~10数万円と幅広く、通学か通信講座かなど、受講内容やボリュームによって異なります。講座によっては学校独自の割引・助成制度や、一般教育訓練給付金・母子父子家庭等自立支援教育訓練給付制度が利用できるため、事前に対象となるかどうかを確認しましょう。
独学の場合は、市販の参考書や問題集にかかる費用のみとなります。長寿社会開発センターから発行されている介護支援専門員基本テキストは7,480円(税込)、その他の一般的な参考書を利用した場合には、2,000~3,000円ほどかかります。
7. ケアマネジャー(介護支援専門員)を仕事で活かす
ケアマネジャーが活躍できる場所は、在宅と施設の2つに分かれます。
在宅の場合は、居宅介護支援事業者(ケアプランセンター)で働くことが多いでしょう。住み慣れた自宅や地域で、自立した生活を送ることができるようなケアプランの作成が求められます。
そのため、利用者宅への訪問や関係機関との調整などを行うことが多く、身体介護などの直接的支援に関わることはほとんどありません。
一方、施設の場合は、介護保険施設や有料老人ホーム、グループホームなどが活躍の場となります。介護保険施設では職員の人手不足を理由に、生活相談員や介護職員の仕事を兼任することもあります。
どちらで働く場合でも、自立した生活を送ることができるよう、利用者の生活をマネジメントする仕事であることに変わりはありません。介護を必要としている人を総合的に支えたいと思っている場合には、ケアマネジャーは取得したい資格の一つといえるでしょう。
8. ケアマネジャー(介護支援専門員)は今後廃止される?
介護業界では「ケアマネジャー資格が廃止される」などと噂する声があるため、職業の将来性に疑問を持つ人もいるでしょう。しかし、現段階で噂を裏付ける事実や厚生労働省・関係団体で廃止に向けた議論が行われた記録はありません。
では、なぜ、資格の廃止を噂する人がいるのでしょうか。以下では、噂が出回った理由や社会的な背景を解説します。
8-1.受験資格の厳格化
介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格は、2018年に厳格化されました。一部の人は厳格化の理由を「ケアマネジャーの人数を減らし、最終的には資格ごと廃止する狙いがある」と考えます。
しかし、受験資格が厳格化された実際の理由は、ケアマネジャーの質や専門性を高めることです。ケアマネジャーには今後も、介護保険制度を運用する要として重要な役割を果たすことが期待されます。
8-2.合格者数の激減
ケアマネジャー試験の合格者数は2018年以降、激減しました。一部の人は激減の理由を「将来的に資格を廃止する狙いがある」と考えます。しかし、合格者数が激減した背景には以下の理由があるとも言われるため、資格の廃止と関連づけることは不自然です。
- 受験資格の厳格化により、そもそもの受験者数が減少したこと
- ケアマネジャー試験が難関であること
ケアマネジャーは受験資格を得ることのみでも難易度が高い上、合格基準を満たすためには深い専門知識を要求される資格です。結果として受験者数が減少し、合格者数の激減につながったと考えられます。
8-3.AI技術の発展
近年では介護の現場においても、AI技術の活用が広まっています。「よりAI技術が発展すると、ケアマネジャーの思考パターンや過去のデータに則ったケアプラン作成をコンピューターが代行できる」と考える人もいることは事実です。
しかし、ケアマネジャーは、コンピューターに代行できない仕事も多く担当します。たとえば、アセスメント対象者の生活ぶりや表情から心身状態を推測し、支援内容や利用サービスを検討する仕事は、コンピューターによる代行が不可能です。高齢者や家族の立場で悩みや不安と向き合い、満足度の高いケアプランを作成することも、コンピューターに代行できない仕事と言えます。
現時点においてAI技術を活用したシステムは、ケアマネジャーの業務効率を高めるためのツールの1つにすぎません。また、コンピューターには代行できない仕事がある以上、有資格者に対する需要は減らないものと考えられます。
9. ケアマネジャー(介護支援専門員)の今後
少子高齢化の進行や介護サービス需要の変化を受けて、ケアマネジャー資格制度を含む介護制度の多くは近年、大幅に改革されてます。ケアマネジャー資格制度やケアマネジャーの待遇に関する改革の方向性を正しく把握することで、職業の将来性を見極めましょう。
9-1.国家資格化の可能性
日本介護支援専門員協会の調査によると、2003年の国会答弁書においてケアマネジャーは、国家資格の1つに含められたことがあります。
(出典:日本介護支援専門員協会「「国家資格」及び「民間技能審査事業認定制度による資格」に関する質問主意書・答弁書について」/ https://www.jcma.or.jp/?p=497835)
介護業界では現状、「ケアマネジャーは国家資格として認められていない」とする意見が主流です。今後「ケアマネジャーは国家資格である」と考える意見が一般化すれば、職業の社会的地位はより一層高まるでしょう。
なお、介護業界の専門家の中には「ケアマネジャーが国家資格として認められるためには根拠法の設定や認定者の見直しが必要」と主張する人もいます。場合によっては、ケアマネジャー資格が国家資格と認められる状態を整えるため、資格のあり方が根本から見直される可能性もあります。
9-2.処遇改善の可能性
2022年10月以降、介護業界で運用される処遇改善加算は、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の3種類です。
(出典:厚生労働省「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の概要」/ https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000953647.pdf)
ケアマネジャーは介護職員と比較して給料水準が高い傾向にあるため、介護職員処遇改善加算の対象から外されてきました。2022年10月以降に運用が開始される「介護職員等特定処遇改善加算」は、一部の施設ケアマネジャーも対象です。
居宅ケアマネジャーは処遇改善の対象から外されているものの、「職場における給料バランスを整えるため、対象に含めてほしい」との要求がすでに出ている状況です。今後の動向によってはケアマネジャー全体の処遇改善が一層進み、年収アップを期待できる可能性もあるでしょう。
まとめ
ケアマネジャーは、介護を必要とする人の相談に乗り、ケアプランの作成・訪問介護サービス事業者や施設介護サービス事業者との調整などを担当する職業です。ケアマネジャーになるためには介護福祉士として一定の実務経験を積んだ後にケアマネジャー試験を受験し、合格することが必要です。ケアマネジャー試験に合格するためには自分自身に合う学習方法で、十分な事前準備を行いましょう。
マイナビ介護職では、ケアマネジャーを目指す人の転職活動を介護業界に強いキャリアアドバイザーがサポートいたします。希望通りのキャリアビジョンを叶えるための転職を検討している方はぜひ、マイナビ介護職をご利用ください。
※当記事は2022年8月時点の情報をもとに作成しています
関連記事

|
資格
| 公開日:2025.04.15 更新日:2025.04.15 |
ホームヘルパーとは?必要な資格や介護福祉士との違いを解説
ホームヘルパーは、高齢者や障害者が自宅で安心して生活できるよう、居宅を...(続きを読む)
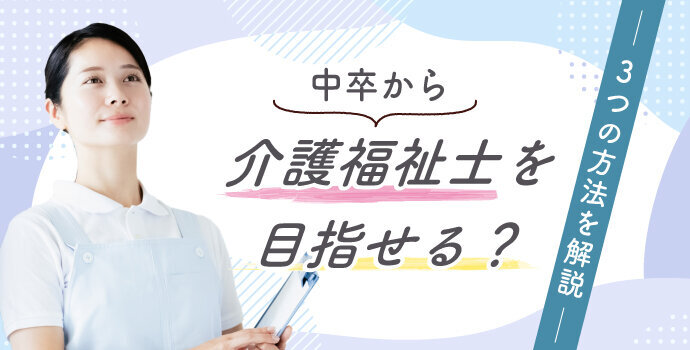
|
資格
| 公開日:2024.12.17 更新日:2024.12.17 |
中卒から介護福祉士を目指せる?3つの方法を解説
介護福祉士の資格を取得するためには、いくつかの条件があります。介護福祉...(続きを読む)

|
資格
| 公開日:2024.08.21 更新日:2024.08.21 |
介護福祉士の資格でできる仕事には何がある?主な転職先について解説
介護の専門資格である介護福祉士を取得することで、無資格の状態に比べて、...(続きを読む)
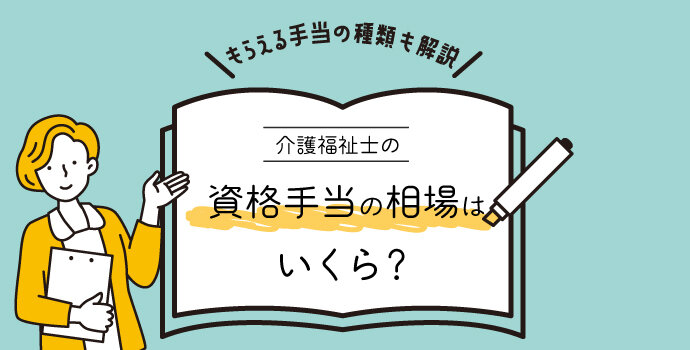
|
資格
| 公開日:2024.08.21 更新日:2024.08.21 |
介護福祉士の資格手当の相場はいくら?もらえる手当の種類も解説
基本給以外の給料アップにつながる手当として、資格手当があります。介護福...(続きを読む)