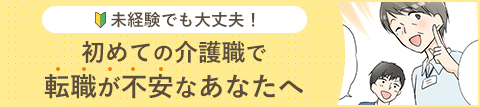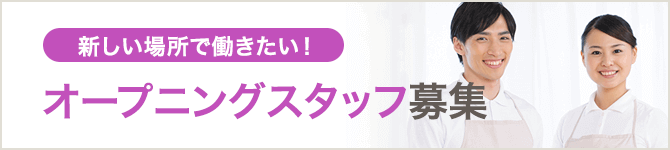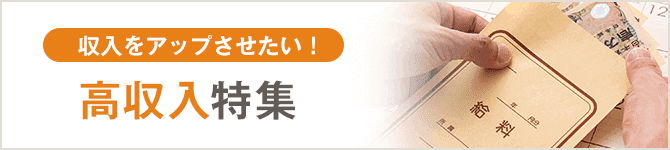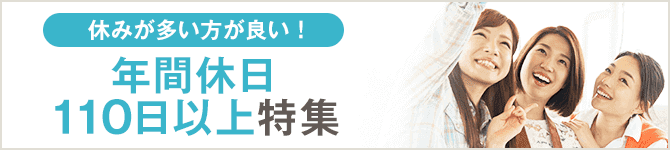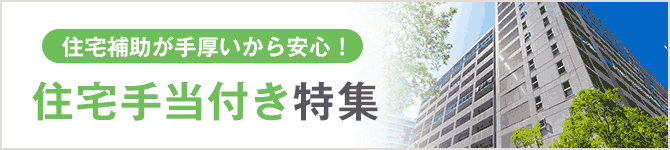【外国人介護士の4つの分類】期限無しで働ける資格と定着に必要とされる支援

介護の現場でも外国人職員の姿が見られるようになってきました。政府が受け入れ拡大をめざしている外国人介護職、その資格別の特徴・在留期限など基本情報から、外国人職員を受け入れるにはどういった体制や支援が必要なのか、解説しました。
厚生労働省の資料によると平成30年度に事業所に受け入れられた外国人介護職員の実人数は773人。すでに受け入れている施設はどのような生活支援を行い、どのように職場の仲間になっているのでしょうか。
【無料転職】マイナビ介護職に登録してキャリアアップできる職場がないか聞いてみる
目次
介護の現場の外国人。実は雇用形態も、それぞれ
外国人職員、利用者さんの感想は?
平成31年1月の時点で累計4,302人の外国人介護職員が日本で働いています。過去も含めて808箇所の施設等が雇用実績ありと答えています。
では実際、利用者さんやそのご家族にとって、外国人介護職員に対する評価はどうなのでしょうか。
平成30年度のアンケート調査※では、「満足」と答えたのが約65%、「普通」と答えたのは約25%でした。ほぼ90%が日本人介護職員と変わらないか、それ以上と感じていることになります。
また受けたサービスの中でよかったことについて聞いたところ、「いつも笑顔をたやさない」「熱心」「丁寧な声かけや対応」といった声が多かったようです。
しかし外国人介護職員といっても、その受け入れに関する制度は4つもあり、どの制度を使って来日しているのかによって、じつはめざす目的も大きく異なるのです。
EPAに基づく外国人介護福祉士候補者
皆さんは、EPA介護福祉士候補者について、ご存知でしょうか。経済連携協定に基づいて日本の介護施設で就労・研修をしながら日本の介護福祉士の資格取得をめざすという受け入れ制度のひとつです。受け入れ国はインドネシア、フィリピン、ベトナムの3カ国で、それぞれ自国での厳しい要件をクリアし、日本語でのコミュニケーション能力に関しても一定のレベルに達しているとみなされた方々です。来日後は介護施設等で働きながら、決められた期間内で日本の国家資格である介護福祉士と、在留資格「介護」の取得をめざすことを目的としています。
受け入れ事業所にとっては、資格が取れれば将来永続的に働いてもらえるかもしれない貴重な人材資源です。同アンケート調査※によると、すでにこのEPA介護福祉士候補者を雇用している介護施設では、約80%が「今後も受け入れる予定」と回答しているほか、雇用したことのない施設でも約20%が受け入れる予定と答えています。
日本の介護福祉士養成学校を卒業した在留資格「介護」をもつ外国人
2つめの受け入れ制度としては、日本の介護福祉士養成学校に留学し、卒業して介護福祉士の資格を取得した外国人は、在留資格「介護」を取得できるというものです。在留資格は本人が望む限り繰り返し更新できるので、永続的に働くことができます。
就職活動に関しては、他の受け入れ制度のような調整機関がないため、介護福祉士養成学校の支援によって、個人で行うことになります。
※アンケート調査/平成30年度 厚生労働省 老人保健健康増進等事業「外国人介護人材の受入れに関するアンケート調査」(平成30年10月1日時点調査)
対人サービスで初。外国人技能実習「介護」とは?
技能実習制度を活用した外国人技能実習生
一方、外国人技能実習制度は、日本の産業現場で一定期間、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)を通じて学んだ技能や技術を母国にもち帰り、母国の経済発展に役立ててもらうことを目的としています。2017年、対人サービスで初となる「介護」についても施行されました。働きながら学ぶという形なので、事業所と雇用関係を結び、1〜2年ごとの試験に合格することで、最長5年間の在留が認められています。
日本の場合、実習生に求める日本語でのコミュニケーション能力のレベルが高く、実習生たちにとって日本語の試験が難関となっています。たとえば台湾などは、語学力試験を実施することもなく、実習生を受け入れています。そのため日本で学びたくても、他国に流れてしまう外国人実習生も少なくないといいます。
あえて日本を選んで学ぶ実習生は、日本が好きだったり、介護先進国である日本で高い技能や技術を身に付けたいという強い志をもって、日本が定めた厳しい語学力試験にもパスしたたいへん意欲的な方々であることを理解しておきたいですね。
外国人技能実習制度は国際貢献の一環として行われているものです。原則として実習終了後は帰国することになっています。そうした本人の立場をよく理解して、有意義な実習期間を過ごせるようあたたかく見守る姿勢も大切だと思います。
なお外国人技能実習生であっても、実習期間中に介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更し、日本で永続的に働くことができるという選択肢もあります。
技能実習生にも開かれた、日本でずっと働く、という選択肢
在留資格「特定技能1号」をもつ外国人
4つめの在留資格「特定技能1号」は、2019年4月から導入された新制度です。
まず自国で技能水準・日本語能力水準を試験等で確認された上で、日本に入国します。介護事業所で最長5年間働いて技術や技能を身につけたら、帰国することになりますが、介護福祉士の国家資格を取得することで在留資格「介護」に切り替えれば、日本で永続的に働くことができるようになります。
今後も外国人介護職員がますます増えていくことを考えると、同じ事業所で長く勤めるベテランの外国人介護職員がいるということは、後進にとっても大きな励みとなるはずです。
外国人職員を受け入れるにあたっては、事業所も、職員の処遇や雇用環境等を見直したり、整備し直すなどの努力が必要になります。このことは、日本人の介護職員にとっても、働きやすい職場であることの目安になるといえるかもしれません。
考えてみよう。外国人職員とともに働く職場について
事業所ではどんな支援を行っている?
日本で働きながら介護を学びたいという意欲はもっていても、家族と離れ、文化や風習も違う土地で働きながら学ぶには、大きな不安や不自由さがあるはずです。介護施設では、外国人介護職員に対してどのような支援を行っているのでしょうか。
たとえばEPA介護職員を雇用している施設の多くでは、住居支援、行政手続きや住まいの契約手続き等の支援、日本語教室等のコミュニケーション円滑化のための支援や、メンタルヘルスケア、文化・風習、信仰への配慮などの生活支援を行っているそうです。
語学を学んできているとはいえ、住まいをはじめ各種契約や手続きなどの作業は、外国人にとってかなりむずかしいものではないでしょうか。日頃の生活に関しても、最初は身近な日本人の支援を必要とする場合が多くあると思います。同僚である日本人職員が、業務として支援に当たる機会も増えてくるでしょう。
また日本人、外国人を問わず、介護職員の処遇・労働環境の改善については、業界全体で取り組まれているテーマで、道半ばであるという事業所もまだまだあると思います。働きやすい職場で誰もがやり甲斐を持って長く勤められる環境づくりを、介護業界全体でめざしていくことも大切ですね。
ともにいい職場づくりを行う、仲間として。
外国人技能実習生を見ていると、むしろ言葉のハンデをカバーしようとするためか、笑顔や表情が豊かで、明るく感じます。やや舌足らずな言葉で丁寧に語りかける様子には、利用者さんもやさしい眼差しで応えていました。
彼らがつくりだす独特な雰囲気や熱心に学ぶ姿勢は、日本人の職員にとっても大きな励みとなります。ともにいい職場づくりを行っていく仲間として日本人が心を開くことで、外国人介護職員の存在は、やがて日本の介護の風景に自然と馴染んでいくことでしょう。
文:十勝 恵子
プロフィール
監修/中谷ミホ(Miho Nakaya)
介護福祉士・ケアマネジャー・社会福祉士
福祉系短大を卒業後、介護職員、相談員、ケアマネジャーとして、障害者支援施設、介護老人保健施設などの介護現場で活躍。現在は介護業界での経験を生かしながら、ライターとして活動しており、介護・福祉に関わる記事を数多く手がける。保育士、福祉住環境コーディネーター3級も取得。

関連記事

|
働き方
| 公開日:2025.04.15 更新日:2025.04.15 |
介護士の給料は今後上がる?給与水準や給与アップの方法を解説
日本は急速に高齢化が進む中で、介護職の需要が高まり続けています。しかし...(続きを読む)

|
働き方
| 公開日:2025.04.15 更新日:2025.04.15 |
未経験でも訪問介護で働ける?仕事内容・必要な資格を解説
訪問介護は高齢者や障害のある方の生活をサポートする重要な仕事です。未経...(続きを読む)

|
働き方
| 公開日:2025.04.15 更新日:2025.04.15 |
ホームヘルパーのやりがいは?仕事の魅力や向いている人の特徴
ホームヘルパー(訪問介護員)は、高齢者や障害を持つ方々の暮らしを支える...(続きを読む)
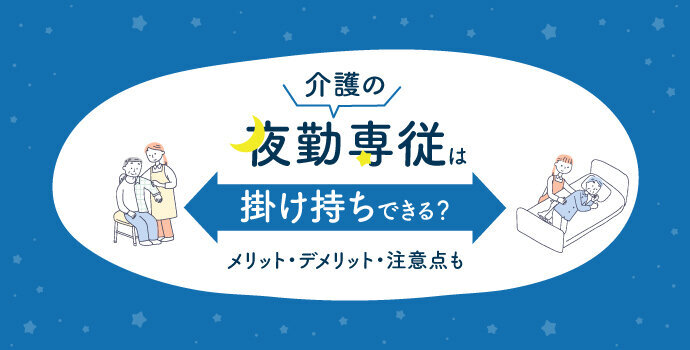
|
働き方
| 公開日:2025.04.15 更新日:2025.04.15 |
介護の夜勤専従は掛け持ちできる?メリット・デメリット・注意点も
介護の夜勤専従として働くことは、安定した収入を得たり、経験を積んだりで...(続きを読む)