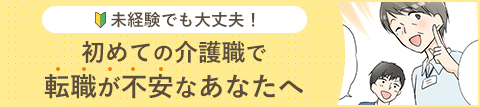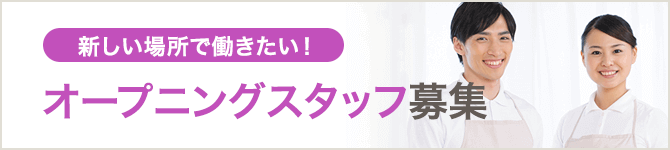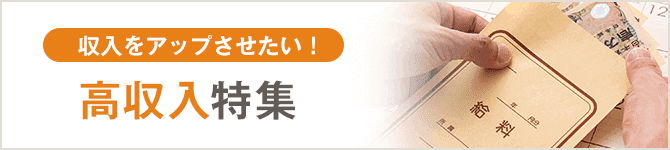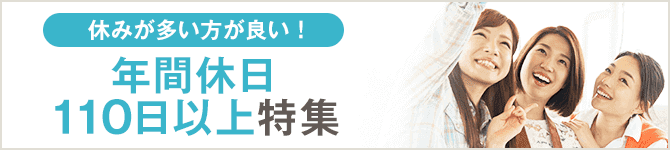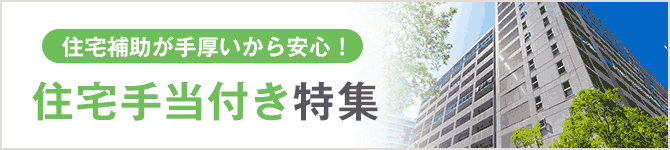ホームヘルパーの仕事内容とは?1日の流れを分かりやすく解説
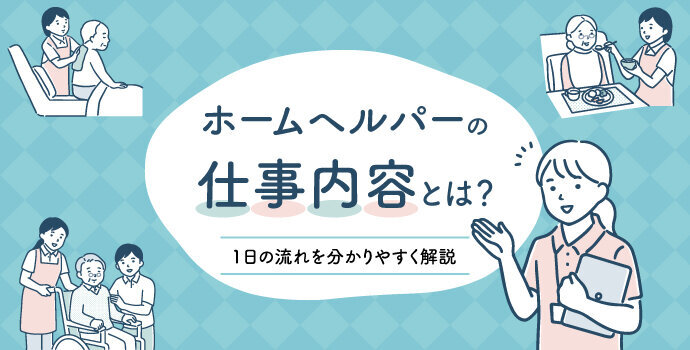
ホームヘルパー(訪問介護員)は、高齢の方や障害のある方が自宅で生活できるように、身体介護や生活援助、通院介助などの業務を通じて自立した生活を支える専門職です。ホームヘルパーになるにあたっては、介護職員初任者研修(旧:ホームヘルパー2級)資格に認定される必要があります。利用者の希望に応じて柔軟なサービスを提供できる場合もありますが、基本的にホームヘルパーは介護保険制度に基づくサービスを提供する仕事のため、制度外のサービスは提供できません。
この記事ではホームヘルパーの仕事内容や必要な資格、1日の流れについて解説します。ホームヘルパーを目指している方は、ぜひこの記事をご一読ください。
目次
1. ホームヘルパー(訪問介護員)とは
ホームヘルパー(訪問介護員)は、高齢者や障害のある方の自宅を訪問し、日常生活のサポートを行う専門職です。主に介護保険制度や障害者総合支援法に基づく介護サービスを提供し、利用者さんが在宅で自立した生活を維持できるよう、身体介護や家事援助を行います。身体介護では食事・入浴・排泄・衣類の着脱などの介助、家事援助では調理・洗濯・掃除・買物などをサポートします。
また、利用者さんやそのご家族に対する精神的ケア、および介護技術の指導も、ホームヘルパーの大切な役割です。単独で行う仕事もありますが、多くの場合、ほかの医療や福祉の専門職と連携しながら進められます。定期的な訪問や夜間対応など、利用者さんの生活時間に合わせた柔軟なサポートが求められる職場の多い仕事です。
(出典:厚生労働省jobtag「訪問介護員/ホームヘルパー」
/
https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/133)
2. ホームヘルパーに必要な資格
ホームヘルパーとして介護や援助などの各業務を行うためには、「介護職員初任者研修」の修了が必要です。かつては「ホームヘルパー2級」という名称でしたが、2013年の介護保険法改正によって変更されました。介護職員初任者研修で介護における基礎的な知識や技術を学び、資格取得後は身体介護や生活援助を行えるようになります。資格取得条件は、厚生労働省が定めるカリキュラムを修了した上で、筆記試験に合格することです。
介護職員初任者研修の内容は、介護職として働くための基本的な知識や技術を幅広くカバーしており、利用者さんに対する支援方法やコミュニケーション技術なども学びます。また、認知症や障害に関する理解も重要なカリキュラムの一部です。
以下は、介護職員初任者研修のカリキュラムの概要です。
・介護職員初任者研修のカリキュラム
| 項目 | 時間 |
|---|---|
| 職務の理解 | 6時間 |
| 介護における尊厳の保持・自立支援 | 9時間 |
| 介護の基本 | 6時間 |
| 介護・福祉サービスの理解と医療との連携 | 9時間 |
| 介護におけるコミュニケーション技術 | 6時間 |
| 老化の理解 | 6時間 |
| 認知症の理解 | 6時間 |
| 障害の理解 | 3時間 |
| こころとからだのしくみと生活支援技術 | 75時間 |
| 振り返り | 4時間 |
| 合計 | 130時間 |
(出典:厚生労働省「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修関係)」
/
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000331389.pdf)
初任者研修修了者になれば、訪問介護員として利用者さん宅での支援が可能になります。また、サービス提供責任者を目指して介護福祉士実務者研修を受ける場合、一部の科目が受講免除されるのも魅力です。ホームヘルパーとしての経験を積むと、さらに上位資格の「介護福祉士」へのステップアップも視野に入ります。
介護福祉士実務者研修とは?働くメリットや資格の取得方法を解説!
2-1. ホームヘルパーと介護福祉士の違い
ホームヘルパーと介護福祉士は、介護者として働く場合の仕事内容に大きな違いはありませんが、資格の性質や役割が異なります。
ホームヘルパーは「介護職員初任者研修」や「介護福祉士実務者研修」を修了すればよく、資格取得のハードルは比較的低めです。一方、介護福祉士は介護系の唯一の国家資格であり、ホームヘルパーよりも専門的な知識と技術が求められます。
また、ホームヘルパーは訪問介護や施設内の支援業務を中心に行い、より現場に近い支援者としての役割を持ちます。対して介護福祉士は職場でリーダー的な役割を担うことが多く、ほかの介護スタッフに指示や指導を行う役割です。また、求人情報でも、資格手当などがつく介護福祉士のほうが給与額や待遇面で優遇される傾向にあります。
(出典:厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要」
/
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/22/dl/r04gaiyou.pdf#page=18)
3. ホームヘルパーの仕事内容|訪問先ですることは?
ホームヘルパーの主な仕事内容は、「身体介護」「生活援助」「通院介助」の3つに大別されます。いずれの仕事も、利用者さんが自宅で安全かつ快適に生活を続けるために欠かせないサポートです。以下では、それぞれの仕事内容を解説します。
3-1. 身体介護
身体介護とは、利用者さんの身体に直接触れて行う介助サービスです。食事・入浴・排泄・着替えなどを介助し、日常生活の基本的な動作を手助けすることで、利用者さんの自立を支援します。
食事介助では、利用者さんが食事を摂取できるようサポートし、誤嚥しないよう姿勢を整えたり、一口の量を調整したりするなどの工夫が必要です。また、入浴介助では、身体の清潔を保つだけでなく、リラックス効果も提供するスキルが求められます。
排泄介助でトイレの補助やオムツの交換を行う際には、利用者さんの尊厳を傷つけないよう細心の注意を払わなければなりません。こういった身体介護には専門的な知識と技術が求められるため、身体介護を行うホームヘルパーには「介護職員初任者研修」以上の資格が必要です。
(出典:厚生労働省「訪問介護(ホームヘルプ)」
/
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group2.html)
(出典:厚生労働省「訪問介護」
/
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001123917.pdf#page=5)
3-2. 生活援助
生活援助は、身体介護以外の日常生活を支援する業務です。主な仕事内容には、料理・掃除・洗濯といった家事のサポートが挙げられます。特に一人暮らしの高齢者や家事を行うのが難しい障害者の方が、自立した生活を続けるために重要な支援です。また、買物の代行や薬の受け取りなども生活援助に含まれます。
ただし、生活援助はあくまでも利用者さんが自立して生活を送れるようサポートするものであり、家事全般を代行するわけではありません。 利用者さんの希望に沿ったサービスを提供しつつも過度なサービス提供は行わず、利用者さんの能力を引き出すことが大切です。
(出典:厚生労働省「訪問介護(ホームヘルプ)」
/
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group2.html)
(出典:厚生労働省「訪問介護」
/
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001123917.pdf#page=5)
(出典:厚生労働省「介護保険と訪問介護」
/
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kaigi/050412/dl/9-3.pdf#page=6)
3-3. 通院介助
通院介助は、利用者さんが医療機関へ通院する際の移動をサポートする業務です。自宅から病院へ向かうときの移動介助や、受診手続きの補助などを行います。歩行が困難な利用者さんに対しては、車椅子の操作や介護タクシーの手配を行うこともあります。ホームヘルパーが自ら運転して病院まで連れて行くことも可能です。ただし、診察室や待機時間のつき添いは原則として行いません。
また、薬の受け取りや必要な手続きのサポートも通院介助の一環 です。通院介助は、利用者さんが定期的に医療を受けるための重要な支援であり、健康維持に大きく貢献します。
(出典:厚生労働省「訪問介護(ホームヘルプ)」
/
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group2.html)
(出典:厚生労働省「訪問介護」
/
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001123917.pdf#page=5)
(出典:総務省「訪問介護における通院等乗降介助」
/
https://www.soumu.go.jp/main_content/000468034.pdf)
4. ホームヘルパーがやってはいけないこと
ホームヘルパーは、介護保険制度に基づくサービスを提供する仕事であり、業務範囲には制約があります。以下は、ホームヘルパーがやってはいけないことの代表的な例です。
身体介護
・医療行為(服薬管理・注射・傷の処置など)
・利用者さんの趣味に関する外出の同行(パチンコ・カラオケなど)
・散髪
・自家用車を使った外出の送迎
生活援助
・利用者さん以外の家族への家事支援(調理・洗濯など)
・大掃除や家具の移動、模様替え
・庭木の手入れやペットの世話
・嗜好品や贈答品の購入
通院介助
・病院内での受診待ち時間中や診察室へのつき添い
・転院のつき添い
そのほか
・金銭管理や金融機関での手続き代行
・単なる話し相手としての同行
これらの行為は介護保険の対象外となるため、ホームヘルパーが行うことはできません。市区町村によってもルールが異なるため、詳しくは職場のある市区町村の条例などを確認してください。
(出典:愛媛県松前町「介護保険 訪問介護の適正な利用について」
/
https://www.town.masaki.ehime.jp/uploaded/life/16521_38283_misc.pdf)
(出典:神戸市介護サービス協会「訪問介護でできること・できないこと」
/
https://kaigo-kobe.net/cms/wp-content/uploads/2022/03/%EF%BC%92%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%93%E3%81%A8.pdf)
5. ホームヘルパーの1日の流れ
ホームヘルパーは1日で複数の訪問先を回るのが基本で、利用者さんの介護状態によっても身体介護や生活援助、通院介助など仕事が多岐にわたります。以下は、ホームヘルパーの1日のスケジュール例です。
・ホームヘルパーの1日の流れ
| 9:00 | 訪問介護事業所に出勤し、1日の訪問スケジュールや連絡事項を共有する |
|---|---|
| 9:30 | 最初の訪問先へ移動。移動手段は車やバイク、自転車など、状況に応じて使い分ける |
| 10:00 | 1件目の利用者さん宅を訪問。掃除や洗濯などの日常生活を支援する。体調の確認や会話を通じた精神的サポートも行う |
| 11:00 | 2件目へ移動する |
| 11:30 | 2件目の訪問先で昼食の配膳や排泄の介助など、身体に直接触れる介助を行う |
| 12:30 | 一度事務所に戻り、午前中の業務を報告する。昼食を取り、午後のスケジュールを確認してから3件目へ移動する |
| 14:00 | 3件目の訪問先で、利用者さんが安全に入浴できるよう配慮しながら入浴をサポートする |
| 15:00 | 4件目へ移動する |
| 15:30 | 最後の訪問先で日用品の買い物への同行や夕食の準備を行う |
| 16:30 | 事務所へ戻る |
| 17:00 | 1日の業務報告と事務作業を行う |
| 18:00 | 次の日の訪問予定を確認し、退社する |
移動時間が多いホームヘルパーは、効率的なスケジュール管理が重要です。忙しいときは、移動の合間に事務作業をこなす場合もあります。
まとめ
ホームヘルパーの仕事には、食事・入浴・排泄などを介助する「身体介護」、料理・掃除・洗濯など生活を支える「生活援助」、通院をサポートする「通院介助」があります。ただし、介護保険制度上のサービスを行う仕事であるため、直接利用者さん本人の援助にならない業務や、日常生活の範囲を超える業務、趣味や嗜好に関する業務はできません。
ホームヘルパーとして現在働いている方・ホームヘルパーを目指している方は、転職にあたってマイナビ介護職をぜひご利用ください。介護業界に精通したキャリアアドバイザーが、過去のキャリアやご希望に合った職場を非公開求人も含めた多数の求人の中から紹介します。
※当記事は2024年9月時点の情報をもとに作成しています
介護・福祉業界の転職事情|仕事の種類・平均給与・おすすめの資格
関連記事

|
働き方
| 公開日:2025.04.15 更新日:2025.04.15 |
介護士の給料は今後上がる?給与水準や給与アップの方法を解説
日本は急速に高齢化が進む中で、介護職の需要が高まり続けています。しかし...(続きを読む)

|
働き方
| 公開日:2025.04.15 更新日:2025.04.15 |
未経験でも訪問介護で働ける?仕事内容・必要な資格を解説
訪問介護は高齢者や障害のある方の生活をサポートする重要な仕事です。未経...(続きを読む)

|
働き方
| 公開日:2025.04.15 更新日:2025.04.15 |
ホームヘルパーのやりがいは?仕事の魅力や向いている人の特徴
ホームヘルパー(訪問介護員)は、高齢者や障害を持つ方々の暮らしを支える...(続きを読む)
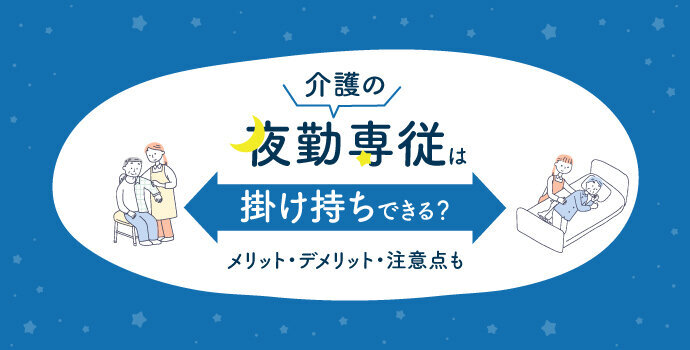
|
働き方
| 公開日:2025.04.15 更新日:2025.04.15 |
介護の夜勤専従は掛け持ちできる?メリット・デメリット・注意点も
介護の夜勤専従として働くことは、安定した収入を得たり、経験を積んだりで...(続きを読む)