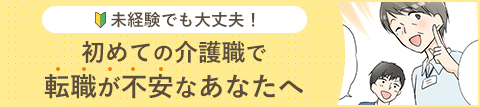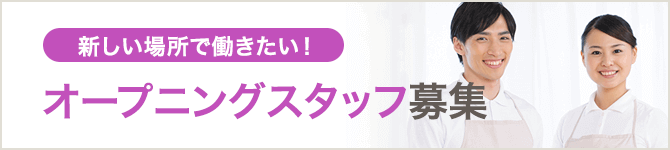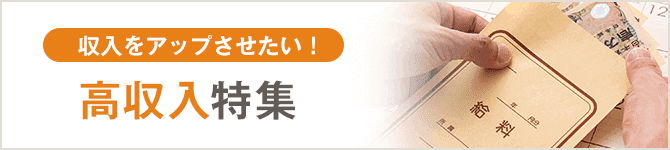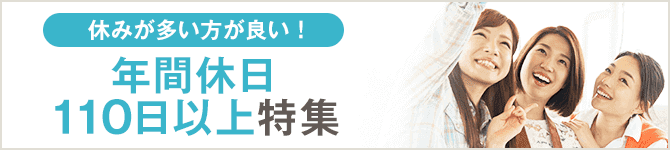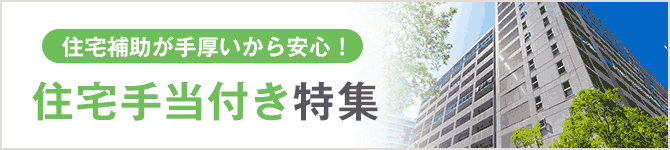デイサービスの生活相談員とは?仕事内容や必要な資格を解説
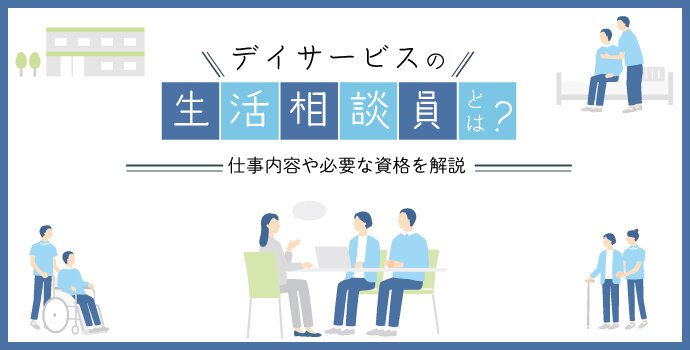
介護事業所には、介護老人福祉施設や介護老人保健施設、短期入所生活介護施設など、多様な形態がありますが、いずれも1名以上の生活相談員の配置が必要とされています。規模が小さな介護事業所であれば、生活相談員だけでなく介護職員として、介護業務を兼任することもあるでしょう。また、経験年数を重ねれば、生活相談員の仕事に付随してマネジメント業務を担うこともあります。
当記事では、介護事業所の中でもデイサービスで働く生活相談員(ソーシャルワーカー)の仕事内容や1日のスケジュール例、生活相談員になるために必要な資格について紹介します。
目次
1. デイサービスで働く生活相談員(ソーシャルワーカー)とは?
デイサービスにおける生活相談員(ソーシャルワーカー)とは、主に高齢者や障がい者の方などが、自宅で自立した生活を送ることができるように支援する専門職です。生活相談員は、単に「相談員」と呼ばれることもあり、ソーシャルワーカーという言葉も一般的に普及しています。
デイサービスでは、事業所ごとに専従の生活相談員を1名以上配置することが、法令により定められています。また生活相談員は、国家資格の「社会福祉士」か「精神保健福祉士」の資格を取得していることが一般的です。
(出典:厚生労働省「参考資料3 参考資料(通所介護・療養通所介護)」
/
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000168705.pdf)
(出典:厚生労働省 job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))「福祉ソーシャルワーカー - 職業詳細」
/
https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/409)
2. デイサービスで働く生活相談員の仕事内容
デイサービスで働く生活相談員の仕事は、以下のように多岐にわたります。
・調整業務
生活相談員は、デイサービスの利用者さんとその家族はもちろん、ケアマネジャーやほかの医療施設・介護施設と、こまめに連携する必要があります。各種会議やミーティングに参加し、利用者さんの状況や進行状況を共有することも業務の1つです。
・契約業務
生活相談員は、利用者さんやその家族との契約業務も行います。具体的には、デイサービスの施設の案内や利用規約の説明、利用契約の締結作業なども担当します。
・相談業務
生活相談員は、デイサービスの事業所において窓口的な役割を果たします。利用者さんやご家族からの相談を受け付け、問題解決のためにアドバイスやサポートを行うのも仕事の1つです。適切なサポートができるように、サービスや介護に関する深い知識を日々身に着けることが大切です。
2-1. 介護職と兼務できる
生活相談員は介護職として兼務することも可能です。つまり、生活相談員の仕事を行いながら、介護職として一緒に利用者さんのサポートをすることができます。
ただし、生活相談員と介護職を兼任できるのは、以下のように生活相談員の配置基準を見たいしている場合のみとなります。
★デイサービスにおける生活相談員の配置基準
事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従で1以上
(※生活相談員の勤務時間数としてサービス担当者会議、地域ケア会議等も含めることが可能。)
(引用:厚生労働省「参考資料3 参考資料(通所介護・療養通所介護)」
/
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000168705.pdf引用日2023/05/11)
同じ厚生労働省の資料によれば、デイサービスの利用者数や費用額は年々増加しており、日本の中でもニーズが高い施設であることが分かります。そのため、生活相談員としての仕事を行いながら、介護領域でのサポートもできる方は、どの職場でも重宝されるでしょう。
3. デイサービスで働く生活相談員の1日スケジュール
デイサービスで働く生活相談員の1日スケジュールは、事業所ごとによって異なります。ただ、日中は基本的に利用者さんの対応を行い、夕方の送迎が終わった後に事務作業を片付けることが一般的です。
【デイサービスで働く生活相談員の1日の仕事の流れ】
| 時刻 | 仕事内容 |
|---|---|
| 8:00 | 出勤、1日の準備 ・デイサービスに出勤し、その日のスケジュールや利用者さんの状況を確認する ・ほかのスタッフとの簡単なミーティング・朝礼を開き、共有事項などをシェアする |
| 9:00 | 利用者さんの送迎・受け入れ ・デイサービスセンターに到着する利用者さんを迎える ・利用者さんのその日の体調や気分を確認したり、特別な要望やニーズがある利用者さんの対応を行ったりする |
| 10:00 | 連絡・調整業務 ・利用者さんの個別援助計画を作成・更新する ・ほかの医療施設・介護施設と電話・メールなどで連携しあう |
| 11:00 | 相談業務 ・利用者さんやその家族との個別の相談を実施する ・支援対象者さんとの面談予定を確認する ・ケアマネジャーと一緒に、利用検討している方の施設案内やサービス内容の説明なども行う |
| 12:00 | 昼食 ・休憩時間 ・事業所によっては利用者さんと一緒に食べたり、生活相談員が調理や配膳を手伝ったりすることもある |
| 13:00 | 契約業務 ・新たにデイサービスを利用することになった利用者さんやご家族との契約手続きを行ったり、既存の契約の更新を行ったりする |
| 14:00 | 相談業務 ・事業所によっては、相談者さんの自宅を訪問して、本人やご家族と面談することもある |
| 15:00 | 記録・報告 ・1日の相談記録をまとめる ・翌日の相談業務の準備などをする |
| 16:00 | 利用者さんの送迎・お見送り ・事業所によっては生活指導員が送迎バスに同乗し、利用者さんの自宅まで送迎することもある |
| 17:00 | 事務作業・ミーティング ・施設の運営面に関するミーティングや、利用者さんの状態に関する情報共有を行う ・その日まだ片ついていない事務作業・パソコン作業などを実施する |
| 18:00 | 退勤 ・忙しい日は30分~1時間程度残業することもある |
上記はあくまで参考例ですので、事業所ごとに1日のスケジュールは異なります。また、介護業務と兼任している場合は、午前・午後にそれぞれプログラムがあるので、入浴・機能訓練・レクリエーションなども担当することになるでしょう。
4. デイサービスで働く生活相談員に求められる資格
生活相談員になるためには、社会福祉や介護に関する資格を取得しておく必要があり、一般的には、社会福祉士や精神保健福祉士が生活相談員になるための資格として想定されています。
ただし、社会福祉士か精神保健福祉士が必要という明確な規定があるわけではありません。たとえば、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準では、下記のように「これと同等以上の能力を有すると認められる者」と抽象的に規定されています。
■特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第五条2項
生活相談員は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(引用:e-Gov法令検索「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」
/
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411M50000100046引用日2023/05/11)
また、自治体によっても要求される資格が異なっています。以下は和歌山県と北海道の例です。
◆和歌山県の場合
(1)社会福祉主事任用資格
(2)社会福祉士
(3)精神保健福祉士
(4)介護福祉士
(5)介護支援専門員
(6)その他同等以上と認められる能力を有する者
(※介護業務の実務経験が1年以上ある者)
(引用:和歌山県「生活相談員の資格要件について」
/
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/998/soudanninn.pdf引用日2023/05/11)
和歌山県では、国の基準が曖昧であるとして、和歌山県として上記の解釈を明示しています。
◆北海道の場合
(1)社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者
→社会福祉主事任用資格、社会福祉士、精神保健福祉士とする。
(2)介護支援専門員
(3)社会福祉施設等において、実務経験が1年以上ある介護福祉士
(4)社会福祉施設等において、介護に係る計画の作成に関する業務、または相談・援助業務
の実務経験が2年以上ある者
(引用:北海道「生活相談員の資格要件について(通知)」
/
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/7/6/0/2/0/6/9/_/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E7%9B%B8%E8%AB%87%E5%93%A1%E3%81%AE%E8%B3%87%E6%A0%BC%E8%A6%81%E4%BB%B6%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf引用日2023/05/11)
上記のように、北海道と和歌山県でも要件が多少異なることが分かります。社会福祉主事任用資格、社会福祉士、精神保健福祉士を取得している場合は、実務経験が問われないケースが多く見られます。
以下では、生活相談員になるために取得を検討してみたい資格を紹介します。
4-1. 社会福祉士
社会福祉士は、日常生活を送るのになんらかの困難や問題ごとがある人の相談に応じ、その援助をする福祉の専門家です。 社会福祉士及び介護福祉士法に基づく国家資格となります。
社会福祉士になるには、年に1回実施される国家試験に合格し、登録を受ける必要があります。国家試験の受験資格は、福祉系大学ルート・短期養成施設ルート・一般養成施設ルートの3つがあります。
4-2. 精神保健福祉士
精神保健福祉士も国家資格の1つであり、精神障害者の保健と福祉に関する専門的な知識と技術を持ち、相談・援助業務を行う仕事です。精神保健福祉士は、精神科病院や精神保健福祉センター、保健所、企業や学校など、多岐にわたる職場で精神障害者やその家族の社会復帰支援・生活支援を行います。
精神保健福祉士になるには、大学や専門学校で指定された科目を履修し、国家試験に合格する必要があります。
4-3. 社会福祉主事任用資格
社会福祉主事任用資格とは、社会福祉法に基づく任用資格の1つです。社会福祉主事任用資格を持つ人は、公務員試験に受かれば、社会福祉主事として公的な福祉事務所や社会福祉施設などで働けます。 社会福祉の援護や育成、更生などの業務に携わることができる仕事です。
社会福祉主事任用資格を取得するためには、大学・短期大学卒業ルートや、社会福祉士もしくは精神保健福祉士の国家資格を取得するルート、講習会ルートなど、いくつかの方法があります。社会福祉主事任用資格を取得するための試験などはありません。
4-4. 介護支援専門員(ケアマネジャー)
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、要介護者や要支援者からの相談に応じて、介護サービスの計画(ケアプラン)を作成するスペシャリストです。関係者間の連絡や調整も行い、利用者さんの自立した日常生活を支援します。
介護支援専門員(ケアマネジャー)に関しては、自治体によって生活相談員になれるか否かは異なります。 実際、国の基準では生活相談員になれる資格の中に、介護支援専門員が含まれるとは明確には言えません。一方で、和歌山県や北海道などのように、自治体の判断によっては介護支援専門員を生活相談員になれる資格に含めていることもあります。
まとめ
生活相談員の仕事が向いている人にとって、デイサービスでの仕事は大変やりがいがあります。また、生活相談員は高齢者施設で働いている人が多く、デイサービスでの需要が高くなっています。基本的には相談業務がメインとなるので、日勤のみで夜勤はなく、平日出勤・土日休みのことがほとんどです。ただし勤務先によっては、異なるケースもあるので求人情報をしっかりと確認するようにしましょう。
マイナビ介護職では、デイサービスの求人や生活相談員の求人も多数保有しています。マイナビ介護職のサイト上で見つからない場合は、キャリアアドバイザーからも直接紹介が可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
※当記事は2023年7月時点の情報をもとに作成しています
生活相談員の求人・転職一覧ページ
介護・福祉業界の転職事情|仕事の種類・平均給与・おすすめの資格
関連記事

|
資格
| 公開日:2025.04.15 更新日:2025.04.15 |
ホームヘルパーとは?必要な資格や介護福祉士との違いを解説
ホームヘルパーは、高齢者や障害者が自宅で安心して生活できるよう、居宅を...(続きを読む)
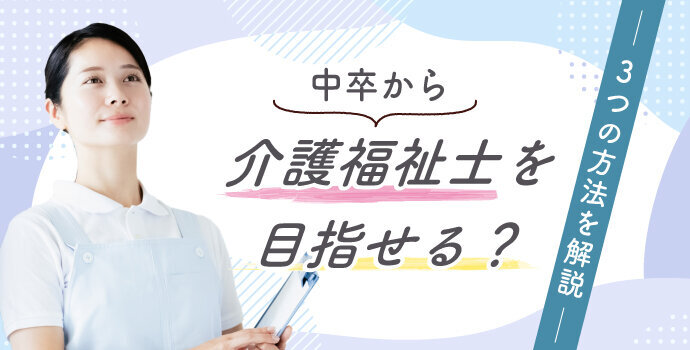
|
資格
| 公開日:2024.12.17 更新日:2024.12.17 |
中卒から介護福祉士を目指せる?3つの方法を解説
介護福祉士の資格を取得するためには、いくつかの条件があります。介護福祉...(続きを読む)

|
資格
| 公開日:2024.08.21 更新日:2024.08.21 |
介護福祉士の資格でできる仕事には何がある?主な転職先について解説
介護の専門資格である介護福祉士を取得することで、無資格の状態に比べて、...(続きを読む)
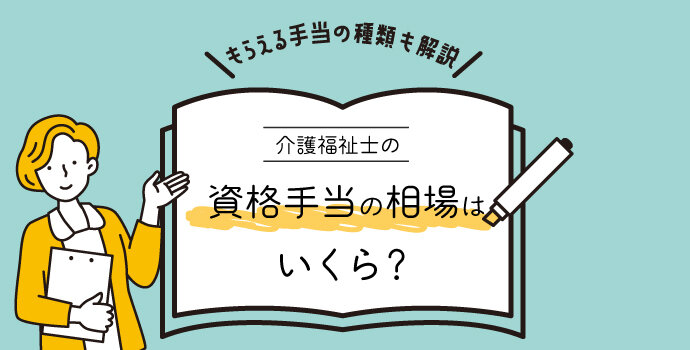
|
資格
| 公開日:2024.08.21 更新日:2024.08.21 |
介護福祉士の資格手当の相場はいくら?もらえる手当の種類も解説
基本給以外の給料アップにつながる手当として、資格手当があります。介護福...(続きを読む)