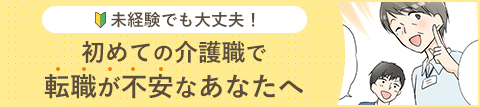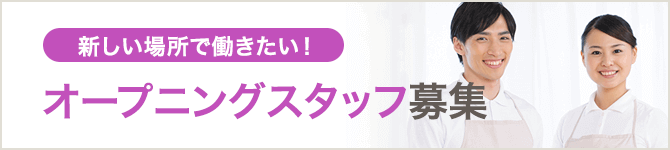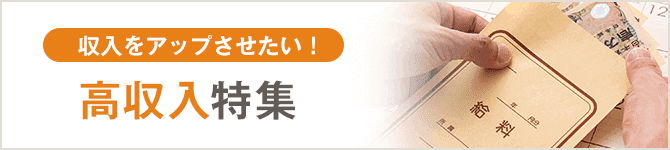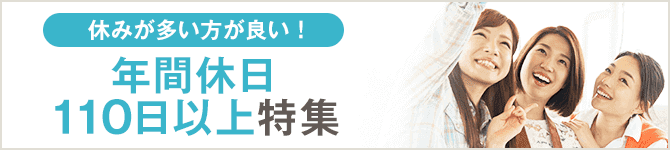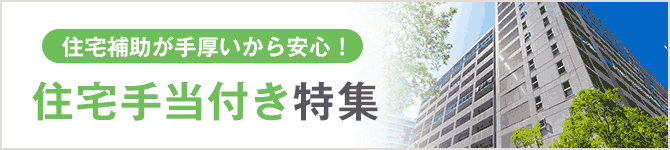看護師が介護福祉士とのダブルライセンスを目指すメリットとは?
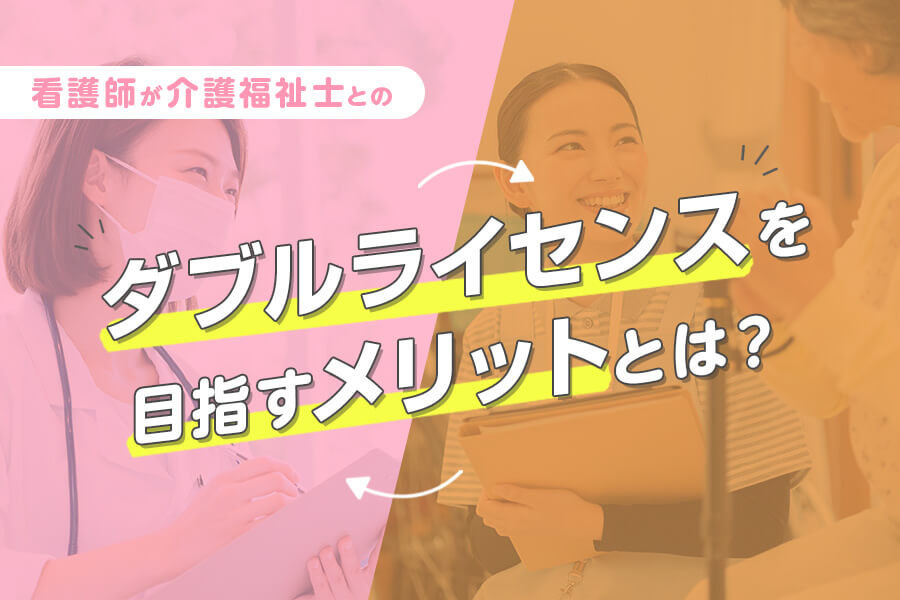
看護師と介護福祉士はどちらも国家資格であり、就職や転職にはライセンスを取得する必要があります。高齢社会の今日、看護・介護の現場では、双方の垣根を超えて看護師と介護福祉士の両方の知識を持つ人材のニーズが高まっています。特に介護業界で働く介護福祉士の方が転職やキャリアアップを考えたときに、看護師のライセンス取得を希望する方が増えているのが現状です。
この記事では、看護師と介護福祉士のダブルライセンスを目指すメリットと、それぞれの資格・仕事内容の違い、展望と現在の問題について解説します。看護師と介護福祉士のダブルライセンスを検討中の方は、ぜひご一読ください。
目次
1. 看護師と介護福祉士の違い
看護師と介護福祉士は、専門資格を取得して支援が必要な方をサポートするといった点では共通していますが、資格取得の流れや仕事内容などに違いがあります。ダブルライセンスを目指し、就職・転職の幅を広げたい場合、それぞれの違いについても理解しておきましょう。
ここでは、看護師と介護福祉士の資格と仕事内容について解説します。
1-1. 資格の違い
看護師と介護士福祉士では、資格の条件や取得の流れに違いがあります。
看護師の資格を取得するには、3年制の看護学校や看護学科を有する短大、または4年制の看護大学を卒業後、看護師国家試験に合格すると資格を取得できます。准看護師として働きながら看護師国家試験を受験する方法もあり、自身の状況に応じた選択が可能です。
介護福祉士の場合は、養成施設や福祉系の高校を卒業、もしくは介護士として3年間の実務経験を積んだ上で実務者研修を修了すると、介護福祉士国家試験の受験資格を得られます。高齢者などをケアする介護現場では、介護福祉士の資格があると就職・転職に有利です。
(出典:福祉医療機構「看護師」
/
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/fukushiworkguide/jobguidejobtype/jobguide_job34.html)
(出典:福祉医療機構「介護福祉士」
/
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/fukushiworkguide/jobguidejobtype/jobguide_job02.html)
1-2. 仕事内容の違い
看護師と介護福祉士では、主に医療行為を行えるかどうかに違いがあります。
看護師の仕事内容は、大きく分けて下記の3つです。
・医師が患者さんを診察する際のサポート
・障害を持つ人などが日常生活を送るためのサポート
・健康的な身体づくりに関する教育
看護師は対象者の年齢に関係なく、病気やケガをした患者さんの検温、血圧、脈拍の測定を行います。また、採血、注射、点滴、投薬などの医療行為を医師の代わりに行うことも可能です。
看護師は認定看護師と専門看護師の2種類に分けられます。認定看護師とは、特定の看護分野において専門知識や優れた技術を持つ看護師のことです。一方、専門看護師とは、専門看護分野で優れた看護能力を有する看護師を示します。
看護師が活躍できる職場は、下記の通りです。
・病院
・診療所、クリニック
・有料老人ホーム
・介護施設
・訪問看護事業所
・保健所
・学校 など
(出典:福祉医療機構「看護師」
/
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/fukushiworkguide/jobguidejobtype/jobguide_job34.html)
一方で、介護福祉士は、寝たきりの高齢者や障害を持つ人など、一人で日常生活を送ることが困難な人を対象に介護サポートをします。また、介護が必要な人の相談に対応することも介護福祉士の仕事です。
介護福祉士は利用者さんの食事、入浴、排泄などの身体介護から、状態の観察、服薬の介助、通院時の付き添い、救急時の対応までを支援します。また、介護福祉士は利用者さんの人権を尊重し、生命の安全を確保しながら、利用者さんができることをなるべく自分自身で行えるようにサポートします。
このように、介護福祉士の仕事内容は多岐にわたりますが、採血や注射などの医療行為をすることはできません。
介護福祉士の職場としては、下記が挙げられます。
・訪問介護事業所
・居宅介護支援事業所
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・通所介護事業所
・障害者施設 など
(出典:福祉医療機構「介護福祉士」
/
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/fukushiworkguide/jobguidejobtype/jobguide_job02.html)
2. 【看護師×介護福祉士】ダブルライセンスのメリット3つ
ダブルライセンスとは、2つ以上の資格を持つ労働者のことです。医療や介護の現場では、専門職のライセンスを取得していることが労働の条件となっているケースもあります。
看護師と介護福祉士のダブルライセンスを取得した方は、看護師または介護福祉士の一方のライセンスを取得している方と比べてさまざまなメリットが得られます。ここでは、看護師と介護福祉士のライセンスを持つ3つのメリットを紹介します。
2-1. 介護の知識が求められる現場で対応できるようになる
医療業界では、看護の知識だけでは対応が難しい業務が多数発生することがあります。看護に加えて介護の知識も持っていると、介護の知識が必要な現場でも対応することが可能です。
また、看護と介護の知識の両方を持っていると、さまざまな場面に対応できることから業務の幅も広がります。対応できる業務が増えると技術の経験値も高まり、施設では一目置かれる存在になれるでしょう。
2-2. 就職・転職に役立つ
介護福祉士は看護師のように医療行為ができないため、転職を希望するケースは珍しくありません。介護福祉士が転職の際に看護師のライセンスを取得しておくと、医療行為も担当できるため仕事の幅が増え、就職先を探しやすくなります。 逆もまた然りで、看護師が転職する際にも介護福祉士のライセンスを取得することで求人を見つけやすくなるでしょう。
また、看護師と介護福祉士の2つのライセンスを取得することで就職・転職の幅が広がれば、スムーズなキャリア形成にもつながります。老年看護では看護師の知識だけでは不十分なことも多く、介護福祉士の知識があるとさまざまな場面で柔軟な対応が可能です。
介護現場では介護職の人手が不足しています。高齢者施設においてダブルライセンスの介護スタッフは、介護士と看護師の業務が兼任できるため、施設に重宝されるでしょう。 ダブルライセンスの方は、就職・転職に有利な条件の求人が散見されます。
2-3. 昇進・昇給につながる
介護・看護業界では、ライセンスの取得数に応じて昇給するシステムを採用している職場も多く、ダブルライセンスになると昇給の可能性が高まります。 例として、2022年12月の時点で介護業界では看護師としてライセンスを持っている方の平均月給は、介護職として働いている方の平均月給を約54,700円上回っています。
(出典:厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要」
/
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/22/dl/r04gaiyou.pdf#page=16)
また、介護の現場では専門知識を持った人材の確保を目指しており、看護師と介護福祉士のダブルライセンスは特に求められている傾向です。 知識が豊富な人材を確保するために好待遇を提示する求人情報も多く、好待遇の施設などで働ければ、キャリアアップも目指しやすいでしょう。
3. 【看護師×介護福祉士】ダブルライセンスのデメリット3つ
ただし、現在看護師として病院で働いている方が介護福祉士資格を取得して介護施設で働く場合、デメリットと感じる部分が存在します。介護福祉士資格を取得するためには時間もお金も必要になるため、デメリットを知った上で将来設計をするのが大切です。
3-1. 再就職の場合給料が下がる恐れがある
厚生労働省の「令和4年賃金構造基本統計調査」では、看護師の平均月給は35万1600円、平均ボーナスは86万2100円です。対して、「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」では、介護福祉士のボーナスを含む平均月給は33万4,510円であり、介護福祉士のほうが給与が低いと言えます。
年収に換算した場合の差は、以下の通りです。
【介護福祉士と看護師の年収の違い(2022年)】
| 介護福祉士の平均年収 (月収×12か月で計算) |
看護師の平均年収 |
|---|---|
| 約397万円 | 約508万円 |
(出典:厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」
/
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/22/dl/r04kekka.pdf#page=166)
(出典:厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査」
/
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040029185)
そのため、転職によって賃金が低下する可能性があります。ただし、介護施設では夜勤がなく、業務プレッシャーが低いほか、スキルやキャリアによって昇進や昇給しやすい点がメリットです。下がった給与以上に負担が小さくなった、あるいは自分の能力を評価されやすくなったと感じる方も一定存在する ため、完全にデメリットとは言えません。
また、現在介護福祉士の方が看護師資格を取得する場合は、賃金アップが見込めます。
3-2. 介護業務は体力的な負担がかかりやすい
介護士の仕事は体力的に負担が大きく、限界を感じている方も多く存在します。介護労働安定センターの2022年調査では、介護職の29.8%が不安として「身体的負担が大きい(腰痛や体力に不安がある)」と回答しています。 特に、入所型の施設および居住型の施設では身体的な負担に悩まされる方が多く、体力に不安がある方にとってはデメリットです。
(出典:介護労働安定センター「介護労働者の就業実態と就業意識調査」
/
https://www.kaigo-center.or.jp/report/pdf/2023r01_chousa_cw_kekka.pdf#page=73)
介護職では入浴介助、排泄介助などの業務があり、利用者さんの身体を支える、持ち上げるなどの業務内容があります。中腰になりおむつを替える際に、腰に負担がかかり慢性的な腰痛に悩まされる介護福祉士は少なくありません。施設によっては夜勤の業務を任されることもあり、予想以上に体力的な負担が大きくなるでしょう。
ただし、介護施設の場合は病院と違い、夜勤がない施設も存在します。夜勤でかかる心身の負担が大きいと感じている場合、介護職は選択肢の1つとなります。
3-3. 看護業務にブランクができる
介護士として介護施設で働く場合は、看護師経験にブランクができるため、最先端の医療技術のスキル、医療知識を身につけにくくなります。 これまで行っていた、注射や点滴などの医療行為のスキルが低下する可能性もあります。
ブランクが長くなると看護師へ戻りにくくなるため、復職するには改めて勉強が必要です。復職に不安がある場合には、各都道府県のナースセンターが行う「復職支援研修」に相談をしましょう。
都道府県のナースセンターでは、就業、復職を希望する看護職に向けた各種支援を行っております。
求人施設の紹介・あっせんを行う職業紹介事業だけでなく、長期離職から復帰を希望する看護職向けの復職支援研修・実習を行っております。
また、就業支援にとどまらず、子育て中の看護職や定年退職者同士が交流できる交流カフェなどの企画を行っております。
各都道府県の研修やイベントの詳細については、eナースセンターのお知らせ検索をご参照ください。
(引用:公益社団法人日本看護協会「情報提供」
/
https://www.nurse.or.jp/nursing/nc/koyo/index.html 引用日2024/02/11)
また、看護師から介護福祉士へ転職するとキャリアがリセットされる点にも注意が必要です。 新しい仕事や業界について1から学ぶ必要があり、人間関係も新しく築いていくため、ストレスを抱える可能性もあります。
4. 看護師が介護福祉士の資格を取得する流れ
看護師が介護福祉士の資格を取得するためには「養成施設ルート」「福祉系高校ルート」「実務経験ルート」があります。また、フィリピン、ベトナム、インドネシア国籍の方は「経済連携協定(EPA)ルート」で資格取得が可能です。
各ルートの詳細は、以下の通りです。
4-1. 養成施設ルート
養成施設ルートとは、養成施設を卒業して介護福祉士になる方法 で、以下4パターンのルートがあります。
・介護福祉士養成施設(2年以上)を卒業
・福祉系大学にて指定科目を履修し、その後介護福祉士養成施設(1年制)を卒業
・社会福祉士養成施設等を卒業し、その後介護福祉士養成施設(1年制)を卒業
・保育士養成施設等を卒業し、その後介護福祉士養成施設(1年制)を卒業
(出典:公益社団法人日本介護福祉会「養成施設ルート図」
/
https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_05.html)
上記のルートを辿り、2016(平成28)年度までに介護福祉士養成施設を卒業していれば、介護福祉士の資格を取得(登録)できます。一方で2027(令和9)年度以降に卒業した場合は、卒業後「介護福祉士試験」の受験が必須です。
2017(平成29)年~2026(令和8)年度に介護福祉養成校を卒業した場合、上記2パターンと少し違う流れになります。
| 卒業後に受験する場合 |
|---|
| 筆記試験を受ける 合格の場合は、介護福祉士資格取得 不合格の場合は「受験しない場合」と同じ |
| 卒業後に受験しない場合1 | 卒業後に受験しない場合2 |
|---|---|
| 介護福祉士資格取得 (卒業後5年間の期限付き登録) ↓ 実務経験5年(継続勤務に限る) ↓ 介護福祉士資格取得 |
介護福祉士資格取得 (卒業後5年間の期限付き登録) ↓ 期限中に筆記試験再受験 ↓ 介護福祉士資格取得 |
(出典:公益社団法人日本介護福祉会「養成施設ルート図」
/
https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_05.html)
4-2. 福祉系高校ルート
文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した福祉系高校、もしくは特例高校を卒業した場合、以下3つのパターンで介護福祉士資格取得が可能 です。
| 平成21年度以降の入学者 |
|---|
| 筆記試験を受ける(実技試験は免除) ↓ 合格後、介護福祉士資格取得 |
| 平成20年度以前の入学者 | 平成20年度以前の入学者 |
|---|---|
| 受験申込時に 「介護技術講習または介護過程・介護過程III」を受ける ↓ 筆記試験(実技試験免除) ↓ 合格後、介護福祉士資格取得 |
筆記試験 ↓ 実技試験 ↓ 合格後、介護福祉士資格取得 |
| 特例高校などを卒業 | 特例高校などを卒業 |
|---|---|
| 実務経験9か月以上 ↓ 受験申込時に 「介護技術講習または介護過程・介護過程III」を受ける ↓ 筆記試験(実技試験免除) ↓ 合格後、介護福祉士資格取得 |
実務経験9か月以上 ↓ 筆記試験 ↓ 実技試験 ↓ 合格後、介護福祉士資格取得 |
(出典:公益社団法人日本介護福祉会「養成施設ルート図」
/
https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_05.html)
4-3. 実務経験ルート
実務経験ルートは、実務経験(3年以上介護等の業務に従事しており、実務者研修を修了した方)を行った方に介護福祉士の受験資格を与えるルート です。
受験資格の実務経験は、必要な就労期間と日数が決められています。従業期間と従事日数は「3年以上(1095日以上)かつ540日以上」 です。必要期間と日数にプラスして「実務者研修(EPA介護福祉士候補者以外)または介護職員基礎研修・喀痰吸引等研修」のどちらかの研修修了も必要です。
要件を満たした場合、介護福祉士試験の筆記試験に合格すれば介護福祉資格を取得できます。
4-4. 経済連携協定(EPA)ルート
経済連携協定とは、貿易の自由化、投資、人の移動、知的財産の保護など、さまざまな分野で協力の要素を含む経済関係の強化を目的とする協定を指します。日本で雇用契約を締結した施設で、日本の介護福祉士国家試験の合格を目的とした研修を受けながら就労するインドネシア人、フィリピン人、ベトナム人が対象です。
国内で現在看護師として働いている方が介護福祉士を目指すルートとしては「養成施設ルート」「実務経験ルート」が現実的です。
5. 看護師資格を取得していることで免除される内容
看護師資格取得者として介護の職場で仕事をしていても、介護福祉士の資格取得のための「実務経験の免除」「養成施設の期間短縮」などは受けられません。 医師、看護師、准看護師は「主たる業務が介護等の業務と認められない職種」に該当します。
ただし、以下の場合は実務経験として算入でき、受験の資格者となります。
1、職種の兼務について
・介護等の業務とそれ以外の業務を兼務している事実が、辞令等で明確であって、主たる業務が介護等の業務である場合に限り対象となります。
・施設長または事業所の長が、介護等の業務を兼務している場合、介護等の業務に従事した日数に限り対象となります。
2、代表者の自己証明について
実務経験証明書の「代表者」欄が受験申込者自身である場合、受験申込者自身が代表者であること、実務経験の対象となる事業を行なっていることが確認できる「法人の履歴事項全部証明書」の原本を必ず提出してください。
なお、この場合、「証明書作成者」欄は、受験申込者以外の第三者が作成するようにしてください。
(引用:公益社団法人日本介護福祉士会「実務経験の範囲」
/
https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_09.html引用日2024/02/11)
5-1. 今後ダブルライセンスが容易になる?「共通基礎課程制度」の議論
ただし、現在は共通基礎課程制度という、1つ目の資格取得者が2つ目の資格取得に向けた過程に入る際に、一定の科目の履修が免除される資格制度が検討されています。 共通基礎課程制度は、看護師と介護福祉士の医療福祉系の教育課程を共通知識として受講を免除することで、双方のライセンス取得のための時間を大幅に短縮することが目的です。
これからの高齢社会に対して、医療や福祉サービスを支えるために、人材を確保して社会保障制度が持続できるようにするために、共通基礎課程制度は有用です。キャリアアップを目指す方にも、魅力のある制度となるでしょう。
6. 介護福祉士国家試験の概要
介護福祉士国家試験(国家資格)を受験するために必要な手数料や試験科目、合格基準や合格率など資格の取得方法を解説します。
介護福祉国家試験の概要
| 試験日 第37回(令和6年度・予定) |
・筆記試験:令和7年1月下旬 ・実技試験:令和7年3月上旬 |
|---|---|
| 受験申込み受付期間 | ・令和6年8月上旬から9月上旬 |
| 手数料(第36回) | ・18,380円 |
| 試験地(筆記試験) | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
| 試験地(実技試験) | 東京都、大阪府 |
| 試験科目(第36回の筆記試験) | ①人間の尊厳と自立、 ②人間関係とコミュニケーション、 ③社会の理解、 ⑨介護の基本、 ⑩コミュニケーション技術、⑪生活支援技術、 ⑫介護過程、 ④こころとからだのしくみ、 ⑤発達と老化の理解、 ⑥認知症の理解、 ⑦障害の理解、 ⑧医療的ケア、 ⑬総合問題 |
| 試験科目(第36回の実技試験) | 介護等に関する専門的技能 |
| 合格基準(筆記試験) | ア 問題の総得点の60%程度を基準として、問題の難易度で補正した点数以上の得点の者。 イ アを満たした者のうち、以下の試験科目11科目群すべてにおいて得点があった者。 [1] 人間の尊厳と自立、介護の基本 [2] 人間関係とコミュニケーション、コミュニケーション技術 [3] 社会の理解 [4] 生活支援技術 [5] 介護過程 [6] こころとからだのしくみ [7] 発達と老化の理解 [8] 認知症の理解 [9] 障害の理解 [10] 医療的ケア [11] 総合問題 |
| 合格基準(実技試験) | 課題の総得点の60%程度を基準として、課題の難易度で補正した点数以上の得点の者を実技試験の合格者とする。 |
| 合格率 | 第35回の合格率は84.3% |
(引用:公益社団法人日本介護福祉士会「試験概要」
/
https://www.sssc.or.jp/kaigo/gaiyou.html引用日2024/02/11)
(引用:公益社団法人日本介護福祉士会「合格基準」
/
https://www.sssc.or.jp/kaigo/kijun/kijun_02.html引用日2024/02/11)
筆記試験は全国35か所で行っていますが、実技試験は東京都と大阪府の2か所になるため注意しましょう。試験は午前の部、午後の部に分けられています。
過去の試験問題は、マークシート方式で配点は1問1点でした。合格するには、筆記試験で75点以上をとらなければなりません。近年の合格率は70%程ではありますが、油断をせずにしっかりと試験対策を行いましょう。
まとめ
看護師と介護福祉士のダブルライセンス取得者の求人は、今後も高い需要が予想されます。どちらのライセンスも現在の日本社会には不可欠であり、ダブルライセンスの方は好条件で就職・転職できる可能性が高まります。
看護師が介護福祉士のライセンスを取得することで、さらに専門的なケアを提供することが可能です。看護の現場においても同様に、専門的な知識や技術を習得すれば患者さんの状態を総合的に把握できるようになるため、適切なケアを行えるようになります。
マイナビ介護職では、キャリアアドバイザーが求職者様の希望などをヒアリングし、ベストな求人情報を提供しております。また、面接対策や入社後のサポートなども対応していますので、介護業界への就職・転職をご希望の方は、ぜひマイナビ介護職にご相談ください。
※当記事は2024年2月時点の情報をもとに作成しています
介護・福祉業界の転職事情|仕事の種類・平均給与・おすすめの資格
関連記事

|
資格
| 公開日:2025.04.15 更新日:2025.04.15 |
ホームヘルパーとは?必要な資格や介護福祉士との違いを解説
ホームヘルパーは、高齢者や障害者が自宅で安心して生活できるよう、居宅を...(続きを読む)
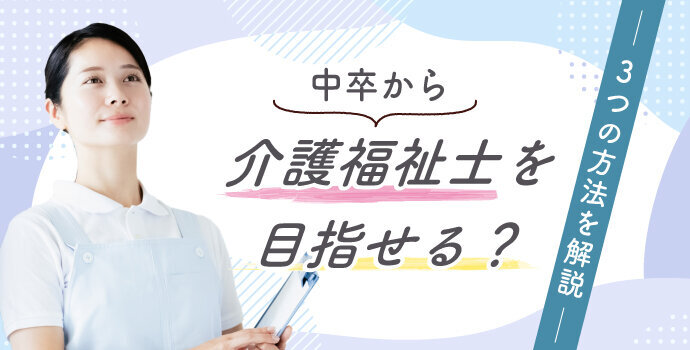
|
資格
| 公開日:2024.12.17 更新日:2024.12.17 |
中卒から介護福祉士を目指せる?3つの方法を解説
介護福祉士の資格を取得するためには、いくつかの条件があります。介護福祉...(続きを読む)

|
資格
| 公開日:2024.08.21 更新日:2024.08.21 |
介護福祉士の資格でできる仕事には何がある?主な転職先について解説
介護の専門資格である介護福祉士を取得することで、無資格の状態に比べて、...(続きを読む)
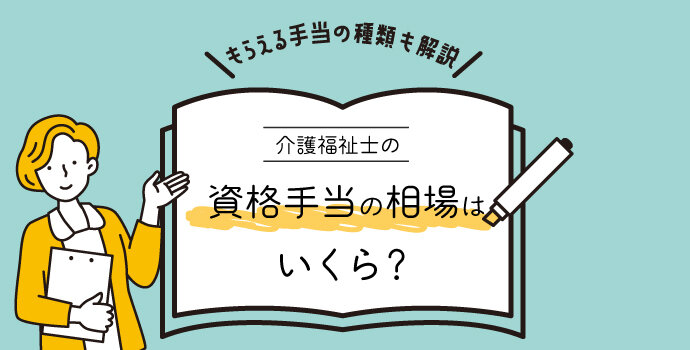
|
資格
| 公開日:2024.08.21 更新日:2024.08.21 |
介護福祉士の資格手当の相場はいくら?もらえる手当の種類も解説
基本給以外の給料アップにつながる手当として、資格手当があります。介護福...(続きを読む)