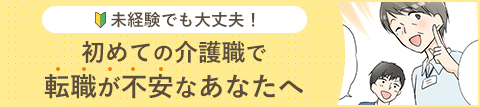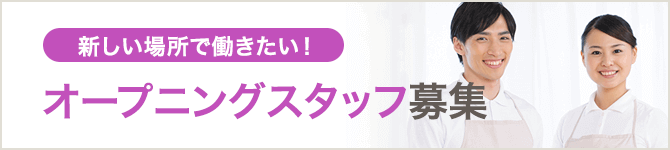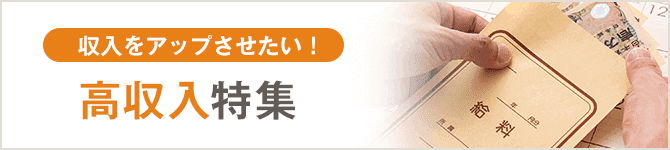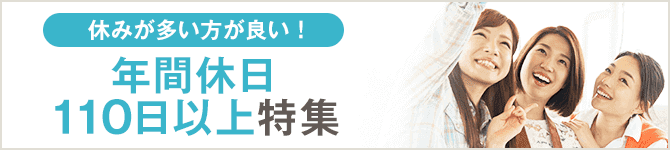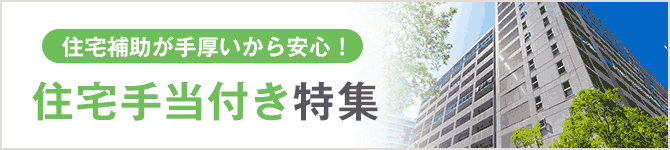リハビリ特化型デイサービスとは?特徴や仕事内容・やりがいを解説

日本の高齢化が進行する中、リハビリ特化型デイサービスの需要も高まっています。
リハビリ特化型デイサービスで提供されるプログラムは、通常のデイサービスのような食事・入浴のサービスや、レクリエーションなどよりも、運動や体操などの身体機能の訓練がメインです。身体的な負担を減らして働きたい介護職の方や、高齢者の方がより元気になる姿を支えたい介護職の方に向いている仕事です。
当記事では、リハビリ特化型デイサービスのサービス内容や1日の仕事内容などを紹介します。
目次
- 1. リハビリ特化型デイサービスとは
- 1-1. リハビリ特化型デイサービスの利用者さんの特徴
- 1-2. リハビリ特化型デイサービスと普通のデイサービスの違い
- 1-3. リハビリ特化型デイサービスとデイケアの違い
1. リハビリ特化型デイサービスとは
リハビリ特化型デイサービスとは、個別機能訓練や身体機能の改善などを目的としたデイサービスの一種です。介護保険上は、通所介護(デイサービス)に分類されます。 施設によっては、「リハビリ型デイサービス」「リハビリデイサービス」などと称されることもあります。
リハビリ特化型デイサービスの主な目的は、機能回復や維持を促進し、自立した生活をサポートすることです。 たとえば、脳卒中の後遺症で歩行が困難な方に対しては、歩行訓練を中心にしたプログラムが提供されたり、関節リウマチなどの慢性的な疾患を持つ方に対しては、関節の可動域を向上させるエクササイズが行われたりするでしょう。
また、リハビリ特化型デイサービスには理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師などの機能訓練指導員が在籍している点も大きなポイント です。利用者さんの利用時間は、おおよそ3〜5時間程度で、半日単位の利用となるのが一般的となります。
1-1. リハビリ特化型デイサービスの利用者さんの特徴
リハビリ特化型デイサービスは、通所介護(デイサービス)の一種であるため、基本的には、要介護1以上の認定を受けた方が利用対象 です。ただし、介護予防通所介護では要支援1または要支援2の認定を受けた方も利用できます。各市町村が提供している介護予防通所介護相当サービスに該当する場合は、要支援1・要支援2の方も、リハビリ特化型デイサービスを利用できる場合があります。
リハビリ特化型デイサービスを利用する方の特徴例は、以下の通りです。
・介護サービスを利用することが初めての方
・介護サービスに抵抗を感じており、介護保険をまだ使ったことがない方
・専門のリハビリ設備がある施設でリハビリをしたい方
・機能訓練をしたい方
・デイサービスで丸1日や長時間過ごすことに不安がある方
・運動の必要性は分かるが、あまりに辛い運動をするは嫌な方
・レクリエーションがあまり得意でない方
・全員で同じことを一緒にすることが苦手な方
・筋力・体力の低下が気になり、介護予防を始めたい方
このように、リハビリ特化型デイサービスを利用する目的や思いは、人によってさまざまです。リハビリ特化型デイサービスと一口に言っても、各施設によって特徴はそれぞれ異なるため、求人を探す際は自分に合った職場を探すことが大切です。
1-2. リハビリ特化型デイサービスと普通のデイサービスの違い
リハビリ特化型デイサービスは、介護保険上の正式名称ではなく、区分はあくまでデイサービスとなります。
デイサービスのサービスの特徴は、食事や入浴、機能訓練、レクリエーションなどがメインであり、日常生活のケア・生活支援が主な目的です。また、ご家族のレスパイト(休息)として、介護負担の軽減にも寄与します。利用時間は、8時間未満や7時間〜9時間程度で運営されていることが多い傾向です。
一方でリハビリ特化型デイサービスは、一人ひとりの利用者さんに合わせた機能訓練やリハビリ、運動がメインです。短時間のサービスで提供されているため、午前・午後で利用者が入れ替わるスタイルとなります。
1-3. リハビリ特化型デイサービスとデイケアの違い
デイサービスと似た言葉に「デイケア」があります。 デイケアは、通所リハビリテーションの通称であり、介護予防サービスを含むサービスです。以下は、リハビリ特化型デイサービスとデイケアの違いを示した表となります。
| リハビリ特化型デイサービス | デイケア(通所リハビリテーション) | |||
|---|---|---|---|---|
| 主な設置主体 | 民間企業、社会福祉法人など | 医療法人など | ||
| 受けられる サービス |
・リハビリテーションに特化したサービス | ・医師の指示によるリハビリテーションおよび食事・入浴 | ||
| 人員配置基準 | 生活相談員 | 事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従で1以上 | 専任の常勤医師 | 1以上 |
| 看護職員 | 単位ごとに専従で1以上 | 従事者 (理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、看護師・准看護師、介護職員のいずれか) | 単位ごとに利用者10人に1以上 | |
| 介護職員 | ① 単位ごとにサービス提供時間に応じて専従で次の数以上(常勤換算方式) ア 利用者の数が15人まで:1以上 イ 利用者の数が15人を超す場合 アの数に利用者の数が1増すごとに0.2を加えた数以上 ② 単位ごとに常時1名配置されること ③ ①の数及び②の条件を満たす場合は、当該事業所の他の単位における介護職員として従事することができる |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 | 上の内数として、単位ごとに利用者100人に1以上 | |
| 機能訓練指導員(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、看護職員、柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師) | 1以上 | |||
(出典:厚生労働省「通所介護及び療養通所介護(参考資料)」
/
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000168705.pdf)
(出典:厚生労働省「通所リハビリテーション(参考資料)」
/
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000168706.pdf)
リハビリ特化型デイサービスは、機能訓練指導員が中心となり、一人ひとりに合わせたマシントレーニングや機能訓練をメインに行います。
一方でデイケアでは、病気・けがの後や退院後などにおける生活機能の回復がサービスの目的です。専任の常勤医師が在籍しており、医師の指示に沿ったリハビリテーションが行われます。
【項目別】デイケアとデイサービスの違い|働く際に役立つ資格も紹介
2. リハビリ特化型デイサービスの1日の仕事内容
以下では、リハビリ特化型デイサービスの1日の仕事内容として、半日型・1日型の2通りのタイムスケジュール例を紹介します。ただし、施設によってスケジュールは異なるため、あくまで参考としてご確認ください。
【半日型の場合】
| 9:00 | 利用者の送迎 |
↓
| 9:30 | 利用者到着、バイタルチェック、個別のニーズ確認 |
↓
| 10:00 | 準備運動 |
↓
| 10:15 | 一人ひとりに合わせた機能訓練・リハビリテーション・体操 |
↓
| 11:45 | 整理体操、休憩 |
↓
| 12:00 | バイタルチェック、次回の予定確認 |
↓
| 12:30 | 利用者の送迎 |
【1日型の場合】
| 9:00 | 利用者の送迎 |
↓
| 9:30 | 利用者到着、バイタルチェック、個別のニーズ確認 |
↓
| 10:00 | 準備運動 |
↓
| 10:15 | 一人ひとりに合わせた機能訓練・リハビリテーション・体操 |
↓
| 11:30 | 整理体操、バイタルチェック |
↓
| 12:00 | 昼食 |
↓
| 13:00 | 口腔機能向上のための体操 |
↓
| 13:30 | 入浴 |
↓
| 14:30 | レクリエーション活動 |
↓
| 15:30 | おやつ |
↓
| 16:00 | 利用者の送迎 |
利用者を自宅に送迎する前の時間や後の時間には、スタッフ間でミーティングが行われたり、メールを返すなどの事務処理を行ったりもします。
3. リハビリ特化型デイサービスのやりがい
リハビリ特化型デイサービスで働く場合、ほかのデイサービスや介護施設とは違ったやりがいを感じられます。リハビリ特化型デイサービスでの勤務を検討している介護士さんはぜひ参考にしてください。
3-1. 心身にかかる負担が小さい
リハビリ特化型デイサービスは、比較的介護度の低い方が利用するため、身体介助の必要がないことも多いです。そのため、ほかの介護施設よりも、介護者の体にかかる負担が小さくすむでしょう。
また、身体機能向上のためのリハビリや筋力トレーニングに積極的に取り組む方のサポートができるため、前向きに働きやすい点もメリットです。
3-2. 利用者さんが元気になるところを見られる
介護度が低い方が多いということは、利用者さんが元気になっていく姿を見やすいということでもあります。一方で、介護度が高い方を対象とする介護施設だと、利用者さんが回復する姿を見るのは、なかなか難しいかもしれません。
利用者さんが回復した後も、利用者さんの健康と長期的に向き合いながらサービスを提供できる点はメリットと言えるでしょう。
まとめ
リハビリ特化型デイサービスでは、機能訓練が中心となって行われ、機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師など)が担当します。
機能訓練指導員などの専門職と一緒に働けるため、介護士として新しい視点や考え方を学びながらキャリアを積めるでしょう。
※当記事は2023年8月時点の情報をもとに作成しています
介護・福祉業界の転職事情|仕事の種類・平均給与・おすすめの資格
関連記事

|
転職市場
| 公開日:2025.04.15 更新日:2025.04.15 |
介護業界で働く魅力は?将来性や仕事の種類も解説
介護業界は、高齢者や障害を持つ方々の生活を支えています。介護業界で働く...(続きを読む)
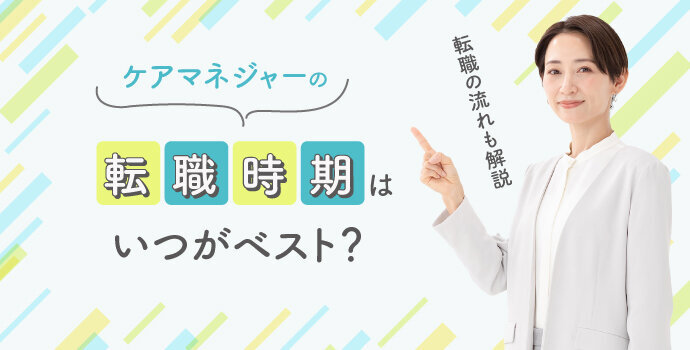
|
転職市場
| 公開日:2025.04.15 更新日:2025.04.15 |
ケアマネジャーの転職時期はいつがベスト?転職の流れも解説
ケアマネジャーとして転職を考える際、最適な時期を選ぶことは非常に重要で...(続きを読む)
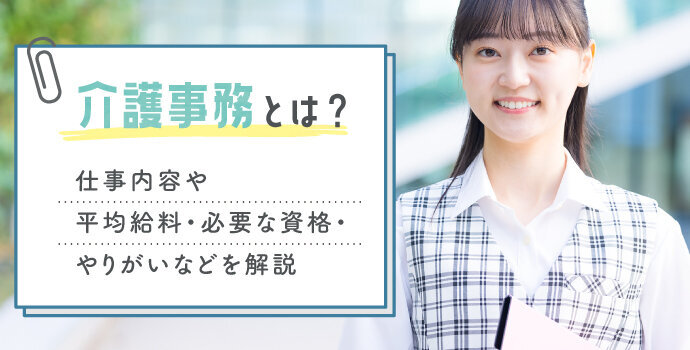
|
転職市場
| 公開日:2025.04.15 更新日:2025.04.15 |
介護事務とは?仕事内容や平均給料・必要な資格・やりがいなどを解説
介護事務の仕事は、高齢化が進む日本において、今後ますます需要が高まると...(続きを読む)

|
転職市場
| 公開日:2023.12.11 更新日:2023.12.14 |
介護のアルバイトは未経験でもできる?仕事内容や時給を解説
介護業界は人手不足であり、アルバイトを積極採用しています。施設によって...(続きを読む)