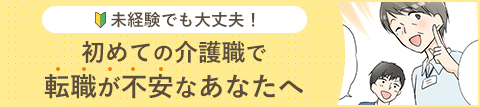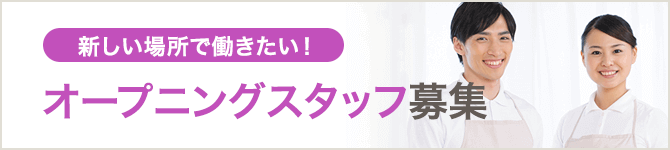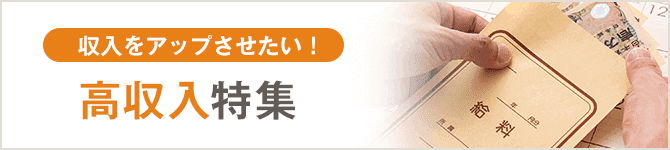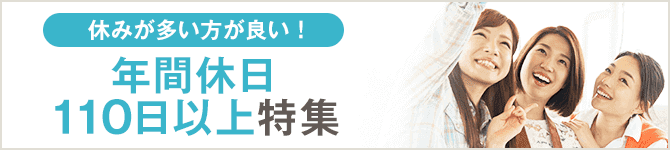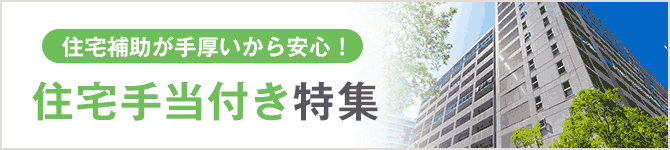介護支援専門員(ケアマネジャー)の受験資格とは?要件や流れを解説

介護支援専門員(ケアマネジャー)は介護を必要とする方からの相談に応じて、適切なサービスを受けられるようにケアプランの作成や関係機関との調整を行う職業です。介護支援専門員は介護支援のスペシャリストであり、専門的な知識が必要なため、資格試験の受験要件は厳しく、試験内容も高レベルになっています。
この記事では介護支援専門員になるための資格試験の受験要件や、最短で介護支援専門員になるのに必要な期間、資格取得までの流れについて解説します。
目次
- 3. 介護支援専門員の資格の取り方|取得までの基本的な流れ
- 3-1. 介護支援専門員実務研修受講試験に合格する
- 3-2. 介護支援専門員実務研修を受講する
- 3-3. 各自治体に登録する
- 3-4. 登録後も5年ごとに更新研修を受講する
1. 介護支援専門員(ケアマネジャー)になるには
介護支援専門員(ケアマネジャー)とは、主に「介護が必要な方への相談援助介護」「保険制度を利用するためのケアプラン作成」「関係機関との連絡および調整」の3つのケアマネジメントを行う公的資格のことです。介護保険法に規定された専門職であり、居宅介護支援事業所や介護保険施設などに配置義務があるため、取得によって就職で有利になります。
介護支援専門員になるには、一定の要件を満たした上で介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、介護支援専門員実務研修課程を修了する必要があります。
ケアマネジャーの具体的な仕事内容などについては以下の記事を参考にしてください。
2. 介護支援専門員実務研修受講試験の要件になる資格・実務経験
介護支援専門員実務研修受講試験を受けるためには、以下の資格を取得した上で、規定の実務経験を修了することが必要です。
【介護支援専門員実務研修受講試験の受験要件】
| A.受験要件となる資格 | 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、機能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、管理栄養士、精神保健福祉士 |
|---|---|
| B.受験要件となる実務経験(相談援助業務) | ・生活相談員(介護予防を含む特定施設入居者生活介護もしくは介護老人福祉施設に勤務) ・支援相談員(介護老人保健施設に勤務) ・相談支援専門員(計画相談支援もしくは障害児相談支援に従事) ・主任相談支援員(生活困窮者自立相談支援事業に従事) |
| AおよびBの実務期間が通算して5年以上であり、業務に従事した日数が900日以上 | |
(出典:東京都福祉保健財団「令和5年度 東京都介護支援専門員実務研修受講試験」
/
https://www.fukushizaidan.jp/101caremanager/shiken/)
Aの資格を保有している場合、業務への従事期間として数えられるのは「資格の登録日以降」であることが条件です。ただし、Aの資格を保有している場合でも「要援護者に対する直接的な対人業務ではない業務(教育や研究、営業、事務など)」を行っている期間は、実務経験に含まれない ため注意してください。また、同一期間に重複して、複数業務に従事した場合は実務経験として通算できません。もし「1日に2か所で業務に従事した」という場合、従事日数は1日とカウントされます。
実務経験期間の具体的な算定例については、東京都福祉保健財団が公表しているこちらのページを参考にしてください。
また、試験を受ける場所については、主な勤務地が所在している都道府県での受験となります。申込後に受験場所を変更することはできないため注意してください。
2-1. 最短で介護支援専門員になるのに必要な期間
最短で介護支援専門員になるのに必要な期間は、資格の有無によって異なります。
「無資格者」の場合は、最短で8年かかります。 例として、介護支援専門員実務研修受講試験の受験要件となる介護福祉士資格を取得するのには最短3年が必要です。その上で5年以上の実務経験が必要になるため、最短でも合計8年が必要です。
すでに介護支援専門員実務研修受講試験の受験要件となる介護・医療系資格の有資格者であれば、5年間、900日以上業務に従事することで介護支援専門員になれます。
介護福祉士資格については、以下の記事で詳しく解説しています。
3. 介護支援専門員の資格の取り方|取得までの基本的な流れ
介護支援専門員を目指すには最短8年(有資格者は5年)が必要であるため、計画を立てて受験要件を満たす必要があります。受験要件を満たした上で、介護支援専門員資格を取得する流れは以下の通りです。
3-1. 介護支援専門員実務研修受講試験に合格する
まずは介護支援専門員実務研修受講試験を受けて合格しましょう。試験の概要は以下の通りです。
| 試験形式 | 問題は五肢複択方式 解答はマークシート方式 |
|
|---|---|---|
| 試験時間 | 120分(点字受験者は180分・弱視等受験者は156分) | |
| 試験内容 | 介護支援分野 | 介護保険制度の基礎知識 要介護認定等の基礎知識 居宅・施設サービス計画の基礎知識など合計25問 |
| 保健医療福祉サービス分野 | 保健医療サービスの知識など20問 福祉サービスの知識など15問 |
|
| 合格率 | 19.0%(令和4(2022)年の第25回試験の場合) | |
(出典:東京都福祉保健財団「令和5年度東京都介護支援専門員実務研修受講試験受験要項」
/
https://www.fukushizaidan.jp/wp-content/uploads/2023/05/%E3%80%90%E5%85%A8%E4%BD%93%E7%89%88%E3%80%91R5%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%83%8D%E8%A9%A6%E9%A8%93%E5%8F%97%E9%A8%93%E8%A6%81%E9%A0%85.pdf#page=10)
(出典:厚生労働省「第25回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について」
/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187425_00009.html)
試験は毎年10月に年1回開催されます。受験チャンスが少ない上に合格率も低いので、毎年しっかり勉強時間を確保することが大切です。
試験内容と合格発表日は全国の受験地で同じですが、申し込み期間は各自治体で異なるため、自分が受験する地域の期間を忘れずにチェックしておきましょう。また、指定された会場以外では受験できない点に注意してください。
例として、東京都の令和6年介護支援専門員実務研修受講試験の詳細な受験日程は、東京都福祉保健財団の公式サイト上で4月中旬に公表されます。受験希望者は忘れずにチェックしておきましょう。
3-2. 介護支援専門員実務研修を受講する
介護支援専門員実務研修受講試験に合格したら、介護支援専門員実務研修を受講しましょう。介護支援専門員実務研修では、介護支援専門員になるために必要なケアマネジメントの基本について学びます。
具体的なカリキュラムは自治体ごとに異なるものの、いずれも「合計87時間以上」の研修が必要です。東京都における具体的なカリキュラムは以下の通りです。
【介護支援専門員実務研修のカリキュラム(東京都の場合)】
| 日程 | カリキュラム名 | 形式 | 時間 |
|---|---|---|---|
| オリエンテーション | オリエンテーション | 講義 | 約1時間 |
| 前期課程 | 介護保険制度の理念・現状及びケアマネジメント | 講義 | 約3時間 |
| ケアマネジメントに係る法令等の理解 | 講義 | 約2時間 | |
| 自立支援のためのケアマネジメントの基本 | 講義・演習 | 約6時間 | |
| 人格の尊重及び権利擁護並びに介護支援専門員の倫理 | 講義 | 約2時間 | |
| ケアマネジメントのプロセス | 講義 | 約2時間 | |
| 相談援助の専門職としての基本姿勢及び相談援助技術の基礎① | 講義・演習 | 約1時間 | |
| 相談援助の専門職としての基本姿勢及び相談援助技術の基礎② | 講義・演習 | 約3時間 | |
| 利用者、多くの種類の専門職等への説明及び合意 | 講義・演習 | 約2時間 | |
| 介護支援専門員に求められるマネジメント(チームマネジメント) | 講義・演習 | 約2時間 | |
| 地域包括ケアシステム及び社会資源 | 講義 | 約3時間 | |
| ケアマネジメントに必要な医療との連携及び他職種協働の意義 | 講義 | 約3時間 | |
| 受付及び相談並びに契約 | 講義・演習 | 約1時間 | |
| アセスメント及びニーズの把握の方法① 居宅サービス計画等の作成① |
講義・演習 | 約6時間 | |
| サービス担当者会議の意義及び進め方① | 講義・演習 | 約2時間 | |
| アセスメント及びニーズの把握の方法② 居宅サービス計画等の作成② |
講義・演習 | 約4時間 | |
| サービス担当者会議の意義及び進め方② | 講義・演習 | 約2時間 | |
| モニタリング及び評価 | 講義・演習 | 約4時間 | |
| 実習 | ケアマネジメントの基礎技術に関する実習 | 実習 | - |
| 後期課程 | 基礎理解 | 講義・演習 | 約3時間 |
| 脳血管疾患に関する事例① | 講義 | 約2時間 | |
| 認知症に関する事例① | 講義 | 約2時間 | |
| 脳血管疾患に関する事例② | 講義・演習 | 約3時間 | |
| 認知症に関する事例② | 講義・演習 | 約3時間 | |
| 筋骨格系疾患及び廃用症候群に関する事例① | 講義 | 約2時間 | |
| 内臓の機能不全(糖尿病、高血圧、脂質異常症、心疾患、呼吸器疾患、腎臓病、肝臓病等)に関する事例① | 講義 | 約2時間 | |
| 筋骨格系疾患及び廃用症候群に関する事例② | 講義・演習 | 約3時間 | |
| 看取りに関する事例① | 講義 | 約2時間 | |
| 看取りに関する事例② | 講義・演習 | 約3時間 | |
| 実習振り返り | 講義・演習 | 約3時間 | |
| 内臓の機能不全(糖尿病、高血圧、脂質異常症、心疾患、呼吸器疾患、腎臓病、肝臓病等)に関する事例② | 講義・演習 | 約3時間 | |
| アセスメント及び居宅サービス計画等作成の総合演習 | 講義・演習 | 約5時間 | |
| 研修全体を振り返っての意見交換、講評及びネットワーク作り | 講義・演習 | 約2時間 | |
| 計 | 約87時間 | ||
(引用:東京都福祉保健財団「令和5年度東京都介護支援専門員実務研修受講試験受験要項」
/
https://www.fukushizaidan.jp/wp-content/uploads/2023/05/%E3%80%90%E5%85%A8%E4%BD%93%E7%89%88%E3%80%91R5%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%83%8D%E8%A9%A6%E9%A8%93%E5%8F%97%E9%A8%93%E8%A6%81%E9%A0%85.pdf 引用日2024/1/16)
介護支援専門員実務研修は、大きく前期と後期に分けて実施されます。
前期では主に、介護士支援専門員として働く上で必要な基礎知識について研修を受けます。具体的な講義・演習内容は、介護保険制度や関連法令の理解、ケアマネジメントを行う際の心構えなどです。上記の基礎知識を頭に入れることで、介護士支援専門員がケアマネジメントによる支援を行う際、利用者さんやご家族の希望にマッチしたサービスを提供できるようになります。
後期では主に、具体的なケアプランの作成や事例の検討会などを行います。事例の検討会では、生活機能や実際の利用状況などを掘り下げながら、利用者さんやご家族の希望を実現したケアプランを作成できているか確認することがメインです。
3-3. 各自治体に登録する
介護支援専門員実務研修を修了したら、3か月以内に介護支援専門員として各自治体の「介護支援専門員資格登録簿」に登録しましょう。登録簿への登録を実施しすべての手続きが完了すると、介護支援専門員証が交付されて、介護支援専門員として働けるようになります。
登録時に必要な主な書類は自治体によって異なりますが、一般的に必要な書類は以下の通りです。
・介護支援専門員登録申請書
・住民票
・実務研修修了証明書の写し
・証明写真
・都道府県の収入証紙
3-4. 登録後も5年ごとに更新研修を受講する
介護支援専門員の資格を取得した後は、5年ごとに更新研修受講が必要です。
更新研修の時間数は、従事している業務の種類によって異なります。介護支援専門員の業務に従事していない方(実務非従事者)の場合は、実務研修と同内容の54時間以上の研修受講が必要です。
資格の有効期間内に実務に就いたことがある方(実務経験者)の場合は、原則として合計88時間の研修を受講します。研修は実務就業後6か月以上の人を対象とした「専門研修I(56時間以上)」、実務就業後3年以上の人を対象とした「専門研修II(32時間以上)」の2段階があります。
もし実務経験者で、かつ専門研修Iと専門研修IIの双方を資格の有効期間内に受講した場合は、以後は更新研修がすべて免除され、そのまま更新申請が可能です。
(出典:福祉医療機構「実務研修受講試験からの流れ」
/
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/caremanager/caremanagerworkguide/caremanagerworkguide_n002.html)
まとめ
介護支援専門員になるには、無資格者の場合は最短8年、有資格者の場合でも最短5年の実務経験が必要です。その上で介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、合計87時間以上の介護支援専門員実務研修を受講すれば、自治体に介護支援専門員として登録できます。以降は5年ごとに更新研修の受講が必要ですが、実務経験者の場合は専門研修IとIIを有効期間内に受講すれば、研修が免除されます。
介護支援専門員を目指している方や、介護支援専門員資格を取得した方の職場探しは、ぜひマイナビ介護職をご利用ください。資格取得支援がある職場や、手厚い資格手当がある職場など、ご要望に合った職場を非公開求人含む多数の求人の中から紹介します。
※当記事は2024年1月時点の情報をもとに作成しています
介護・福祉業界の転職事情|仕事の種類・平均給与・おすすめの資格
関連記事

|
資格
| 公開日:2025.04.15 更新日:2025.04.15 |
ホームヘルパーとは?必要な資格や介護福祉士との違いを解説
ホームヘルパーは、高齢者や障害者が自宅で安心して生活できるよう、居宅を...(続きを読む)
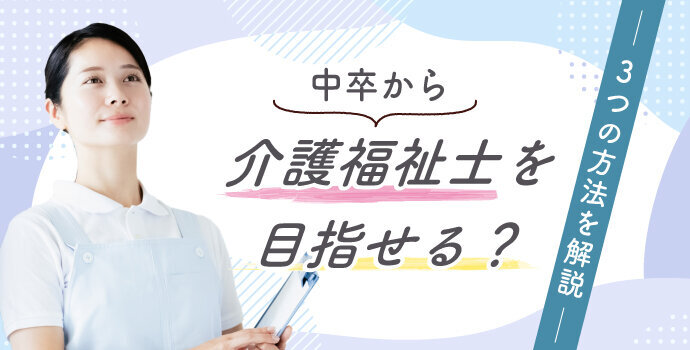
|
資格
| 公開日:2024.12.17 更新日:2024.12.17 |
中卒から介護福祉士を目指せる?3つの方法を解説
介護福祉士の資格を取得するためには、いくつかの条件があります。介護福祉...(続きを読む)

|
資格
| 公開日:2024.08.21 更新日:2024.08.21 |
介護福祉士の資格でできる仕事には何がある?主な転職先について解説
介護の専門資格である介護福祉士を取得することで、無資格の状態に比べて、...(続きを読む)
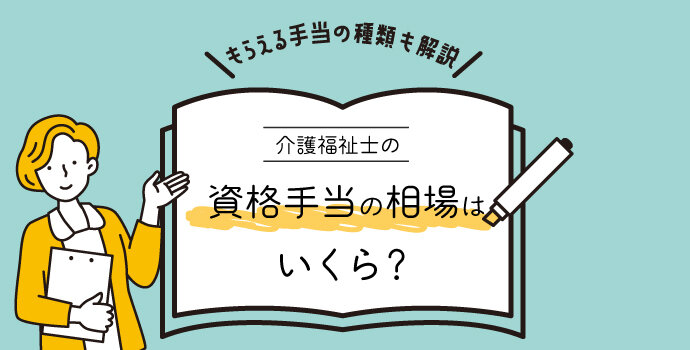
|
資格
| 公開日:2024.08.21 更新日:2024.08.21 |
介護福祉士の資格手当の相場はいくら?もらえる手当の種類も解説
基本給以外の給料アップにつながる手当として、資格手当があります。介護福...(続きを読む)