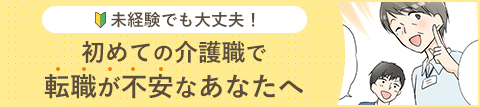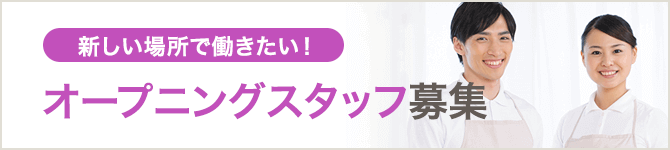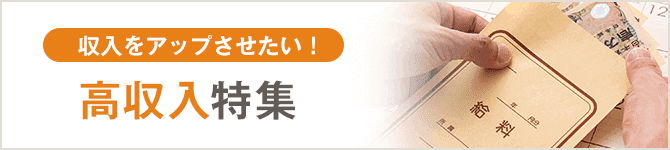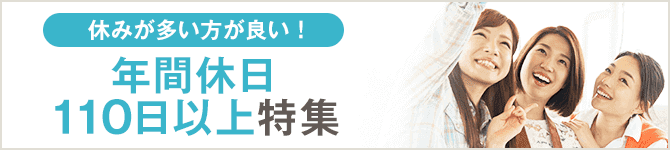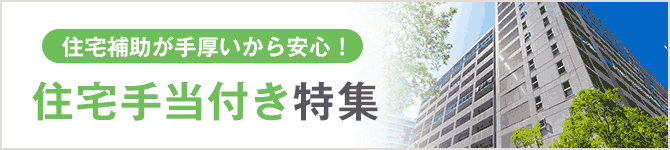精神保健福祉士の将来性|需要とより活躍する方法も

精神保健福祉士は国家資格の1つであり、精神疾患を抱える方のサポートやメンタルケアを行う職業です。医療・福祉系資格の中では認知度が低く、資格取得者数も多くないものの、メンタルケアの必要性が高まる現代社会において、今後さらに需要が高まることが予想されます。
当記事では、精神保健福祉士の将来性が高いと言われる5つの理由に加え、将来的に活躍できる精神保健福祉士になるためのポイントについて詳しく解説します。精神保健福祉士を目指している方、精神保健福祉士として働いている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
- 1. 精神保健福祉士には将来性がある!安心して働ける理由5つ
- 1-1. 精神疾患が注目を集めているため
- 1-2. 活躍の場が増えているため
- 1-3. 資格取得者が少ないため
- 1-4. 平均年収が上がっているため
- 1-5. AIでは代替できない仕事であるため
1. 精神保健福祉士には将来性がある!安心して働ける理由5つ
昨今の日本では、精神疾患を抱える方が増加しています。従来は入院による治療・回復を目指すケースが多くありましたが、現在では地域社会の一員として暮らし続けるためのサポートが重視されるようになりました。精神保健福祉士は、精神科病棟をはじめとする医療施設以外にも、さまざまな場所で患者さんを支援しています。
ここでは、精神保健福祉士が安心して働ける理由を5つ紹介します。
1-1. 精神疾患が注目を集めているため
2013年度の医療計画により、がん・脳卒中・糖尿病・心筋梗塞からなる4大疾病に精神疾患が加わりました。
(出典:厚生労働省「5疾病・5事業について」/
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000127304.pdf)
精神疾患が5大疾病の1つとなり、国民に広く関わる重大な疾患として認識されていることが分かります。
また、2017年の内閣府の調査によると、精神疾患を抱える方は、外来患者だけでも約389万人にのぼりました。
(出典:内閣府「参考資料 障害者の状況」/ https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/r02hakusho/zenbun/siryo_02.html)
心の問題を抱えた方が増えている分、メンタルケアや相談支援に取り組む精神保健福祉士は、多くの場で求められるようになっています。
今後は、精神疾患を持った方が自立した社会生活を送るためのサポートを行う施設も増加していくことが考えられます。精神保健福祉士は、精神障害者の就労支援や社会復帰支援についても知識・スキルを備える専門家であるため、重要な役割を担う存在であると言えるでしょう。
1-2. 活躍の場が増えているため
現在の日本は「ストレス社会」と呼ばれており、心の問題を抱える方が社会全体として増加しています。精神保健福祉士は、医療・福祉関係の施設以外にも、さまざまな職場で必要とされています。
例えば学校などの教育機関では、ソーシャルスクールワーカーとして勤務することで、いじめに悩む子どもたちやその家族、教員のメンタルサポートが可能です。また、最近では多くの一般企業がうつ病対策や精神支援、労働環境改善に力を入れており、企業の専属カウンセラーとして精神保健福祉士を雇用することも少なくありません。
精神保健福祉士は、司法機関でもニーズが高まっています。精神障害を持つ犯罪者の審判や更生保護施設のスタッフ、精神障害者の社会復帰をサポートする社会復帰調整官など、その役割はさまざまです。
精神保健福祉士は多様な職場でスキルを生かすことが可能であり、就職時の選択肢が幅広いのが強みの1つです。
1-3. 資格取得者が少ないため
精神保健福祉士は国家資格の1つですが、同じく国家資格である社会福祉士や介護福祉士と比較すると、精神保健福祉士の取得者・登録者数は非常に少ない のが現状です。
精神保健福祉士・社会福祉士・介護福祉士の年度別登録者数の推移は、以下の通りです。
| 精神保健福祉士 | 社会福祉士 | 介護福祉士 | |
|---|---|---|---|
| 2016年度 | 76,200人 | 208,261人 | 1,503,574人 |
| 2017年度 | 80,891人 | 221,251人 | 1,558,897人 |
| 2018年度 | 85,122人 | 233,517人 | 1,624,829人 |
| 2019年度 | 89,121人 | 245,181人 | 1,694,630人 |
| 2020年度 | 93,544人 | 257,293人 | 1,754,486人 |
| 2021年度 | 97,339人 | 266,557人 | 1,819,097人 |
(出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「登録者の資格種類別-年度別の推移」/
https://www.sssc.or.jp/touroku/pdf/pdf_tourokusya_graph_r03.pdf)
精神保健福祉士の登録者数は年々増加しているものの、福祉系国家資格の中では人数が少ないことが分かります。資格取得者が少ない中で需要が増えているということは、将来性が高い職業であると考えられるでしょう。
1-4. 平均年収が上がっているため
2019年度に行われた就労状況調査によると、精神保健福祉士の平均年収は404万円です。
(出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「精神保健福祉士就労状況調査実施結果報告書(令和2年)」/
https://www.sssc.or.jp/touroku/results/pdf/r2/results_04.pdf)
また、2011年度の調査では340万円、2015年度の調査では347万円であり、平均年収は増加傾向にあることが分かります。
(出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「精神保健福祉士就労状況調査実施結果の実施概要(平成27年)」/
https://www.sssc.or.jp/touroku/results/pdf/h27/results_p_h27.pdf)
(出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「平成24年度精神保健福祉士就労状況調査結果」/ https://www.sssc.or.jp/touroku/results/pdf/h27/results_p_h27.pdf)
特に2019年度の404万円という金額は、前回調査の2015年度と比較すると57万円増加しています。平均年収が大きく上がっている点からも、精神保健福祉士の待遇がよくなっていること、需要が高まっていることが推測できるでしょう。
1-5. AIでは代替できない仕事であるため
近年目覚ましい発展を続けているAIは、多様な分野・業種において、人間の代わりに正確な業務を行うことが可能です。しかし、精神保健福祉士の業務であるメンタルケアや相談支援は、AIには行えません。
医療・福祉における業務の中でも、精神医学は特に複雑です。人の心のケアを行うには人間的な理解や創造性・協調性が不可欠であり、患者さん一人ひとりの心身状態や環境などによっても対応が大きく異なるのが特徴です。
精神保健福祉士が行う心理的支援は非定型的な業務内容であり、今後AIがさらに発展した場合でも、仕事が減ることはないと考えられます。
2. 将来的に活躍できる精神保健福祉士になるために
心のケアの必要性が高まっている現代の日本において、精神保健福祉士のニーズは精神科病棟以外でも広がり続けています。精神疾患を持つ方が増加していること、組織・地域単位でのサポート体制の構築が進んでいることから、今後ますます精神保健福祉士の需要は高まると予想できるでしょう。
多くの患者さんを支えられる精神保健福祉士となるには、時代の流れを見据え、自己研鑽を怠らないことが重要となります。
将来的に活躍できる精神保健福祉士になるためのポイントは、以下の2つです。
| ・資格取得後も勉強し続ける |
|---|
|
職場の仲間や患者さんから頼りにされる「よい精神保健福祉士」とは、患者さんに寄り添いながら、意図的に関われる人材です。 精神保健福祉士は、患者さんの疾患の種類や精神疾患を患った背景、できることとできないことの内容など、さまざまなポイントから関わり方を探る必要があります。一人ひとりに合わせた意図的な関わり方を続けることで信頼関係が生まれ、患者さんの回復に向けた密なサポートが実現します。 担当する患者さんに最適な対応・ケアを判断するには、精神分野に関する専門知識が不可欠です。精神保健福祉士資格を取得した後も、専門職として知識のアップデートを怠らず、学び続ける姿勢を持つことが重要です。 |
| ・他の資格を併せて取得する |
|---|
|
精神保健福祉士の需要は増え続けている一方で、正社員雇用が多いことから離職率が低く、求人は年度末に集中しやすいという特徴があります。 しかし、今後日本の高齢化社会が進む中で、認知症などを含む精神疾患患者の増加により、精神保健福祉士のニーズは介護業界でも高まることが予想されます。介護施設では、介護福祉士やケアマネジャーの資格を取得しておくと、頼れる人材として重宝されるでしょう。 介護福祉士とは、介護施設や訪問支援などで利用者さんの身体介護や食事・排泄などの生活支援を行う仕事です。また、ケアマネジャーとは、介護サービスの利用が必要な利用者さんからの相談に基づいてヒアリングを行い、サービス事業者との連絡・調整を行う仕事です。 介護に関わる資格とのWライセンスにより、精神保健福祉士としての仕事の幅を広げられるでしょう。 ケアマネジャーとは?仕事内容と資格の取得方法を解説 |
まとめ
ストレス社会や高齢化によって精神疾患を患う方が増えていることを背景に、精神保健福祉士の需要は年々高まっています。精神保健福祉士は、精神疾患が5大疾病の1つとして注目されていること、平均年収が上がっていることなどから、将来性が高く安心して働ける職業であると言えるでしょう。
精神保健福祉士として求められる人材となるためには、国家試験合格後にも勉強を続けることが大切です。また、今後求人数の増加が予想される介護分野の資格を併せて取得しておくのもよいでしょう。
「マイナビ介護職」では、介護・福祉職の求人を多数取り扱っています。無料会員登録により、キャリアアドバイザーの転職サポートや非公開求人の紹介など、さまざまなサービスを利用可能です。精神保健福祉士としての就職・転職を考えている方は、ぜひお役立てください。
※当記事は2022年8月時点の情報をもとに作成しています
介護・福祉業界の転職事情|仕事の種類・平均給与・おすすめの資格
関連記事

|
転職市場
| 公開日:2025.04.15 更新日:2025.04.15 |
介護業界で働く魅力は?将来性や仕事の種類も解説
介護業界は、高齢者や障害を持つ方々の生活を支えています。介護業界で働く...(続きを読む)
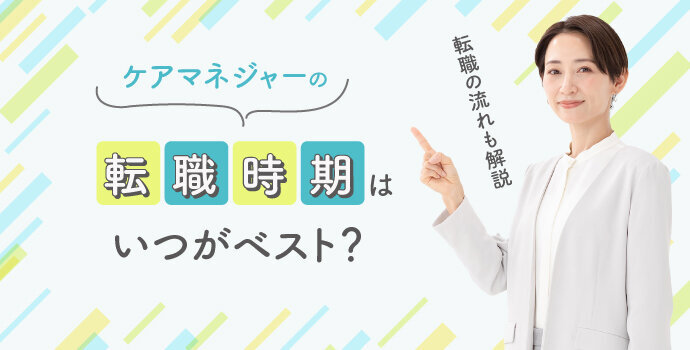
|
転職市場
| 公開日:2025.04.15 更新日:2025.04.15 |
ケアマネジャーの転職時期はいつがベスト?転職の流れも解説
ケアマネジャーとして転職を考える際、最適な時期を選ぶことは非常に重要で...(続きを読む)
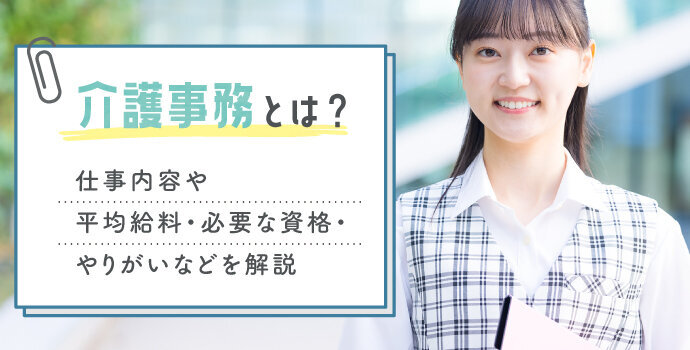
|
転職市場
| 公開日:2025.04.15 更新日:2025.04.15 |
介護事務とは?仕事内容や平均給料・必要な資格・やりがいなどを解説
介護事務の仕事は、高齢化が進む日本において、今後ますます需要が高まると...(続きを読む)

|
転職市場
| 公開日:2023.12.11 更新日:2023.12.14 |
介護のアルバイトは未経験でもできる?仕事内容や時給を解説
介護業界は人手不足であり、アルバイトを積極採用しています。施設によって...(続きを読む)