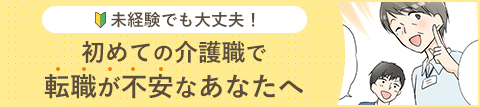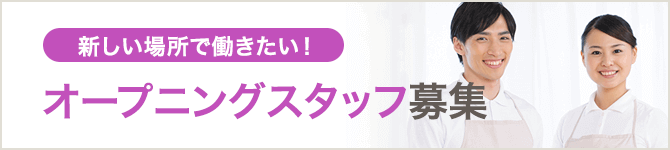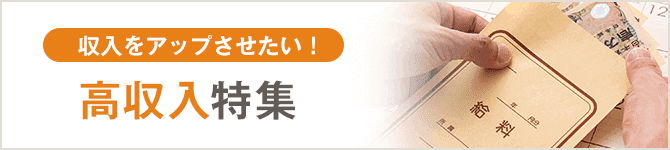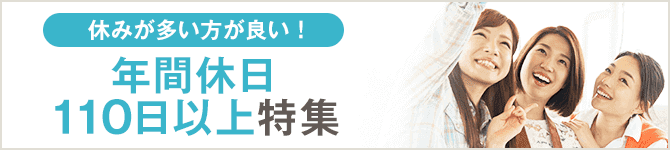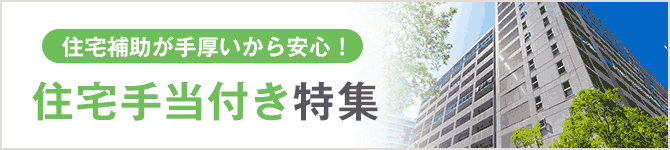サービス提供責任者が「辞めたい」と思ったら?転職・退職の選択肢も

サービス提供責任者は、利用者さんの立場で訪問介護計画を考え、計画どおりにサービスが提供できるようコーディネートをする、訪問介護サービス現場の責任者です。法令によって、訪問介護事業所には利用者さん40人につき1名以上の配置が義務付けられており、訪問介護の要となる存在です。
ただ、やりがいを持って働ける仕事である一方、忙しさや責任の重さといった苦労の多い仕事でもあるので、「辞めたい」と考えるサービス提供責任者も少なくありません。
辞めるべきか続けるべきか迷ったときに、後悔のない決断をするためには、サービス提供責任者ならではのメリット・デメリットの両方を見直し、転職先の候補についても知っておくことが大切です。
ここでは、サービス提供責任者が「辞めたい」と思う理由と、同職ならではのやりがいや魅力のほか、転職先の候補、転職を成功させるためのポイントについてご紹介します。
目次
- 4. サービス提供責任者を辞めるときの伝え方
- 4-1. 退職の意思は早めに伝える
- 4-2. 直属の上司に伝える
- 4-3. 理由はポジティブなものを伝える
- 4-4. 引き止めにあったときの対処法を考えておく
1. サービス提供責任者が辞めたいと思う理由
サービス提供責任者が「もう辞めたい」と思ってしまう背景には、次のような事情があります。
・忙しくて休みが取りにくい
サービス提供責任者の仕事は、利用者宅への訪問・聞き取りを行った上での訪問介護計画書の作成、ケアマネージャーとの連絡、ヘルパーの指導・教育、利用者対応と多岐にわたり、ヘルパーが休んだときは自ら訪問介護に入ることもあります。常に忙しく、職場によってはなかなか休みが取れないケースもあります。
・ケアマネージャー、ヘルパー、利用者さんのあいだで板挟みになりがち
ヘルパー、ケアマネージャー、そして利用者さんのパイプ役でもあるサービス提供責任者。利用者さんから無茶な要求を伝えられたり、ケアマネージャーとヘルパー、ヘルパーと利用者さんそれぞれの相性が悪く意見の相違が起こったりすることも、日常的に起こります。「あちらを立てればこちらが立たず」の板挟みに苦しむ方もいます。
・人間関係が難しい
ヘルパーの指導・教育は、サービス提供責任者の仕事です。ヘルパーの人手不足問題や、専門性の低下などで頭を悩ませることも少なくありません。 そのため、ケアマネージャーや施設管理者との関係を含め、人間関係に疲れを感じる人は珍しくありません。
・周囲の無理解
サービス提供責任者の仕事内容は多岐にわたりますが、利用者さんはもちろん、ケアマネージャーや施設管理者もその仕事を十分理解していないことが少なくありません。忙しさや精神的な負担に加え、周囲の無理解もサービス提供責任者の悩みの1つになっています。
・頼れる人がいない
サービス提供責任者は、法令により配置人数が決まっている役職なので、前任者の退職などに伴い、急に抜擢されることもあります。訪問介護の経験が浅い、誰も指導してくれる人がいないといった状態のまま任されてしまうと、大きな不安とストレスを抱えがちです。
2. サービス提供責任者の仕事内容
サービス提供責任者は、訪問介護サービスを提供するために管理や調整を行う役割を担っています。サービス提供責任者の配置基準については、以下の通りです。
●サービス提供責任者の配置基準
・訪問介護員等のうち、利用者の数40人に対して1人以上
(原則として常勤専従の者であるが一部常勤職員でも可。)
・以下の要件を全て満たす場合には、利用者50人につき1人
・常勤のサービス提供責任者を3人以上配置
・サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置
・サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合
(引用:厚生労働省「訪問介護におけるサービス提供責任者について」
/
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000106770.pdf 引用日2024/06/17)
また、下記でサービス提供責任者がどのような仕事を担当するのか、仕事内容について詳しく解説します。
2-1. 利用者・家族との面談
訪問介護のアセスメントはサービス提供責任者が担当する重要な仕事の1つです。
訪問介護におけるアセスメントでは、利用者さんのADL(日常生活動作)や家族構成、生活環境などさまざまな情報を把握・分析します。さらに、利用者さんやご家族が望む生活や、今の生活の課題を明確にして、最適な介護サービスを提供できるようにします。
訪問介護のアセスメントはサービス提供責任者が利用者さんやご家族と面談・ヒアリングすることが一般的です。ただし、事業所によっては実際に介護サービスを提供する介護職員が面談に同席するケースもあります。
2-2. サービス担当者会議への出席
サービス担当者会議とは、利用者さんに関わる担当者が集まり、よりよいサービスの提供を目指す会議を指します。出席するのは、介護職員やケアマネジャー、かかりつけ医、リハビリ職員、場合によっては福祉用具専門相談員や栄養士などです。訪問介護のサービス提供責任者も、サービス担当者の1人としてサービス担当者会議に出席します。
サービス担当者会議ではケアプランの内容を検討し、それぞれの立場から情報共有をしたり意見を出し合ったりします。サービス提供責任者もケアプランを確認した上で、必要なサービスの提案を行う必要があります。
(出典:厚生労働省「サービス担当者会議の位置づけと目的」
/
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/03/dl/s0313-4a_0002.pdf)
2-3. 訪問介護計画書の作成
訪問介護計画書とは、利用者さんの状態に合わせた訪問介護サービスの内容や提供方法などの計画を記載する書類です。
訪問介護計画書作成業務は、まずアセスメントを行い利用者さんの情報収集をして、ニーズを抽出・特定してから訪問介護計画書作成を行うという流れで行います。利用者さんの現状に即しているか、ケアプランと異なっていないかなどを確認しながら訪問介護計画書を作成しなければなりません。
(出典:堺市ホームページ「訪問介護計画書作成の流れ」
/
https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/fukushikaigo/koreishafukushi/jigyo/jigyosha/76230620230116165214394.files/03sakuseitopoint.pdf)
2-4. ホームヘルパーの業務管理
サービス提供責任者は、ホームヘルパーのスケジュール管理や、ホームヘルパーが提供したサービス内容・実施状況などの確認と管理を行います。利用者さんの状況や希望、ホームヘルパーの能力、勤務可能な時間などを確認しながら、業務を調整します。また、新しく利用者さんのもとに訪問するヘルパーに同行して、作業の内容を指導することも管理業務の1つです。
3. サービス提供責任者ならではのメリット
サービス提供責任者の仕事は、つらいばかりではありません。他の介護職と比較して次のようなメリットがあると言えます。
・正社員として、安定して働ける
サービス提供責任者は、法令で常任での配置が求められていることなどから、多くが正社員としての採用になります。サービスの提供が昼間だけの訪問介護施設であれば夜勤もないため、安定した就業環境で働けます。
・キャリアアップにつながり、転職にも有利
サービス提供責任者は、一般介護職の中でも、給与が高い傾向にあります。サービス提供責任者を経験するとスキルアップになるだけでなく、転職時の高評価にもつながるでしょう。
・マネジメント能力、コミュニケーション力などのスキルが身に付く
サービス提供責任者はマネジメントを行うポジションです。施設管理者、ケアマネージャー、勤務するヘルパー、利用者さんなどさまざまな人のあいだに立って働くうちに、調整力・マネジメント能力が鍛えられます。また、コミュニケーション能力や効率的に問題を処理する判断力など、幅広いスキルが身に付きます。
・多くの人に感謝される
サービス提供責任者は、利用者さんやその家族に直接会い、悩みや相談を聞いてどうすればいいのか一緒に考えることも大切な仕事です。そのため、直接感謝の言葉をもらえる機会も多く、大きなやりがいを持って働けるのも魅力です。
4. サービス提供責任者を辞めるときの伝え方
サービス提供責任者を担当する中で、業務量や給与面など、さまざまな事情を鑑みた上で退職を考えることもあるでしょう。サービス提供責任者が退職する際にはマナーに沿ってきちんと退職の意向を伝えることが大切です。ここでは、サービス提供責任者を辞めるときの伝え方を紹介します。
4-1. 退職の意思は早めに伝える
退職の意思を伝えるときは、就業規則を確認した上で早めに伝えるとよいでしょう。法的には退職する日の2週間前までに退職の意思を伝えることが必要です。しかし、就業規則ではそれより早く伝えるよう求められている場合もあるため、無用なトラブルを避けたい場合は、あらかじめ就業規則をチェックしておきましょう。
また、退職の時期は繁忙期を避けると引き止めに合いにくくなります。職場の状況を確認して、適切なタイミングで退職の旨を伝えましょう。
4-2. 直属の上司に伝える
退職の意思を最初に伝える相手は、直属の上司です。人事部長や専務などの上司よりも上の役職の人に先に退職の意思を伝えてしまうと、上司が監督責任を問われてしまう場合があります。
他にも、同僚や施設管理者など同じ職場で働く方に先に伝えると噂になって、職場全体に広まることも考えられます。トラブルを避けるためにも、最初は直属の上司に伝えるのがマナーです。
4-3. 理由はポジティブなものを伝える
退職理由はキャリアアップなどポジティブなものを伝えましょう。人間関係の悪さや給料の低さなど、不満を理由にすると引き止めにあったりトラブルになったりするケースもあるため、避けましょう。
ポジティブな理由としては、例えば「介護職として別の分野の施設で働きたい」「経験したことがない別の分野の仕事に挑戦したい」などです。ステップアップや前向きな理由の場合は引き止められにくくなり、円満に辞められる可能性が高くなるでしょう。
4-4. 引き止めにあったときの対処法を考えておく
退職を申し出ると引き止められることがあるため、あらかじめ対処法を考えておきましょう。よくある引き止め方と対処法は、以下をご参考ください。
・退職期限の引き延ばしをされる
退職の話し合いを避けられたり、退職期限を何度も引き延ばされたりした場合、自分で決めた退職期限を伝え続けましょう。退職の意思表示の証拠となる退職届を残して後任者に仕事の資料を作成すれば、トラブルを回避できます。
・待遇改善などで引き止められる
辞められたら困ると情に訴えられたり、待遇を改善するからと説得されたりするケースもあります。今の職場では叶えられない将来のビジョンや転職活動していることなどを伝えて、意志の固さをアピールするとよいでしょう。
・威圧や脅しをされる
退職の意思を伝えると、「そんなことでは他の事業所でも通用しない」などと威圧される場合があります。さらにひどいケースだと、「迷惑がかかる分の損害賠償請求する」と脅されることもあります。理不尽な要求はまともに取り合わず、損害賠償などの金銭を請求された場合は、労働基準監督署などの第三者に相談するとよいでしょう。
5. サービス提供責任者の転職後の活躍場所
サービス提供責任者は、転職してもさまざまな場所で活躍できます。サービス提供責任者が転職した後の主な選択肢は、以下の通りです。
・働きやすい職場に転職する
サービス提供責任者の仕事自体が嫌ではない場合は、今よりも働きやすい職場に転職するとよいでしょう。サービス提供責任者を募集している介護施設があれば、転職先で実務経験者として優遇されることがあります。
・介護士として転職する
サービス提供責任者の仕事を続けるのではなく、もう一度介護士として介護事業所で介護業務を担当することも選択肢の1つです。業務内容は介護現場での利用者さんのケア・支援が中心となり、安定した勤務時間で働きやすくなるでしょう。介護スタッフとしてある程度勤務時間が安定すれば、仕事と家庭の両立もしやすくなります。
・ケアマネジャーを目指す
サービス提供責任者はケアマネジャーとの関わりが多いため、ケアマネジャーの仕事に興味を持つ方も少なくありません。サービス提供責任者業務の中で身につけた訪問介護に関する知識や経験は、ケアマネジャーの業務に生かせるものも多くあります。特にサービス提供責任者には利用者さんの情報を把握・分析して最適なサービスを決定するという仕事があり、実務で得た経験はケアマネジャーの業務である介護計画書などの作成に役立ちます。
・介護以外の業界に転職する
介護業界に関わる職種ではなく、全く違う業界に進むという選択肢もあります。未経験の業界に転職する場合は、新しい分野に飛び込む覚悟や情報収集、新たな勉強が必要になります。
6. サービス責任提供者を長く続けるためのポイント
サービス提供責任者として長く働き続けていくためには、次の2点が重要なポイントとなります。
| 職場を見極めた上で入職する |
|---|
|
施設の運営方針やともに働くケアマネージャーの考え方、ヘルパーとの相性などを、自分から働きかけて変えるのは困難です。サービス提供責任者として働く場所を選ぶ段階で、運営方針や規模、施設の教育体制、どのような人たちが働いているかなどを確認し、自分の希望に合った施設を選ぶことが大切となります。 職場との相性は、求人広告やウェブサイトの情報だけでは判断が難しいので、知り合いがいたら内情を聞いたり、転職エージェントに特徴を聞いたりするのもおすすめです。 |
| 相談できる仲間や先輩を頼る |
|---|
|
環境は同じでも、相談できる人がいるかどうかで、実際にかかるストレスは大きく変わります。入職後はできるだけ早く信用できる仲間や先輩を見つけ、相談できる相手を作っておくことが大切です。 サービス提供責任者が複数配置されているなら、お互いに情報を交換するのもおすすめです。 |
まとめ
サービス提供責任者として働くメリットと現在の問題を比べた上で、この職を辞めたいと思えるなら、思い切って転職をするのも1つの手段です。転職にあたって一番避けたいのは、「こんなはずではなかった」と後悔することです。
しかし、キャリアプランを見据えて、自分にはどのような働き方が向いているのか、どのように働きたいのかを一人でまとめるのは、なかなか大変な作業です。
介護職内での転職を考える場合、実務経験が5年以上あるなら、試験を受けてケアマネージャーを目指せます。また、マネジメントより現場を希望するのであれば、一般の介護職に戻る道もあるでしょう。
「サービス提供責任者の仕事は好きだけれど、今の環境や待遇に不満がある」という場合は、サービス提供責任者として新たな職場を探すこともできます。しっかり自分で考え、情報が足りない場合にはエージェントにも聞いてみる事をお勧めします。
※当記事は2024年6月時点の情報をもとに作成しています
介護・福祉業界の転職事情|仕事の種類・平均給与・おすすめの資格
関連記事
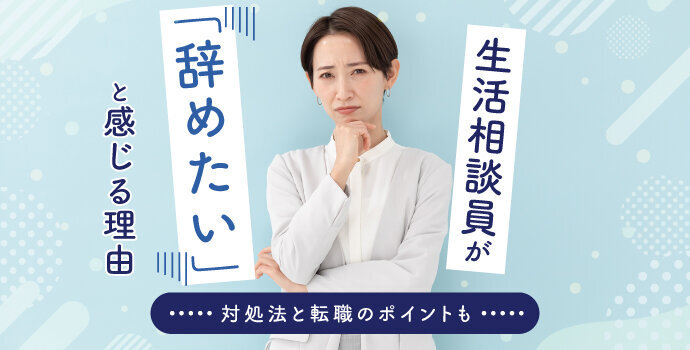
|
転職理由
| 公開日:2024.12.17 更新日:2024.12.17 |
生活相談員が「辞めたい」と感じる理由|対処法と転職のポイントも
生活相談員は、介護施設の入退所手続きから利用者さんとその家族の相談援助...(続きを読む)
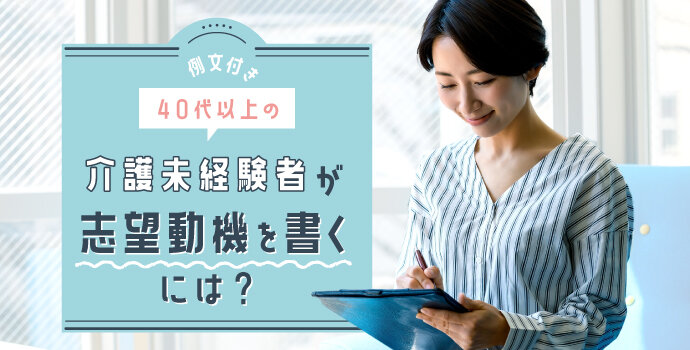
|
転職理由
| 公開日:2024.02.20 更新日:2024.04.02 |
【例文付き】40代以上の介護未経験者が志望動機を書くには?
介護業界は慢性的な人手不足状態に陥っているほか、選考にあたって応募者の...(続きを読む)

|
転職理由
| 公開日:2021.09.07 更新日:2024.12.05 |
介護職のよくある転職理由とは?転職が多い場合の志望動機の例文
「転職理由」は、採用面接で必ず聞かれる項目のひとつです。介護職の場合...(続きを読む)
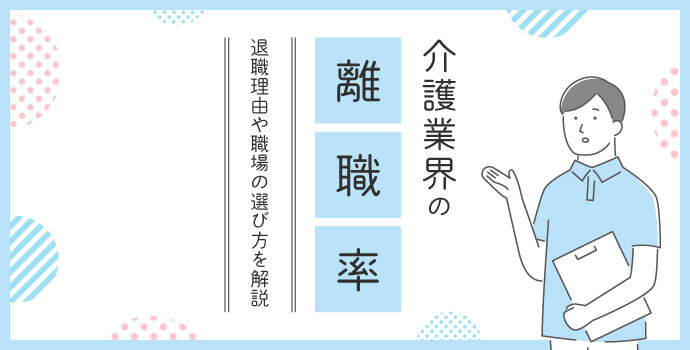
|
転職理由
| 公開日:2020.12.11 更新日:2024.07.12 |
介護業界の離職率|退職理由や職場の選び方を解説
介護業界は、人手不足や薄給激務のイメージを持たれがちです。しかし、令和...(続きを読む)