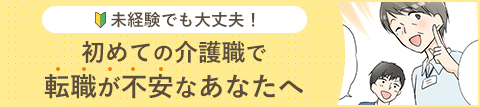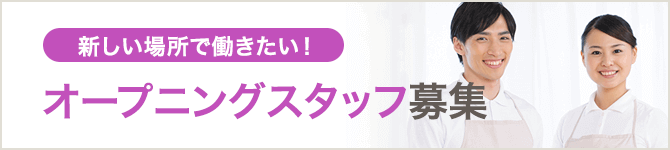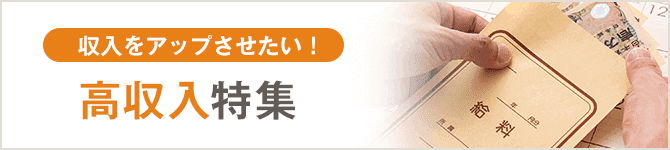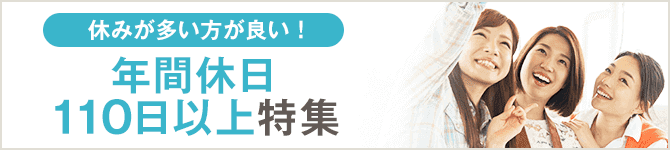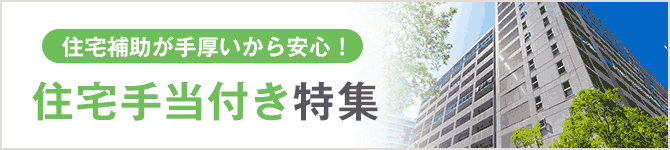生活相談員が「辞めたい」と感じる理由|対処法と転職のポイントも
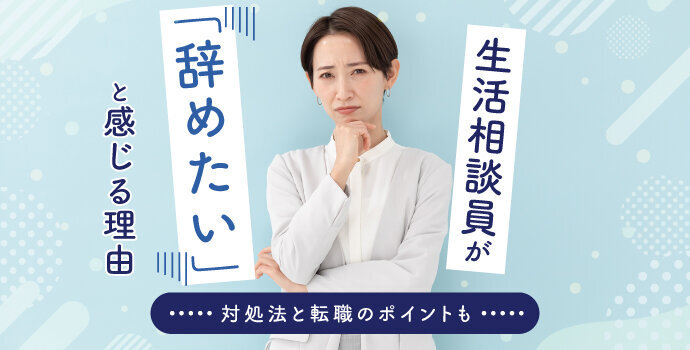
生活相談員は、介護施設の入退所手続きから利用者さんとその家族の相談援助、スタッフや外部の医療機関・地方自治体などとの連絡・調整までを、一手に担う職種です。
法令によって、特別養護老人ホームなどの介護施設には1名以上の配置が義務付けられているため、介護現場では欠かせない存在です。しかし、やりがいが大きい仕事である一方で業務の幅が広く、調整役としてプレッシャーや負担を感じることが多いことから、現在の職場を「辞めたい」と思う生活相談員も少なくありません。
就業先で後悔しないために、転職を決めたときの進路選びや、転職を成功させるポイントをご紹介します。
【無料】マイナビ介護職に登録して自分に合った職場がないか聞いてみる
目次
- 5. 生活相談員が転職を成功させるためのポイント
- 5-1. 転職先に求める条件を明確にしておく
- 5-2. 転職活動は在職中に始めておく
- 5-3. 応募先の職場環境や待遇を調べておく
- 5-4. 転職後のキャリアビジョンを明確にしておく
1. 「生活相談員を辞めたい」と感じる理由
生活相談員はやりがいのある仕事で、法的にも施設ごとの配置義務があるなど就職・転職にあたって有利な職業です。しかし、以下のような理由から「もう辞めたい」と考える方も存在します。
1-1. 板挟みによるストレスが大きい
生活相談員は、介護に関わる方たちの相談を受け、お互いの橋渡しをしながら意見を調整し、連携を図ることが仕事です。しかし、利用者さんやその家族、ケアマネジャー、施設の介護士、看護師、施設の運営者、さらには行政機関など、生活相談員が関わる人間は多岐にわたり、全員の意見を合わせることは容易ではありません。
「あちらの意見を聞くと、こちらから不満が出る」の板挟みとなって神経をすり減らし、ストレスから退職の道を選ぶという生活相談員も存在します。
1-2. 業務量の割に給与が少ない
厚生労働省の「令和4年度介護従事者処遇状況等調査」によると、介護職員の平均給与月額は317,540円であるのに対して、生活相談員・支援相談員の平均給与月額は342,330円です。 また、介護支援専門員(ケアマネジャー)の平均給与月額は361,770円でした。
(出典:厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査」
/
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/22/dl/r04kekka.pdf)
一般の介護職員には、経験の浅い方もキャリアのある方も含まれます。一方で、生活相談員はキャリアを積んで都道府県・自治体ごとに異なる社会福祉士・介護福祉士などの資格要件を満たさなければなれない役職です。
一般介護職から見れば、キャリアアップであるにもかかわらず、給与の面では一般職と大きな差がないことはデメリットと感じやすい点です。また、同じキャリアアップ職であるケアマネジャーに比べて、給与水準が低めであることも、生活相談員が転職を考える理由の1つと考えられます。
1-3. 悩みを相談できる相手がいない
特別養護老人ホームや介護老人保健施設では、利用者さん100人あたりに対し、常勤の生活相談員が1人以上という配置基準が定められています。介護職員の方に比べると生活相談員として働いている方の割合は少なく、施設によっては配置される生活相談員が1人だけの場合もあります。
介護職員の方は、同じ職種で働く方が周りに多いため、疑問や質問があってもすぐに相談可能です。一方、生活相談員の場合は、相談業務などで分からないことや悩みがあっても、相談相手がいない場合があります。
問題に対して自分1人で考えて解決しなければならず、愚痴や悩みを相談しにくい環境にストレスを感じる生活相談員もいます。
2. 生活相談員を続けるメリット
しかし、生活相談員の仕事は辛い・辞めたいと思うようなことばかりではありません。辞めたいと感じた場合は、現在の仕事のメリットに目を向けてみるとよいでしょう。生活相談員という職種ならではのメリットとして、次のようなものが挙げられます。
2-1. 夜勤なしで働ける
介護の現場で見ると、介護士の場合、施設勤務であれば早番、日勤、遅番、夜勤をシフト制で入るのが基本です。夜勤シフトに入れば、その分の手当は入りますが、昼夜逆転する生活になったり、友人や家族との時間を合わせ辛かったりといった弊害があります。
その点、生活相談員は日中勤務が基本なので、生活のリズムを整えやすい環境にあるのがメリットです。
2-2. 身体的な負担が少ない
業務で入浴介助なども行う介護士は、体力が必要な場面も多く、体に負担がかかってしまう場合もあります。生活相談員は基本的に現場で直接介護を行うことはないので、体力にそれほど自信がない方でも心配はありません。
2-3. やりがいを感じられる
生活相談員は、利用者やその家族に最初に対応する施設の顔です。また、スタッフの意見を調整して、満足度の高い介護サービスを提供するためには、なくてはならない縁の下の力持ちでもあります。自分の力量次第で、利用者やその家族に大きな満足を感じてもらうことができるため、やりがいを感じられる仕事だと言えるでしょう。
2-4. 多くの人に感謝される
さまざまな人をつなぐ業務は、大変な労力を必要としますが、その分、多くの人から感謝される仕事でもあります。利用者さんやその家族から直接「ありがとう」と言われる機会も多く、自分の仕事が人の役に立っていることを実感できます。
2-5. キャリアアップにつながる
生活相談員としての実務経験や知識はキャリアアップを目指すときに役立ちます。代表的なキャリアアップ先として、ケアマネジャーが挙げられます。
ケアマネジャーの資格は、生活相談員としての実務経験が5年以上あり、資格試験に合格することが資格要件の1つです。また、生活相談員から介護福祉施設の施設長や管理職を目指すことも可能です。
生活相談員の業務は、利用者さんやその家族と信頼関係を築くスキルが高められ、キャリアアップに生かせる貴重な経験を多く積めます。よりよい介護サービス実施に向けての生活相談員としての取り組みに活用できるため、現在の業務に課題を感じている場合は、キャリアアップを視野に入れるのがおすすめです。
3. 生活相談員を辞めたいと感じたときの対処法3選
生活相談員の業務は、体力面と精神面の両方で大変さを感じることがあります。しかし、生活相談員としての実務経験は、将来的なキャリアアップやビジョン達成を目指す際に重要であり、生活相談員として働き続けるメリットも多くあります。
一方、今後に向けて生活相談員としての仕事を継続する場合でも、ストレスを限界まで溜め込んでしまうと心身に影響を及ぼしかねません。
ここでは生活相談員を辞めたいと感じたときの対処法を3つ紹介します。具体的な対処法を知っておくことで、すぐに対処できる可能性も上がるため、参考にしてください。
3-1. 上司や管理職に相談して働き方を見直す
生活相談員として1人で業務にあたっている場合、周りに相談できず悩むことがあります。この場合、まずは上司や管理職に相談し、働き方を見直すのがおすすめです。
1人で悩みを抱え込んでしまうと、ストレスによる体調不良につながる恐れがあります。相談することで、1人では解決が難しかった悩みや業務における困りごとが解決し、状況が改善する場合があります。
相談する場合は、「仕事量が多く、負担が大きいため人員を増やしてほしい」など、具体的に伝えましょう。
3-2. 将来のビジョンを明確にして目標を設定する
「ケアマネジャーにキャリアアップしたい」「管理職を目指したい」など、目標を明確に設定することで仕事にやりがいが持てます。すぐにでも辞めたいと考えている場合でも、目標があれば現状を乗り越えられる可能性があります。1年後、5年後、10年後と区切り、より具体的にキャリアプランを考えて設定するのがおすすめです。
生活相談員の仕事は覚えることが多く、業務負担が大きいと感じる場合もあります。しかし、長い目で見ると着実に将来の目標に近づけると考えれば、乗り越えられる課題もあると言えます。
3-3. 別の職場に転職する
生活相談員の仕事は続けたいが、給与やそのほかの待遇・人間関係に不満があり、働き続けるのが難しい場合は、生活相談員として職場を変えるのもおすすめです。
施設によって利用者さんの対応人数や業務範囲、人間関係は異なります。今働いている職場だけで判断して生活相談員を辞めるのではなく、ほかの職場も検討することで、自分に合った環境を見つけられる可能性があります。
自分に合った職場が見つかれば、悩みが軽くなりストレスの少ない状態で生活相談員として働くことが可能です。また、別の職場に転職すると、業務内容や環境面の改善だけでなく、気持ちもリフレッシュした状態で仕事に取り組める効果が見込めます。
4. 生活相談員の業務経験を生かした3つの転職パターン
これまで長く働いてきたものの、生活相談員の仕事自体を辞めたいと考える方もいるでしょう。生活相談員の仕事で培ったスキルは別の仕事でも生かせる場合があり、転職時のアピールポイントにつながります。
ここでは、生活相談員の仕事を辞めたいと考えている方に向けて、生活相談員の業務経験を生かした転職パターンを3つ紹介します。
4-1. ケアマネジャー
ケアマネージャーは、介護サービスを利用する方のケアプランを作成するポジションです。生活相談員と同じマネジメント系の職種ですが、生活相談員は調整役として外に出ていく仕事を主に行います。対して、ケアマネージャーの仕事は、ケアプランの作成とその説明に特化しているケースも多い点が特徴です。
在宅介護と施設介護の両方で必要とされるため、活躍の場は広く、厚生労働省の調査結果では、平均給与水準も生活相談員より高くなっています。
ただし、ケアマネージャーになるには5年以上の介護実務経験を積んだ上で試験に合格し、実務実習を修了する必要があります。
4-2. 社会福祉士
社会福祉士は、身体的・精神的・経済的にハンディキャップを抱えている方やその家族の相談にのり、スムーズに日常生活を送れるよう、サポートするのが仕事です。的確なアドバイスや指導を行い、援助計画を立てて実行し、医療機関や行政と連携して公的手続きの代行や公的支援につなげていくことが業務の中心です。
職場は高齢者介護施設のほか、児童福祉施設や医療機関、地方自治体の福祉事務所、知的障害者施設、地域包括ケアセンターなどが挙げられます。
社会福祉士は、国家資格がなければ就けない職業であり、受験資格を得るには、福祉系大学・短大で、指定科目を履修しておく必要があります。卒業生でない場合は、一定期間の実務経験や養成施設に通うことが必要です。
4-3. 現場の介護職に戻る
介護福祉士の資格を生かして、再び介護士に戻る道もあります。夜勤があるなど、体力的に負担が大きくなる部分はありますが、マネジメントや調整役の仕事をするより、専門の道を極めたいという方には、介護士のほうが向いていると言えるでしょう。
日本政府が進めている介護人材の処遇改善政策では、経験豊富な介護福祉士を中心に報酬額引き上げが進められているため、将来的に給与が生活相談員を上回る可能性もあります。
5. 生活相談員が転職を成功させるためのポイント
自分に合った理想的な職場へ転職するには、事前に次の職場に求める条件や将来のビジョンを明確にし、計画的に転職活動を行うのが大切です。
ここでは、生活相談員が転職を成功させるために押さえておきたいポイントを解説します。
5-1. 転職先に求める条件を明確にしておく
生活相談員としてほかの職場に転職する場合や、別の職種に転職する場合に関わらず、自分の希望する職種や職場など、求める条件を明らかにしておく必要があります。希望の条件がすぐに思いつかない場合は、自分の退職理由から考えるのがおすすめです。
たとえば、1人で業務にあたる時間が多く、周りに相談しにくい環境で働く状況にストレスを感じて退職を考える方の場合を考えましょう。別の職場に転職しても、1人で業務にあたる環境であれば、同じく相談できないストレスを感じることになります。
1人で業務にあたるのがストレスであれば、ほかに同職種の方がいる環境や、周りに相談しやすい環境が整った職場を選ぶことが必要です。同じ理由で再度退職を考える状況を避けるためにも、転職先に求める条件を事前に洗い出してください。
5-2. 転職活動は在職中に始めておく
転職活動は、働きながらあるいは休職しながら、在職中から進め始めるのがおすすめです。転職先が未定のまま退職した場合、仕事がないことに焦りを感じ、急いで次の職場を決めてミスマッチが起こる可能性があります。
また、心身に限界を感じてから転職活動を行うと、無理をした状態で転職先を探すことになります。限界を感じる前に上司へ相談したり、転職活動を始めたりするなど早めの対処が重要です。
急いで転職活動をしたり、落ち着いての判断が難しい状態で転職活動をしたりした結果、転職理由になったポイントを抱える転職先に努めてしまう可能性もあります。時間、心身の状態に余裕を持ち、在職中から転職活動を始めましょう。
5-3. 応募先の職場環境や待遇を調べておく
求人に応募する際は、応募先の職場環境や待遇について十分下調べが必要です。職場の下調べが不十分な状態で応募し採用された場合、退職理由が解消されない状態のまま働くことになりかねません。
特に、職場環境や仕事内容、待遇面で不満があり退職する場合は、以下の方法で情報を収集するのがおすすめです。
・直接職場へ見学に行く
・転職エージェントや転職サイトを活用する
職場見学の場合、利用者さんや職員の方の表情、職場の様子を直接把握できます。また、転職サイトや転職エージェントを活用する場合は、実際に働いている方の声を参考に、自分が働く際の懸念点がないかを考えられます。
あらかじめ職場の雰囲気が分かっていれば気持ちの整理ができ、リラックスした状態で転職活動に臨めるため、入念に下調べすることが大切です。
5-4. 転職後のキャリアビジョンを明確にしておく
生活相談員を続ける場合もそうでない場合も、将来自分がどのように働きたいのかを考えておく必要があります。
たとえば、将来的にケアマネジャーを目指す場合、生活相談員として最低5年は働く必要があります。現在の職場環境にストレスがあり転職を考える際には、生活相談員の仕事自体を辞めるのではなく、生活相談員として働ける別の職場を探さなければなりません。
また、介護業界以外の業種に応募する場合も、キャリアビジョンが明確でないと具体的な志望動機が書けず、転職活動が難航する可能性があります。ほかの業種にチャレンジする際には、なぜその業種で働きたいのか、転職後のキャリアビジョンから逆算して考えることが大切です。
専門エージェントならではの強みがある、マイナビ介護職をご利用ください
現在の職場に満足していない方や、生活相談員への転職をお考えの方は、マイナビ介護職にご相談ください。
マイナビ介護職では、介護福祉系専門のコンサルタントが各職場の内情を丁寧にお伝えし、面談時に施設見学や直接現役スタッフから話を聞く機会も設けるなど、情報収集ができるよう、サポートします。
「転職しない」という選択肢を含めて、キャリアプランから一緒に考えていきますので、転職にお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。
※当記事は2024年6月時点の情報をもとに作成しています
介護業界の離職率と退職の理由|職場の選び方や転職のコツも紹介
介護職のベストな転職タイミングは?未経験者と経験者における違い
介護職へ転職するのにベストな時期はいつ?円満退職するためのポイントとは
介護・福祉業界の転職事情|仕事の種類・平均給与・おすすめの資格
関連記事
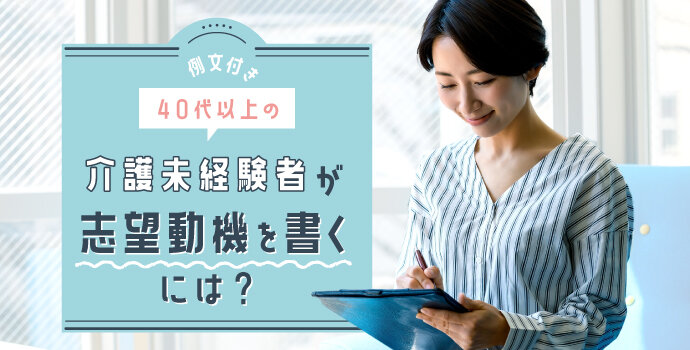
|
転職理由
| 公開日:2024.02.20 更新日:2024.04.02 |
【例文付き】40代以上の介護未経験者が志望動機を書くには?
介護業界は慢性的な人手不足状態に陥っているほか、選考にあたって応募者の...(続きを読む)

|
転職理由
| 公開日:2021.09.07 更新日:2024.12.05 |
介護職のよくある転職理由とは?転職が多い場合の志望動機の例文
「転職理由」は、採用面接で必ず聞かれる項目のひとつです。介護職の場合...(続きを読む)
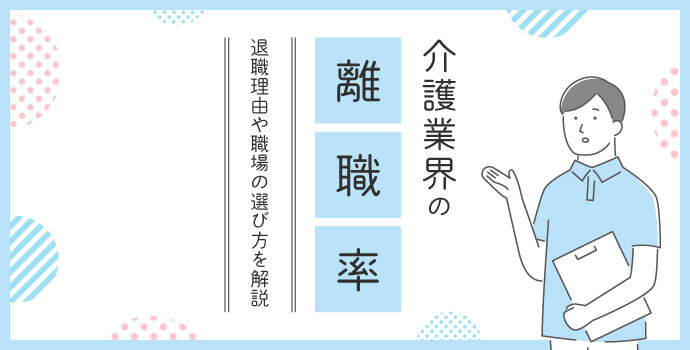
|
転職理由
| 公開日:2020.12.11 更新日:2024.07.12 |
介護業界の離職率|退職理由や職場の選び方を解説
介護業界は、人手不足や薄給激務のイメージを持たれがちです。しかし、令和...(続きを読む)

|
転職理由
| 公開日:2020.01.31 更新日:2024.12.17 |
サービス提供責任者が「辞めたい」と思ったら?転職・退職の選択肢も
サービス提供責任者は、利用者さんの立場で訪問介護計画を考え、計画どおり...(続きを読む)