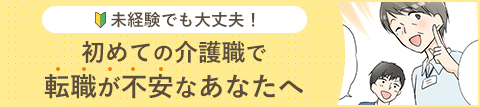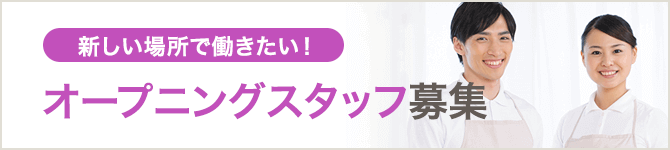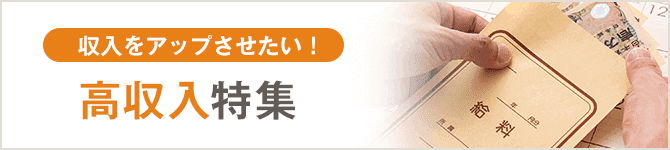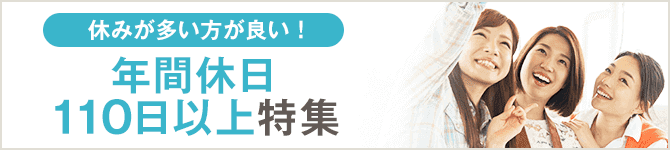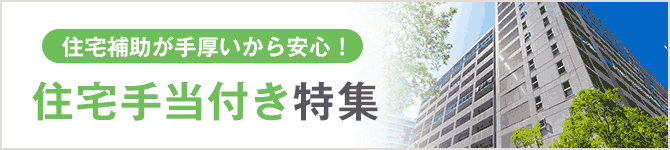介護士(介護福祉士)になるには?資格取得方法・試験内容を解説

超高齢社会を迎え、今後も高齢化が進むと予測される日本において、介護士は必要不可欠な職業の1つとして挙げられます。介護士の需要は非常に高いものの、介護人材は慢性的に不足しています。そのため、これから介護業界で働きたいという方で介護関連の資格を持たない方や未経験者でも、恐らく就職先に困ることはないでしょう。
当記事では、介護業務に直接携わる「介護士」「介護福祉士」について、職種の概要やそれぞれの職種に就く方法、資格取得に関する情報を紹介します。介護福祉士の仕事内容や、資格取得のメリット、さらに介護福祉士からステップアップする流れも併せて確認し、介護士としてのキャリアプランを考えてみましょう。
目次
1. 介護士とは?
介護士とは、介護の現場で介護業務に従事している方を表す言葉です。「介護士」は正式名称ではなく、一般的には介護職・介護スタッフ全般を指す言葉として広く定着しています。なお、当記事内においても、介護従事者を総称する表現として「介護士」を用いて解説します。
介護士の仕事は多岐にわたりますが、高齢者などの要介護者・要支援者に対する介護ケアの提供・生活補助・自立支援などが主な業務です。介護士が活躍できる場所は介護施設や訪問介護などさまざまであり、仕事内容は勤務先によって異なります。
2. 介護士になるには?
介護士になるには、「無資格可や未経験可の介護事業所を探して就職する」「介護職初任者研修を取得した後で、介護事業所を探して就職する」という2種類の方法があります。働きながら介護に関する基礎知識やスキルを身につけ、経験を重ねていきたい場合は前者の方法を、身体介護に従事する希望が強い場合は後者の方法を検討するとよいでしょう。
ここでは、介護士になるための方法について詳しく解説します。それぞれの方法の内容や働き方・業務内容の違いを確認し、自分に合った方法を選びましょう。
2-1. 無資格OKや未経験OKの介護事業所で働く
介護士として働くために取得必須とされる資格や実務年数などはありません。したがって、「無資格OK」「未経験OK」とする介護事業所であれば、介護に関する資格を保有していない方や介護未経験の方でも介護士として働くことができます。
ただし、介護系資格を保有していない方は、排泄介助、入浴介助、服薬介助、外出介助など、利用者さんの身体に触れる必要がある「身体介護業務」を1人で行うことができません。行える介護は、生活補助や介護補助などの業務に限定されます。
| 無資格の介護士が従事できる主な業務 |
|---|
|
●生活補助業務 介護事業所における「生活補助」とは、介護サービス利用者の身体に触れずにできる生活面のケアを指します。食事の準備・片付け、掃除・整理整頓や洗濯、買い物代行、ベッドメイクなどが含まれます。 ●身体介護業務の補助 介護施設内で介護福祉士などの資格を保有するスタッフの指導がある場合は、無資格の介護士も身体介護業務のサポートに入ることが可能です。レクリエーションの事前準備なども行います。 ●事務業務 介護事業所における電話や来客の対応、備品発注などの事務業務も、無資格の介護士が担当できる業務の1つです。ただし、介護保険に関する知識がなければ介護報酬の請求業務ができないことに注意しましょう。 ●送迎業務 通所型施設(デイサービスなど)では、利用者さんを自動車で送迎する業務も無資格の介護士が担当できます。普通自動車免許を取得していれば、送迎車のドライバーとして働くことも可能です。 |
介護士としてスキルアップしたい方には、実務経験を積みながら介護関連の資格取得を目指すのをおすすめします。資格取得に向けた受講料の補助など、資格取得の支援制度を用意している職場もあるため、まずは介護職員初任者研修の取得を目指しましょう。
【関連リンク】介護業界は無資格でも転職可能?できる仕事や面接でのポイントも
2-2. 2024年4月以降は認知症介護基礎研修の受講が必須
2021年4月に行われた介護報酬改定に伴い、2024年4月以降に無資格で介護士として働きたい場合は「認知症介護基礎研修」の受講が必須となります。
認知症介護基礎研修とは、認知症の方の介護に必要な知識・技術を習得できる公的研修です。2015年策定の「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」にもとづき、認知症介護に関する入門編の研修として創設されました。
認知症介護基礎研修の受講対象者は、介護施設において直接介護サービスに携わる無資格の職員のみとなっています。すでに医療福祉分野の国家資格を保有している方や介護関連の研修を修了している方の場合、受講する必要はありません。
2-3. 介護職員初任者研修を取得して介護事業所で働く
介護士になるための方法の1つとして、「介護職員初任者研修」を修了・取得した上で介護事業所に就職することが挙げられます。
介護職員初任者研修とは、「介護業務に従事する方が、基本的な業務を行えるようになること」を目的とした研修です。介護職員初任者研修の資格を取得するためには、下記の10科目の講座(講義・演習)を規定の時間数受講し、すべての課程を修了する必要があります。
| 介護職員初任者研修における研修科目・時間数 | ||
|---|---|---|
| 研修科目 | 時間数 | |
| 1 | 職務の理解 | 6時間 |
| 2 | 介護における尊厳の保持・自立支援 | 9時間 |
| 3 | 介護の基本 | 6時間 |
| 4 | 介護・福祉サービスの理解と医療との連携 | 9時間 |
| 5 | 介護におけるコミュニケーション技術 | 6時間 |
| 6 | 老化の理解 | 6時間 |
| 7 | 認知症の理解 | 6時間 |
| 8 | 障害の理解 | 3時間 |
| 9 | こころとからだのしくみと生活支援技術 | 75時間 |
| 10 | 振り返り | 4時間 |
| 合計 | 130時間 | |
(引用:厚生労働省「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修関係)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000331389.pdf 引用日2024/1/18)
介護職員初任者研修を履修すれば、介護業務に関する最低限の知識や介護提供能力、実践の際の思考プロセスを身につけられ、身体介護業務にも従事できるようになります。介護の現場で即戦力となるため就職活動・転職活動の際に有利になる可能性が高まります。また、無資格の介護士と比べて時給や月給などの待遇がよいケースも珍しくありません。
介護職員初任者研修は、介護関連資格の入門資格として位置付けられることが多く、正社員の求人では取得必須を採用条件とする就業先もあります。今後キャリアアップする上で重要な資格のため、介護士として活躍を続けたい方は取得をおすすめします。
介護職員初任者研修を修了するためには、受講者が修了試験を受けて合格する必要があります。試験日や試験時間、試験内容は実施するスクールによって異なりますが、おおむね次のような傾向があります。
| 介護職員初任者研修・修了試験の概要 |
|---|
|
【筆記試験】 ・試験時間...1時間 ・出題形式...選択式・記述式の混合型 ・設問数...32問以上 【実技試験】 ・知識に基づいた実践的な介護(体位変換や食事介助、移乗介助など) |
3. 介護福祉士は介護職向けの国家資格
介護福祉士とは、介護分野における唯一の国家資格であり、介護業務に関する多様な専門知識や高いスキルを身につけている職種 を指します。介護福祉士は介護士の中に含まれる職業であり、「社会福祉士及び介護福祉士法」では下記のように定義されています。
2 この法律において「社会福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者(第四十七条において「福祉サービス関係者等」という。)との連絡及び調整その他の援助を行うこと(第七条及び第四十七条の二において「相談援助」という。)を業とする者をいう。
(引用: e-Gov法令検索「社会福祉士及び介護福祉士法」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=362AC0000000030 引用日2024/1/18)
なお、介護福祉士は「名称独占資格」の1つであり、介護福祉士国家試験の合格者のみが、資格取得者として「介護福祉士」を名乗ることができます。
介護福祉士は、幅広い知識と高い専門スキルを保有しているため、介護業務全般に加えて、他の介護士の指導・教育などの人材育成・まとめ役を担う場合も少なくありません。介護リーダーやサービス提供責任者、施設長などの役職者になることも多く、要介護者・要支援者の社会活動支援や相談援助業務を任せられる場合もあります。
4. 介護福祉士資格を取得するメリット
介護士として働きたい方が介護福祉士の資格を取得することには、さまざまなメリットがあります。特に代表的なメリットは、下記の3つです。
●収入アップにつながる
●介護スキルがあると証明できる
●スキルアップにつながる
ここからは、それぞれのメリットについて詳しく説明します。
4-1. 収入アップにつながる
介護福祉士資格を取得する最大のメリットは、収入アップにつながる点です。
多くの介護施設では、介護福祉士資格をはじめとした医療福祉分野の資格を取得した方に向けて「資格手当」が用意されています。この資格手当によって、資格を取得したその月からスムーズに収入アップを実現することが可能です。
また、国は「介護職員処遇改善加算」という制度を設けています。介護職員処遇改善加算とは、要件を満たした介護施設に対し、職員の収入をアップするためのお金を支給するシステムです。対象の介護施設で働く職員は、介護福祉士資格を取得するだけでも大幅な昇給が見込まれるでしょう。
(出典:厚生労働省「「介護職員処遇改善加算」のご案内」
/
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199136.pdf)
4-2. 介護スキルがあると証明できる
介護に関する資格は豊富にありますが、その中でも介護福祉士資格は介護職唯一の国家資格です。一定以上の介護知識・技術がなければ取得できないことから、介護福祉士資格者は「介護レベルが高い人材」とみなされます。
慢性的な人手不足に陥っている介護業界においては、即戦力として働ける人材を優先的に採用する傾向にあります。介護福祉士の国家資格保有者は「介護に関する確かなスキルと経験がある」と判断され、採用率が大きくアップするでしょう。
4-3. スキルアップにつながる
介護職唯一の国家資格である介護福祉士資格よりも、取得難易度の高い上位資格はいくつか存在します。ケアマネジャーや認定介護福祉士は、代表的な上位資格となります。これら上位資格を取得することで、昇進・昇給も大いに期待できるでしょう。
上位資格を取得するためには、介護福祉士資格と介護福祉士としての実務経験が必須です。介護福祉士資格の取得が遅いと上位資格をスムーズに取得できなくなり、スキルアップの機会も遠のいてしまいます。
今後のキャリアプランとして、ケアマネジャーや認定介護福祉士として働くことも視野に入れている場合は、できる限り早い段階で介護福祉士資格を取得するとよいでしょう。
5. 介護福祉士になるには?
介護福祉士資格を取得するためには、大きく分けて「実務経験ルート」「養成施設ルート」「福祉系高等学校ルート」の3つのルートがあります。各ルートにはそれぞれ、適している方・試験内容・取得期間などが異なるため、各ルートの概要を把握することが大切です。
5-1. ルート1:3年以上の実務経験を積む
実務経験ルートは、病院や介護施設で働きながら介護福祉士国家試験の受験を目指すルートを指します。
社会人の場合は、未経験・無資格から働ける施設に就職して勤務を行いながら、3年後に受験資格を得る実務経験ルートが一般的です。働きながら介護福祉士国家試験の受験資格を得られるため、収入を減らすことなく介護福祉士資格の取得を目指せます。異業種から未経験で介護職へ転職したいと考える方にとっては、学校に通い直す必要がないルートとなるため、最も目指しやすい方法です。
なお、介護福祉士国家試験の受験資格を得るためには、実務経験3年以上と「介護福祉士実務者研修」を修了していることが必須条件です。よって、介護福祉士資格を取得するまでに、最短でも3年かかります。
5-2. ルート2:養成施設に入学する
養成施設ルートは、高等学校卒業後、国が指定した介護福祉士養成施設で学ぶことで資格取得を目指すルートです。そのため、養成施設ルートは主に高校生に適したルートとなります。
養成施設は、専門学校・短期大学・大学のいずれかです。高等学校卒業後、養成施設に2年以上通うことで介護福祉士の受験資格を得られます。最短2年で取得できるため、社会人であっても養成施設に通う時間とお金がある場合は、養成施設ルートを選ぶことも選択肢の1つと言えます。
なお、福祉系大学や社会福祉士養成施設・保育士養成施設を卒業している方は、養成施設に1年以上通えば受験資格を得ることが可能です。
5-3. ルート3:福祉系高等学校に入学する
福祉系高等学校ルートは、福祉系高等学校、福祉系特例高等学校に通い、介護福祉士資格の受験資格を得るルートです。一般的に中学生におすすめの方法であり、転職者が福祉系高等学校ルートを選ぶことは稀と言えます。
なお、福祉系高等学校は定員充足率が80%前後であるため、福祉系高等学校に入学することは、比較的容易な傾向です。
(出典: 厚生労働省「介護福祉士資格の取得方法について」)
6. 状況別!介護福祉士になるには?
介護福祉士の資格取得ルートは複数あるため、自身の状況に合ったルートを選ぶことが大切です。ここでは、状況別にどのようなルートを選べばよいか確認しましょう。
| 【状況別】介護福祉士になるためのルート |
|---|
|
●ホームヘルパーとして働いている場合 現在、ホームヘルパー(訪問介護員)として働いている場合、実務経験ルートで介護福祉士資格の取得を目指すこととなります。介護福祉士試験の受験資格として、実務経験や実務者研修修了(予定)の期日も定められているため、スケジュールに注意して申し込みましょう。 ●社会人として別の仕事に就いている場合 介護以外の業界で働いている方の場合、「介護現場で働く(実務経験ルート)」「介護福祉士養成施設を卒業する(養成施設ルート)」の2通りのルートが考えられます。 ●最終学歴が中卒の場合 介護福祉士国家試験を受けるために満たすべき学歴や年齢の条件はありません。最終学歴が中卒の場合も受験できますが、「3年以上の実務経験を得た上で介護福祉士実務者研修を修了する」という実務経験ルートのみとなることに注意しましょう。 |
6-1. 介護福祉士になれる年齢は何歳まで?
介護福祉士に年齢は関係なく、何歳でも目指すことが可能です。
介護福祉士国家試験の合格者の年齢層を見ると、幅広い年代の方が資格取得を目指していることが分かります。
【年齢別の介護福祉士の合格者数】
| 年齢区分(歳) | 人数(人) | 割合(%)※ |
|---|---|---|
| ~20 | 5,001 | 7.5 |
| 21~30 | 16,934 | 25.4 |
| 31~40 | 12,920 | 19.4 |
| 41~50 | 16,877 | 25.3 |
| 51~60 | 12,197 | 18.3 |
| 61~ | 2,782 | 4.2 |
| 計 | 66,711 | 100.0 |
(出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター「第35回介護福祉士国家試験の合格発表について」
/
https://www.sssc.or.jp/kaigo/past_exam/pdf/no35/k_happyou.pdf)
※割合は、小数点第2位を四捨五入しているため、必ずしも合計とは一致しない。
特に多いのは「21~30歳」と「41~50歳」であり、若い方だけでなく40代以降の方も資格取得を目指しています。40代以降の合格者は合計で47.8%と、全体の半数近くを占めていることも読み取れます。
また、割合は少ないものの、中には61歳以降で介護福祉士資格を取得する方もいます。
7. 【ルート別】介護福祉士になるために必要な経験・費用
前述の通り、介護福祉士を目指すためのルートには「実務経験ルート」「養成施設ルート」「福祉系高校ルート」の3つがあります。各ルートの必要な実務経験および履修時間は、下記の通りです。
| 実務経験ルート | 実務経験1095日以上、かつ従事日数540日以上 |
|---|---|
| 養成施設ルート | 1850時間以上(2年以上)の履修時間 |
| 福祉系高校ルート | 1855時間以上(3年以上)の履修時間 |
なお、実務経験ルートの場合は上記の実務経験に加え、実務者研修または介護職員基礎研修・喀痰吸引等研修の修了が必要となります。
介護福祉士になるためのルートのうち、最も費用がかからないルートは実務経験ルートです。実務経験ルートにおける、資格取得までにかかる費用はおよそ10万〜20万円です。ただし、筆記試験の対策方法などにより、費用の総額は前後します。
養成施設ルート・福祉系高等学校ルートは、通う学校によって費用が変動します。養成施設ルートは100万〜400万円程度、福祉系高等学校ルートは200万〜400万円程度が目安です。
8. 介護福祉士の受験資格である「実務者研修」とは
介護福祉士の資格を得るために、求められる要件の1つが「実務者研修の修了」です。実務者研修は、全国各地の資格スクールで開講されており、誰でも有料で受講できます。
下記は、実務者研修を受講することで得られるメリットです。介護福祉士国家試験の受験要件を満たす以外にも、さまざまなメリットがあります。
●介護福祉士国家試験の実技試験が免除される
●介護経験の有無に関係なく、サービス提供責任者になることができる
●たん吸引・経管栄養などの専門的な知識を活かした業務を担当できる
●職場によっては資格手当を得られる
特に訪問介護事業所では、サービス提供責任者を利用者の数に応じて配置しなければならないという規定があります。そのため、サービス提供責任者は需要が高く、実務者研修を受講することで就職先の選択肢が増えるでしょう。
8-1. 実務者研修の取得方法とカリキュラム
実務者研修は、合計450時間のカリキュラムを受講する必要があります。ただし、介護関連資格の保有者は、保有資格によって一部の科目が免除されます。
下記は、実務者研修のカリキュラム・保有資格ごとの免除科目です。
| 科目名 | 所要時間数 (時間) |
初任者研修目 | ヘルパー1級 | ヘルパー2級 | ヘルパー3級 | 介護職員 基礎研修 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間の尊厳と自立 | 5 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 |
| 社会の理解Ⅰ | 5 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 |
| 社会の理解Ⅱ | 30 | ○ | 免除 | ○ | ○ | 免除 |
| 介護の基本Ⅰ | 10 | 免除 | 免除 | 免除 | ○ | 免除 |
| 介護の基本Ⅱ | 20 | ○ | 免除 | 免除 | ○ | 免除 |
| コミュニケーション 技術 |
20 | ○ | 免除 | ○ | ○ | 免除 |
| 生活支援技術Ⅰ | 20 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 |
| 生活支援技術Ⅱ | 30 | 免除 | 免除 | 免除 | ○ | 免除 |
| 介護過程Ⅰ | 20 | 免除 | 免除 | 免除 | ○ | 免除 |
| 介護過程Ⅱ | 25 | ○ | 免除 | ○ | ○ | 免除 |
| 介護過程Ⅲ | 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | 免除 |
| 発達と老化の理解Ⅰ | 10 | ○ | 免除 | ○ | ○ | 免除 |
| 発達と老化の理解Ⅱ | 20 | ○ | 免除 | ○ | ○ | 免除 |
| 認知症の理解Ⅰ | 10 | 免除 | 免除 | ○ | ○ | 免除 |
| 認知症の理解Ⅱ | 20 | ○ | 免除 | ○ | ○ | 免除 |
| 障害の理解Ⅰ | 10 | 免除 | 免除 | ○ | ○ | 免除 |
| 障害の理解Ⅱ | 20 | ○ | 免除 | ○ | ○ | 免除 |
| こころとからだの しくみⅠ |
20 | 免除 | 免除 | 免除 | ○ | 免除 |
| こころとからだの しくみⅡ |
60 | ○ | 免除 | ○ | ○ | 免除 |
| 医療的ケア | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 受講時間数 | 450 | 320 | 95 | 320 | 420 | 50 |
※〇印は受講が必要な科目です
(出典: 厚生労働省「介護福祉士の資格取得方法の見直しの延期について」)
なお、たん吸引など、より専門的・実践的な知識を学ぶ講義である「医療ケア」は、講義とは別に演習を修了する必要があります。実務者研修を実施するスクールの中には、夜間に開講しているスクールもあるため、自分のライフスタイルに合った方法で受講しましょう。
8-2. 実務者研修を修了するための費用・期間
実務者研修を修了するための費用相場は10万〜20万円です。ただし、受講するスクールや保有資格によって費用相場は前後します。
実務者研修をより安く受講したい方は、「専門実践教育訓練給付金」を利用することがおすすめです。専門実践教育訓練給付金は、国が行う教育訓練給付制度の1つです。雇用保険の加入期間などの条件を満たすことで、教育訓練施設の受講にかかる費用を、一定の割合額でハローワークから受給できます。
また、実務者研修を修了するまでの期間も、保有資格によって異なります。例えば、無資格者の場合、450時間の実務者研修を受講しなければならないため、6か月ほどかかります。
介護福祉士国家試験を受ける手続きを含めると、遅くとも8月までに実務者研修の受講を開始し、12月31日までに終えなければなりません。
9. 介護福祉士になるには国家試験合格が必須
介護福祉士国家試験は毎年1回開催され、筆記試験が1月下旬・実技試験が3月下旬に行われます。 なお、介護福祉士国家試験の受験資格は卒業見込みでも得られるため、学生は卒業年の受験が可能です。
実務経験ルートの場合、3年の実務経験が必要です。最短での受験を目指したい場合は、秋頃~年内までに働き始められるようにするとよいでしょう。また、実務経験ルートの場合は、実務経験が3年以上あること・実務者研修を修了していることから、実技試験が免除されます。
9-1. 筆記試験の日程・試験地
介護福祉士国家試験の筆記試験は毎年1月下旬、そして実技試験は毎年3月上旬に行われます。下記は、令和5年度における第36回介護福祉士国家試験の各種試験日です。
| 筆記試験 | 2024年1月28日(日曜日) |
|---|---|
| 実技試験 | 2024年3月3日(日曜日) |
なお、第36回試験における筆記試験と実技試験の試験地は下記の通りとなっています。
【筆記試験の試験地】
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
(引用:公益財団法人社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験 試験概要」
/
https://www.sssc.or.jp/kaigo/gaiyou.html 引用日2024/1/7)
【実技試験の試験地】
東京都、大阪府
(引用:公益財団法人社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験 試験概要」
/
https://www.sssc.or.jp/kaigo/gaiyou.html 引用日2024/1/7)
実技試験の試験地は、筆記試験の試験地よりも非常に少ないことが分かります。
しかし、実技試験の対象者は2008年以前に福祉系高校の旧カリキュラムを修了した方、または2009年以降に特例高校に入学し、介護技術講習を修了していない方のみとなります。そのため、基本的に大半の受験者は実技試験を免除できることを覚えておきましょう。
9-2. 試験内容と合格率
介護福祉士国家試験では、4領域11科目群の試験科目と事例形式で出題する総合問題からなる、計125問が出題されます。出題形式はすべて五肢択一であり、5つの選択肢から「正しいもの・適切なもの」を1つ選ぶ形となっています。
試験時間は午前(10:00~11:50)と午後(13:45~15:35)に分けられ、計220分で実施されます。
| 試験時間 | 領域 | 試験科目 | 出題数 |
|---|---|---|---|
| 午前 | 人間と社会 | 人間の尊厳と自立 | 18 |
| 人間関係とコミュニケーション | |||
| 社会の理解 | |||
| こころとからだのしくみ | こころとからだのしくみ | 40 | |
| 発達と老化の理解 | |||
| 認知症の理解 | |||
| 障害の理解 | |||
| 医療的ケア | 医療的ケア | 5 | |
| 午後 | 介護 | 介護の基本 | 50 |
| コミュニケーション技術 | |||
| 生活支援技術 | |||
| 介護過程 | |||
| 総合問題 | 12 | ||
(出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験科目別出題基準」
/
https://www.sssc.or.jp/kaigo/kijun/pdf/pdf_kijun_k_no35.pdf)
配点は1問1点の125点満点です。合格基準は総得点の約60%であり、11科目すべてに得点がなければ合格できません。なお、合格率は基本的に70%で推移していますが、第35回(令和4年度)試験では合格率80%を超えました。
【第33回(令和元年度)試験~第35回(令和4年度)試験の合格率推移】
| 第35回(令和4年度)試験 | 84.3% |
| 第34回(令和3年度)試験 | 72.3% |
| 第33回(令和2年度)試験 | 71.0% |
| 第32回(令和元年度)試験 | 69.9% |
(出典:厚生労働省「介護福祉士国家試験の受験者・合格者の推移」
/
https://www.mhlw.go.jp/content/12004000/001073942.pdf)
9-3. 筆記試験の申し込み方法
介護福祉士国家試験の筆記試験を申し込む前には、公益財団法人社会福祉振興・試験センターへ「受験の手引き」を請求する必要があります。受験の手引きには、筆記試験の申し込みに必要となる書類が含まれています。
下記は、筆記試験の申し込みに関する具体的なスケジュールです。
(1)公益財団法人社会福祉振興・試験センターへ「受験の手引き」を請求する
(2)8月上旬から9月上旬までの間に必要書類を提出し、申し込む
(3)12月ごろに受験票が送付される
筆記試験は8月上旬から申し込み可能となるため、「受験の手引き」は7月中に請求手続きを済ませるとよいでしょう。
9-4. 合格後には介護福祉士の登録を
介護福祉士になるためには、介護福祉士国家試験に合格後、介護福祉士資格登録を行う必要があります。登録先は、公益財団法人社会福祉振興・試験センターです。介護福祉士国家試験の合格のみでは、介護福祉士として名乗ることができないため、忘れずに登録を行いましょう。
下記は、介護福祉士資格登録を行う際に提出しなければならない書類をまとめた表です。
【提出書類一覧】
| 1 | ・登録申請書 ・登録免許税の収入印紙原本(9,000円) |
|
|---|---|---|
| 2 | ・貼り付け用紙 ・登録手数料の振替払込受付証明書(お客様用)の原本(3,320円) |
|
| 3 | 下記ア・イ・ウのいずれか1通 ア 戸籍抄本の原本 イ 戸籍の個人事項証明書の原本 ウ 本籍を記載した住民票の原本 |
外国籍の場合: ・国籍等を記載した住民票の原本(中長期在留者、特別永住者) ・パスポートなど身分を証する書類のコピー(短期滞在者) |
| 4 | 介護福祉士養成施設の卒業証明書の原本(※) ※提出が必要なのは以下のいずれかの方のみ ・2017年3月31日までに介護福祉士養成施設を卒業した者 ・2017年4月1日から2027年3月31日までに介護福祉士養成施設を卒業し、経過措置による登録を受ける者 |
|
(出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター「資格登録(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士)」
/
https://www.sssc.or.jp/touroku/shinki.html)
これらの書類を試験センターに簡易書留で提出したのち、審査・登録が行われます。万が一必要書類に不備や漏れがあった場合は返送され登録が遅れるため、正しく準備できたかを必ず確認しておきましょう。提出後は約1か月程度で登録証が自宅へ発送されるため、受け取りも忘れないでください。
10. 介護福祉士の国家試験に向けた勉強方法
介護福祉士国家試験の筆記試験対策は、市販されている問題集やテキストを用いて独学で進めることができます。
下記は、時期ごとの勉強ポイントです。
| 時期 | 勉強のポイント |
|---|---|
| 7月ごろ | 最新版のテキストを1冊以上は購入し、法改正など変更点の確認を行います。受験対策の大まかな計画を練りましょう。 |
| 10月ごろ | テキストに沿って、各科目の学習を進めましょう。 |
| 12月ごろ | 過去問やテキストの予想問題で実力を養う時期です。弱点分野も重点的に学習しましょう。 |
| 1月(受験月) | 過去問などで最終確認を行いつつ、体調管理を行うことも重要です。 |
また、過去問やテキストの問題を解くときは、下記の点を意識しましょう。
●全科目まんべんなく勉強する
●間違えた問題・不安のある部分はメモする
●メモした部分を繰り返し学習する
●過去問を分析して出題形式や傾向を理解する
●試験の時間配分を意識する
●空欄回答を出さない
なお、独学で勉強を進めることが難しい場合は、通信講座を活用する方法もおすすめです。 通信講座のカリキュラムを終えるまでにかかる時間は、およそ4〜6か月となります。
また、学校に通える余裕がある場合は、1か月半程度で試験の要点を押さえられる通学の短期コースを利用する選択肢もあります。
11. 介護福祉士になった後の仕事内容
介護福祉士の試験に合格し所定の手続きを終えた後は、有資格者として福祉施設などで働くことができます。 下記は、介護福祉士の主な仕事内容です。
●食事や排せつなどの身体介助
●洗濯や掃除など生活援助
●レクリエーションの企画・実施
●家族や利用者さんに対する相談・助言
●利用者さんへの社会活動支援
●スタッフや現場のマネジメント
ただし、介護施設の種類は多岐にわたるため、勤務先の施設・場所によって仕事内容が異なります。
介護福祉士の有資格者の中には、サービス提供責任者などに任命される方や現場経験をもとに介護福祉士養成施設の講師を目指す方もいます。介護福祉士資格を活かした、さまざまなキャリア形成が可能です。
【関連リンク】介護職のやりがい・魅力は?活躍できる施設の特徴やキャリアプランも
11-1. 介護福祉士の仕事で得られるやりがい
介護職は、無資格者でも介護福祉施設などで働くことが可能です。しかし、無資格者の場合、すべての業務を任されるわけではありません。
介護福祉士資格の取得者となって初めて担当できる業務もあり、仕事の充実感をより得られるようになるでしょう。
下記は、介護福祉士の仕事で得られる主なやりがいです。
●無資格時と比べて、専門性の高い介護業務を行える
●アドバイスを求められるなど頼られることが多くなる
●利用者や家族から感謝される機会が増える
また、厚生労働省によれば、常勤の介護福祉士の平均月給は33万1,690円と、保有資格がない場合と比較して約6万円高いというデータが明らかになっています。
(出典:厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」
/
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/22/dl/r04gaiyou.pdf)
12. 介護福祉士からステップアップするためには
介護福祉士からステップアップするために、おすすめな資格として下記の2つが挙げられます。
●ケアマネジャー
●認定介護福祉士
介護福祉士として実務経験を積む中で、ケアマネージャー・認定介護福祉士などの上位資格を取得することが可能です。新たな資格を取得することで、現在の職場で活かすことはもちろん、好待遇を狙った転職にも役立つでしょう。
下記では、ケアマネージャー・認定介護福祉士の概要を紹介します。
12-1. ケアマネジャーを目指す
ケアマネジャーとは、介護に関する豊富な知識を持つスペシャリストであり、介護支援専門員とも呼ばれます。ケアマネジャーの主な仕事内容は、ケアプランの作成・サービス事業者などとの調整であり、管理業務が多い傾向です。
下記は、ケアマネージャーの概要です。
| 主な職場 | ●福祉施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設など) ●自治体の介護相談窓口 ●介護関連商品を提供する一般企業 |
|---|---|
| 資格の取得方法 | 以下の要件を満たすことで取得可能 ●指定業務に5年以上かつ900日以上従事する ●介護支援専門員実務研修受講試験に合格する ●所定の研修を受け、登録手続きを完了する ●資格証の交付を受ける |
また、厚生労働省によれば、月給・常勤のケアマネジャー(介護支援専門員)の平均給与は、介護福祉士と比較して約4.4万円高いというデータが明らかになっています。
(出典:厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」
/
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/22/dl/r04gaiyou.pdf)
12-2. 認定介護福祉士の資格を取る
認定介護福祉士は、一般社団法人認定介護福祉士認証・認定機構が運営する、民間資格の一種です。医療・リハビリ分野など、介護福祉士よりもさらに広い専門知識を得られる点が特徴となります。
また、サービスマネージャーとして、10人未満の介護職のチームに対する教育指導・マネジメントを行い、サービスの質向上を促す役割も担います。
下記は、認定介護福祉士の概要です。
| 主な職場 |
●介護施設 ・介護サービスの事業所 ●自治体の介護相談の窓口 ●訪問看護などを行う医療施設 |
|---|---|
| 資格の 取得方法 |
以下の要件を満たすことで取得可能 ●介護福祉士として5年以上の実務経験がある ●認定介護福祉士の養成研修を修了する |
認定介護福祉士の平均月給についてはデータが公開されていませんが、目安として介護福祉士の平均月給は約33万円です。職場によっては、認定介護士にリーダー手当がついたり、介護福祉士と認定介護福祉士の月給に大きな差がなかったりします。
(出典:厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」
/
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/22/dl/r04gaiyou.pdf)
13. 介護職の役に立つその他の資格は?
介護関連の資格はケアマネジャーや認定介護福祉士以外にも豊富にあり、無資格・未経験者でも取得を目指せる資格も多くあります。
ここからは、業務に役立つ介護系資格を4つ、それぞれ概要と取得方法とともに詳しく紹介します。介護資格取得によって、知識・技術の習得やスキルアップを目指したいという方は、ぜひ参考にしてください。
13-1. 喀痰吸引等研修
喀痰吸引等研修とは、「たん吸引」や「経管栄養」を行える介護人材の養成を目的とした研修です。たん吸引や経管栄養は医療行為にあたるため、原則として介護職員が行うことは禁止されています。
しかし、喀痰吸引等研修を修了した介護職員はたん吸引に関する一部の医療ケアを提供することができます。介護現場において活躍の場が広がるほか、スキルアップ・給料アップにもつながるでしょう。
喀痰吸引等研修を受講するためには、申込受付期間内に研修の実施事業所・養成所へ申込書類を提出し、研修の種類に応じて受講料を支払う必要があります。研修を修了した後は、実施後提出書類一式を提出することで、一部医療行為を実施できるようになります。
13-2. レクリエーション介護士
レクリエーション介護士とは、利用者さんが楽しめるレクリエーションを企画・実施できる介護人材の育成を目的とした資格です。レクリエーション活動の質を高めたいという現場の声から2014年に誕生した当資格は、利用者さんのQOLの向上に大きく貢献しています。
レクリエーション介護士は2級と1級に分けられています。レクリエーション介護士2級を取得するためには、日本アクティブコミュニティ協会の認定機関で通信講座または通学講座を受講する必要があります。年齢や経験、さらに資格といった条件はなく、誰もが受講できます。
また、レクリエーション介護士1級はレクリエーション介護士2級を保有している方のみが受講できる上級資格です。取得するためには、全4日間にわたる通信講座または通学講座の受講に加え、日本アクティブコミュニティ協会が指定する会場にて本試験に合格したのち、3施設分の現場実習を実施する必要があります。これらの課程を経なければ、認定書を発行してもらえません。
13-3. ガイドヘルパー
ガイドヘルパーとは、何らかの障がいが原因で、屋外での移動に困難を有する方の外出支援を行える介護人材の育成を目的とした資格です。「移動介護従事者」とも呼ばれています。
ガイドヘルパー資格の取得を目指すためには、都道府県または市町村が指定した通学講座での養成研修を受ける必要があります。
ガイドヘルパーの養成研修には「視覚障がい者同行援護従業者養成研修」と「全身性障がい者ガイドヘルパー養成研修」、さらに「知的・精神障がい者行動援護従業者養成研修」など、障がいの内容に応じて3つの種類があります。それぞれ、受講条件やカリキュラム内容、受講期間が細かに異なります。
13-4. 認知症ケア専門士
認知症ケア専門士とは、認知症ケアに関する専門的な知識・技術と倫理観を備えた、いわば「認知症介護のプロフェッショナル」の育成を目的とした資格です。
認知症ケア専門士の資格を取得するためには、五肢択一形式の筆記試験である第1次試験と論述・研修形式の第2次試験を受験し、合格する必要があります。受験に必須となる資格はありませんが、「受験前10年間における認知症ケアの3年以上の実務経験」という条件を満たしておかなければなりません。また、試験合格後に認知症ケア専門士として認定を受けるためには、登録申請と登録申請料の支払いを行う必要があることも覚えておきましょう。
なお、認知症ケア専門士の上級資格として「認知症ケア上級専門士」、そして下位資格には「認知症ケア准専門士」もあります。認知症ケア分野においてさらなるスキルアップを目指したい場合は認知症ケア上級専門士を、認知症ケアに関する実務経験が足りていない場合は認知症ケア准専門士を取得するのもよいでしょう。
14. 介護士としてのキャリアアップを目指すなら介護福祉士を目指そう
介護士としてキャリアアップしたいと考える場合は、国家資格である介護福祉士の取得が必須と言えます。
キャリアアップの一例としては、介護主任(介護リーダー)・施設長などの上位職へのステップアップが挙げられます。
ポジションが上がれば大幅な給与アップが期待できる一方で、介護知識や基礎技術以外にマネジメントスキルなども求められるようになるでしょう。そのため、ケアマネージャー・認定介護福祉士といった上位資格の取得にも励むことがおすすめです。
介護系資格を取得した上で、介護業界への就職・転職を検討している方は、ぜひマイナビ介護職の無料転職サポートをご利用ください。業界に精通したキャリアアドバイザーが一人ひとりの要望に応じておすすめの介護求人をご紹介いたします。
※当記事は2024年1月時点の情報をもとに作成しています。
介護・福祉業界の転職事情|仕事の種類・平均給与・おすすめの資格
関連記事

|
資格
| 公開日:2025.04.15 更新日:2025.04.15 |
ホームヘルパーとは?必要な資格や介護福祉士との違いを解説
ホームヘルパーは、高齢者や障害者が自宅で安心して生活できるよう、居宅を...(続きを読む)
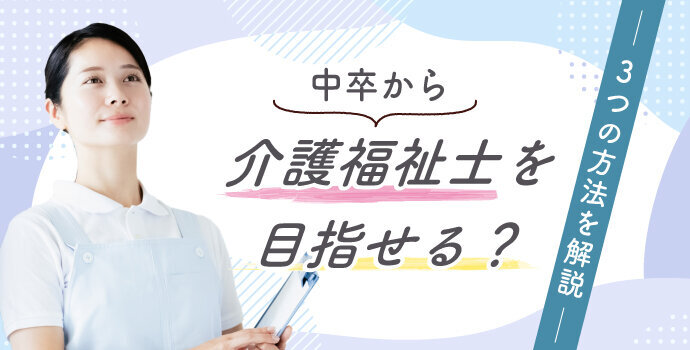
|
資格
| 公開日:2024.12.17 更新日:2024.12.17 |
中卒から介護福祉士を目指せる?3つの方法を解説
介護福祉士の資格を取得するためには、いくつかの条件があります。介護福祉...(続きを読む)

|
資格
| 公開日:2024.08.21 更新日:2024.08.21 |
介護福祉士の資格でできる仕事には何がある?主な転職先について解説
介護の専門資格である介護福祉士を取得することで、無資格の状態に比べて、...(続きを読む)
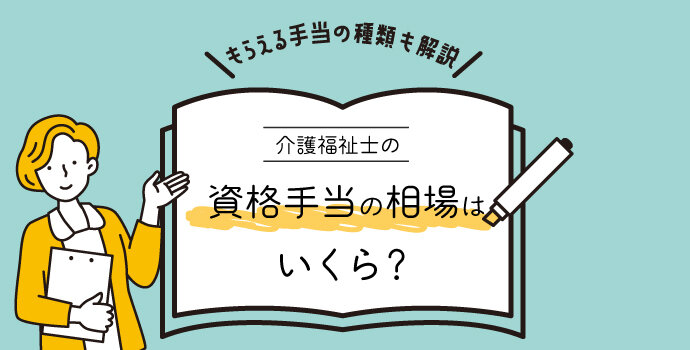
|
資格
| 公開日:2024.08.21 更新日:2024.08.21 |
介護福祉士の資格手当の相場はいくら?もらえる手当の種類も解説
基本給以外の給料アップにつながる手当として、資格手当があります。介護福...(続きを読む)